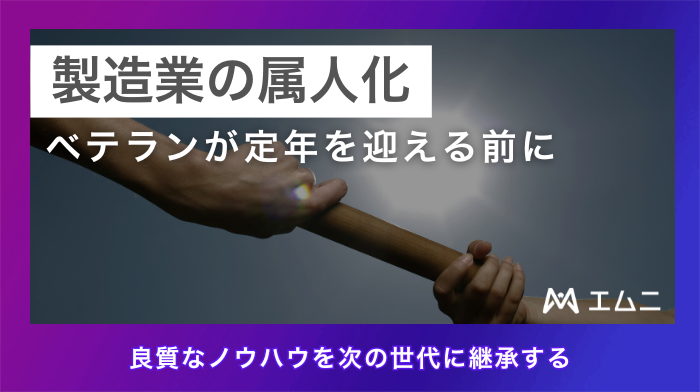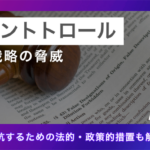
特許訴訟の闇|パテントトロールの実態と企業が備えるべき法的対抗策
2025-07-30
属人化の解消|業務依存から脱却して組織力を強化する方法
2025-07-30未来を託す後継者の選び方|細かなステップからAI活用まで徹底解説
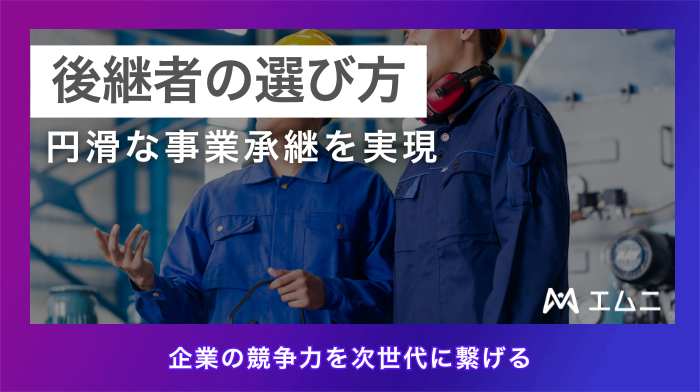
熟練従業員の高齢化が進み、若手の定着も難しい昨今「自分たちの技術を次世代に継承できるのか」という不安を抱える企業は少なくありません。
今や後継者不足は経営層だけの問題ではなく、現場の技能継承や組織の安定運営に直結する重要課題となりつつあります。
このような状況では、事業承継に遅れをとると、技術の空洞化、人材の流出、そして顧客・取引先との信頼関係の喪失を招きかねません。
そうしたリスクを回避し企業の強みを未来に引き継ぐためには、後継者不足問題に対して理解を深め、早期から準備に取り掛かることが不可欠です。
▼製造業の人手不足について詳しく解説した記事はこちらから
製造業の人手不足|浮き彫りになる問題とその解決策
後継者問題の背景
日本の中小企業において喫緊の課題となっている後継者不足。
経営者の多くが高齢化する一方で、親族内に適切な後継者が不在、あるいは後継者候補がいても育成が進まないといった状況が散見されます。
日本政策金融公庫総合研究所が2020年に公表した調査では、調査対象企業の半数以上が廃業を予定していると回答しています。
また、その理由として「子供がいない」「子供に継ぐ意思がない」「適当な後継者が見つからない」といった後継者に関連するものが約3割を占めるという、厳しい現状が報告されています。
この後継者問題を放置すれば、長年培ってきた高度な技術やノウハウ、雇用が失われるだけでなく、収益性の高い企業であっても廃業に追い込まれる「黒字廃業」の可能性も存在します。
さらに、円滑な事業承継には平均で3年以上、場合によっては10年以上の準備期間が必要です。
このような状況では、親族内承継に固執せず、社内承継やM&A等の第三者継承といった多様な選択肢も視野に入れ、早期から計画的な対応を講じることが不可欠と言えるでしょう。
▼製造業の若者離れについて詳しく解説した記事はこちらから
製造業の若者離れ|原因や効果的な対策を解説
▼製造業の高齢化について詳しく解説した記事はこちらから
製造業における高齢化|深刻な問題とその解決策
近年の事業承継トレンド
従来は親族内承継が主流でしたが、現在は様々な承継方法が選択肢として存在します。
ここでは、親族内継承、社内継承、第三者継承のそれぞれについてメリット・デメリットを把握し、自社にとって最適な継承手法を模索しましょう。
親族内継承
企業内外から心情的に受け入れられやすく、後継者の早期決定により長期的な育成期間を確保できることがメリットです。
相続を活用することで、経営と財産の一体的な承継が期待できることも特徴と言えるでしょう。
一方で、近年、親族内承継は減少傾向にあります。
事業や経営の安定性に対する不安、家業にとらわれない職業選択やリスクの少ない安定した生活を望む子供側の価値観の多様化などが背景として考えられます。
このような状況下でも後継者が安心して事業承継を行うためには、現経営者による経営基盤強化や計画的育成が不可欠なのです。
社内継承(従業員継承)
社内継承では長年培われた企業文化やノウハウが維持されやすく、現場を熟知する人材が経営を円滑に引き継ぐことが可能です。
対外的にも、この事業継続性が高く評価される傾向にあります。
また、従来は後継者となる従業員個人の資金調達能力(特に株式の買い取りなど)が課題となることもありましたが、税制面で制度が整備されたことで以前よりも実施しやすい環境が整いつつあります。
一方で、経営者親族と同意や協力を取り付けること、他の従業員と関係性調整を行うことなどが重要となるでしょう。
M&A等の第三者継承
後継者がいない企業であっても事業存続が可能となるだけでなく、買い手側からの新たな経営資源、技術資源、販売チャネルなどが投入されることで、さらなる事業成長が期待できます。
現経営者は事業売却益を得て、リタイア後の資金を確保することも可能でしょう。
ただ、企業文化や経営方針が大きく変化する可能性があり、既存の従業員の理解獲得やモチベーション維持が大きな課題となる場合もあります。
加えて、情報漏洩のリスク、複雑な交渉プロセス、専門家への相談費用なども考慮に入れることが重要です。
後継者選び・事業承継がもたらすメリット
適切な後継者を選ぶことは、企業にとって多くのメリットをもたらします。ここでは、その主要な利点について具体的に解説していきます。
安定した経営の継続
後継者が明確であれば、経営者の引退や不測の事態に直面しても、速やかに事業を引き継ぎ、経営の空白期間を生まず、混乱を最小限に抑えることが可能です。
また、明確な後継者が存在することは取引先や金融機関からの信用維持にも寄与します。
これにより、新たな設備投資や急な納期対応といった製造業特有のニーズに対しても、対応力を維持することが可能です。
さらに、後継者の存在は、経営が短期的な視点に陥ることを防ぎ、中長期的な戦略を一貫して継続することにも貢献します。
現場の混乱が回避されることで顧客対応力が維持・向上され、顧客からの信頼を強固なものにするでしょう。
社員の安心感・組織の一体感の醸成
後継者が明確であることは、従業員にとって大きな安心材料となります。
企業の将来に対する不安を軽減し、業務に集中する環境を整え、組織として一丸となって邁進しようという意識を育むのです。
特に、製造業の現場では熟練従業員が長年の経験から体得した暗黙知が多く存在します。
こうした知見は現場での観察・対話・信頼関係のなかで自然に継承されることも多いため、職場の雰囲気が重要になるのです。
すなわち、組織の心理的安全性が製造現場におけるパフォーマンスの基盤になっていると言えるでしょう。
企業文化やノウハウの継承
長年にわたって培われた企業文化やノウハウは企業の重要な無形資産です。
適切な後継者を選ぶことは、このような貴重な資産を次世代に引き継ぐために不可欠なのです。
特に製造業では、熟練従業員が持つ高度な技能、複雑な状況での判断力、効率的な段取りといった暗黙知が企業競争力の源泉となっていることもあります。
事業承継は、この暗黙知を可視化し、形式知として次世代へ伝承する好機と捉えるべきでしょう。
また、企業文化やノウハウが確実に継承されれば、経営者が変わっても意思決定の指針が一貫することに繋がり、変化の激しい時代においても、自社らしさを担保し長期的な競争優位性を維持することができるのです。
▼技術継承について詳しく知りたい方はこちら
技術継承|製造業の未来を支える知恵と技の伝承 – オウンドメディア
既存の人脈・信頼関係を活かせる
長年にわたって築き上げた社内外との強固な人脈、および社会的信頼は、企業にとって貴重な財産です。
後継者がこの関係性を継承し、発展させることで、既存事業の安定性確保だけでなく新規ビジネスの開拓も期待されます。
特に製造業では、安定した調達、生産、そして販売チャネルが生命線です。事業承継を早期に進め、現経営者が持つネットワークを徐々に引き継ぐことで、取引の安定性を維持できます。
加えて、地域密着型の企業では自治体や地域の他企業との連携も非常に重要です。
後継者が地域との関係性を継承し、コミュニティの一員としての役割を果たすことで、企業の持続可能性はさらに高まります。
そして、社外だけでなく、社内の人間関係も承継において極めて重要です。
社内キーパーソンとの信頼関係が引き継がれることで、現場の隅々まで指揮が行き渡り、企業活動を円滑に進行できるようになるでしょう。
後継者選定のステップとポイント
後継者を選ぶプロセスは、単に人選をするだけでなく、計画的かつ段階的に進める必要があります。ここでは、その重要なポイントと具体的なステップを解説します。
事業承継に対する意識醸成
事業承継に対する意識を醸成することは、企業の未来を切り開く第一歩です。
まず、経営者自身が「事業承継をいつ、どのように進めるか」という意識を明確にすることが求められます。
次に、現状の経営状況を正確に把握し可視化していくことが重要です。
財務状況はもちろんのこと、経営課題、経営資源(設備、技術、人材など)を客観的に評価しましょう。
この際、外部の支援機関や専門家に依頼することで、第三者視点から客観的に現状を把握することが可能になります。
さらに、事業承継の対象が多岐にわたることを理解しておくことも大切です。
具体的には、事業承継は、経営を担う「人」の継承、会社の「資産」の継承、長年培ってきた「知的財産」の継承に大別されます。
こういった要素を複合的に捉え早期から計画を立案することが、円滑な事業承継のための基盤となるでしょう。
後継者選定と経営改善
後継者選定と経営改善は、事業承継の成否の鍵を握る重要なステップです。
まず、後継者候補の有無を確認しましょう。社内に候補者がいる場合、その人物の経営者としての能力、すなわちリーダーシップ、決断力、コミュニケーション能力、そして事業創造力を多角的に評価することが不可欠です。
適切な後継者候補が見当たらない場合は、社内外における候補者の可能性を幅広く検討し、M&A(第三者承継)といった選択肢も視野に入れるべきです。
M&Aの場合、単に売却価格だけではなく、経営理念・企業文化の親和性、事業継続性と将来的な発展に対する意欲、財務健全性などの観点から慎重に選定することが求められます。
また、後継者が引き継ぎたいと思えるように、現経営者による積極的な経営改善が重要となります。
節税対策だけではなく、事業の維持・発展を最優先に考え、後継者候補が事業の将来性に不安を感じないように経営状況を改善していく姿勢が求められるのです。
なお、経営改善の対象は業績や経費にとどまりません。人材育成のほか、知的財産の管理、暗黙知の形式知化など、円滑な事業承継のためには多角的な現状改善が有効でしょう。
承継方法に応じた計画策定
次に、承継方法に応じて具体的な計画策定を行います。
親族内継承および社内承継では、企業の将来を明確に見据え、いつ、どのように、何を、誰に引き継ぐのかを詳細に計画することが求められます。
具体的には、自社の現状分析、外部環境変化の予測、事業全体の方針検討、売上やシェアなどの目標設定、そして資金調達や支援機関への相談などのアクションを盛り込む必要があるのです。
なお、この計画は、経営者と後継者だけではなく、従業員、取引先、金融機関といった全ての関係者と共有することが望ましいでしょう。
一方、M&Aなど第三者へ承継を行う場合は、相手企業の選定が最も重要です。
経営理念・企業文化の親和性、事業継続性と将来的な発展に対する意欲、財務健全性といった観点から、最適なパートナーを見極めます。
そのうえで、専門知識を持つ社外の専門家を適切に活用しつつ、上記の親族内継承・社内継承の場合と同様に、具体的な計画策定を行いましょう。
事業継承の実行
綿密な計画立案ののち、事業承継の実行に移りましょう。
最も重要なのは、承継前だけでなく承継後も継続して後継者のトレーニングを行うことです。
座学による経営知識の習得だけではなく、現場でのOJTを通じて、事業の実態把握、従業員や顧客との関係性の深化に努めましょう。
また、事業環境の変化に応じて、承継計画を随時ブラッシュアップしていくことも欠かせません。
さらに、事業承継を企業の成長機会として捉え、新規事業や社内環境の改善など新たな取り組みを積極的に検討することが大切です。
後継者への円滑な承継を実現するには
円滑な事業承継を実現するためには、後継者の選定と育成だけでなく、組織全体での取り組みが重要となります。ここでは、事業承継を成功に導くために重要なポイントを見ていきましょう。
事業承継は組織全体で推進する
事業承継は組織全体で推進すべきプロジェクトであることに留意しましょう。
まず、事業承継とは経営権の移行に留まらず、企業文化や信頼関係の再構築であるという認識を持つべきです。
このような認識のもとで、現経営者、後継者、従業員はもちろん、取引先や金融機関といった外部関係者まで、あらゆるステークホルダーを巻き込む必要があります。
関係者間で、早期から丁寧なコミュニケーションに取り組みましょう。
具体的には、従業員が抱くであろう漠然とした不安の解消や納得感の醸成のためには、事業承継の目的、詳細な方針や日程などについて、オープンな情報共有を図り、組織全体で共通認識を持つことが重要です。
こうした対話を通じて、心理的障壁を低減し、企業全体が前向きに新しい後継者を受け入れられるような土壌を育むことこそが、事業承継を成功へと導く鍵となるでしょう。
ガバナンス体制・社内制度の整備
事業承継を円滑に進めるために、ガバナンス体制と社内制度の整備は不可欠な要素です。
後継者への権限移譲を進めるにあたっては責任と権限の線引きを明確化することが重要となります。
取締役や監査役といった組織の監督機能を強化することで、経営の透明性を高め、新体制下でも意思決定をより確実なものにできるでしょう。
また、製造業の現場では属人的な業務プロセスや判断基準が残りがちです。
これを形式知に変換することができれば、後継者がスムーズに判断・行動できるようになり、経験の浅い段階でも安定した事業運営が可能となるのです。
エムニでは、熟練従業員の暗黙知を、AIを活用することで形式知化する「AIインタビュアー」を開発しております。詳細はこちらからぜひご覧ください。
リスクに備えた事業・資本設計
事業承継において、リスクに備えた事業・資本設計は企業の未来を守るうえで非常に重要です。
まず、後継者が経営で躓く事態を想定し、事業リスクの分散を検討しましょう。
例えば、特定の取引先に対する依存度を下げる、複数の事業領域を持つことでリスクを分散させるなどが挙げられます。
また、相続税や贈与税といった税務負担を最小限に抑えるための対策も不可欠です。
さらに、経営者の個人保証や会社の借入債務をどのように扱うか、金融機関との関係を整理しておくことも後継者が安心して経営に専念できる環境を作るうえで欠かせません。
加えて、持株会社設立や株式分散などを通じて、後継者による経営権を安定的に確保することも重要です。
このような複雑なリスクマネジメントを進めるためには、税理士、弁護士、金融機関といった専門家との密接な連携が不可欠となるでしょう。
AIの後継者不足問題への貢献
近年急速に進化するAIは後継者不足問題にも大きく寄与することが期待されます。ここでは、AIの事業承継に対する貢献方法について、詳細に解説していきます。
暗黙知の形式知化
製造業の現場には、熟練工が長年の経験を通じて培った高度な技能やノウハウなど、言語化が困難な暗黙知が多く存在します。
これらは企業にとって貴重な財産であり、後継者に引き継いでいくことが強く求められます。
AIは、この暗黙知の継承に大きな力を発揮します。例えば、AIを搭載したインタビュアーが熟練工との対話を通じて、思考過程、判断基準、あるいは作業のカン・コツなどを効率的に引き出し、データとして蓄積することができます。
また、作業映像やセンサーデータとの連携を通じて、従来は言語化できなかった動作や感覚を数値化・可視化し、形式知化する支援も可能です。
AIの活躍は現場のノウハウに留まりません。経営者が長年の経験に基づいて行ってきた意思決定プロセスを、AIが過去の経営判断とその背景にある情報を分析することで、経営者の思考過程や優先順位を可視化することが可能になります。
エムニでは、AIがインタビュアーとなり熟練作業員の暗黙知を形式知化する「AIインタビュアー」を開発。効率的な技能伝承を実現します。詳細な情報はこちらからご覧ください。
▼暗黙知の形式知化について詳細に解説した記事はこちらから
生成AIで暗黙知を形式知化するメリットやプロセスを解説
後継者育成の効率化
AIを活用することにより、後継者候補の適性、現在のスキルレベル、将来担うべき役割などに合わせたパーソナライズされた学習パスを提供することが可能です。
これにより、無駄なく効率的に必要な知識やスキルを習得することができるでしょう。
さらに、AIを搭載した技能伝承アシスタントは、後継者に対してリアルタイムでフィードバックを提供し、熟練者が隣にいるかのように技能習得環境を実現。
これにより、OJTの負担を軽減しつつ、短期間で高いレベルの技能を身につけることが可能です。
加えて、経営層に求められる複雑な意思決定能力の育成にもAIは有効です。
AIを活用したシミュレーションを用いることで、後継者は様々な経営状況や市場変化を想定した仮想環境で、意思決定の練習を繰り返すことができます。
実際の経営リスクを負うことなく、経営者としての実践的な判断力を磨くことに貢献するでしょう。
AIによる意思決定支援
後継者が経験不足な場合でも、AIによるデータ分析は客観的な経営判断を可能にします。
需要予測、在庫最適化、価格設定といった領域でAIが精度の高い分析結果を提供することで、後継者は経験に頼らずデータに基づいた意思決定を行うことが可能です。
また、受発注管理、工程スケジューリング、品質検査といった定型業務をAIで自動化することにより、後継者は戦略的な業務、例えば新たな成長戦略の策定や人材育成といった業務に多くの時間を割けるようになります。
さらに、AIが企業の財務状況、市場環境、競合状況といった膨大なデータを分析することで、事業承継に伴う潜在的なリスクを定量的に評価できます。
これにより、後継者に経験値が蓄積する以前であっても、リスクを把握し適切な対策を講じることができるでしょう。
エムニでは熟練工の技能伝承を実現するAIインタビュアーを開発。事業継承にも大きく貢献します。
まとめ|事業承継は「未来への経営戦略」
事業承継は単なる後継者探しではなく、企業の未来を左右する経営戦略そのものです。
製造業を取り巻く環境が大きく変化する現在、後継者の選定と育成は、経営者だけでなく組織全体で取り組むべき経営課題へと進化しています。
適切な準備と段階的な引き継ぎ、そしてAIをはじめとする新たなテクノロジーの活用により、技能や企業文化の継承、さらには企業の競争力そのものを次世代につなげることができるのです。
事業承継の成否は、企業の未来の姿を大きく左右します。「まだ早い」ではなく「今が最適なタイミング」と捉え、経営層と現場が一体となって準備を始めましょう。
エムニでは、事業承継に不可欠となる技能伝承を実現するAIの開発を行っております。
製造業のお客様に特化して蓄積した豊富な知見とともに、伴走型のサービス開発に取り組んでおりますので、無料相談からぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。
エムニへの無料相談のご案内
エムニでは、製造業をはじめとする多様な業種に向けてAI導入の支援を行っており、企業様のニーズに合わせて無料相談を実施しています。
これまでに、住友電気工業株式会社、DENSO、東京ガス、太陽誘電、RESONAC、dynabook、エステー株式会社、大東建託株式会社など、さまざまな企業との取引実績があります。
AI導入の概要から具体的な導入事例、取引先の事例まで、疑問や不安をお持ちの方はぜひお気軽にご相談ください。

引用元:株式会社エムニ