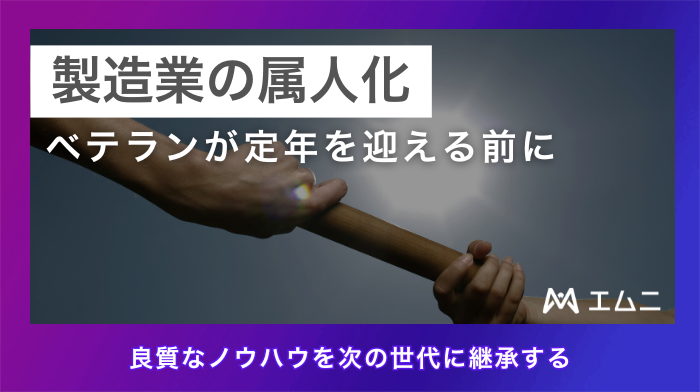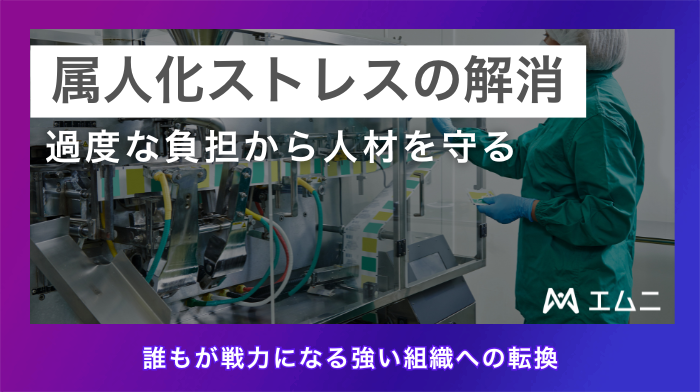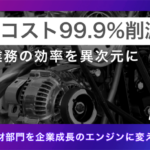
特許調査/分析コスト99.9%削減は製造業に何をもたらすのか
2025-09-25
商標登録で失敗しない|45区分一覧と注意点を徹底解説
2025-09-29後継者育成ガイド|基礎から生成AIの活用方法まで徹底解説

人手不足や熟練従業員の引退など、製造業を取り巻く環境は厳しさを増しています。
「いかに自社の強みを次世代へつなぐか」が重要課題となる昨今、計画的な後継者育成は不可欠です。
一方で、生成AIをはじめとするデジタルテクノロジーの進化は、従来困難であった技能伝承や後継者育成の仕組みを大きく変えつつあります。
今後、後継者育成は「守り」ではなく「攻め」の戦略となり、企業の持続的な成長を支える大きな原動力となるでしょう。
この記事では、後継者育成の重要性やメリットに始まり、具体的な進め方、成功事例、そしてAI技術の活用方法までを包括的に解説します。
▼製造業の人手不足について詳しく解説した記事はこちらから
製造業の人手不足|浮き彫りになる問題とその解決策
後継者育成とは?|製造業における重要性
まず「後継者育成とは何なのか」について理解を深めるとともに、昨今の製造業において後継者育成が重要視されている背景について整理しましょう。
▼近年の事業承継トレンドについて詳しく解説した記事はこちらから
未来を託す後継者の選び方|細かなステップからAI活用まで徹底解説
後継者育成とは?
後継者育成は、ただ次期経営者を探すだけの作業ではなく、企業が持続的に成長していくための戦略的な取り組みです。
従来、後継者育成は「サクセッション・プランニング」と呼ばれ、経営トップの後任者を計画的に選定し、育成する枠組みとして発展してきました。しかし今日、その意味合いはより広がりを見せています。
特に、製造業のように長期的な技術力の蓄積や品質管理の徹底が企業価値の源泉となる業界においては、後継者育成は「企業としてどのような未来を実現したいのか」というビジョンから逆算して設計されるべきものです。
そのため、将来の市場変化や技術革新を見据え、自社が描くビジョンを実現できる人材を計画的に育成していくことが求められます。
また近年は、特定のポジションの承継にとどまらず、優秀な人材を組織全体で選定・育成し、将来的なリーダー候補として継続的にプールする「タレント・プーリング」という考え方も重要視されています。
なぜ後継者育成が重要なのか?
まず、企業統治(コーポレートガバナンス)の観点です。
上場企業では、「コーポレートガバナンス・コード」に基づき、取締役会が後継者候補の育成に責任を持つことが明確に求められているのです。
人的資本に関する国際ガイドライン「ISO30414」でも、後継者育成に関する情報開示が推奨されており、企業はステークホルダーに対して人材戦略への取り組みを示す必要があります。
次に、製造業特有の課題として、製造業の現場では熟練技術者の高齢化が進み、暗黙知が失われるリスクが高まっているという現状があります。
図面やマニュアルに残せないカンやコツ、判断基準が継承されないまま退職が進めば、品質や生産性の低下につながりかねません。
若年層の製造業離れによって人材の母集団自体が縮小している現状もあり、優秀な人材を早期に発掘・育成していくことが急務となっているのです。
さらに、事業継続という観点からは、企業は役職者が突然不在になった場合でも事業を滞りなく継続することが求められています。
後継者育成が進んでいることは、サプライチェーンに対する影響を最小限に抑え、企業価値を守るための保険にもなるでしょう。
▼製造業の若者離れについて詳しく解説した記事はこちらから
製造業の若者離れ|原因や効果的な対策を解説
▼製造業の高齢化について詳しく解説した記事はこちらから
製造業における高齢化|深刻な問題とその解決策
後継者育成のメリット
後継者育成に意欲的に取り組むことは、企業に多面的なメリットをもたらします。ここでは3つの観点から、後継者育成に取り組むメリットを見ていきましょう。
経営の継続性と安定性の確保
後継者育成の最大のメリットは、経営の継続性、企業の安定性を高めることです。
経営者の引退や不測の事態に直面しても、後継者育成が進んでいれば、空白期間を生まず、混乱を最小限に抑えることができます。
また、後継者育成はコーポレートガバナンス・コードへの対応にも直結します。
コーポレートガバナンス・コードでは、取締役会が後継者育成の責任を担うことが明示されているため、計画的な後継者育成は企業統治の健全性を示すのに有効なのです。
加えて、安定した後継者育成計画は、取引先や金融機関からの信頼維持にも直結します。
特に製造業では、長期的な取引や多額の設備投資が一般的であり、経営の継続性が担保されていることは信用向上に直結するでしょう。
さらに、中長期的な戦略の一貫性を確保できることも大きなメリットです。
後継者候補がビジョンや事業戦略を共有しながら成長することで、継承後も戦略がぶれることなく推進できます。
心理的安全性とモチベーションの向上
後継者育成は、組織全体の心理的安全性とモチベーションを高める効果を持っています。
将来のリーダー候補と育成戦略が明確に示されることで、社員は「自分のキャリアがどう発展していくのか」を具体的にイメージできるようになり、安心感とエンゲージメントが向上するのです。
特に製造業の現場では、熟練工の経験や判断力といった暗黙知が多く存在し、それらはマニュアルだけでは十分に伝えきれません。
実際には、観察・対話・信頼関係のなかで自然に受け継がれるケースが多く、職場の雰囲気そのものが技能継承の質を左右します。
そのため、心理的に安全な環境を整えることは、現場のパフォーマンスの基盤を構築するうえで不可欠と言えるでしょう。
また、後継者育成プロセスにおいては、多面評価(360度評価)やメンタリングの仕組みを取り入れることで、従業員が自己認識を深めるとともに、他者からの評価を知る機会を得られます。
これは単に個人の成長を促すだけでなく、組織全体に「学び合い、支え合う文化」を醸成するのです。
企業文化やノウハウの継承
企業文化やノウハウは、長年にわたって蓄積された企業の重要な無形資産です。
特に製造業では、熟練従業員が培ってきた高度な技能や、複雑な状況での判断力、効率的な段取りといった暗黙知が競争力の源泉となるケースが少なくありません。
こうした資産は単なる業務マニュアルでは表現しきれない「自社の強み」であり、次世代に継承できるか否かが企業の将来を大きく左右します。
後継者育成を適切に進めることは、これらの無形資産を確実に引き継ぐために不可欠です。
後継者育成のプロセスを「暗黙知を可視化し、形式知へと変換するチャンス」と捉えれば、属人化した知識や判断基準を体系化し、将来にわたって次世代育成を効率化できる仕組みを構築できます。
また、企業文化やノウハウが確実に継承されれば、経営者が変わっても一貫した意思決定基準を維持でき、自社らしさや競争優位性を長期的に維持するための重要な土台となるでしょう。
AI技術を活用することで、暗黙知を形式知化し、属人化を解消することにご興味がある方は、弊社プロダクトである「AIインタビュアー」をご確認ください。
▼技術継承について詳しく知りたい方はこちら
技術継承|製造業の未来を支える知恵と技の伝承 – オウンドメディア
後継者育成の進め方4ステップ
後継者育成は「人事の仕事」ではなく、企業の将来を左右する経営課題です。
経営戦略と連動した体系的・段階的なステップを踏むことで、後継者育成を効果的に進めることができます。
経営戦略の策定と連動
後継者育成は、企業の中長期的な経営戦略と切り離して考えることはできません。
まず「10年後に自社をどのようにしたいのか」というビジョンを明確に描くことが出発点です。
例えば、海外市場への展開を目指すのか、新規分野への技術開発を加速させるのか、それとも既存事業の品質や効率を徹底的に高めるのか、その方向性によって、後継者に必要となる資質や経験は大きく異なります。
このプロセスを省略して進めてしまうと、経営戦略と後継者の能力とのミスマッチが生じ、承継後に企業の成長を阻害するリスクが高まります。
逆に、経営戦略と連動した後継者育成は、単なる人材育成にとどまらず、次世代経営体制の設計そのものとなるのです。
したがって、このステップは人事部門の課題ではなく、経営トップや部門長を含む経営陣全体で取り組むべき「最重要の経営課題」です。
経営戦略の方向性を共有し、その実現に必要な能力を後継者にどのように習得させるかを議論する機会を意識的に設けることが不可欠となるでしょう。
人材要件の明確化と候補者の選定
経営戦略が明確になったら、その実現にとって重要なポジションを洗い出し、それぞれのポジションに求められる人材要件を明確に定義しましょう。
例えば、海外展開を見据えるのであれば語学力や異文化対応力、研究開発を促進するなら技術理解と判断力、といった具体的な要件設定が求められます。
加えて、製造業では、マネジメントスキルだけでなく、現場で培った技術知識、品質管理や生産効率化の経験、現場従業員と信頼関係を築ける人間力などが重視されます。
この人材要件を明確に言語化することで、人材選定と育成の両方がスムーズに進むのです。
候補者の特定にあたっては、9ボックスモデルやパフォーマンス評価、多面評価(360度評価)など、客観的な評価ツールの活用が有効になります。
製造業では、現場からの信頼、トラブル対応力といった定性的な資質も重視されるため、数値だけに依存せず、多角的に評価する視点が重要でしょう。
また、候補者を最初から1人に絞り込むのではなく、潜在的な能力に応じて「今すぐ後継者になれる人材」「数年で育成可能な人材」「中期的に育成すべき人材」のように階層分けしてプールすることが推奨されます。
候補者ごとの個別育成計画の策定
候補者を特定できたら、全員に同じ研修を与えるのではなく、それぞれの強みや課題に合わせた育成計画を設計することが重要です。
例えば、製造現場に強いが財務経験が不足している候補者には、管理会計や投資判断に関わる業務をローテーションで経験させる。
あるいは、経営企画に強いが現場経験が浅い候補者には、一定期間製造ラインの責任者として配置し、現場従業員との関係構築やトラブル対応を通じて実践的な学びを積ませる、といった具合です。
また、実際の育成ロードマップの策定時には、後継者候補のスキル、キャリア経験などを体系的に把握することが第一歩となります。
そのうえで、単なる知識習得にとどまらず、プロジェクト型の課題解決、メンターによる伴走支援、海外拠点や異部門への派遣など、実務を通じた成長機会を組み込むことが重要です。
計画実行と継続的改善
個別育成計画を策定したら、机上のプランにとどめず、現場で着実に実行しましょう。
重要なのは、候補者ごとの進捗や成果を定期的に確認し、経営陣や人事部門が主体的にフォローすることで、計画が形骸化するのを防ぐことです。
特に製造業では、日々の業務の忙しさに流されて後継者育成が後回しにされやすいため、評価指標(KPI)をあらかじめ設定し、四半期ごとなどのサイクルで見直すことが効果的でしょう。
例えば「品質改善プロジェクトを一定期間リードできたか」といった実績ベースの指標を組み込むと、後継者候補の成長度を客観的に把握できます。
また、計画は実行して終わりではなく、定期的に進捗を可視化し、候補者本人・上司・経営層が三者で確認する機会を設けることが推奨されます。
さらに、新規事業の立ち上げ、技術革新、市場動向といった経営環境の変化に応じて計画そのものを柔軟に見直すことが、実効性のある後継者育成の鍵となるでしょう。
後継者育成へのAIによる貢献
近年注目を集めるAI技術を活用することで、技能伝承の精度を高め、後継者の意思決定力を育み、データに基づいた経営を実現することができます。
ここでは、AIがどのように後継者育成に貢献できるのか、詳細に解説していきます。
暗黙知の形式知化
製造業の現場には、熟練従業員が長年の業務で培ってきたカンやコツ、段取りの工夫といった暗黙知が数多く存在します。
例えば、微妙な音や振動から設備の異常を察知する感覚、品質不良を未然に防ぐ判断の勘所などは、マニュアル化しづらい暗黙知の典型例です。しかし、ベテランの高齢化により、これらが失われるリスクは年々高まっています。
AIは、こうした暗黙知を形式知として継承する有力な手段となります。具体的には、熟練工へのインタビューをAIが支援し、思考の背景や判断基準を深掘りすることで、従来は曖昧だった知識を言語化することが可能です。
また、作業中の映像やセンサーデータと組み合わせれば、熟練工の手の動きや設備調整の勘所を数値やパターンとして可視化し、誰もが学べる教材に変換することもできます。
AIによる暗黙知の形式知化に関心をお持ちの方は、エムニが開発する「AIインタビュアー」をぜひご確認ください。技能伝承の課題を解決し、後継者育成を加速させる具体的な仕組みをご紹介します。
後継者育成の効率化
AIを活用すれば、後継者候補の適性や現状のスキル、将来的に担う役割に応じて、最適化された育成スキームを設計できます。
これにより、従来の一律的な教育で生じていた無駄を排し、効率的に知識とスキルを習得することが可能です。
また、AIを搭載した技能伝承アシスタントは、後継者候補にリアルタイムでフィードバックを提供し、熟練者が常に伴走しているかのような学習体験を実現できます。
これによってOJTにかかる指導側の負担を軽減しつつ、短期間で高水準の技能習得が可能になるでしょう。
さらに、経営層に不可欠な複雑な意思決定力の養成にもAIは有効です。
シミュレーションによって多様な経営環境や市場変化を仮想的に体験し、リスクを伴わずに意思決定の反復練習を行うことで、後継者は実践的な判断力を磨くことができるでしょう。
データに基づいた意思決定支援
後継者にとって大きな課題のひとつは、経験不足ゆえに自信を持って意思決定ができないことです。
AIによるデータ分析は、そうした不安を補い、客観的かつ精度の高い判断を支援します。
需要予測、在庫最適化、価格設定といった領域では、AIがデータ分析をサポートすることで、勘や経験に依存しない合理的な経営判断を下すことが可能になります。
さらに、受発注管理、工程スケジューリング、品質検査など定型業務を自動化することで、後継者は本来注力すべき戦略的な業務、例えば、新たな成長戦略の策定や人材育成などに時間を割くことができます。
加えて、AIは財務状況、市場環境、競合動向といった膨大なデータを統合的に分析し、事業承継に伴う潜在的リスクを可視化することも可能です。
これにより、後継者は経験が浅い段階からでも、リスクを的確に把握し、先手を打った対策を講じられるでしょう。
後継者育成の成功事例
大手製造業各社には既に後継者育成を盛んに進めている企業も。ここでは、具体的な取り組み事例から成功のヒントを探っていきましょう。
▼製造業のAI・DX推進の展望について詳しく知りたい方はこちら
社長対談|製造業界におけるAI・DX推進の展望
株式会社小松製作所
建設機械大手のコマツでは、2006年に制定した「コマツウェイ」において、リーダー層が常に後継者育成を考えることを行動指針として明確化し、後継者育成を推進しています。
まず、人事諮問委員会によって後継者として求められる要件定義を行い、どのようなリーダーを育てるべきかを経営層レベルで合意形成を行います。
そのうえで、サクセッションプランを毎年更新し、主要な役職ごとに後継候補者を選定。
次に、選ばれた後継候補者には「修羅場」となる難しい課題を与え、困難を乗り越える強い意思力を養成します。
さらに、利害が対立する当事者をまとめる組織運営力、不正を許さないコンプライアンス意識の醸成などにも取り組むのです。
このように、計画的な育成機会を提供することで、ただ後継者人材をプールするだけでなく、経営者に必要な資質を磨く機会を体系的に提供していると言えるでしょう。
ユニリーバの事例
世界的消費財メーカー・ユニリーバはUnilever Future Leaders Program(UFLP)と呼ばれる後継者育成に取り組んでいます。
UFLPは新卒入社から数年のうちに経営幹部候補へと成長させるためのプログラムであり、参加者は製造、営業、マーケティング、人事など、部門横断的なジョブローテーションを経験し、全社的な視野を養成。
また、経験豊富な先輩社員が伴走することで早期に壁を乗り越える力を培うメンタリング制度や、経営陣と直接対話する機会を通じて、グローバル企業のリーダーの考えに触れる機会を提供します。
様々なスピード感を持った取り組みの結果、ある参加者は3年半で管理職に昇進し、10年足らずで地域の人事ディレクターに就任するなど、加速的なキャリア形成を実現。
このような早期から多様な経験を積ませ経営者としての目線を育む仕組みは、グローバル競争が激化するなかで、実践力のある後継者を育成するのに有効でしょう。
参考:6 Succession Planning Examples From Companies – AIHR
花王株式会社
大手消費財化学メーカーである花王では、多面的人材評価の基盤となる行動モデルを策定。
この行動モデルでは、「強い信念に基づくリーダーシップ」など次期経営人材に求められる7つの観点に関して6段階で評価を行うことで、多方面から後継者候補としての資質を評価しています。
また、後継者候補となる人材を「Ready Now(今すぐに後任となれる人材)」「Ready Soon(1〜3年で後任として育成する人材)」「Mid Term(3〜5年で後任として育成する人材)」と呼ばれる3段階に分類し、それぞれの能力に応じた育成プランを提供。
このように、後継者候補を適切に評価し、そのうえで、それぞれの候補者に最適化された育成カリキュラムを課すことで、効果的な後継者育成を実現しているのです。
参考:花王の人財開発について
まとめ|後継者育成は企業の成長戦略そのもの
後継者育成とは、ただ会社や業務の引き継ぎ手を指名・育成することではなく、企業の将来の競争力をどのように維持・向上させるのかという経営戦略そのものです。
熟練従業員の技術や現場の文化を次世代に引き継ぐ仕組みを整えることができれば、後継者育成は確実に前進させることができます。
そして、近年急速に発展する生成AI技術を活用することで、そのプロセスはより効率的かつ実践的なものへと進化するでしょう。
製造業の変革が求められる昨今、「今が最適なタイミング」と捉えて準備を始めることが、企業の未来を切り拓くことになるのです。
エムニでは、後継者育成において重要となる暗黙知の伝承を実現するAIの開発を行っております。
製造業のお客様に特化して蓄積した豊富な知見とともに、伴走型のサービス開発に取り組んでおりますので、無料相談からぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。
エムニへの無料相談のご案内
エムニでは、製造業をはじめとする多様な業種に向けてAI導入の支援を行っており、企業様のニーズに合わせて無料相談を実施しています。
これまでに、住友電気工業株式会社、DENSO、東京ガス、太陽誘電、RESONAC、dynabook、エステー株式会社、大東建託株式会社など、さまざまな企業との取引実績があります。
AI導入の概要から具体的な導入事例、取引先の事例まで、疑問や不安をお持ちの方はぜひお気軽にご相談ください。

引用元:株式会社エムニ