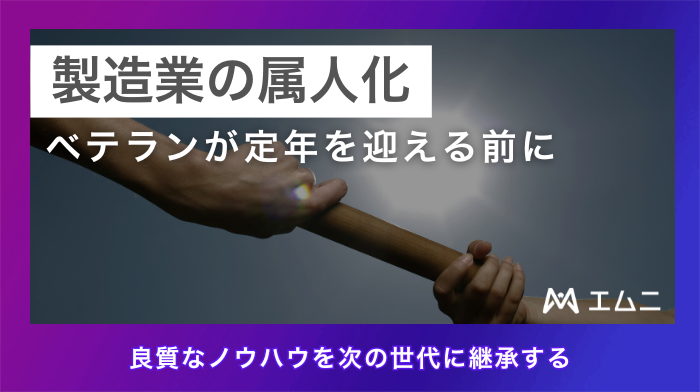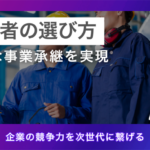
未来を託す後継者の選び方|細かなステップからAI活用まで徹底解説
2025-07-30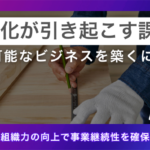
属人化とは?組織課題を解消し、持続可能なビジネスを築く方法を解説
2025-08-22属人化の解消|業務依存から脱却して組織力を強化する方法
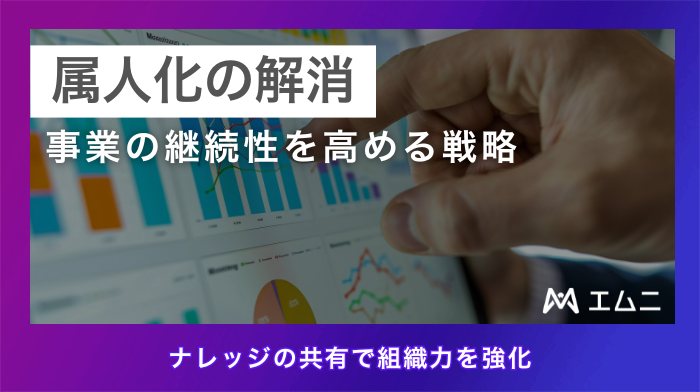
特定の業務が特定の従業員にしかできない「属人化」は、多くの企業が抱える課題です。
一見すると分業がうまくいっているようにも見えますが、その裏には事業継続のリスクや組織成長の阻害といった深刻な問題が潜んでいます。
本記事では、属人化が進む背景とリスク、そして具体的な原因について深掘りしたのち、属人化を解消するための実践的なステップを詳細に解説します。
属人化が進む背景
現代のビジネス環境において、なぜ属人化が進行しているのでしょうか。
その背景には、企業の成長フェーズや業務の複雑化、さらには人材戦略の変化などが大きく関係しています。
例えば、創業期のベンチャー企業では、少数のメンバーが多岐にわたる業務を兼任することが多く、特定の業務がその担当者に集中しやすくなります。
また企業全体や部署が急速に規模を拡大する過程で、業務プロセスの整備が追いつかず、結果として個人のスキルや判断に依存せざるを得ない状況が生まれてしまうことも、属人化を助長する一因です。
さらにコロナ禍でリモートワークが普及したことで情報共有の機会が減り、属人化を進行させています。
属人化に潜むリスク
属人化は組織にとって短期的には効率的なやり方であるように見えるかもしれませんが、中長期的には重大なリスクとなります。
ここでは、属人化が引き起こす主な4つのリスクについて詳しく見ていきましょう。
業務停止リスクの増大
特定の業務が1人の従業員にしかできない状況では、その担当者が不在になった場合、関連する業務全てが停止してしまう危険性があります。
例えば、担当者の急な病気や離職、長期休暇などが発生すると、その間、関係する業務は滞り、顧客への影響や納期遅延といった深刻な問題を引き起こす可能性があるでしょう。
これは、事業継続にとって極めて大きな脅威となり得ます。
品質低下と効率悪化
属人化が進むと、仕事の出来にばらつきが生じます。担当者個人のスキルや判断に依存するため、安定した品質を保つことが難しくなるでしょう。
また、業務が特定の担当者に集中することで負担が増加し、個人の作業の質が低下するだけでなく、結果として全体の業務効率が低下する可能性も考えられます。
さらに新しいメンバーが業務に加わりにくい状況になるため、組織全体の生産性向上が阻害されることも懸念されます。
ナレッジ喪失や継承困難
業務が属人化していると、その業務に関する知識やノウハウが個人の頭の中に留まり、組織全体で共有されなくなります。
引き継ぎが不十分な状態で担当者が異動や退職をした場合、貴重なナレッジが失われてしまい、後任者がゼロから学び直すことになるでしょう。
特に高齢化が進行している製造業のような業種では深刻な問題です。
▼製造業の高齢化問題について詳しく知りたい方はこちら
製造業における高齢化|深刻な問題とその解決策
属人化は知識の継承を困難にし、組織全体の成長を鈍化させる原因となりえます。
組織・人材リスクの拡大
属人化は、組織内の人材育成にも影響を及ぼします。
特定の業務を担当する社員以外は、その業務に関するスキルを習得する機会が失われるため、従業員全体のスキルアップが阻害されるでしょう。
また、業務が特定の個人に集中することで、その社員に過度なプレッシャーがかかったり、長時間の残業が発生したりとモチベーション低下や離職につながるリスクも高まります。
さらに組織全体としては、柔軟な人員配置が困難になり、事業戦略の柔軟な変更ができなくなるなどの悪影響が考えられるため、属人化の対策、解消は非常に重要です。
属人化が発生する主な原因
属人化には様々な要因が複雑に絡み合っていますが、ここでは特に共通して見られる主要な原因を3つ解説します。これらの原因を理解することが、効果的な対策を立てる第一歩となるでしょう。
フローや分担が曖昧
業務プロセスが明確に定義されていなかったり、各担当者の役割や責任範囲が曖昧であったりする場合、属人化の原因となります。
例えば、新しいプロジェクトが立ち上がった際に、誰がどのタスクを担当し、どのような承認プロセスを経て、最終的に誰が責任を持つのかが文書化されていない、あるいは口頭での指示のみで進められているような状況です。
このような場合、経験豊富な特定の個人が「なんとなく」その業務を引き受け、他のメンバーも「あの人が詳しいから」と依存しがちになります。
結果として、業務の進め方や判断基準がその個人の頭の中にだけ存在し、他の人が介入しにくい「ブラックボックス」化が進んでしまうのです。
特に中小企業やスタートアップなど、組織が急成長する過程では、目の前の業務をこなすことに追われ、業務の細分化や役割分担、プロセスの言語化が後回しになりがちなので注意しましょう。
標準化・共有ルールの欠如
業務を標準化するためのルールやガイドラインが整備されていないことは、属人化を引き起こす大きな要因です。
たとえば、業務マニュアルが存在しなかったり、存在していても頻繁に更新されていなかったり、あるいは認知されていなかったりすると、各担当者が自己流の方法で業務を進めることになります。
その結果、業務の進め方や品質にばらつきが生じ、経験豊富な個人の独自のやり方が暗黙のルールとして定着してしまうのです。
具体例を挙げると、特定のベテラン社員しか知らないシステムの設定方法や、長年の経験から培われた顧客対応のコツ、付き合いの長い顧客の情報などが、その人だけの知識となってしまいがちです。
また、こうした状況下では、新入社員は体系的な教育を受けることができず、先輩のやり方を手探りで学ぶしかありません。
以上のように、情報共有の文化が根付いていない組織では、個人のノウハウが共有されずに埋もれてしまい、属人化した状態が引き継がれてしまいます。
ツール・文化が整備できていない
属人化を解消するためのITツールの導入が進んでいなかったり、情報共有を重視する組織文化が形成されていなかったりすることも、属人化を加速させる大きな原因となります。
組織全体でナレッジマネジメントシステムやプロジェクト管理ツールを十分に活用していなければ、情報やタスクの共有は個人の努力に依存せざるを得ません。
社内の膨大な資料が個人のPCや共有フォルダに散逸し、必要な情報を探すのに時間がかかったり、古い情報がそのまま放置されたりします。
さらに、「自分の仕事は自分で抱え込むのが美徳」といった古い考え方が根強く残っていたり、情報共有が個人の評価に結びつきにくい文化が存在すると、ITツールがあってもその効果は半減します。
例えば、SlackやMicrosoft Teamsのようなコミュニケーションツールで重要な議論がなされても、その結論がSharePointなどにまとめられなければ、情報はチャットのログの中に埋もれてしまいます。
こうした環境では、個人が積極的に自身のノウハウや進捗を公開しようとする動機が生まれにくく、結果として属人化がより一層定着してしまうのです。
個人の業務の負担が大きすぎる
属人化による悪影響を深く理解していたとしても、各メンバーの業務負担があまりに大きすぎると、マニュアルの作成やナレッジ共有の仕組みの構築、後進の育成などに十分な時間を割くことができません。
例えば、経理部門で月末の締め作業に追われている担当者は、日々の膨大な伝票処理や支払い業務に加え、決算書の作成にも関わるため、マニュアルを整備するのは後回しになります。
このように業務過多が常態化している場合、属人化解消のための取り組みを行う余力そのものがなく、結果的に現状が維持され、さらに属人化が進行してしまう悪循環に陥ります。
また、慢性的な人材不足によって、ある特定の業務を専門の担当者が一人で担っているケースでは、ナレッジを共有すべき相手が職場に存在しないという状況が生まれます。
例えば、社内システム全体の保守・運用を一人で担当しているIT管理者がいるとします。
彼にとって、マニュアルを作成したり、誰かに引き継ぎを教えたりすることは、喫緊の課題とは感じにくいでしょう。
共有する「相手」が見えないため、属人化を解消するための取り組みを行う必要性を認識しにくく、結果としてその業務の属人化が放置されてますます進行してしまうのです。
属人化を解消する具体的ステップ
属人化の解消は一朝一夕ではありませんが、段階的に取り組むことで着実に組織力を強化できます。
ここでは、属人化解消に向けた具体的な5つのステップをご紹介します。
業務の可視化と現状分析
まず、現在行われている業務のすべてを洗い出し、それぞれの業務が誰によって、どのような頻度で、どのような手順で行われているかを明確にしましょう。
業務フロー図を作成したり、担当者へのヒアリングを行ったりすることで、業務の全体像と属人化している箇所を特定できます。
特にこのヒアリングではナレッジの形式知化を見据えて、作業工程を具体的に深掘りすることが重要です。
▼形式知について具体例や重要さを知りたい方はこちら
形式知とは?暗黙知との違い、メリット、形式知化の手法を詳細に解説
また業務の可視化の過程で、業務のボトルネックや非効率な点も明らかになるでしょう。
特に、特定の個人に依存している業務を優先的にリストアップし、その影響度を評価することが重要です。
マニュアル・標準プロセスの整備
可視化された業務をもとに、誰でも均質な業務を遂行できるよう、マニュアルや標準プロセスを整備します。
丁寧なヒアリングを通じて、ベテラン作業員の勘や経験に基づく暗黙知もできる限り形式知化しましょう。属人化を解消し、ナレッジの継承をする上で非常に重要です。
記事後半で暗黙知のヒアリングと形式知化に強みを持つAIを活用したツール「AIインタビュアー」を紹介しているのでぜひご覧ください。
調査結果を元に手順書やチェックリストを作成する際は、簡潔で分かりやすい表現を心がけ、図や写真も活用しましょう。
タスク分散・責任分散の設計
マニュアルや標準プロセスが一通り整備できたら、特定の個人に集中している業務を、複数のメンバーで分担できるような体制を整えましょう。
まずは、業務をより小さなタスクに分解し、それぞれのタスクを複数の担当者ができるようにトレーニングを実施します。トレーニングの実施によって誰かが不在でも他のメンバーがカバーできる体制を構築できます。
また、意思決定権限や責任を複数の人に分散させることも、属人化の解消には有効なアプローチとなるでしょう。
ただし権限や責任の分散は意思決定の遅延によって効率が過度に下がることも考えられるため慎重に検討することが重要です。
さらに長期的な解決策としてジョブローテーションの導入も考えられます。専門に特化した人材の育成は遅れますが、多様な業務知識を持つ人材を育成する上で効果的です。
ツール導入と情報共有基盤の構築
属人化解消を加速させるためには、ITツールの活用が非常に有効です。
まずは社内wikiやナレッジマネジメントシステムを導入して、業務マニュアルやノウハウ、よくある質問などを一元的に管理し、誰もがアクセスできるようにしましょう。
生成AIを活用したチャットボットを導入することでマニュアルやノウハウの検索を効率化することも有効です。
▼AIを活用した暗黙知の継承はこちら
生成AIで暗黙知を形式知化するメリットやプロセスを解説
また、プロジェクト管理ツールやコミュニケーションツールを活用することで、タスクの進捗状況や連絡事項が共有されやすくなり、情報のブラックボックス化を防ぐことができます。
これらのITツールは、単に導入するだけでなく、組織全体で積極的に活用されるような仕組み作りが重要です。
PDCAによる継続的な改善
属人化の解消には継続的な取り組みが求められます。
一度解消出来たとしても、情報共有の習慣や文化が根付いていないと根本的な解決にはなりません。
暗黙知を発生させないためにも日報を書いたり、トラブル解消の記録をテキストで残したりする習慣付けを行うなど、形式知化の意識改革がとても重要です。
また一度作成したマニュアルやプロセスについては、効果を定期的に評価し必要に応じて改善を加えるPDCAサイクルを回しましょう。
新しい業務が発生したり既存業務のやり方が変わったりした際には、速やかにマニュアルを更新し関連するメンバーに周知徹底するべきです。
従業員からのフィードバックを積極的に取り入れ、より実践的で効果的な改善策を講じていくことが持続的な属人化解消につながります。
AIインタビュアーによる技能伝承
AIインタビュアーは属人化を解消し、暗黙知の継承に役立つ最新のAIサービスです。
製造現場では、熟練工が持つ勘や経験によって品質や生産効率が維持されていますが、言語化が難しいという課題がありました。
特に、異常時の対応策や微細な振動・音から異常を察知する技術などは作業日報や引き継ぎ資料があっても十分に記録しきれません。
ベテランの退職や世代交代が進む中、こうした技術が次々に失われています。
この課題に対し、株式会社エムニは生成AIを活用した「AIインタビュアー」を導入し、暗黙知の形式知化を進めました。
既存のマニュアルを学習したAIが熟練工にインタビューをして技術を深掘りすることで効率的な知識の抽出と保存が可能です。
参考:AIと話すだけで熟練工の技術伝承が出来るAIインタビュアー
▼AIインタビュアーの導入を少しでも検討されている方は、無料トライアルをぜひご確認ください。
まとめ
属人化は、多くの企業が直面する課題ですが、そのリスクを認識し、適切なステップを踏むことで確実に解消できます。
業務の可視化から始まり、マニュアルの整備、タスクの分散、そしてITツールの活用と継続的な改善活動が、属人化解消の鍵となるでしょう。
属人化を解消することで、組織は業務停止リスクを低減し、業務品質と効率を向上させ、貴重なナレッジを次世代へと継承できるようになります。
結果として、個人の能力に依存しない、より強固で持続可能な組織へと進化できるでしょう。
エムニへの無料相談のご案内
エムニでは、製造業をはじめとする多様な業種に向けてAI導入の支援を行っており、企業様のニーズに合わせて無料相談を実施しています。
これまでに、住友電気工業株式会社、DENSO、東京ガス、太陽誘電、RESONAC、dynabook、エステー株式会社、大東建託株式会社など、さまざまな企業との取引実績があります。
AI導入の概要から具体的な導入事例、取引先の事例まで、疑問や不安をお持ちの方はぜひお気軽にご相談ください。

引用元:株式会社エムニ