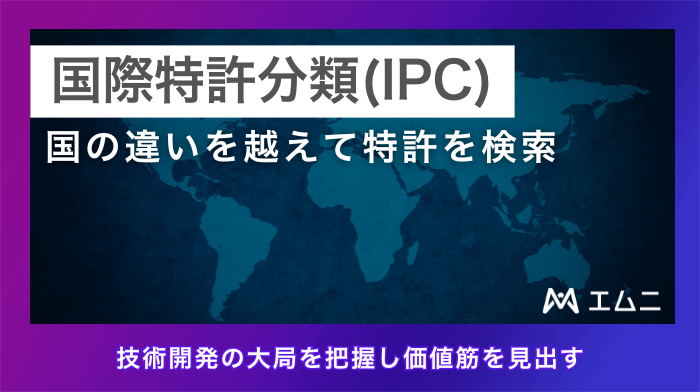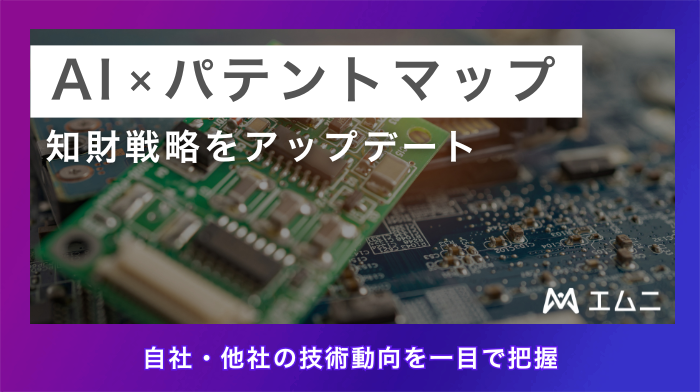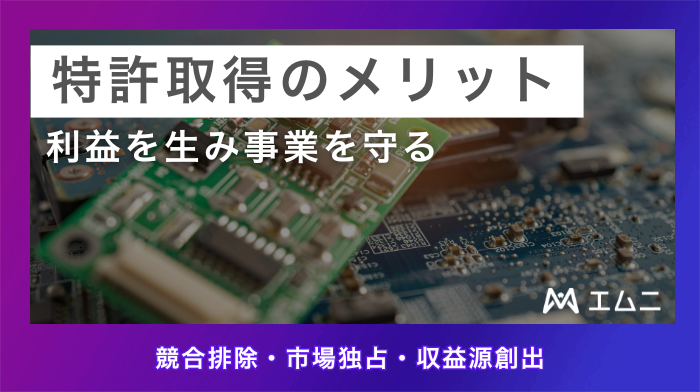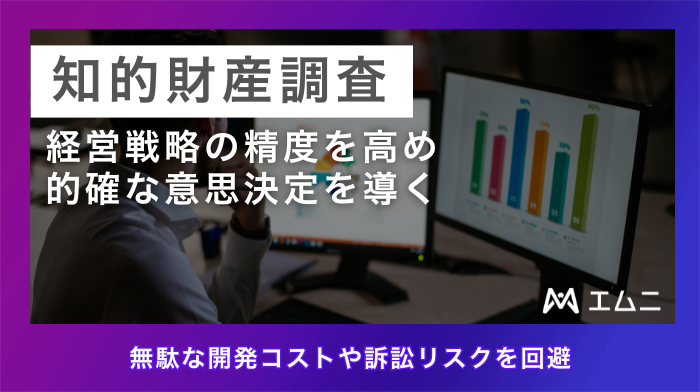属人化の解消|業務依存から脱却して組織力を強化する方法
2025-07-30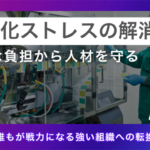
仕事の属人化ストレスを解消|原因や取るべきアクションを徹底解説
2025-08-22属人化とは?組織課題を解消し、持続可能なビジネスを築く方法を解説
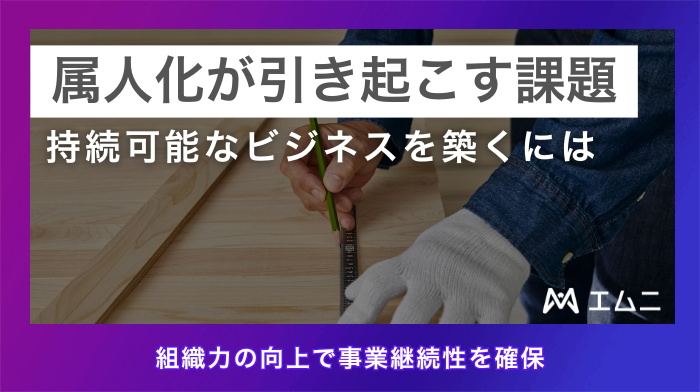
近年のビジネス現場では、「属人化」という言葉をよく耳にします。これは、特定の業務が特定の担当者に依存しすぎている状態を指し、組織にさまざまなリスクをもたらします。そこで注目されているのが、属人化の定義や原因、影響、そして効果的な解消方法です。
本記事では、属人化が引き起こす課題と、それを解消することで得られるメリットをわかりやすく解説します。変化に強く、持続可能な組織づくりのヒントとして、ぜひご覧ください。
属人化とは
属人化とは、特定の業務が特定の担当者の知識や経験に依存し、その人以外には業務内容や進め方がわからない状態を指します。この状態では、その担当者が不在になると業務が滞ったり、トラブル時に他者が対応できなくなったりするなど、組織運営に大きなリスクをもたらすのです。
特に問題となるのが「ブラックボックス化」でしょう。業務の手順や判断の根拠が共有されておらず、他の社員が内容を把握できない状況では、業務改善や人材育成が進まず、企業全体の成長を妨げてしまいます。
属人化と混同されやすいのが「スペシャリスト」という存在です。優れたスペシャリストは知識を他者と共有し、業務の継続性を確保します。一方で、属人化は知識の共有が行われません。
実際には誰でも対応可能な業務であるにもかかわらず、情報が閉ざされていることで「その人にしかできない仕事」に見えてしまう場合があります。
根本的な課題は、情報とプロセスの共有が行われていないことにあるでしょう。これは個人の問題というよりも、マニュアル整備の遅れや情報共有を促さない組織文化など、構造的な問題が背景にあるのです。
2024年の調査でも、情報システム部門の大きな悩みとして属人化が挙げられており、多くの企業に共通する課題であることが明らかになっています。
引用元:全国情シス実態調査 2024 – IIJ 法人IT調査レポート
属人化を放置してしまうと、業務の停滞や品質のばらつき、復旧対応の遅れなど、さまざまなリスクを招く恐れがあります。しかし、業務の標準化やマニュアル化を進めることで、誰でも業務を再現できる体制が整い、変化に強く持続可能な組織を実現できるはずです。
▼ 形式知化の手法を知りたい方はこちら
形式知とは?暗黙知との違い、メリット、形式知化の手法を詳細に解説 – オウンドメディア
参考記事:
なぜ属人化は起こるのか?主な原因と背景
属人化は、単一の原因で発生するものではなく、複数の要因が複雑に絡み合って進行することが一般的です。
ここでは、属人化が起こる主な原因と背景について詳しく解説していきます。
業務の専門性や複雑性
専門性が高い業務では、作業の進め方や判断基準を他人に説明するのが難しく、担当者にノウハウが集中しやすくなります。たとえば、社内システムの保守管理を一人のエンジニアが担っている場合、その人だけが使い方や設定方法を理解しているため、他の社員では対応できません。
また、担当者が独自に作った複雑なExcelマクロや分析ツールなども属人化の一因です。ファイルの構造や計算ロジックが共有されていなければ、他の人が修正や再利用できず、ミスやトラブルが起きたときに手が出せなくなります。
こうした状態は、業務の「ブラックボックス化」を引き起こす原因となり、担当者が不在になるだけで業務が止まってしまうリスクが高まるのです。特に退職や異動があった際には、引き継ぎに大きな時間がかかり、品質やスピードの低下にもつながります。
このリスクを防ぐには、業務内容を可視化し、マニュアル化や標準化を進めることが必要です。
たとえば、定期的に業務フローをドキュメントにまとめたり、社内のナレッジ共有ツールでノウハウを公開することで、「この人にしかできない」作業をなくし、チーム全体で業務を支えられる体制を築くことができます。
参考記事:
情報共有の不足とマニュアル化の不十分さ
属人化は、業務のやり方やノウハウが文書化されていないことで起こります。
OJTや口頭伝承だけに頼ると、知識が担当者の頭の中に留まり、他の人が業務を再現できません。結果として、その人がいないと仕事が回らない状態になります。
たとえば、ある営業担当が商談の進め方や提案の工夫を共有せずに1人で抱えていれば、異動や退職の際に大きな混乱を招きます。マニュアルや引き継ぎ資料がないことで、業務がブラックボックス化し、周囲の人間は支援も改善もできません。
日本企業では、こうした傾向が顕著で、経産省の調査では、OJT以外の人材投資が先進国の中で特に少ないとされています。つまり、情報共有の文化や仕組みが整っておらず、結果として属人化が当たり前になっているのです。
この状況を放置すると、業務が見えず、改善も教育も進まず、ますます属人化が深まるという悪循環に陥ります。だからこそ、業務を言語化し、マニュアル化・共有する仕組みづくりが不可欠なのです。
▼ 高齢化の現場課題を知りたい方はこちら
製造業における高齢化|深刻な問題とその解決策
参考記事:Society 5.0 時代のデジタル人材育成に関する検討会
多忙な業務とリソース不足
業務が忙しく、人手も限られている状況では、「この人に任せた方が早い」と判断され、仕事が特定の担当者に集中しやすくなります。短期的な効率を優先するこの選択は、一時的には合理的に見えても、マニュアル作成や人材育成の時間が取れず、結果的に業務の標準化が後回しにされてしまいます。
こうした環境では、業務の進め方が本人にしか分からない状態になりやすく、属人化が深刻化していくでしょう。
2025年の調査でも、日本企業は人材投資が先進国の中で特に少なく、DXに取り組む企業の多くが「育成予算の不足」や「育成方針が不明確」といった課題を抱えていると報告されています。
引用元:Society 5.0 時代のデジタル人材育成に関する検討会
こういったリソースが不足していることにより、スキルを共有・伝達する余裕がなくなり、結果として特定の人に業務が固定化される傾向が強まるのです。
このような属人化は、担当者が退職したときの業務停止リスクや、改善の停滞、業務の質のばらつきといった長期的な非効率を招きます。本来であれば、時間をかけて業務の標準化や人材育成を行うことで、組織全体の生産性を底上げできるはずです。
しかし、目先の効率を優先するあまり、その機会が失われています。短期的な合理性が、長期的には非効率とリスクを生み出す。
この構造を断ち切るには、属人化を放置せず、人材育成や業務の可視化に計画的に投資する姿勢が不可欠です。個人の努力に依存せず、組織全体で「共有する仕組み」を持つことが、持続的な成長につながります。
▼ 製造業の人手不足問題を知りたい方はこちら
製造業の人手不足|浮き彫りになる問題とその解決策
参考記事:Society 5.0 時代のデジタル人材育成に関する検討会
組織文化と個人の意識
属人化の背景には、業務の難しさや手順の不明瞭さだけでなく、組織文化や評価制度、個人の意識といった見えにくい構造的な要因が深く関わっています。
たとえば、「自分にしかできない仕事が評価される」といった空気や、「専門分野を囲い込む方が得だ」という認識があると、社員は知識を共有しようとしません。
報告では、日本企業ではスキル習得や貢献の基準が不明確で、評価制度がブラックボックス化しており、それが学習意欲や情報共有の動機を下げているとされています。
スキルを他人に教えるよりも、自分だけの価値として囲い込んだ方が得だと考える傾向が、知識の独占を助長しています。情報共有や標準化への貢献が評価対象になっていないことも、それを後押ししているのでしょう。
また、従業員側にも問題があります。熱意やエンゲージメントの低さから、他者と協力しようとする意識が薄れがちです。キャリアパスが見えず、スキルアップしても評価につながらないと感じている人が多い現状では、自分の仕事以外に関心を持つ余裕がないのも無理はありません。
属人化は、こうした制度や文化、個人の意識が複雑に絡み合って起こります。業務が忙しくてマニュアルが作れず、マニュアルがないことでさらに属人化が進む、この悪循環を断ち切るには、業務改善だけでなく、評価制度の見直しやスキル共有を促す文化づくりが欠かせません。
つまり、属人化の解消は経営層の関与なしには難しく、人事制度や組織開発の視点から中長期的に取り組む必要があります。情報共有は従業員の善意に頼るのではなく、制度として仕組むことが求められています。
参考記事:Society 5.0 時代のデジタル人材育成に関する検討会
属人化が組織にもたらす深刻なリスク
属人化は、一見すると特定の業務がスムーズに回っているように見えるかもしれませんが、放置すると組織に深刻なリスクと多大なデメリットをもたらすでしょう。
ここでは、属人化が組織に及ぼす具体的なリスクについて詳しく解説します。
業務の停滞・遅延と事業継続性の危機
業務が特定の担当者に集中していると、その人が急に休んだり退職したりした際、他の社員が対応できず業務が止まるリスクがあります。
たとえば、経理担当が急に辞めて支払い業務が滞り、取引先に迷惑をかけたという事例も見られます。こうした業務の停止は、顧客対応の遅れや納期ミスにつながり、企業の信用を失う原因となるでしょう。
とくに総務、人事、経理、クレーム対応など、正確さと一貫性が求められる業務が属人化している場合、その影響はさらに深刻になります。担当者の退職によってノウハウや顧客との関係が断たれてしまい、組織にとって致命的な損失につながる可能性があるのです。
内閣府の調査によれば、中小企業が事業継続計画を策定しない理由の上位には「人材不足」や「ノウハウ不足」が挙げられています。さらに、計画を策定した企業でも訓練や見直しが不十分なケースが多く、実際の対応力が伴っていないのが現状です。
不測の事態に対して柔軟に対応できる体制を築くためには、業務の属人化を解消し、誰が対応しても仕事が止まらない仕組みを整える必要があります。属人化の放置は、単なる業務効率の問題にとどまらず、企業の存続をも脅かしかねないリスクとなるでしょう。
参考記事:
品質のばらつきと顧客満足度の低下
標準化された手順やチェック体制が整っていない属人化された業務では、誰が担当するかによって成果物の品質に差が出やすくなります。またスキルや判断基準が個人に依存しているため、品質が安定せず、ミスの発見も遅れがちです。
さらに、日本企業では従業員のスキルが明確に可視化されておらず、人材配置のミスマッチが起こりやすい状況にあるといえるでしょう。これがパフォーマンスの差や品質のばらつきを生み出す要因となっているのです。
加えて、評価制度の曖昧さやスキルアップへの動機づけの弱さも、品質のムラに拍車をかける要因です。
業務内容が共有されず、外部から見えにくくなると、ブラックボックス化が進行します。その結果、問題の早期発見や改善が難しくなり、組織全体の対応力も低下してしまうでしょう。実際、ブラックボックス化した業務やシステムは、企業の成長にとって「致命的な足かせ」とも指摘されています。
参考記事:
知識・ノウハウの喪失と組織成長の停滞
業務が属人化すると、業務のやり方や判断基準が担当者個人に依存するため、組織内での知識共有が困難になります。
たとえば、ベテラン社員が長年の経験に基づく独自の手順で業務を進めていた場合、それがマニュアル化されていなければ、異動や退職によってノウハウごと失われてしまうのです。その結果、他の社員が同じ水準で業務を再現できず、品質の低下や対応の遅れを招く要因となります。
2025年版デジタル人材白書によれば、ITエンジニアの48.9%が「自らのスキルや知識が時代遅れになることに不安を感じている」と回答しています。企業側も「必要なスキルと現場のスキルに大きなギャップがある」と認識している状況です。
にもかかわらず、多くの企業では人材への投資が十分とは言えず、社内でもスキルが可視化されていないケースが目立ちます。業務の全体像が不透明なままでは、知識の蓄積や更新が進まず、改善活動も停滞しがちです。
特に影響を受けやすいのが若手社員です。OJTが「なんとなく見て覚える」といった非体系的な状態で行われている場合、明文化されたノウハウが存在せず、若手が何をどう学ぶべきかが不明確になります。その結果、成長機会が限定されてしまうのです。
たとえば、データ分析業務を担う若手社員が「どのデータをどのように使えばよいのか分からない」と感じても、周囲に体系立てた知見がなければ、実践的な成果にはつながりにくい状況となります。
このような属人化の弊害に対し、欧米ではスキルベース組織への転換が進んでいます。すべての社員のスキルを共通言語で定義し、可視化・蓄積することで、適切な人材配置や育成、知識の再利用が可能となるでしょう。
参考記事:
担当者への過度な負担と離職リスク
業務が属人化すると、特定のスキルや経験を持つ社員に業務が集中しやすくなります。
その結果、担当者は長時間労働を強いられ、休暇も取りにくくなり、慢性的な疲労やストレスを抱えるようになるのです。こうした状況は、心身の健康リスクを高めるだけでなく、最終的には燃え尽きや離職の引き金となる可能性が高まるといえます。
実際、DX推進に必要な人材については「質と量の両面で不足している」と資料に明記されています。この構造的な人手不足こそが、特定の従業員への業務集中という属人化を生み出す要因になっているのです。
また、日本の企業では人材評価やキャリアパスが不透明であることが多く、努力やスキルが正当に評価されにくい傾向があります。
年収の上昇理由や役職登用の基準が「よくわからない」と感じる社員が他国に比べて多いという調査結果もあります。このような評価制度の曖昧さは、業務の重さに見合った報酬や承認が得られない不満を生みやすいのです。
その結果として、担当者のモチベーションが低下し、職場へのエンゲージメントも下がり、離職リスクが高まります。担当者が抜けた後に業務を代替できる人材がいなければ、引き継ぎが機能せず業務が滞る危険も無視できません。
さらに、こうした属人化と負担集中は、企業全体の業務効率や生産性の低下にも直結するでしょう。
たとえば、データ活用の現場では専門人材の不足が業務の偏りを生み、十分な分析や施策立案が行えないことがあります。その結果、米国と比較して「ビジネス成果の実感が3分の1以下」といった数値にも表れています。これは、単なる人手の問題ではなく、企業の競争力や将来の成長可能性に関わる深刻な課題なのです。
属人化を放置すれば、特定の社員に業務が依存し続け、業務品質や組織全体の持続性が脅かされます。結果的に、個人の離職だけでなく、顧客満足度の低下や企業全体の損失につながるリスクが避けられない状況となるでしょう。
参考記事:
不正やミスの発見の遅れ
業務が一部の担当者に依存している状態では、他の社員がその業務の中身を詳しく把握していないため、ミスや不備が発生しても周囲が気づきにくくなります。
たとえば、日常的に使われている独自の計算式や判断基準がブラックボックス化している場合、それが誤っていても誰も疑問を持たず、結果的に誤情報が外部に出たり、取引先とのトラブルに発展する可能性があります。
こうした属人化された状態では、業務が可視化されておらず、チェックやレビューの仕組みが機能しにくいのが実情です。そのため、不正が発生しても発見が遅れる傾向が強まります。
業務が見える化されていないことで、本人以外がその妥当性を検証できず、ミスが繰り返される土壌が生まれてしまうのです。不正の多くは、第三者の目が届かないところで行われ、早期に発見されないことによって被害が拡大するケースも少なくありません。
特に経理・購買・契約管理などの重要業務では、複数人による相互チェックが機能しない場合、数年にわたって誤処理が放置されたり、悪意ある行為が発覚しないまま進行してしまうかもしれません。
実際、組織で発生する不正の多くは「見逃された」ことで深刻化しており、仕組みではなく「人」に依存した管理体制では、早期発見や予防が困難であるとされています。
不正やミスは一度発生すると、信頼の失墜や損害賠償、従業員の士気低下など、組織の各方面に悪影響を及ぼすおそれがあります。だからこそ、属人化の解消と業務プロセスの可視化、そして誰でも確認・改善できる体制の構築が、健全な組織運営において不可欠となるのです。
参考記事:
属人化を解消することで得られるメリット
属人化の解消は、単なる問題解決に留まらず、組織全体に多岐にわたるポジティブな影響をもたらします。
これは、業務効率化、人材育成、リスク管理、さらにはDX推進といった組織全体の改善と成長を促す、組織変革の起爆剤となり得るでしょう。
▼ 製造業DXの全体像を知りたい方はこちら
製造業のDXとは?重要性や成功までのロードマップを徹底解説
業務効率化と生産性向上
かつて政府機関の業務には、特定の職員に依存した属人化の問題が深く根を張っていました。
たとえば、LAN端末やネットワーク機器の管理、予算要求や調達業務、復旧対応など、日常的なIT関連業務が限られた担当者に集中し、作業がブラックボックス化。属人的な知識に頼ることで、職員の負担は大きく、引き継ぎも困難で、組織全体の柔軟性や持続可能性が損なわれていました。
こうした課題に対し、政府は「ガバメントソリューションサービス(GSS)」の導入を本格化します。GSSとは、各府省庁に分散していたIT業務を共通サービス化し、専門の組織が一元的に運用・保守を担う仕組みです。
これにより、特定の個人に集中していた業務負荷が分散され、職員はより本質的な業務に注力できるようになったのです。情報システムの標準化も進み、属人化していた知識がシステム内に集約されたことで、ナレッジを組織全体で共有できるようになり、業務の透明性と継続性が大きく向上しました。
また、業務フローの見直しとデジタル技術の導入も並行して進められています。たとえば、福岡県古賀市では道路橋梁点検にドローンを導入し、従来の人手による近接目視を効率化。委託費の削減や作業時間の短縮に成功し、住民の利便性向上にもつながったと言えるでしょう。
沖縄県糸満市では、産後ケア申請のオンライン化によって、窓口に出向く必要がなくなり、申請業務の迅速化が実現しました。福島県南相馬市では、作付確認に衛星画像を活用することで、現地調査を大幅に削減することに成功しています。
さらに、マニュアルの読み解きや問い合わせ対応に手間がかかっていた業務では、生成AIを活用したヘルプチャットの導入も進んでいます。出張旅費精算システム「SEABIS」では、AIが膨大なマニュアルの中から適切な回答を返す仕組みが整えられつつあり、会計担当職員の負担軽減にもつながっているのです。
引用元:各府省庁DXの更なる効果発現に向けた依頼事項について
このように、属人化という構造的課題に真正面から取り組み、業務の標準化とデジタル活用を進めた結果、業務効率は飛躍的に向上しました。特定の個人に依存しないかたちで、組織全体で知識や仕組みを共有する体制が整いつつあり、政府機関の生産性は着実に高まりつつあるといえます。
参考記事:各府省庁DXの更なる効果発現に向けた依頼事項について
組織全体のスキルアップと成長
組織が持続的に成長するためには、スキルやノウハウを特定の個人に依存せず、全社員で共有・活用できる体制の構築が不可欠です。
実際、経済産業省の調査によれば、DX注目企業の100%が経営層を含めた全社員向けにリスキリングなどの教育制度を整備していると回答しています。このような仕組みにより、若手社員にも学びと成長の機会が広がり、組織全体のスキルの底上げが着実に進んでいる状況です。
また、94%の企業がスキル評価に基づく人事制度や実践的な人材配置を導入しており、習得したスキルを適切に活かせる環境が整いつつあります。社員が自らの希望に応じてキャリアを選び、長期的に成長していける土壌が築かれていると言えるでしょう。
業務の進め方に関しても、DX銘柄企業の97%が「行動指針」を策定・公開しており、従業員が迷わず行動できるような共通基準が設けられています。これは実質的にマニュアルの役割を果たしており、属人化を防ぎながら誰もが業務を遂行できる環境づくりに貢献しているのです。
こうした取り組みは、新たな挑戦や業務改善にも直結しています。DX銘柄企業のすべてが既存事業の変革および新規事業の創出に取り組んでおり、その効果を実感しているとされています。
スキルの共有と活用が組織の変革力を支える原動力となっている点は、非常に注目すべきポイントです。スキルが組織全体に浸透することで、特定の個人に依存しない、柔軟で持続可能な体制が築かれているのです。
参考記事:デジタルトランスフォーメーション調査2025 の分析
事業継続性の確保とリスク低減
属人化を解消することは、組織の事業継続性を高め、さまざまなリスクを未然に防ぐうえで極めて有効です。
特定の業務が特定の人にしか分からない状態では、急な退職や長期休職、人事異動といった予期せぬ事態が発生したとき、業務の停滞や中断につながりかねません。
属人化をなくし、業務の知識やプロセスが複数人に共有されていれば、こうした突発的な人員変動が起きても、組織は柔軟に対応し、安定的な運営を続けられるでしょう。
実際、国が中小企業に推奨する事業継続計画(BCP)の考え方も、属人化のリスクと深く関係しています。
BCPでは、災害や事故などで通常の体制が維持できなくなっても事業を継続するためには、「人材の偏り」を排除し、誰が欠けても対応できる柔軟な体制が不可欠だとされています。
これは日常的な人事リスクにも当てはまり、特定の人に業務が集中している状態では、平時であっても大きな脆弱性を抱えることになるのです。
また、属人化が解消されることで、情報の透明性が増し、業務の可視化が進みます。これにより、隠蔽やミスの温床が減り、不正やヒューマンエラーの早期発見にもつながります。
さらに、個人への過度な負担が軽減されることで、ストレスや疲労による健康問題、離職リスクの抑制にも寄与し、組織全体の安定性が高まります。
属人化の解消は、単に効率を上げるためだけでなく、予測不能なリスクに強い、しなやかで持続可能な組織づくりに欠かせない土台となるのです。
参考記事:中小企業庁
労働環境の改善と従業員満足度の向上
属人化の解消は、組織の労働環境を整え、従業員の満足度を高めるうえでも有効な手段です。
特定の社員に業務が集中している状態では、その社員の残業が常態化し、過重労働による健康リスクやモチベーションの低下を引き起こすおそれがあります。
一方で、業務が標準化され、誰もが対応できる体制が整えば、業務負担の偏りが緩和され、複数人で分担できる仕組みが可能となります。その結果、長時間労働の抑制にもつながり、ワークライフバランスの改善にも寄与するのです。
特に近年では、フレックスタイム制やテレワーク、勤務間インターバル制度など、多様な働き方が広がりを見せています。こうした制度については、厚生労働省も実態を把握するための調査を行っており、国としても関心の高い領域だといえるでしょう。
制度の整備に加えて属人化を解消することで、従業員が柔軟に働ける環境が整い、働きやすさと満足度の両立が実現できます。
さらに、業務の透明化が進むことで社内の情報共有が活性化し、チーム間の連携や相互理解も深まっていきます。属人化された業務は、担当者以外にとって「見えない仕事」となりやすく、孤立感や不信感の原因にもなりかねません。
反対に、業務内容や進捗がオープンになれば、自然と相互支援が生まれ、職場の風通しがよくなる環境が形成されます。このような風土は従業員の帰属意識を高め、組織に対するエンゲージメントの向上にもつながるのです。
属人化の解消は、単なる業務効率化にとどまりません。組織全体の働き方を見直し、より持続可能で人に優しい労働環境を実現するための重要なステップだといえるでしょう。
参考記事:【2024年度実施・一般統計調査】 労働時間制度等に関する実態調査について
DX推進への貢献
業務の標準化と可視化は、DXを推進するうえで不可欠な基盤です。
特定の個人に業務が依存している状態では、情報の共有が進まず、業務のデジタル化も停滞しがちになります。
政府が推進するガバメントクラウドやGSSは、こうした属人化を解消し、システムや業務の共通化・効率化を図る仕組みです。
この取り組みによって、従来は各府省庁が個別に管理していたシステム運用や端末管理、問い合わせ対応といった業務が統一され、担当者の負担軽減とコスト削減の両立が進みつつあります。
また、生成AIの導入事例としては、旅費精算システム「SEABIS」の操作マニュアルをAIが検索・回答することで、職員への問い合わせ対応が大幅に削減されました。属人化していた業務が仕組みに置き換えられた好例といえるでしょう。
これは、RPAやナレッジマネジメントと同様に、再現性のある業務をデジタルで共有・自動化する実践的な取り組みです。
属人化の解消は、単なる業務改善にとどまりません。情報を組織全体で活用できる体制を築くことにつながり、DXを根本から支える要素となります。
業務が誰にでも把握・実行できる状態になれば、部門間の連携が強化され、組織内の壁が低くなり、結果としてイノベーションの起こりやすい風土が醸成されるのです。DXの成否は、こうした属人化の克服から始まるといっても過言ではありません。
参考記事:各府省庁DXの更なる効果発現に向けた依頼事項について
属人化を解消するための具体的なステップと対策
属人化の解消は一度きりの対応ではなく、組織の変化に応じて継続的に見直すべきプロセスです。
マニュアル化だけに頼らず、業務全体を標準化・改善し続けることで、組織は柔軟で強靭な体制へと進化します。これは、持続的な競争力を維持するために欠かせない取り組みです。
現状分析と属人化業務の洗い出し(業務の可視化)
属人化を解消するには、まず業務の実態を正確に把握することが出発点です。
業務フローを可視化し、誰が・何を・どのように行っているかを明らかにすることで、特定の担当者に依存している作業や非効率な手順を発見できます。とくに、属人的な判断やノウハウに支えられている業務ほど、ボトルネックやリスクの温床となるため、見過ごせません。
このプロセスでは、現場担当者への丁寧なヒアリングが欠かせません。実務を担う人こそが業務の「勘所」や判断基準を最も深く理解しており、それを言語化することが属人化の可視化に直結します。また、手順の難易度や汎用性を明確にすることで、他の人材への引き継ぎや再配置も可能になります。
洗い出した業務は、重要度と属人化の度合いを軸に評価し、優先順位をつけて対応していくことが効果的です。
たとえば、熟練技術者の経験に依存している製造プロセスや、マニュアル化されていないカスタマーサポート、担当者しか対応できない社内トラブル対応などは、業務継続性への影響が大きいため、早期に着手すべき対象です。
こうした分析は、一度行えば終わりではなく、組織の成長や環境の変化に応じて継続的に見直す必要があります。業務の可視化と属人化の特定は、効率化や標準化の第一歩であり、組織が柔軟かつ持続可能に成長するための礎になります。
参考記事:
業務の標準化とマニュアル作成(手順書、動画マニュアルなど)
属人化の解消には、まず特定の担当者に依存している業務を優先的に抽出し、それらを標準化することが不可欠です。
その鍵となるのが、業務手順やノウハウを整理・明文化したマニュアルの整備です。
マニュアルは、未経験の社員でも迷わず業務を再現できるように、具体的かつ平易な表現で作成する必要があります。単なる作業手順だけでなく、「なぜその工程が必要なのか」「どのような判断基準で進めるべきか」といった“勘所”まで言語化することで、実務における再現性が格段に高まります。
業務の全体像を把握するために、まず大まかな流れを示す概要版を作成し、その後、必要に応じて詳細な手順書へと掘り下げていく手法が有効です。この段階的な整理により、業務全体の構造が明確になり、改善点の抽出や業務最適化にもつながります。
視覚情報の活用も効果的です。図や写真を交えることで理解が深まり、さらに動画マニュアルを併用すれば、業務習得のスピードが向上します。特に、操作手順や動作の伴う業務では、動画は研修時間の短縮や新人教育の効率化に大きく寄与します。
マニュアル作成の過程では、曖昧な手順や個人に依存していた判断を洗い出し、それに代わる新しいルールや基準を定義することが求められるでしょう。この作業こそが、組織としての再現性と業務の品質安定を生む標準化の核心であり、結果として業務の属人化を抜本的に解消する基盤となります。
参考記事:
ITツール・システムの導入と活用
属人化を解消し、業務の効率化や情報共有の円滑化を実現するうえで、ITツールやシステムの導入は非常に有効な手段です。
これらは単に業務をデジタル化するだけでなく、組織全体で知識を共有し、標準化されたプロセスを構築するための土台ともなります。
たとえば、ナレッジマネジメントシステムや社内Wikiを活用すれば、属人的に蓄積されていたノウハウを形式知として整理・保存することができ、新人教育や引き継ぎの負担を大幅に軽減できるようになります。
RPAは帳票作成などの定型業務を自動化し、ヒューマンエラーの防止と業務時間の削減を同時に実現できる技術です。
また、業務の進捗や負荷状況を可視化するプロジェクト管理ツールは、特定の人材への依存状態を発見しやすくし、ボトルネックの早期発見と是正を促します。
参考文献:現場主導による 業務プロセス可視化ツール
クラウドストレージや文書管理システムを導入すれば、情報共有をリアルタイムで行うことが可能となり、部門間の連携も円滑に進められるようになります。
ERPの活用によって、見積書作成や申請といった業務が一元化され、各部門での入力作業やデータの重複が削減されるでしょう。これにより、全体としての業務効率が向上することが期待されます。
さらに、AIチャットボットを社内に導入すれば、業務上の問い合わせにリアルタイムで対応できる仕組みが整備され、従業員の生産性向上にもつながります。POSレジも、サービス業においては日々の販売・会計業務を効率化し、業務の標準化と仕組み化を支援する重要なツールです。
ただし、ITツールはあくまで手段にすぎません。その効果を最大限に引き出すためには、現場の理解と協力、活用ルールの整備、そして継続的な改善を支える組織文化の醸成が欠かせないのです。ITを活用した業務改革は、テクノロジーと人の運用が噛み合ってこそ、真の価値を発揮できます。
▼ DX成功のステップを知りたい方はこちら
製造業DXを成功させるための5ステップを解説 – オウンドメディア
▼ 生産計画xAIの活用事例を知りたい方はこちら
生産計画にAIを使うメリットとは?活用事例5選! – オウンドメディア
▼ 在庫管理システム×AI活用を知りたい方はこちら。
製造業向け在庫管理システム|特徴や生成AI活用を解説 – オウンドメディア
参考記事:
組織文化の醸成と人材育成
知識やノウハウを個人の中に抱え込む属人化を防ぐには、情報共有を前提とした組織文化の醸成が不可欠です。
業務プロセスの見える化や手順書の作成は、現場の知識を形式知として共有する第一歩であり、それが日常的なコミュニケーションの活性化にもつながります。
情報共有を促す風土を根付かせるためには、個人の業績だけでなく、改善提案やナレッジ共有といった「組織全体への貢献」も評価の対象とする制度への見直しが重要です。従業員が「自分の知識を共有することが評価につながる」と実感できれば、自発的な行動が生まれるようになるでしょう。
クロストレーニングの導入も、有効な手段の一つです。ジョブローテーションやメンター制度、ペアワークといった仕組みによって、個人が持つ知識を他者に伝える機会が自然と生まれ、特定の人にしかできない業務は徐々に減っていきます。
また、手順の難易度を設定し、誰でも取り組める業務に分解することで、スキルの均一化が図られ、属人化の解消にもつながるといえます。
業務手順書を活用した育成や、1on1ミーティング、OJTなどの教育制度を通じて、従業員の経験やノウハウを組織の資産として蓄積していくことが求められます。
これらの情報は静的なままでは意味を持ちません。現場からの提案を反映し、継続的に更新される仕組みによって初めて「使える知識」として活用されるのです。
こうした取り組みを組織全体に定着させるには、経営層が率先してその価値を発信し、現場と対話を重ねながら方向性を示す姿勢が不可欠です。経営者の言葉が現場の意識を動かし、「情報共有は評価される行動である」と実感されるようになれば、組織は継続的に進化していくはずです。
参考記事:
定期的な見直しと継続的な改善(PDCAサイクル)
属人化の解消は一度限りの取り組みではありません。
継続的に見直しを行いながら、段階的に改善を重ねていくことが求められます。業務の標準化を行ったあとも、現場で得られる新たな知見や改善提案を定期的に集約し、それをマニュアルや業務フローに反映していくことが重要です。
この継続的な改善を支える枠組みが、PDCAサイクルです。まず、現状分析(Plan)により業務の課題や属人化の要因を明らかにし、次に標準化・マニュアル化(Do)を通じて、誰でも実行可能な手順へと落とし込んでいきます。
その後、ITツールの導入やOJT、手順書を用いた教育によって人材育成を進めていきます(Check/Do)。さらに、定期的な手順書の見直しや内部監査によって改善点を洗い出し(Check)、それを次の改善計画(Action)に反映させるという流れです。
このサイクルを繰り返すことで、現場の知見を活かしたマニュアルの精度が向上し、形式知の質も高まります。
属人化の再発を防ぐとともに、現場のモチベーションや組織の柔軟性が育まれる効果も期待できるでしょう。改善提案制度やプロジェクトレビューの仕組みが整っていれば、従業員の声を継続的に反映することも可能となります。
PDCAサイクルを日常業務に組み込むことは、単なる文書管理にとどまらず、実効性のある業務改善を継続できる体制づくりに直結します。これは、組織全体の適応力と生産性の底上げを実現する、非常に実践的なアプローチだといえるでしょう。
参考記事:
業界別に見る属人化の課題と解決策
属人化の課題は、業界の特性によってその現れ方や解決策が異なります。
各業界が抱える固有の課題と、それに対する具体的な対策を理解することは、より効果的な属人化解消に繋がるでしょう。
▼ 業界横断の解決策を知りたい方はこちら
技能伝承とは?問題点、解決策、導入方法について徹底解説
製造業における課題と技術継承
製造業では、設計変更への迅速な対応、高品質と短納期の両立、人材不足といった課題が複合的に存在しています。とりわけ技術継承の停滞は、属人化をさらに深刻化させる要因となっているのが現状です。
2023年時点において、製造業の従業員数過不足DIはマイナス20.4と、依然として人手不足の傾向が強く見られます。若年層の就業者数も259万人と、横ばいの状態が続いています。
加えて、技術伝承が不十分なままベテランに業務が集中し、「教える時間も人もいない」という状況が、中小企業を中心に広がっているのです。
指導人材の不足を課題とする製造業事業所は6割を超えており、小規模事業所では、技能を体系的に継承する取り組み自体が困難なケースも少なくありません。
こうした属人化の温床は、廃棄物管理など専門性の高い業務で特に顕著であり、特定の社員の知識や判断に業務が依存するリスクが高まっているといえるでしょう。
このような状況を打開するためには、ベテラン社員の技能や暗黙知を形式知として残す仕組みの構築が求められます。たとえば、熟練者のノウハウを映像や文章で記録し、動画マニュアルとして整備すれば、新人が短期間で戦力化されるだけでなく、品質の安定にもつながるのです。
さらに、標準化と可視化を同時に進めることで、教育担当者が不在の場面でも新人が自走できる環境を整えることが可能となります。
加えて、生産管理システムの導入により、設計・営業・製造の情報を一元化し、属人性を排除しながら全体最適の視点で業務を判断できる体制を築くことも効果的です。類似図面の検索や再利用が可能なシステムを導入することで、設計の迅速化や手戻りの削減につながり、設計者の負担軽減にも寄与します。
実際に、日産自動車ではナレッジマネジメントシステム「V-3P」を導入し、技術者の知識を再利用可能な形で共有することで、設計変更の85%削減、開発コスト30%以上削減という成果を上げています。技術継承をシステムで支える体制の構築こそが、製造業の持続的成長を支える鍵となるのです。
▼ 若者離れ対策を知りたい方はこちら
製造業の若者離れ|原因や効果的な対策を解説
参考記事:
サービス業における顧客対応と品質均一化
サービス業では、特定のスタッフに業務が集中する属人化が課題とされており、不在時の対応力の低下や品質のばらつきにつながる可能性があります。
人手不足が慢性化する中、このような状況は業務の停滞や人材育成の遅れを引き起こし、経営上のリスクにもなりかねません。
この属人化を解消するうえで有効なのが、業務の可視化と標準化です。
たとえば製造業の分野では、熟練者のノウハウを形式知として蓄積・共有する仕組みが導入されており、同様の考え方はサービス業にも応用できます。株式会社旭ウエルテックでは、熟練職人の知識を「トラの巻」としてデータ化し、若手への技能継承と業務の平準化を実現しています。
また、北海道ワインではブドウ受入作業をデジタル化し、従来の手作業や口頭伝達に依存する運用から脱却しました。リアルタイムでの情報共有を実現したことで、標準的な作業が可能となり、マニュアルの整備や人材育成の効率化にもつながっています。
引用元:ものづくり基盤技術の振興施策
業務の見える化を支える仕組みも重要です。たとえば長島製作所では、生産実績や不良率を自動で記録し、工程ごとの効率や品質を客観的に把握できるようにしています。こうした可視化は、改善の指針を明確にするうえで大きな意味を持つといえるでしょう。
属人化の解消は、単なる引き継ぎのしやすさを目的とした施策ではありません。誰もが一定の品質で業務を遂行できる体制を整えることで、組織の事業継続性を高める戦略的な取り組みとなるのです。特定の人材に依存しない組織は変化に強く、持続的な成長を遂げる可能性も高くなります。
参考記事:
IT・システム開発における専門性と情報共有
IT・システム開発の分野では、プログラミングや広告戦略の立案など専門性の高い業務が多く、特定の担当者に依存する属人化が起こりやすい傾向があります。
複雑な設計や独自の開発手法が共有されず、業務がブラックボックス化することが大きなリスクです。
実際、多くの企業で部門ごとにカスタマイズされたシステムが構築されており、その内容を把握しているのはごく一部の担当者に限られるケースが少なくありません。経営層がIT戦略を現場任せにしていることも、知識の偏在を加速させています。
この属人化を解消するには、まず業務を棚卸しし、標準化とマニュアル化を進めることが必要です。旭ウエルテックでは、ベテラン職人の技術や経験をデータベースに記録し、誰でも検索・活用できるナレッジ共有システムを自社開発しています。これにより技能の継承と業務の平準化が実現されました。
また、業務責任や判断権限を特定の人物に集中させず、分散して実行スピードを高める体制づくりも有効です。現場に裁量を与えることで、属人化の回避と同時に現場力の強化にもつながります。
さらに、ITツールの活用は情報共有の促進に不可欠です。長島製作所では、社員の作業効率を可視化するシステムや、社内連絡・休暇申請をアプリに集約する取り組みにより、全社的な業務の見える化とデジタルリテラシーの底上げを実現しています。
属人化を防ぐには、「可視化」「標準化」「IT活用」「人材育成」の仕組みを組み合わせて全社で取り組むことが重要です。属人化の解消は、一部の個人だけでなく、組織全体の持続的な成長と安定につながる鍵となります。
承知いたしました。エムニが開発しているAIインタビュアーについて、ご指定の流れでご紹介します。
エムニでは、熟練工の持つ暗黙知や技能をAIとの対話で抽出・継承するAIインタビュアーを開発しています。技能伝承にかかる工数を約80%削減し、属人化を防ぎ、教育・育成コストを削減することが可能です。
ご興味のある方は、ぜひお問い合わせください。
まとめ
属人化とは、特定の業務が特定の人に依存し、他の人が内容を把握できない状態です。これにより、業務停滞やミスの見逃し、ノウハウの喪失など多くのリスクが生じます。その背景には情報共有不足や業務の煩雑さ、組織文化などがあります。
属人化を解消すれば、業務効率化、スキルの底上げ、事業継続力の向上など、多くのメリットが得られます。そのためには、業務の可視化・標準化、IT活用、情報共有を促す文化づくり、継続的な見直しが不可欠です。
属人化対策は一時的な施策ではなく、変化に強い組織をつくるための継続的な取り組みです。今こそ、組織全体で改善を進めることが求められています。
エムニへの無料相談のご案内
エムニでは、製造業をはじめとする多様な業種に向けてAI導入の支援を行っており、企業様のニーズに合わせて無料相談を実施しています。
これまでに、住友電気工業株式会社、DENSO、東京ガス、太陽誘電、RESONAC、dynabook、エステー株式会社、大東建託株式会社など、さまざまな企業との取引実績があります。
AI導入の概要から具体的な導入事例、取引先の事例まで、疑問や不安をお持ちの方はぜひお気軽にご相談ください。
引用元:株式会社エムニ