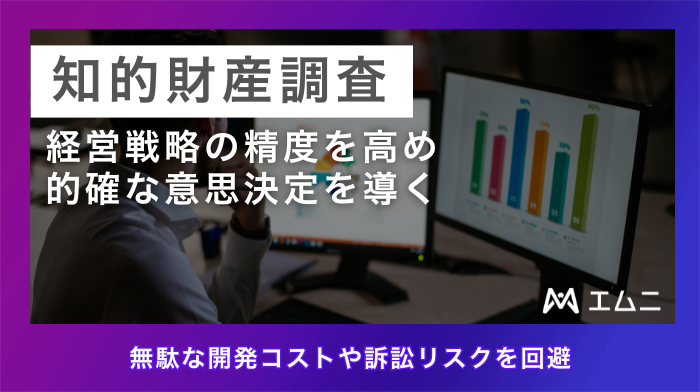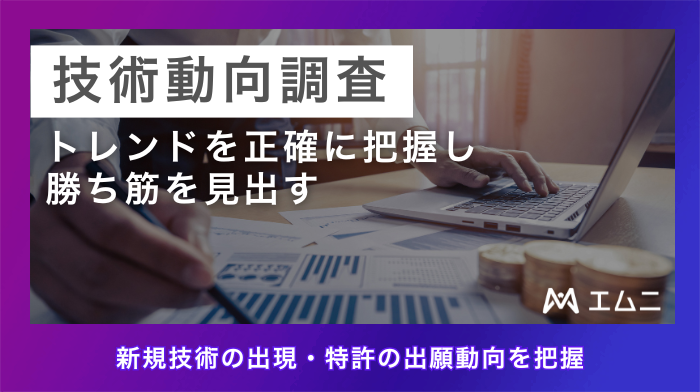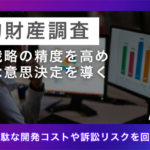
知的財産調査|目的、種類、実践方法まで徹底解説
2025-06-29特許取得のメリット・デメリット|利益を生み事業を守る知財戦略
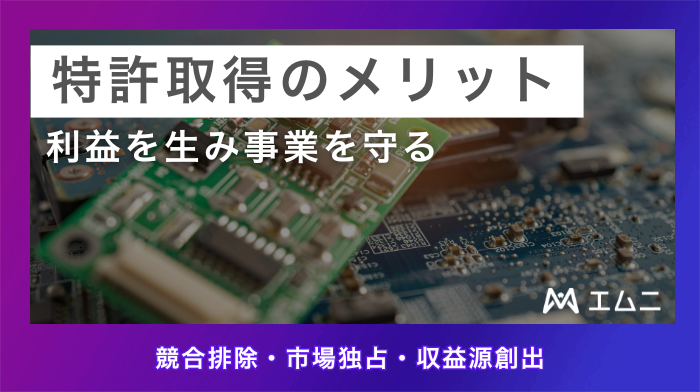
競争が激しい現代、独自の技術やアイデアをどう守り、成長に活かすかは重要な課題です。特許は、その有力な手段のひとつです。
ただし、特許にはメリットだけでなく、コストや情報公開といった注意点もあります。自社の事業戦略と照らし合わせて、出願すべきかどうかを慎重に見極めなくてはなりません。
本記事では、特許の利点・リスク、そして出願判断の基準までをわかりやすく解説します。
特許制度の基本|ビジネスにおける権利の重要性
特許とは、たとえば「バッテリーの充電効率を高める新技術」や「AIを使った画像処理アルゴリズム」など、技術的なアイデア(発明)に対して、国が発明者に与える20年間の独占権です。
この間、他社がその技術を勝手に製造・販売・使用することは法律で禁止されます。違反すれば、損害賠償や差止め請求が可能です。
一方で、発明内容は出願から1年6ヶ月後に公開されます。これにより、他社はその技術を参考にして新たな製品を開発でき、産業全体の成長につながる仕組みになっています。
特許は、製品やサービスを模倣から守るだけでなく、ライセンス収入を得たり、交渉材料として使ったりできる経営資源です。たとえば、特許を持つ中小企業が、大手企業と技術提携や買収交渉を進めるケースもあります。
技術を権利化することで、単なるアイデアがビジネスの武器になるのです。
▼ 参入障壁を築くための特許戦略はこちら
企業価値を創る知財戦略|特許ポートフォリオの構築・分析・活用
特許を取得する4つのメリット
特許を取得するメリットの1つとして、製品を独占的に販売でき、他社との差別化によって収益を上げることができます。
このほかにも、特許にはさまざまな利点があり、ビジネスにどのように役立つのか、4つの具体的なメリットをご紹介します。
競合排除・市場独占
特許権は、発明に新規性や非自明性、産業上の利用可能性が認められた場合に、出願人に与えられる排他的な法的権利です。この特許権は設定登録から原則として20年間有効であり、その期間中、権利者は当該発明を独占的に商業利用できます。
つまり、他者による無断の製造や販売、使用を法的に差し止める力を持ち、競合を市場から排除する強力な手段となります。
これにより、企業は価格競争に巻き込まれることなく、自社製品に対する価格決定権を維持できるため、高い利益率と収益の安定性を確保することが可能です。
また、特許は単独での利用にとどまらず、戦略的に複数の特許を組み合わせることでより大きな効果を発揮します。
製品やサービスに関連する複数の発明を網羅する「パテントポートフォリオ」を構築すれば、模倣や技術的な回避策を難しくし、後発企業の市場参入を実質的に困難にできます。
このように特許制度は、単なる技術保護を超えて、長期的に市場優位性と先行者利益を維持するための経営戦略の中核となる資産でもあるのです。
参考文献:
対外的信用力・交渉力の強化
スタートアップにとって、特許の取得は自社の技術力や独自性を対外的に示すための非常に効果的な手段です。
特許は、専門機関による厳格な審査を経て、「新規性」や「進歩性」といった技術的価値が客観的に認定されたものです。
これは単に技術を保護するだけでなく、製品やサービスが他社の模倣ではなく、自社で開発されたものであることを示す証拠になります。そのため、顧客からの信頼を高めることにもつながります。
また、特許を保有していることは、OEM供給や業務提携といった企業間取引の場面で、自社の技術的優位性や独自性をアピールする材料です。これにより、価格や契約条件の交渉においても有利な立場を築きやすくなるでしょう。
さらに、特許は金融機関やベンチャーキャピタル(VC)から「将来の利益を生む知的資産」として高く評価されます。
実際、調査会社PitchBookのデータによると、特許を持つスタートアップは、そうでない企業に比べて高い企業評価額が付く傾向があり、特にシリーズAといった初期段階の資金調達において企業価値を押し上げる要素です。
また、融資審査の際には、担保や信用補完の材料として扱われる可能性もあり、金融面での信用力向上にも寄与します。
さらに、大学や大企業との共同研究や技術連携においても、特許を保有していることは大きな強みとなります。
すでにその分野で独自の知的財産を持っているという証明になり、スタートアップが対等な立場で交渉に臨むための後押しになるでしょう。単なる外注先ではなく、パートナーとしての信頼や尊重を得やすくなるのです。
このように、特許は技術力の証明にとどまらず、スタートアップの対外的な信用力と交渉力を多角的に高める重要な資産です。
参考文献:How patents boost 409A startup valuations and fundraising
ライセンス契約による新たな収益源を確立する
自社で事業化しない発明であっても、特許権を取得していれば、他社にその技術の使用を許可する「ライセンス契約」を結ぶことができます。
たとえば、開発した新しいセンサー技術が自社製品には採用されなかったとしても、他社の製品開発に有用であれば、年間数百万円のロイヤリティ収入を得る可能性もあります。
このように、事業化には至らなかった研究開発成果いわば「休眠技術」を収益化する有効な手段として、特許のライセンス提供は注目されているのです。
大学や大手企業でも、未活用の特許を専門の知財部門が管理し、外部に積極的にライセンス展開するケースが増えています。
さらに、例えば自社が持つ画像処理アルゴリズムの特許と、他社が持つ高速通信技術の特許を互いに無償または低額で利用し合う「クロスライセンス契約」を通じて、新製品の共同開発やアライアンスの構築に発展することもあります。
つまり、特許権は単なる防御策ではなく、収益源や戦略的提携の入り口としても活用できる経営資源なのです。
参考文献:
- Technology Transfer Licensing Survey | AUTM
- Volkswagen is latest carmaker to join Avanci’s 5G licensing programme – The Global Legal Post
優秀なエンジニアの採用と定着につながる
企業が優秀なエンジニアを採用し、長期的に活躍してもらうためには、技術や発明を正当に評価する環境づくりが不可欠です。
特に、特許取得を積極的に奨励し、発明者に対して相応の報奨や承認を与える企業文化は、創造的な人材にとって強く魅力的に映ります。
特許は、エンジニアリング分野における高い専門性と独自性の証明であり、まるでノーベル賞やグラミー賞のように、その人のキャリアにおいて名誉ある成果とみなされるものです。
自らが設計した技術が知的財産として認められることは、単なる成果以上に、スキルや知見が社外から肯定された証であり、それが可視化されることで大きな自信と誇りにつながります。
こうした環境を整える企業は、単に報奨金などの経済的インセンティブを用意するだけでなく、社内外に「創造性を大切にする会社」という明確なメッセージを発信していることになります。
その姿勢は、将来有望なエンジニアの目に「この企業なら自分の技術が活かせる」「成果が正当に評価される」という安心感として映り、採用の場面でも強い差別化要因となるでしょう。
さらに、すでに働いている技術者にとっても、特許制度を活用できる環境は日々の業務に対する動機づけになります。
自分のアイデアがきちんと形になり、組織として評価してくれるという実感は、仕事への集中力や仲間との協働意識を高め、結果として離職率の低下にも寄与します。
特許制度は、単なる法的保護手段にとどまらず、企業文化の中核に据えることで、採用と定着の両面において非常に大きな戦略的価値を持つのです。
参考文献:
- Benefits of a Patent for Every Engineer – Michelson IP
- What Engineers Need to Know About Filing for Patents
特許取得の3つの注意点
多くのメリットがある一方で、特許取得には相応のコストやリスクが伴います。
これらのデメリット、すなわち注意点を事前に把握し、対策を講じておくことは、知財戦略を成功させる上で避けては通れないプロセスです。
ここでは、企業が特許出願を検討する際に直面する3つの主要な注意点を解説します。
出願から権利維持まで継続的なコストが発生する
出願から権利維持まで継続的なコストが発生する 特許を取得し、権利を維持するためには多岐にわたる費用負担が求められます。
まず出願段階では、書面での申請に際してはページ数に応じた電子化手数料(2,400円+ページ数×800円)や、オンライン出願との差額が発生し、さらに特許庁に対しては特許出願料(14,000円)、外国語書面出願の場合は22,000円が必要です。
続いて、審査請求を行う際には、基本料金138,000円に加えて請求項1件につき4,000円の費用が発生し(2019年4月1日以降の出願)、請求項数が増えるほどコストは増大します。
無事に特許査定が下りた後は、いわゆる「特許年金」に相当する毎年の特許料を納付し続けなくてはなりません。
例えば、審査請求を平成16年(2004年)4月1日以降に行った場合、第1~3年は4,300円+請求項×300円、第4~6年は10,300円+請求項×800円、第7~9年は24,800円+請求項×1,900円、第10~25年は59,400円+請求項×4,600円といった具合に、権利存続年数の経過に合わせて費用が段階的に上昇します。
これにより、複数年にわたって維持費が累積し、保有する特許件数が多い企業では負担が大きく膨らむおそれがあります。
以上のように、特許関連の手続きでは出願料や審査請求料、毎年の特許料のみならず、各種手続きにかかる手数料も考慮する必要があり、長期的な予算計画を立てることが不可欠です。
▼ 特許調査コストを削減する方法はこちら
特許調査の費用軽減|生成AIがもたらす効率化と省コスト化
参考文献:
発明の内容が社会に公開される
特許制度では、発明者に一定期間(特許は最長20年、実用新案は10年)の独占的な権利を与える代わりに、発明の技術内容を社会に公開することが求められます。
これは、技術情報を広く共有することで、さらなる技術革新や社会全体の発展を促すという目的があります。
ただし、この「公開」の仕組みには注意すべき点があります。出願から18か月(1年6か月)が経過すると、特許庁はその出願内容を「公開特許公報」として公表します。
この公報は、J-PlatPatなどのウェブサイトを通じて、誰でも無料で閲覧することができます。つまり、一度出願した技術は、原則として自動的に世の中に公開されるのです。
また、「早期に公開したい」として出願人が早期公開(公開請求)を行った場合、その請求は後から取り下げることができません。仮にその後に出願を取り下げたり、特許として認められなかったとしても、内容は公開され、誰でも見られる状態になります。
さらに、外国でも特許を取得するための「PCT国際出願」を経て日本国内に移行した場合も、翻訳文の提出後に同様に公開される仕組みです。
ここで重要なのは、一度公開された発明内容は、もう秘密には戻せないという点です。特許が認められなかった出願であっても、内容だけは社会に広まり、企業の技術的ノウハウが他社に知られてしまう可能性があるのです。
しかも、出願内容が公開された段階では、まだ特許権は確定していません。そのため、その技術を他社が模倣したとしても、直ちに差止めや損害賠償を請求することはできません。
ただし、後に特許が成立した場合には、出願が公開された日以降の侵害に対して「補償金(旧:実施補償金)」を請求する権利が発生します。
こうした公開のリスクを考えると、特許を出願するかどうかの判断は、単に法的な問題だけでなく、企業戦略上の重要な決断となります。
特に、自社にとって極めて重要なコア技術や製造ノウハウなど、他社に知られること自体がリスクとなる情報については、あえて特許を出願せず、営業秘密として社内で管理する「ブラックボックス戦略」を選択する方が効果的な場合もあります。
つまり、特許制度には「技術の独占」と「情報の公開」という両面があり、発明内容を公開することによる影響を十分に理解したうえで、出願の是非やそのタイミング・開示範囲を慎重に検討する必要があるということです。
参考文献:
権利化までには専門知識と時間が必要となる
特許は、書類を提出しただけでは自動的に認められるものではありません。出願後、特許庁の審査官がその発明について「新規性」や「進歩性」があるかどうかを厳しく審査します。そして、多くの場合、「拒絶理由通知」という形で問題点が指摘されます。
これを受け取った場合は、通知の内容に応じて意見書や手続補正書を提出し、期限内に反論や修正を行う必要があります。
ここでは、発明内容を特許法の要件に照らして論理的に主張を構成しなければならず、技術と法律の両面にわたる知識が求められます。そのため、弁理士といった専門家のサポートを受けながら進めるのが一般的です。
出願から特許が認められるまでには、まず一度きりの審査請求を行って審査を開始し、その後に行われる拒絶理由通知への対応や補正などの手続きを経る必要があります。これらの過程には一定の期間を要するため、特許の取得には相応の時間がかかります。
特許手続きにかかる時間や必要な専門的対応は、製品開発や資金調達のスケジュールにも影響を及ぼすため、事前に十分な準備をしておくことが望ましいでしょう。
▼ 効率的な特許調査の手順はこちら
特許調査とは|効率的な進め方を徹底解説
参考文献:
特許出願をすべきか|判断するための3つの基準
自社の発明を特許出願すべきかどうかは、企業の事業戦略や市場の状況によって変わります。
そこで、判断の助けとなる3つの客観的な基準を紹介します。自社の状況をこれらに照らして考えることで、より戦略的な判断ができるようになるでしょう。
事業における発明の重要性
ある発明が特許出願に値するかどうかを判断するには、まずその発明が自社の事業にとってどれだけ重要かを見極めることが大切です。
単なる技術的な改良にとどまらず、製品やサービスの差別化に直結する「中核技術」であれば、特許によってしっかりと守るべき価値ある資産といえます。もし他社に模倣されれば、自社の競争力が大きく損なわれる可能性もあるためです。
特許を出願すべきかどうかを判断する際には、次のような点が重要です。
- 発明が将来の主力商品やサービスに使われる予定があるか
- 技術が競争優位の源泉であり、模倣された場合のリスクが高いか
- ライセンスや提携などを通じて収益化の可能性があるか
これらの条件を満たしている場合は、出願費用や維持費用がかかっても、特許を取得する意義は十分にあります。
一方で、その技術が他の方法で代替可能だったり、事業の中心から外れていたりする場合には、特許出願の優先度は下がります。特許出願には費用だけでなく、出願により技術内容が公開されるというリスクもあるため、得られるメリットがそれらの負担を上回るかどうかを慎重に見極める必要があります。
知的財産は、企業にとって単なる法的保護手段ではなく、戦略的資産でもあります。発明の事業への影響や経済的可能性を適切に評価し、それに基づいて保護戦略を設計することが、特許出願の妥当性を判断するうえでの基本です。
▼ 発明を事業価値に変える方法はこちら
ビジネスモデル特許|企業競争力を強化する新たな知財戦略
参考文献:
- Business Model Canvas – Download the Official Template
- Making intellectual property work for business
模倣されるリスクの高さ
技術力は企業にとって重要な競争力の源ですが、その価値は他社に模倣されやすいかどうかで大きく変わります。
製品を分解したり、ソフトウェアを解析したりして仕組みを明らかにする「リバースエンジニアリング」は、EUでは合法的な手段として認められており、広く利用されています。
そのため、技術が簡単に解析されてしまうようであれば、秘密として保持し続けることは難しくなり、特許を取得することの戦略的な重要性が増します。
こうした模倣のリスクに対抗するには、技術の性質に応じた知的財産の保護戦略を立てることが不可欠です。特許制度では、技術の内容を公開する代わりに、出願から最長20年間はその技術の独占的な利用が認められます。
この期間中は法律によって他社の利用を排除できるため、市場における優位性を確保する強力な手段となります。ただし、特許を公開すると誰でもその内容にアクセスできるようになるため、保護期間が終了した後を見据えたビジネスモデルの準備も必要です。
一方で、技術が製造工程に深く関わっており、外部からの解析が難しい場合には、特許を取得せず、営業秘密として管理する選択肢もあります。営業秘密は登録不要で、秘密を守り続ける限り、法的な保護が無期限で続きます。ただし、この方法では、秘密保持体制の徹底が保護の有効性を左右します。
加えて、製品設計や開発の段階から、リバースエンジニアリングそのものを困難にするような技術的な工夫を取り入れることも効果的です。
たとえば、ハードウェアの部品を一体化して分解しにくくしたり、ソフトウェアに難読化や認証機能を組み込んだりすることで、解析にかかるコストや時間を大きく増やすことができます。
このような技術的対策を法的保護と組み合わせることで、模倣のリスクに対してより強固な防御を構築することが可能となります。
▼ 特許侵害を防ぐ・対処するための手段はこちら
特許侵害の要件と対策を徹底解説|事前予防から紛争解決まで
▼ 製法の模倣を防ぐための保護手段はこちら
製法特許とは|定義や権利化までのプロセスを徹底解説
参考文献:
- WIPO Guide to Trade Secrets and Innovation – Part III: Basics of trade secret protection
- How to Protect Trade Secrets?
- The legality of reverse engineering or how to legally decipher trade secrets
- MODULE 03. Inventions and Patents
費用対効果の見込み
特許の出願から維持に至るまでには、予想以上に多くの費用がかかります。たとえばアメリカでは、年間およそ43億ドルが特許取得のために使われており、特許訴訟を起こした場合には、2001年時点で1件あたり片方の当事者だけでも平均150万ドルという高額な費用がかかると試算されています。
日本でも同様に、特許に関わるコストは決して小さくありません。出願には基本手数料として14,000円(外国語による出願の場合は22,000円)がかかり、審査を請求するには13万8,000円に加え、クレーム(権利範囲を示す請求項)1項ごとに4,000円の加算があります。
さらに特許を維持するためには年ごとに年金(維持手数料)を支払う必要があり、たとえば最初の3年間では年額4,300円+クレーム1項につき300円、10年目以降になると年額59,400円+クレーム1項あたり4,600円へと増加します。
これらの費用は期日までに納めなければ追徴金が発生し、その金額は通常の2倍に及ぶこともあります。失効した特許権を回復する場合にも、別途手数料が必要です。
さらに、審査期間が長くなったり、クレームの数が多かったり、追加の技術調査を行う場合は、弁理士に支払う費用がさらにかさみます。海外在住者は原則として日本国内の代理人を通じて手続きを行う必要があるため、実際の負担はより大きくなります。
こうした大きな投資に見合うリターンが得られるかどうかは、多面的に考える必要があります。まず、特許によって技術の独占的な使用が可能になるため、競合他社を排除しながら市場での優位性を確保できます。
また、訴訟を起こさずともライセンス収入を得ることができ、たとえばIBMは年間5億ドル以上をライセンス契約のみで稼いでいるという事例もあり、特許は収益源としても非常に大きな価値を持ちます。
さらに、特許を保有していること自体が、技術力を示す重要なシグナルとなり、ベンチャーキャピタルや投資家の信頼を得る材料になります。これにより、資金調達の条件が有利になることも期待できます。
また、半導体業界のように特許紛争が頻発する分野では、自社保有の特許を交渉材料(いわゆる“バーゲニングチップ”)として活用することで、他社からの訴訟を防ぐ効果もあります。
特許の保護期間は原則として出願日から20年間、年金は最長25年目まで支払い可能です。したがって長期的には、特許を第三者に技術移転する手段として活用したり、価値の高い特許であれば数百万ドル単位の損害賠償を得るチャンスも生まれます。
このように、特許にかかる費用と得られるリターンを比較検討する際には、単に発明を守るという視点だけでなく、自社の事業戦略や市場環境、技術のライフサイクルなどを見据えた、20年単位の長期的な視点が欠かせません。
確かに特許取得には高額な費用がかかりますが、その一方で、適切な判断と戦略に基づけば、将来の事業成長に大きく貢献する投資ともなり得るのです。
参考文献:
- Schedule of fees | Japan Patent Office
- Fees | Japan Patent Office
- Innovation with and without patents arXiv:2210.04102v1 [econ.GN] 8 Oct 2022
- Valuable Patents
まとめ
特許は単なる「守りの手段」ではなく、事業を成長させる「攻めの戦略」として重要です。特許の価値を最大限に活かすには、事業戦略と知財戦略を一体で考える必要があります。
まず、自社の技術を整理し、それぞれがどのようにビジネスに貢献しているかを明確にしましょう。ビジネスモデルキャンバスなどを使って、どの技術が価値の核で、どれが重要なリソースかを見える化することが大切です。
その上で、技術ごとに「特許を取る」か「秘密にする」かを判断し、特許をどう事業に活かすかまで考えることが、効果的な知財戦略につながります。
特許はコストではなく、将来の利益を生み出す投資と捉え、経営の中心に据えることが、長期的な競争力の鍵となります。
エムニへの無料相談のご案内
エムニでは、製造業をはじめとする多様な業種に向けてAI導入の支援を行っており、企業様のニーズに合わせて無料相談を実施しています。
これまでに、住友電気工業株式会社、DENSO、東京ガス、太陽誘電、RESONAC、dynabook、エステー株式会社、大東建託株式会社など、さまざまな企業との取引実績があります。
AI導入の概要から具体的な導入事例、取引先の事例まで、疑問や不安をお持ちの方はぜひお気軽にご相談ください。
引用元:株式会社エムニ