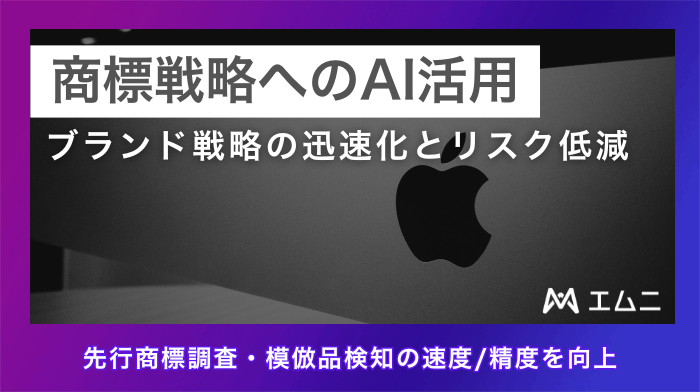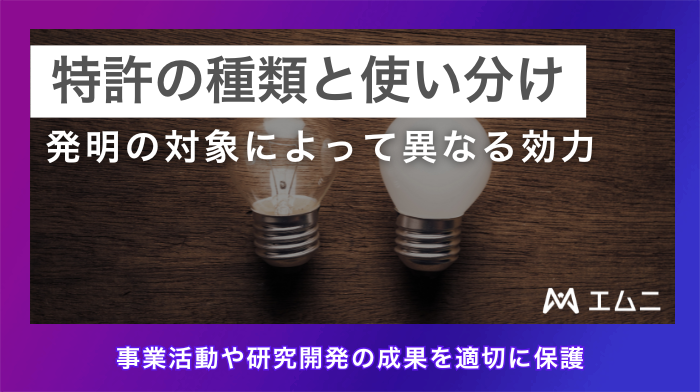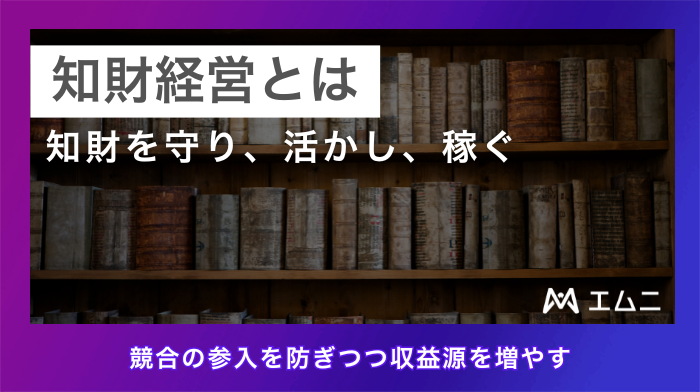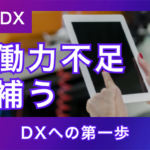
製造業のデジタル化|メリットやロードマップを詳しく解説
2025-05-23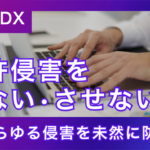
特許侵害の要件・事前予防・紛争解決方法を徹底解説
2025-05-29国際特許検索とは|海外展開の失敗を防ぐ生成AI時代の調査戦略
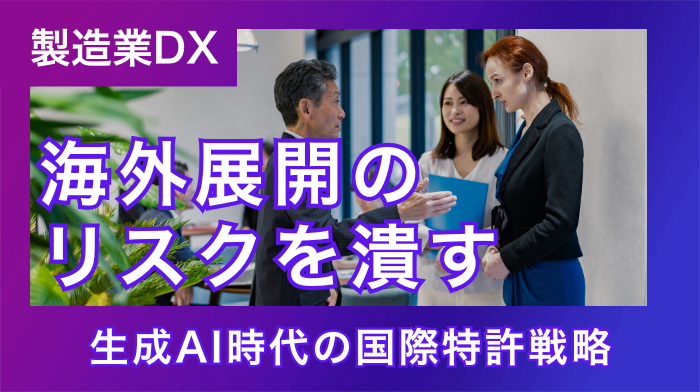
製品や技術を海外展開する際、最も見落とされがちでありながら、実は重大な障害となり得るのが「特許リスク」です。
市場投入後に他社の特許を侵害していたと判明すれば、多額の損害賠償や撤退を余儀なくされ、技術投資も販路も一瞬で無に帰します。そうした事態を避けるためには、国際特許検索を通じて事前にリスクを洗い出し、対策すことが欠かせません。
本記事では、なぜ国際特許検索が重要なのかという基本から、検索準備、効率的な進め方、AIツールの活用法まで、製造業・技術開発現場で実践できる形で網羅的に解説します。
国際特許検索が必要な理由
海外市場への展開を目指す企業にとって、国際特許検索は開発初期にわずかな手間をかけるだけで、将来の巨額損失や機会損失を未然に防ぐために重要なステップです。
加えて、競合の技術動向を把握し、提携や買収などの戦略的判断を支える情報基盤としても欠かせません。以降では、具体的な活用場面とその効果を丁寧に解説していきます。
海外特許に関するリスクを早期に把握するため
製品開発において、海外特許に関するリスクの早期把握は事業の成否を左右する最重要事項の一つです。
開発した技術が他国ですでに特許化されていないかを事前に確認しておかないと、後から思わぬ侵害リスクが発覚し、多額の損失や事業撤退につながる可能性があります。
実際、イーストマン・コダック社は1976年に発売したインスタントカメラでこのリスクを痛感しました。同社は独自のカメラとフィルムを米国市場に投入しましたが、わずか一週間でポラロイド社に特許侵害で提訴されます。
引用元:Polaroid Wins Patent Suit Against Kodak
その後1985年には連邦地裁が侵害を認定し、1986年には生産・販売差止命令が発令。結果としてコダックは即座に市場から撤退し、1991年には約9億2,500万ドルの和解金を支払って、インスタント写真事業から完全に撤退することになりました。
このような悲劇は、事前に十分な特許調査を行い、対象国における出願・登録状況を把握していれば回避できた可能性があります。
ただし、いかなる調査もリスクを完全にゼロにすることを保証するものではなく、リスクを把握し、低減させることが目的である点に留意が必要です。
特に特許出願件数が多く、技術革新の激しい分野では、リスクが水面下で進行していることが少なくありません。
だからこそ、製品開発の初期段階での特許調査は、「もしも」の損失を未然に防ぐための“情報的な保険”となるのです。設計変更やライセンス交渉も早期であれば柔軟に対応できます。
海外展開を見据える企業にとって、これはもはや選択肢ではなく、不可欠な工程だと言えるでしょう。
▼生成AIで先行技術調査とリスク評価の工数を半減したい方はこちら
特許調査の費用軽減|生成AIがもたらす効率化と省コスト化
参考文献:
- IP and Business: Launching a New Product: freedom to operate
- Freedom to Operate Search: Avoid Infringement Claims
- FREEDOM TO OPERATE, PRODUCT DECONSTRUCTION, AND PATENT MINING: PRINCIPLES AND PRACTICE
- Instant Artifact: Kodak’s Polaroid Moment | Polaroidland
- Kodak Settles Polaroid Case for $925 Million – Los Angeles Times
技術動向と競合活動を把握するため
新たな技術や製品を国際的に展開するうえで欠かせないのが、海外における技術動向と競合企業の動きの把握です。
なぜなら、国際市場には日本国内とは異なる競争環境が広がっており、自社が挑もうとしている分野にどれほど強力なプレイヤーが存在するのかを知らずに進出することは、極めてリスクが高いためです。
こうした判断の土台となるのが、各国で公開されている特許文書なのです。
特許は単なる技術説明資料ではありません。発明の仕組みや図面に加え、出願日、出願国、権利の存続状況、譲渡履歴など、企業の戦略を読み解くための多様な情報が盛り込まれています。
特に特許は国ごとに出願されるため、どの企業がどの市場を重視しているのかといった地政学的な視点からも分析が可能です。
たとえば、スマートフォン向けのカメラモジュールに関する特許群を時系列で追えば、どのメーカーがいつ頃から高画素センサーや手ぶれ補正技術の強化に取り組み始めたのかが手に取るようにわかります。
また、出願された国や地域を地図上にプロットしてみると、各企業がどの市場を主戦場と見なしているか、その国際展開の意図が浮き彫りになるでしょう。
このような統計的アプローチは「パテントアナリティクス」と呼ばれ、研究開発の方向性を定める際や、海外展開の判断材料として広く活用されています。さらに、特許出願は製品投入よりも1〜2年早く公開されることが多いため、競合の次の一手を先読みするうえでも有効です。
特許情報を読み解くことによって、すでに確立された解決策や技術の蓄積を踏まえた上で自社の開発を進めることが可能になります。これにより、ゼロからの再発明に陥ることなく、時間やコストを大きく削減することができるのです。
このように特許情報を通じて技術や市場の動向を把握することは、国際展開における重要な判断材料となります。競合の動きや市場の特性を見極めることで、開発や投資の方向性をより的確に定めることができるでしょう。国際特許検索は、そのための基盤となる手段です。
▼技術動向を可視化し、競合活動を把握したい方はこちら
パテントマップとは?具体的な用途から導入方法まで
参考文献:
投資・提携前のデューデリジェンスをするため
国際特許検索を徹底すべき理由の一つは、買収後に思わぬリスクが発覚するのを未然に防ぐことにあります。
一見すると有望に見える特許ポートフォリオであっても、実際には事業に活かせない使えない特許が混ざっていることは珍しくありません。こうした見落としが、のちに製品の撤退や事業戦略の修正を強いられる原因となることもあります。
そのため、買収や業務提携を検討する際には、相手企業が本当に使える特許を保有しているかどうかを最優先で見極めなければなりません。単に特許の件数や登録国を並べただけでは、知的財産の価値もリスクも見えてこないのです。
たとえば、審査中のまま失効が迫っている特許や、ライセンス契約の制限で自由に活用できない特許は、将来の展開を阻む“落とし穴”になり得ます。
さらに、従業員との発明譲渡契約が不完全で所有権が不明確なケースや、国によって特許制度が異なる場合(例:インドではソフトウェア関連発明の特許化に独自の要件があり、審査が厳格である)には、予期せぬ訴訟や製品設計のやり直しが発生するリスクもあります。
こうしたリスクを事前に把握するためには、国際特許検索を中核としたデューデリジェンスにおいて、保有特許の法的ステータス(出願中・審査中・維持・失効)を精査し、請求項ごとに権利範囲や対象地域を突き合わせる必要があるでしょう。
同時に、譲渡履歴や担保設定、ライセンス契約の内容も確認し、FTO分析(第三者の特許を侵害せずに製品やサービスを実施できるかを確認する調査)を通じて、競合特許による阻害要因を排除します。
このように、多面的かつ詳細な調査を通じて初めて、対象特許の実質的な価値や潜在リスクを正確に把握することができます。そしてそれが、将来のトラブルを防ぎ、後悔のない投資判断につながるのです。
つまり、特許デューデリジェンスは、買収後にリスクを抱え込まないための最前線の防御線なのです。
参考文献:
- Intellectual Property Due Diligence in Mergers & Acquisitions
- The Crucial Role of Patent Due Diligence in Mergers & Acquisitions: Spotting Patent Litigation Risks Before Closing a Deal – Insights – Proskauer Rose LLP
- インドにおいて特許を受けることができない発明
検索前に準備すべき3つのポイント
国際特許を調べる際に、ただ思いついたキーワードを検索窓へ入力するだけでは、重要な先行技術を取りこぼしたり、無関係な文献が大量にヒットして時間を浪費したりする危険があります。
そういったリスクを避けるためにも、以下では検索に入る前に整えておくべき3つの基本項目を紹介します。
出願番号・公開番号とファミリー情報の整理
特許調査を始めると、まず戸惑うのが「同じ発明なのに、国ごとに番号や形式がバラバラで追いにくい」という現実です。
たとえばドイツで公開された特許は DE 19830566 A1、登録されると DE 19830566 B4 に変わります。同じ発明がアメリカでは US 10/123456、中国では CN 111111111 A のように、まったく異なる番号体系で管理されているのです。
さらに、これらの番号には kind code(A1 や B4 など) が付き、公開文書か登録文書かといった種類まで区別されます。つまり、同じ発明を調べたいだけなのに、情報が国ごとに分散しており、ひと目で追えません。
このとき役に立つのが 特許ファミリー という考え方です。これは、同じ技術に基づく出願を「家族」としてまとめて表示してくれる仕組みです。
ある国での出願をもとに、他国でも「この発明はあれと同じです」と優先権を主張して出願された場合、それらは兄弟のように紐づけられ、共通の発明として扱われます。
また、PCT出願(国際出願) を経由して各国に移行したケースも、同じ技術をもとにしていればファミリーとして整理されます。
このように、国ごとに分散した特許番号を“同一技術”として再構成してくれるのがファミリー情報なのです。
無料のEspacenetやPATENTSCOPE、有料のDerwent WPIなどのデータベースは、このファミリー情報を元に「同じ技術に属する文献群」を一覧化して表示してくれます。
ただし、どこまでを“家族”と認識するかはデータベースごとに異なるため、あるDBでは家族が30件、別のDBでは90件ということも珍しくありません。
だからこそ、調査者がまず行うべきは、個々の国でバラバラに公開されている特許文献を、ファミリー情報でまとめるための共通フォーマットに変換することです。具体的には、出願番号や公開番号を標準化し、ファミリー検索に対応した形式に直す作業が必要になります。
この準備が甘いと、検索から本来見るべき関連特許を漏らしてしまい、重要な先行技術や侵害リスクを見逃すおそれがあります。調査の精度を高めるためには、ファミリー概念の理解と、正確な番号の扱いが不可欠です。
国際特許分類(IPC)の抽出と同義語展開
国際特許分類(IPC)を起点に検索戦略を設計する際、最初のステップとなるのは、対象技術の「本籍」にあたるセクション・クラス・サブクラスを正しく特定することです。
たとえば、リチウムイオン電池なら「H01M 10/44」、医薬化合物であれば「A61K 31/00」など、技術の核心を示すコードを絞り込むことで、そのコード自体が文献をふるい分けるフィルターとして機能します。
IPCは世界共通の技術座標系であり、国ごとの出願文献が混在する検索結果においても、共通のコードを手がかりに横断的な比較が可能です。
ただし、分類コードだけに依存すると、用語の違いや表記の揺れにより関連文献を見落とすリスクがあります。そこで重要となるのが、キーワードの同義語展開です。
たとえば、電池関連の検索では「battery」を中心に、「accumulator」「secondary cell」「蓄電池」「electrochemical storage device」などの表現が用いられます。リチウム系に限定すれば、「Li-ion」「LIB」「リチウムイオン」など、業界固有の略語や日本語表現も検索語に含まなければなりません。
こうした語句を技術辞書や既存特許の請求項などを参考にリストアップし、OR演算子で束ねて検索式に組み込むことで、言語差や表記揺れによる取りこぼしを防ぐことができます。
実務上は、まずIPCで文献集合を絞り込んだうえで、要約(AB)や請求項(CL)といったフィールドに対してキーワード検索を掛け合わせる「多段階検索」が効果的です。
たとえばIC:H01M10/44 AND AB:(battery OR accumulator OR “secondary cell”)
といった検索式を設定すれば、対象技術に該当し、かつ要約中に関連語が現れる文献を効率よく抽出できます。
このように「分類コード × キーワード」という掛け合わせは、広く拾い上げてから的確に絞り込むという検索の基本戦略として非常に有効です。ノイズを抑えつつ、読むべき文献を短時間で浮かび上がらせることが可能になります。
検索式の精度は、同義語リストの網羅性に大きく左右されます。社内で蓄積された用語集や、生成AIによる自動シソーラスの活用などを組み合わせることで、検索の“抜け”を最小限に抑えることができます。こうした準備の徹底こそが、特許調査の成否を分けるカギとなるのです。
参考文献:
翻訳環境とPDFビューアのセットアップ
国際特許を読むときに最初に立ちはだかるのが「言語の壁」です。
ですが中国語やドイツ語など、日本語とは系統の異なる言語で書かれた公報でも、WIPOの提供する「WIPO Translate」ボタンを押せば、その場で日本語訳に切り替えることができます。
引用元:WIPO
この翻訳はニューラル翻訳エンジンによって行われ、特許用語を学習済みなので、従来よりもクレームなどの専門的な文でも文意を把握しやすくなっています。
同様に、欧州特許庁の「Espacenet」では、「Patent Translate」機能を選ぶだけで、32言語の間で即座に翻訳できます。
さらに、翻訳された文の上にカーソルを合わせると、元の原文がポップアップ表示されるので、原語との照合も簡単に行えます。
ただし、これらの機械翻訳はあくまで概要把握や一次スクリーニングのための補助ツールです。権利範囲の厳密な解釈や侵害判断など、法的に重要な場面では、必ず原文を確認するか、専門家による翻訳を利用しましょう。
これらのツールは言語の壁を低くする助けにはなりますが、完全に解消するものではない点に注意が必要です。
翻訳が済んだら、次は公報PDFをまとめて手元に保存しましょう。WIPOの「PATENTSCOPE」にはログインユーザー向けに「Multi-document download」機能があり、検索結果にチェックを入れるだけで、複数のPDFを一括ダウンロードできます。
大量の公報をローカルに保存しておけば、オフライン環境でも読み比べたり、注釈を加えたりすることが可能になります。
最後に重要なのが、「文献同士の違いをひと目で把握できる」環境の整備です。たとえばAdobe Acrobat Proには「Compare Files」機能があり、2つのPDFの相違点を色付きでハイライト表示してくれます。
コストを抑えたい場合は、同様の機能を備えたFoxit PDF Editorを使うのも手です。
このように、①翻訳、②一括保存、③差分比較の3ステップを事前に整えておけば、特許文献の精読や分析がぐっと効率的かつ正確になります。
▼AI翻訳で海外特許を正確に日本語化し、調査を効率化したい方はこちら。
特許翻訳にAIを導入するメリットを事例付きで詳しく解説
参考文献:
- Patent Translate | epo.org
- WIPO Translate
- PATENTSCOPE Data Formats:WIPO
- Compare two versions of a PDF file (Acrobat Pro)
- How to Compare PDF Files – Easy Step to Follow | Foxit
国際特許検索を効率よく成功させるポイント
効果的な国際特許検索には、調査の方向性を明確にし、複数のデータベースを戦略的に使い分け、AIを活用しながら組織のナレッジとして蓄積していくという4つの視点が重要になります。
これらを押さえることで、検索は単なる情報収集から意思決定支援へと進化するでしょう。
調査の目的と範囲を明確にする
特許検索を行う際には、まず「調査の目的」を明確にすることが重要です。何を知りたいのかがはっきりしていないと、検索結果に無関係な文献が多く含まれ、あとから精査する手間が膨らんでしまいます。調査の効率を高めるためには、検索の前段階での設計が欠かせません。
たとえば、2027年に米国とEUでウェアラブル端末を発売する企業が、特許侵害を避けたいと考えているとしましょう。
この場合には、「侵害予防調査(FTO:Freedom to Operate)」として、発売予定地域で現在も有効な特許だけを対象に調査を行う必要があります。検索式の設計では、CPC分類のA61B(生体センサー)やG06F(情報処理)といった関連技術コードを用いるのが一般的です。
WIPO(世界知的所有権機関)の教育資料でも、検索の目的ごとに手法を明確に区別すべきだとされています。
たとえば、FTO調査、特許性の評価、無効資料の探索、競合動向の把握など、それぞれに適した調査設計があるとされており、手法の混同は避けるべきだと指摘されています。
競合調査が目的の場合には、出願国を広くとり、過去20年分程度の公開特許を対象にすることが望ましいでしょう。また、特許文献に限らず、論文データベースなど他の情報源にも目を通すことで、より多角的な分析が可能になります。
検索範囲を広げすぎたり、技術テーマを曖昧なままにしたりすると、ノイズが増えて判断に時間がかかってしまいます。後工程での手戻りを防ぐためにも、検索式は可能な限り精緻に設計すべきです。
結局のところ、特許調査の成果は「設計段階」でほぼ決まってしまうといっても過言ではありません。目的、国、期間、技術領域を的確に設定することで、無駄を省きつつ信頼性の高い調査結果を得ることができるのです。
参考文献:
- Shaping Business Strategy Through Competitive Intelligence
- Webinar: Fundamentals of Using Patent Databases Questions and answers
AIを活用する
AIを活用することで、特許検索の方法が大きく変わり始めています。
これまでは、「AND/OR」などの論理演算子を使って条件を設定し、手作業で文献を絞り込むのが一般的でした。しかし今では、生成AIが文章の意味を読み取り、対話形式で検索をサポートする技術が広がりつつあります。
たとえばPatSnapでは、自社開発の大規模言語モデル「PatSnap GPT」を活用し、35億件を超える特許データを学習した検索機能を提供しています。
仕組みの詳細は明かされていませんが、実際には、先行技術調査やFTO調査を数分で完了できるケースもあり、業務の効率化に大きく寄与しているようです。
同様に、Solve Intelligenceの「Patent Copilot」も注目されています。このツールでは、特許明細書や図面ラベルをAIが自動で生成することが可能です。実際に導入した企業では作業全体の40〜60%が効率化されたと報告されています。
検索エンジンそのものも進化しています。Patenticsは、ユーザーが入力した自然文を「概念グラフ」に変換し、その意味に沿った関連特許を自動的に抽出するセマンティック検索を搭載しました。
これにより、複雑な検索条件を事前に設計する必要がなくなり、非特許文献も含めた幅広い検索が可能になっています。
とはいえ、AIが提示する検索結果はあくまで“候補”にすぎません。最終的にどの請求項を重視し、どう戦略を立てるかといった判断には、弁理士など人間の専門的な見解が欠かせません。
こうした技術の進展に伴い、近年では「先行技術とは何か」という根本的な定義そのものも見直され始めています。これからは、AIと専門家が連携し、それぞれの強みを活かした調査体制を構築していくことが求められるでしょう。
▼AIで特許調査を効率化したい方はこちら
AIで特許調査のコストを1000分の1に|活用戦略を詳しく解説
参考文献:Best AI Tools for Patent Attorneys 2025 | Solve Intelligence
複数データベースを横断的に活用する
特許調査では、ひとつのデータベースだけでなく、複数のデータベースを組み合わせて使うことが不可欠です。なぜなら、国や地域によって収録範囲や公開タイミングが異なり、ある情報が一方には載っていても、他方には見つからないことがあるからです。
たとえば、WIPOの「PATENTSCOPE」は約60の国や地域の特許を収録し、EPOの「Espacenet」は欧州の特許に対応しています。
日本の「J-PlatPat」、中国の「CNIPA」、アメリカの「USPTO」など、各国ごとに公式な検索ツールも整備されています。さらに「Google Patents」や「The Lens」のように、複数国を一括で検索できるツールも活用されています。
引用元:J-PlatPat
国際的な出願状況や審査内容を確認したいときには、「Global Dossier」や「CCD(Common Citation Document)」が便利です。これは、日本・米国・欧州・中国・韓国の特許庁が連携して提供するもので、同じ発明が各国でどう扱われているかを比較できます。
検索の際には、ブール演算子(AND/OR)やIPC・CPC分類も活用しましょう。言語の違いによる検索漏れを防ぐために、PATENTSCOPEの「CLIR(Cross-Lingual Information Retrieval)」機能のような同義語・翻訳支援も有効です。
このように、各データベースの特性を理解し、横断的に使い分けることで、抜けや漏れのない特許調査が可能になります。
参考文献:
記録と共有で組織のナレッジを強化する
特許検索は、単に情報を探すだけの作業ではありません。キーワードの選び方、分類コードの指定、除外条件の設定など、細かい判断が必要な知的作業です。
だからこそ、こうした検索の工夫や工夫した検索式を記録し、チーム内で共有することが大切です。毎回ゼロから検索をやり直すのではなく、過去の検索式を再利用すれば、無駄な時間を減らすことができます。
WIPOの「PATENTSCOPE」では、自分で作成した検索条件を保存しておき、名前をつけて管理できます。それだけでなく、チーム内で共有したり、新しい情報が出たときに自動で知らせる「RSSフィード」という機能も使えます。
これにより、同じテーマに取り組むメンバーが、すぐに検索を始められるだけでなく、特許情報の更新を見逃すことも減ります。
またPATENTSCOPEでは、発明者名や出願人、国際特許分類(IPCやCPC)、公開日などを自由に組み合わせて検索できます。
さらに、「AND」「OR」「NOT」といった言葉を使って検索を絞り込むことも可能です。これらの条件を保存しておけば、あとから誰でも同じ検索がすぐにできるようになります。
このように、検索の工夫を見える形で残し、共有することで、作業の効率が上がるだけでなく、組織全体の知識が積み重なっていきます。検索ツールをうまく使えば、日々の仕事の質を高めながら、チームの力も底上げできるのです。
参考文献:
- the patentscope user’s guide | wipo
- Patent information for strategic technology management | LexisNexis IP
基本的な国際特許検索の進め方
国際特許検索を実際に進める際は、段階的に調査の精度を高めていく構造で進行するのが効果的です。以下に、よく用いられる調査のステップを順を追って解説します。
ステップ1:キーワード検索で全体像把握
特許検索の第一歩は、情報を広く集めるためのキーワード検索です。
この段階では、文献を厳密に絞り込むことよりも、自社の技術や製品に関わる語句を幅広く入力し、どのような先行技術があるのか、競合がどの分野に注力しているのかを把握することが目的となります。
J-PlatPatでは、キーワードをスペースで区切って入力することで「OR検索」が可能です。たとえば「ライト」「照明」「電灯」といった類義語をまとめて検索でき、意味の違いによる取りこぼしを防ぐことができます。
また、「ライト」と「らいと」のように表記が異なる語についても、長音や促音、ひらがな・カタカナ、大文字・小文字の差異をシステム側が自動で補正します。これにより、利用者は表記ゆれを気にせず、効率よく情報を拾うことが可能です。
さらに便利なのがワイルドカード機能です。
たとえば「光*」と入力すると、「光源」「光線」「光学」など、「光」で始まるさまざまな単語が一括で検索対象になります。これは、単語の前半だけを指定し、残りの文字列を自由に検索する方法で、技術用語のバリエーションに対応しやすいという利点があります。
検索を実行すると、関連する特許文献が一覧で表示されます。出願人や公開日、要約などの基本情報を通じて、技術の分布や傾向を視覚的に捉えることができるでしょう。
こうして得られた知見は、次のステップで行う「ノイズ除去」や「注目領域の深掘り」に向けた、確かな土台となるはずです。
参考文献:
- International Patent Classification (IPC)
- 特許情報プラットフォーム
- the patentscope user’s guide | wipo
- Guide to the International Patent Classification (2024)
ステップ2:IPC+キーワードでノイズ除去
最初の検索では広く文献を拾いましたが、このままでは関係のない特許も多く含まれています。そこで次のステップでは、「分類コード」を使って不要な文献を取り除き、調査の精度を上げていきます。
特許には、どんな技術分野かを示す「分類コード」がつけられています。中でも国際的に使われているのがIPC(国際特許分類)です。たとえば「C05D7/00」というコードは、「二酸化炭素を出す肥料」というように、技術内容が明確にわかる仕組みになっています。
このIPCを検索条件に加えると、技術的に本当に関係のある文献だけを取り出すことができるのです。
さらに、日本ではIPCのほかにも、FIやFタームという独自の分類が使えます。FIはIPCをもっと細かくしたもの、Fタームは「用途」や「構造」といった視点で分類するもので、複数の観点から文献を探すのに役立ちます。
こうした分類コードは、J-PlatPatの「分類照会」機能を使えば簡単に調べられます。選んだ分類はそのまま検索に使えるので、手間もかかりません。
また、分類コードとキーワードを組み合わせてAND検索をすると、両方の条件を満たす文献だけが表示されます。逆に、NOT検索を使えば関係ないものを除外することもできます。
さらに、複雑な検索式を一度作っておけば、保存して何度も使えるので、チームで調査する際にも役立ちます。
このように、分類コードと論理検索を活用すれば、ノイズを削って本当に調べるべき文献だけを見つけることができます。つまり、このステップは、調査の「精度」を一気に高めるために欠かせない工程なのです。
参考文献:
- International Patent Classification (IPC)
- 特許情報プラットフォーム
- the patentscope user’s guide | wipo
- Guide to the International Patent Classification (2024)
ステップ3:ファミリー展開で各国出願を確認
注目すべき特許が見つかったら、その技術がどの国で出願され、どのように審査が進んでいるのかを確認する必要があります。
これは、単に特許の有無を確認する作業ではなく、競合がどの市場をターゲットにし、どのような知財戦略をとっているかを読み解く重要な手がかりになります。
このとき活用するのが、J-PlatPatの「特許・実用新案番号照会/OPD」機能です。
ここでは、ひとつの発明に基づいて各国で出願された特許群、いわゆるパテントファミリーを一覧で確認できます。どの国に出願されているか、いつ出願されたのかが時系列で把握でき、技術のグローバルな展開状況を俯瞰できます。
さらに、同機能からは「ドシエ情報(審査経過)」にもアクセス可能です。これには、審査官とのやりとり(オフィスアクション)、補正の履歴、出願から登録までの手続きの流れが含まれており、その特許が現在どの段階にあるのか、あるいは登録済みなのか、拒絶されたのかといった情報が明確になります。
またJ-PlatPatを通じて、日本だけでなく、米国、欧州、中国、韓国といった主要国(五大特許庁)や、WIPO-CASEに参加している各国の情報も参照できます。
こういった機能により、各国での出願状況や審査の進み具合を比較しながら、競合の特許戦略を立体的に把握できるようになりました。表示形式は一覧性に優れており、調査の手間を大きく削減できるでしょう。
ファミリー展開と審査経過の確認は、単なる情報収集を超えて、自社の事業展開先における侵害リスクの予見や、競合のグローバルな出願戦略の分析にまで踏み込んだ調査手法です。これこそが、検索を“戦略”に変える最後のステップだといえるでしょう。
参考文献:
- International Patent Classification (IPC)
- 特許情報プラットフォーム
- the patentscope user’s guide | wipo
- Guide to the International Patent Classification (2024)
ステップ4:経過情報と法的ステータスを取得
各国でどのように出願されているか、どこまで技術が展開しているかを調べたあとは、それぞれの特許が今「生きているかどうか」を確かめる必要があります。つまり、その特許が現在も有効なのか、それともすでに無効になっているのかを調べる段階です。
たとえば、日本ではすでに登録されていても、他の国では拒絶されていたり、年金が支払われずに権利が消えていたりすることもあります。こうした違いを一つずつ丁寧に見ていくことが大切です。
このときに使えるのが、J-PlatPatの「経過情報」という機能です。ここでは、日本国内の特許について、出願日や審査の進み具合、登録されたかどうか、年金の支払い状況まで確認できます。関連する書類も見ることができます。
前のステップでは、どの国に出願されているかという「広がり」に注目しましたが、このステップでは、一件ずつの特許が今どうなっているかという「中身」に注目します。「登録されて有効なのか」「審査中なのか」「すでに無効になったのか」といった点を確認します。
こうして調べた情報はとても重要です。たとえば、相手の特許がまだ有効なら、こちらが侵害してしまうリスクもありますし、競合が実際にその権利を活用する可能性も見えてきます。
ただ出願されているだけの特許と、ちゃんと登録されて維持されている特許とでは、意味が大きく違います。
ただし、データベース上の情報は更新の遅れや誤りを含む可能性もあるため、最終的な権利の有効性や権利行使の可否といった法的な判断を下す際には、各国の特許庁が提供する公式な登録情報や、必要に応じて現地の専門家による確認が推奨されます。
この段階での確認は、調査の信頼性を大きく左右する、大事なプロセスです。
参考文献:
- International Patent Classification (IPC)
- 特許情報プラットフォーム
- the patentscope user’s guide | wipo
- Guide to the International Patent Classification (2024)
ステップ5:引用・被引用関係で漏れをチェック
検索式や分類コードをどれだけ工夫しても、わずかに条件から外れただけで重要な文献が漏れてしまうことは珍しくありません。こうした「検索漏れ」は、後々の分析や競合対応において致命的な抜け穴となる可能性もあります。
そこで検索戦略の“最終確認”として有効なのが、文献の引用・被引用関係をたどる「芋づる式調査」です。
これは、ある特許文献が技術的根拠として参照した他の文献(引用元)、あるいはその文献を後から参照した別の文献(被引用先)を手がかりに、関連技術のつながりを洗い出していく方法です。
たとえばJ-PlatPatでは、特許や実用新案の「特許・実用新案番号照会/OPD」機能を利用することで、文献の引用記録やファミリーに紐づく分類情報を確認できます。
また意匠に関しても、検索結果画面から「参考文献情報」ボタンを選べば、当該意匠が参照した類似の意匠文献を時系列でさかのぼることが可能です。
これらの機能を使えば、初期検索では見逃していた周辺技術や関連出願を補足的に拾い上げることができ、検索結果の抜け漏れを補完する「検算」としての役割を果たします。
もっとも、J-PlatPatに収録されていない引用情報もあるため、引用関係の調査を重視する場合には、EspacenetやGoogle Patentsとの併用も視野に入れると安心です。
検索の網からこぼれ落ちた重要文献を見つけ出す手がかりとして、引用関係をたどる手法は非常に有効です。とくに出願人の技術展開や業界の技術トレンドを分析したいとき、検索戦略の締めくくりとして、この芋づる式の確認は欠かせないプロセスと言えるでしょう。
参考文献:
- International Patent Classification (IPC)
- 特許情報プラットフォーム
- the patentscope user’s guide | wipo
- Guide to the International Patent Classification (2024)
まとめ
海外でのビジネス展開を成功させるには、国際特許検索が欠かせません。競合他社の権利状況を把握し、思わぬリスクを避けることで、自社の技術を安全に守ることができます。
そのためには、出願番号や分類コードを正確に扱い、翻訳環境を整えることが基本です。さらに、AIや複数の特許データベースを組み合わせて使えば、検索の正確さや作業の効率を大きく高められます。
また、検索式や調査の結果を社内で共有すれば、特許調査が特定の人に依存せず、組織の知的資産として積み重ねていけます。近年では、生成AIの進化によって、以前は専門家にしかできなかった調査も、実務の現場で幅広く活用できるようになってきました。
特許検索は単なる情報収集ではなく、戦略を立てる出発点です。企業が国際市場で競争力を持ち続けるためには、この視点での継続的な取り組みが求められます。
なお、本記事は国際特許検索に関する一般的な情報提供を目的としており、個別の事案に対する法的な助言や見解を示すものではありません。実際の調査、権利の解釈、侵害判断、その他の法的な意思決定にあたっては、必ず弁理士や弁護士などの専門家にご相談ください。
エムニへの無料相談のご案内
エムニでは、製造業をはじめとする多様な業種に向けてAI導入の支援を行っており、企業様のニーズに合わせて無料相談を実施しています。
これまでに、住友電気工業株式会社、DENSO、東京ガス、太陽誘電、RESONAC、dynabook、エステー株式会社、大東建託株式会社など、さまざまな企業との取引実績があります。
AI導入の概要から具体的な導入事例、取引先の事例まで、疑問や不安をお持ちの方はぜひお気軽にご相談ください。
引用元:株式会社エムニ