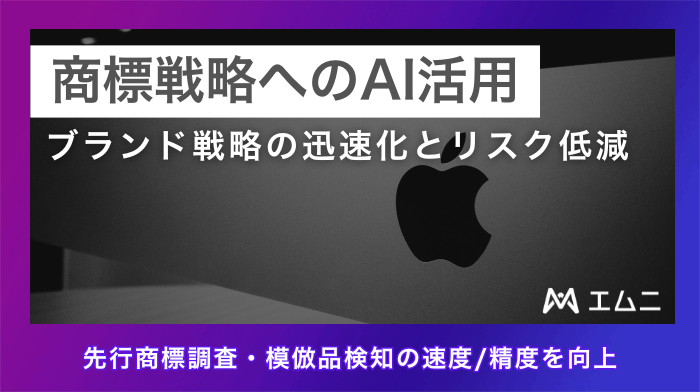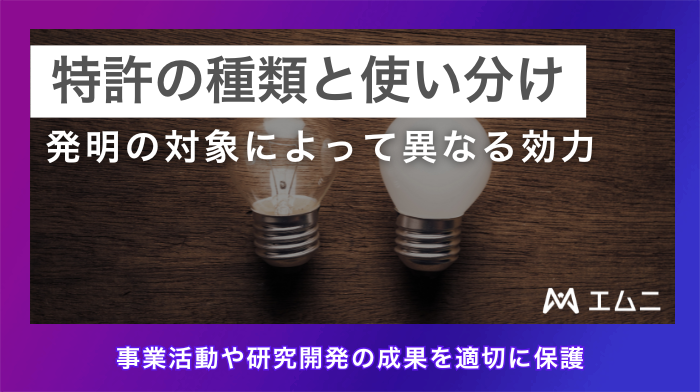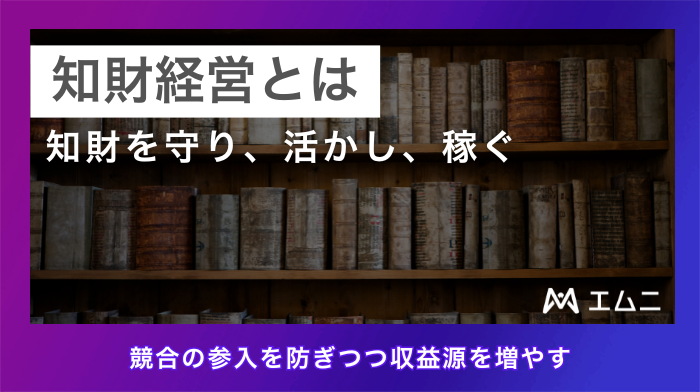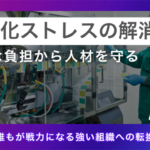
仕事の属人化ストレスを解消|原因や取るべきアクションを徹底解説
2025-08-22
産業財産権(工業所有権)とは?特許・実用新案・意匠・商標の違い
2025-08-26国際特許分類(IPC)を徹底解説|グローバル競争を勝ち抜く武器
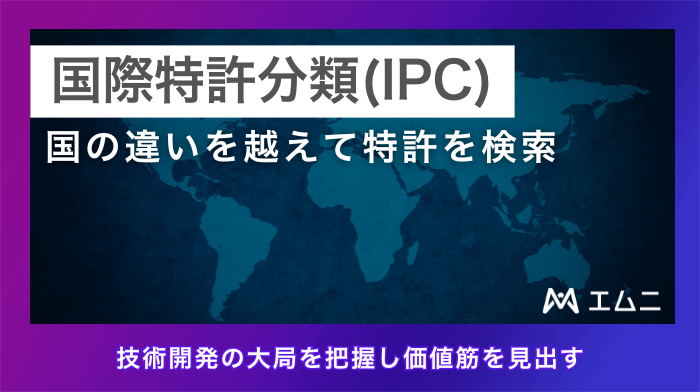
世界では毎年およそ300万件の特許が出願されます。特許調査や技術動向の分析では、この膨大な情報の中から必要な文献を正確かつ効率的に探し出せるかどうかが、調査の成否を左右します。
その際に欠かせないのが、世界中の特許文献を技術内容に基づいて整理する「国際特許分類(IPC)」です。IPCは単なる専門知識ではなく、研究開発や競合分析など、イノベーションに関わるあらゆる場面で役立つツールです。
本記事では、IPCの概要、日本独自のFI、米欧のCPCとの違い、調査方法や活用メリット、注意点までをわかりやすく解説します。
国際特許分類(IPC)とは
国際特許分類は、世界中の特許情報を体系的に整理し、誰もが効率的にアクセスできるようにするための国際的な規格です。
ここでは、IPCがどのような仕組みで成り立ち、なぜ創設され、どのような構造を持つのかといった基本的な概要を解説します。
世界共通の特許分類システム
国際特許分類(IPC:International Patent Classification)は、世界知的所有権機関(WIPO)が管理する世界共通の特許分類システムです。
具体的には、アルファベットと数字を組み合わせた分類記号を用いて特許の技術内容を体系的に整理したものです。
これにより、国や言語の違いを越えて同じ基準で検索できるのが最大の特徴です。各国の特許文献には通常「Int. Cl.」という表示とともにIPCコードが記載され、国際的な特許調査の出発点となります。
IPCが導入される以前は各国で独自の特許分類体系が構築されており、国際的な特許調査を非常に困難なものにしてきました。
この課題を解決するためにIPCが整備され、世界共通の基準で先行技術調査を行える仕組みが確立されました。
現在IPCは新規性や進歩性の審査だけでなく、技術分野の動向把握や技術発展の統計作成といった役割も担い、国際的な特許情報の活用を大きく促進しています。
IPCの階層構造
IPCは、広い分野から個別の技術へと段階的に分ける「階層構造」を採用しています。この仕組みにより、約8万項目に及ぶ分類の中から、目的の技術分野を正確に特定できます。
最上位にはA(生活必需品)からH(電気)までの8つの「セクション」があり、その下に「クラス」「サブクラス」「メイングループ」「サブグループ」という順に細分化された階層を持ちます。
| セクション | クラス | サブクラス |
| A 生活必需品 | 01 農林水産業など | B 土作業/C 植付け… |
| 21 生地製造・加工 | B 焼窯/C 加工機械… | |
| … | … | … |
| B 処理操作・輸送 | 01 物理的・化学的手法と装置 | B 沸騰/D 分離/F 混合… |
| … | … | … |
| H 電気 | 01 電気素子 | B ケーブル/C 抵抗器/F 磁石… |
例えば、ベーカリー用オーブンはセクションではA、クラスでは21、サブクラスではBに該当するので、A21B〇〇〇といったコードが割り当てられます。
このような構造を理解しておくと、特許調査を効率的に行えるようになります。例えば、まず大まかな技術分野をセクションで絞り込み、続いてクラスやサブクラスで詳細化することで、膨大な特許文献の中から目的の技術に素早く辿り着けます。
IPCと他の特許分類
IPCは世界共通の基盤ですが、より詳細な調査や特定地域の特許調査を行う際には、各国や地域が独自に展開している分類体系の理解が不可欠です。
中でも、日本独自のFIと欧米で共同開発されたCPCは特に重要です。それぞれの特徴とIPCとの違いを把握し、調査の目的や対象国に応じて使い分けることで、効率性と精度の高い特許調査が可能になります。
日本独自の分類「FI」
FI(File Index)は、日本国特許庁(JPO)がIPCをさらに細分化して作成した、日本独自の特許分類です。
IPCがおよそ8万項目からなるのに対しFIは約19万項目に及び、よりピンポイントでの文献検索を可能にしています。
FIはIPCのサブグループの末尾に3桁の数字(展開記号)やアルファベット1文字(分冊識別記号)を付与したもので、日本の技術事情に即した詳細分類を実現しています。
また日本国内での無効資料調査や侵害予防調査など、深度のある先行技術調査において欠かせない存在です。
▼FIについて詳しく知りたい方はこちら
特許FIとは|分類の整理・利用メリットを徹底解説
米国・欧州の共通分類「CPC」
CPC(Cooperative Patent Classification)は、欧州特許庁(EPO)と米国特許商標庁(USPTO)が共同開発・運用している特許分類体系で、IPCをベースにさらに詳細化されています。分類項目は25万以上に及び、世界で最も精緻な分類体系といえます。
FIと同様にIPCを細分化したものでありながら、欧米だけでなく中国や韓国などでも採用が広がっており、グローバルな特許調査ではCPCの重要性が高まっています。
特に、技術革新の激しい分野や分野横断的な新技術(Yセクション)では、強力な調査ツールとして機能します。
IPC・FI・CPCの使い分け
IPC、FI、CPCはいずれも特許調査における重要な分類体系ですが、それぞれ得意とする分野は異なります。
調査の目的や対象市場に応じて、適切に使い分けることが高精度な調査の鍵となります。
| 分類体系 | 主な用途 | 得意な調査範囲・分野 | 活用例 |
| IPC | 世界中の特許を広く網羅的に調査 | 独自分類を持たない国、国際的な技術動向把握 | 海外市場の参入前に全体の特許状況を俯瞰する |
| FI | 日本国内向けの詳細調査 | 日本特許の無効資料調査、侵害予防調査 | 国内製品開発前に関連特許を精査 |
| CPC | 米国・欧州を中心とした先端分野調査 | 技術革新の速い分野、分野横断的技術(Yセクション) | 欧米市場向け新技術の特許動向調査 |
IPCを活用するメリット
IPCを用いた特許調査は、単に文献を探しやすくするだけではありません。言語の壁を越え、調査の網羅性を高め、さらに技術開発の大きな流れを把握するなど、戦略的な利点をもたらします。
ここでは、その代表的な3つのメリットを紹介します。
言語の壁を超えて調査できる
特許文献は世界中で様々な言語で公開されますが、IPCは世界共通の分類記号で整理されているため、言語に依存しない検索が可能です。
例えば、日本の企業が中国の特許を調べたい場合、関連するIPCを指定するだけで、キーワードを中国語に翻訳することなく、該当する技術分野の文献を効率的に抽出できます。
この「言語の壁を越える」特性は、国際的な先行技術調査やグローバル市場の技術動向分析で特に有効です。
網羅的な技術調査が可能になる
キーワード検索だけでは、同義語や言い回しの違いによって重要な文献を見逃すリスクがあります。
しかしIPCは発明の「技術的本質」に基づいて分類されるため、異なる表現が使われていても同じ技術内容であれば同じ分類が付与されます。
例えば、ドローンの配送技術に関する特許は「無人航空機」や「小型飛行体」など、表現が異なっても同じ分類で検索可能です。この特性は、無効資料調査など、網羅性が求められる場面で特に力を発揮します。
技術動向の分析に活用できる
IPCは個別文献の検索だけでなく、特許出願データを集計・可視化することで、技術全体の動向を読み解くこともできます。
例えば、特定のIPCを持つ特許出願件数の推移を分析すれば、その分野が成長期にあるのか、成熟期に入っているのかを把握できます。
また、競合企業がどの分類に重点的に出願しているかを調べれば、研究開発戦略や将来の事業展開を予測する手がかりになります。
▼技術動向の分析をはじめとした知財戦略について詳しく知りたい方はこちら
企業価値を創る知財戦略|特許ポートフォリオの構築・分析・活用
IPCの調べ方
日本の特許情報プラットフォーム「J-PlatPat」を活用すれば、誰でも無料で高度な分類検索が行えます。
ここではその基本的な調査手順と、検索精度を高める応用方法を解説します。
J-PlatPatを使った基本的な調査手順
日本での特許調査において最も基本的なツールが、INPIT(工業所有権情報・研修館)が提供する特許情報プラットフォーム「J-PlatPat」です。
まず「特許・実用新案分類照会(PMGS)」機能にアクセスし、調査対象となる技術のキーワード(例:「ドローン 配送」)を入力します。すると、関連性の高いIPCやFIの候補が表示されます。
次に、その分類コードの定義を確認し、最も適切なものを選択して「特許・実用新案検索」画面で検索を実行します。これが分類調査の基本的な流れです。
キーワードを組み合わせて精度を上げる方法
最も効率的な特許調査は、分類検索とキーワード検索を組み合わせた「ハイブリッドアプローチ」です。
まずはIPCなどの広めの分類を指定して関連文献を網羅的に抽出し、その後、具体的な用途や技術的特徴を示すキーワードを掛け合わせることで、ノイズ(無関係な文献)を減らします。
例えば「A21B 1/42 AND 回転式」などと指定すれば、ベーカリー用回転式オーブンの特許文献に効率的に絞り込むことができます。この二段階検索によって、網羅性と精度の両立が可能になります。
分類表(パテントマップ)の活用
IPCはパテントマップ(特許マップ)作成の軸としても有効です。
例えば縦軸に出願人(企業名)、横軸にIPC(技術分野)を置き、各マスに出願件数をプロットすれば、「どの企業がどの分野に強いのか」が一目で把握できます。
この分析によって、競合の強みや弱み、さらには誰も手を付けていない「ホワイトスペース(空白技術領域)」の発見が可能となり、研究開発や事業戦略の立案に役立ちます。
▼パテントマップについて詳しく知りたい方はこちら
パテントマップとは?具体的な用途から導入方法まで
またエムニでは、こうしたパテントマップ作成や分析を効率化するために、独自のAI特許分析ツール「AI特許ロケット」を提供しています。
膨大な特許情報を自動で分類・可視化し、従来では見落としがちな技術トレンドや競合動向を迅速に抽出可能なので、気になる方はぜひご確認ください。
国際特許分類(IPC)の注意点
IPCは非常に有用な調査ツールですが、その特性や限界を理解せずに利用すると、重要な情報を見落とす恐れがあります。ここでは、特に注意すべき3つのポイントを解説します。
分類付与のブレが生じることがある
IPCは世界共通の基準で運用されますが、実際に分類を付与するのは各国の特許庁の審査官です。
そのため、同じ発明内容でも、審査官や国によって分類が微妙に異なることがあります。
この「分類付与のブレ」を考慮せずに単一のIPCコードだけで検索を行うと、本来見つけるべき重要な文献を見逃すリスクがあります。
関連する複数の分類を組み合わせ、多角的に調査することが重要です。
最新技術への対応に時間がかかる場合がある
IPCの改訂は年1回のため、急速に発展する分野では分類が追いつかない場合があります。特にAIやIoTのような新技術では、適切な分類がまだ存在しない、あるいは複数の分類に分散してしまうケースが散見されます。
こうした分野の調査では、分類検索だけでなく、最新の技術用語を使ったキーワード検索を併用することが欠かせません。
IPCだけでは詳細な調査に限界がある
IPCは約8万項目から成る詳細な分類体系ですが、日本や欧米のように特許出願が集中する国ではそれだけでは十分に絞り込みきれないことがあります。
特に、特定の分野に数千件規模の特許が集中している場合、最も細かいサブグループで検索してもノイズが多くなる可能性があります。
こうした場合には、日本独自のFIや、欧米のCPCといったさらに細分化された分類を併用することで、精度と効率を両立させることができます。
まとめ
国際特許分類(IPC)は、特許文献を整理するための単なる索引ではなく、世界中の技術情報を結びつけ、言語や国境を越えて共有するための「共通言語」です。
その階層構造を理解し、キーワード検索や他の分類体系(FI・CPC)と組み合わせれば、調査の網羅性と精度を大きく向上させることができます。
さらに、IPCデータを分析してパテントマップを作成すれば、競合の戦略を読み解いたり、新たな事業機会を見つけたりすることも可能です。
技術開発や事業戦略において、IPCを自在に使いこなす力は、もはや専門家だけのものではなく、グローバル競争を勝ち抜くための、現代の必須スキルです。
エムニへの無料相談のご案内
エムニでは、製造業をはじめとする多様な業種に向けてAI導入の支援を行っており、企業様のニーズに合わせて無料相談を実施しています。
これまでに、住友電気工業株式会社、DENSO、東京ガス、太陽誘電、RESONAC、dynabook、エステー株式会社、大東建託株式会社など、さまざまな企業との取引実績があります。
AI導入の概要から具体的な導入事例、取引先の事例まで、疑問や不安をお持ちの方はぜひお気軽にご相談ください。
引用元:株式会社エムニ