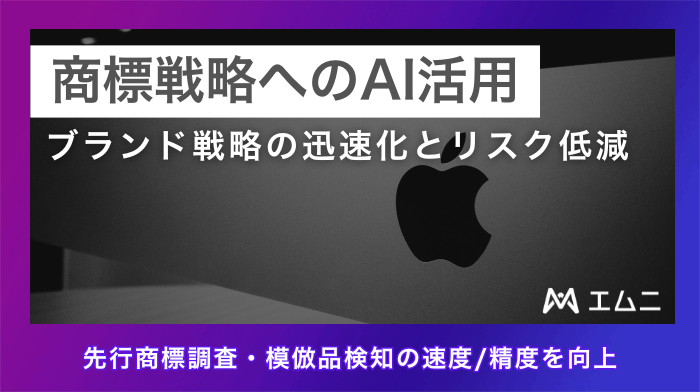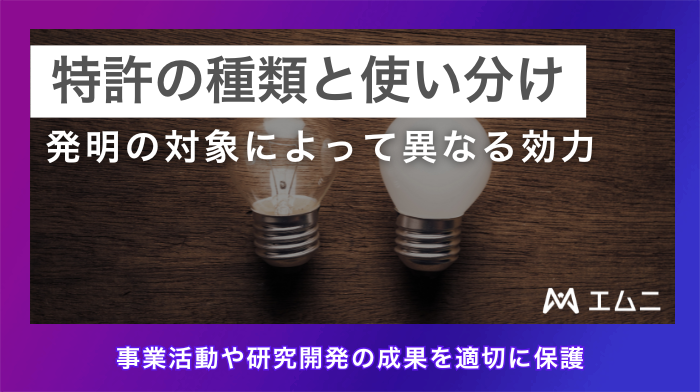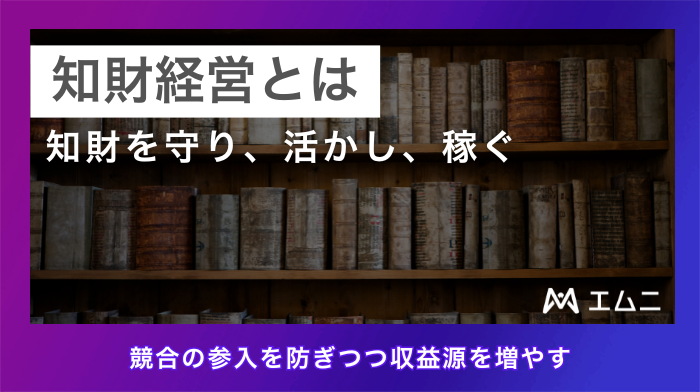特許取得のメリット・デメリット|利益を生み事業を守る知財戦略
2025-06-30
パテントマップの作り方やAIを活用した効率化を徹底解説
2025-07-23AIでパテントマップ作成の質・速度を劇的にUP
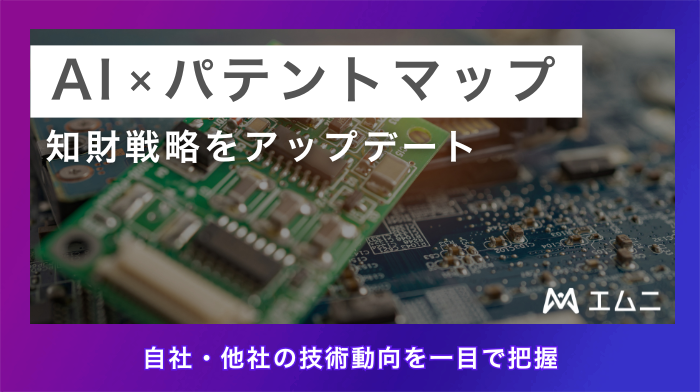
「パテントマップを作成したいけれど、時間も手間もかかってしまう」「専門知識がなければ、正確な特許分析は難しいのではないか」。そんな悩みを抱えていませんか?
近年のAI技術の進化は、知的財産の分野にも大きな変化をもたらしています。これまで専門家が膨大な時間をかけて行っていたパテントマップの作成も、AIを活用することで大幅に効率化できるようになりました。
この記事では、AIを活用したパテントマップ作成の具体的なメリットと手順などを解説します。
そもそもパテントマップとは?なぜ重要なのか
パテントマップとは、膨大な特許情報を特定の切り口で整理・分析し、その結果を図やグラフなどで可視化したものです。
パテントマップの最大の特徴は、“現状を一目で把握できる”点です。これまで手探りで技術動向を探っていた状況から、一目で全体像を示す地図のおかげで進むべき方向がはっきりと見え、自信を持って開発を進められるようになります。
この技術により、経験や勘に頼らず、データに裏打ちされた意思決定が可能となり、研究開発の無駄を省きながら効率的に競争優位を築くことができるでしょう。
例えば、競合他社がどの技術分野に、いつから、どれくらいの資源を投下しているのかを時系列で把握することで、他社の技術開発動向を予測し、自社の立ち位置を明確にすることが可能です。
また、市場全体でどの技術が伸びているのか、どこに技術的な課題が残されているのかをマクロな視点で捉えることで、無駄な研究開発を避け、より確度の高いテーマにリソースを集中させられるといえるでしょう。
さらに、新規事業へ参入する際の市場性評価や、まだ競合が少なくビジネスチャンスが眠る技術の空白領域(ホワイトスペース)を発見するためにも、パテントマップは極めて有効な手段といえます。
こうしたパテントマップの活用は、あらゆる技術分野で有効ですが、特にその真価を発揮するのが「製法特許」に関する領域です。製法特許とは、製品そのものではなく、製造方法や工程に対して付与される特許のことを指します。
製造プロセスが差別化の要となる業界では、どのような製法がすでに特許化されているのか、競合がどの技術に注力しているのかを把握することが極めて重要です。
パテントマップを用いれば、こうした情報を体系的に整理・可視化することができ、自社の技術的な強みや差別化のポイントを明確にすることが可能になります。
▼ 製法特許とは|定義や権利化までのプロセスを徹底解説はこちら
参考記事:What is patent mapping? | epo.org
従来のパテントマップ作成が抱える課題
その重要性にもかかわらず、従来のパテントマップ作成には多くのハードルがありました。
まず最大のボトルネックは、膨大な特許公報を手作業で読み込み、分類・集計するために必要となる時間と労力です。
東芝レビューによると、特許情報を分類しマトリックスマップを作成する際には、数十件の出願を俯瞰するだけでも数時間から十数時間を要し、その負荷をいかに軽減するかが大きな課題とされていました。
また、自前のデータベースを構築・維持するだけでも相当な労力を要し、新規分野の特許調査では特にそのハードルが高まります。
有料データベースを用いても、自社の目的に合わせた加工には限界があり、結果として日々更新される膨大な特許情報を常に最新かつ正確に反映させることは容易ではありません。
さらに、キーワード検索だけでは「スマートフォン」「携帯端末」「モバイルデバイス」といった表記ゆれや類義語の問題から重要な特許が漏れてしまうリスクが常につきまといます。
この検索漏れを防ぐためには、国際特許分類(IPC)や日本独自の細かな分類コード(FI・Fターム)など、技術領域ごとに割り振られた分類を使いこなす高度な検索スキルが求められました。
こうした手作業中心のワークフローは、ヒューマンエラーを誘発しやすく、分析結果の信頼性を損ないかねない点も無視できません。
結果として、パテントマップの作成には多くのコストと時間を要し、事業部門が迅速に意思決定を行ううえで大きな障害となっていました。これが、従来のパテントマップ作成における最大のボトルネックといえるでしょう。
参考文献:
AIがパテントマップ作成にもたらす3つの恩恵
このような従来の課題を解決するのが、AI技術です。AIの活用は、パテントマップ作成のプロセスを根底から変え、これまで一部の専門家のものだった高度な特許分析を、多くのビジネスパーソンにとって身近なものにしました。
AIがもたらす恩恵は多岐にわたりますが、ここでは特に重要な3つのポイントについて解説します。
調査・分析時間を最大80%削減
AIが特許調査にもたらす最も顕著な変化は、従来の常識を覆すほどの時間短縮です。
これまで専門家が数週間かけて行っていた特許公報の読み込みや、膨大な関連文献のスクリーニング、不要な文書の除去といった作業が、AIの導入により、わずか数分から数時間で完了するようになりました。
これは単に「速くなった」という次元にとどまらず、調査プロセスそのものを根本から再構築するものといえるでしょう。AIは、大量の特許データや技術文書を一括で処理し、分野横断的に情報を整理・抽出する能力を備えています。
その結果、従来は時間的制約から調査対象外とされていた文献群もカバーできるようになり、調査の網羅性と精度が大幅に向上したのです。
実際に、AIを活用したプラットフォームでは、調査から分析にかかる時間を最大80%削減できたという報告もあります。
この短縮によって生まれた余剰時間は、単なる事務的な処理を超え、戦略的な思考や、知財価値を高めるための創造的な業務に充てられるようになっています。
AIは、知財プロフェッショナルの役割を、より高度かつ本質的なものへと進化させる有力な手段となりつつあるのです。
参考記事:What is AI Patent Validity Search? A Clear Explanation • Patlytics
専門家でなくても高精度な分析が可能に
AIの進化により、特許調査はもはや限られた専門家だけの業務ではなくなりつつあります。
従来の特許調査には、高度な検索スキルや分類知識、さらには業界固有の用語に対する深い理解が求められてきました。
しかし現在では、自然言語処理(NLP)を活用したAIツールの登場によって、非専門家でも直感的かつ高精度な検索や分析が可能になっています。
たとえば、PQAIのような自然文検索に対応したAIツールを使えば、「〇〇を可能にする技術」といった日常的な言葉で入力するだけで、AIがその意味を理解し、関連する特許文献を抽出してくれます。
キーワードの厳密な指定や複雑な分類コードの知識がなくても、アイデアの内容に基づいた的確な先行技術検索が行えるのです。
さらに、WIPOの「IPCCAT」やPQAIの「AI Powered CPC Lookup」など、AIベースの自動分類ツールを活用することで、専門的な知識がなくても入力テキストに応じた適切な特許分類(IPCやCPC)が提案されます。
引用元:IPC/CPC Suggestion Tool – PQAI
これらのツールは、すでに膨大な特許データで訓練されたAIモデルを活用しており、ユーザーが記述した技術内容に対して、最も関連性の高い分類コードを自動で提示してくれる仕組みです。
このような技術の進化は、従来人間の経験と勘に大きく依存していた初期分析の工程を大幅に効率化しつつあります。誰もが手軽に、しかも高い精度で特許調査を行える環境が整いつつあると言えるでしょう。
AIは、特許分析へのアクセス障壁を取り除き、知財に不慣れなユーザーにも新たな可能性を開く強力な支援ツールとなっているのです
参考記事:
- AI-Powered Patent Searches – Inventors Digest
- AI-based Classification for IP Data
- PQAI – Patent Search Tool | Parola Analytics
検索漏れや解釈ミスをAIが防ぐ
パテントマップの作成において、まず重要なのは「必要な特許情報を漏れなく収集できているかどうか」です。
しかし、従来のキーワード検索では、専門的かつ多様な表現に対応しきれず、入力語と完全に一致しない文献が検索から漏れてしまうケースが多く見られました。これにより、調査の網羅性と信頼性に大きな課題が残っていたのです。
この問題に対して、AIによるセマンティック検索(意味検索)が大きな革新をもたらしています。これは単語の一致ではなく、文全体の意味や文脈を理解し、関連性の高い情報を抽出する仕組みです。
たとえば、「自動車の自動ブレーキ」と検索すれば、「車両の衝突回避システム」や「先行車検知による減速制御」といった、異なる言い回しでも本質的に同じ技術を含む特許が的確にヒットします。このように、言語の表現ゆれを吸収しながら、必要な情報を漏れなく拾うことが可能になります。
この背景には、自然言語処理(NLP)の進化があります。AIは単語を単なる文字列ではなく、文脈の中で意味を持つ情報として理解・処理します。実際、米国特許庁などでは、単語やフレーズを意味単位で再構成し、検索者の意図と文献情報を照合する仕組みが導入されています。
こうした意味理解に基づく検索技術は、Clarivateの「Smart Search」など、既に実用化されているAIツールにも反映されています。AIは自然言語の入力から、関連性の高い特許を短時間で抽出し、パテントマップの網羅性と精度を高める役割を果たしているのです。
さらに、非構造化データ(テキストや音声など)を活用したフィードバックループを通じて、検索精度は時間とともに継続的に向上していきます。
つまり、意味検索の導入は、パテントマップの精度と信頼性を根本から底上げする技術革新であると言えるでしょう。
▼ パテントマップの基礎知識を知りたい方はこちら!
パテントマップとは?具体的な用途から導入方法まで
参考記事:
- PATENTSCOPE | WIPO Inspire
- Search smarter with Smart Search | Clarivate
- US20160147878A1 – Semantic search engine – Google Patents
- 生成AIを使った電話対応の効率化・自動化~インフラ(電気・ガス・水道)業界編~ | コラム | クラウドソリューション|サービス|法人のお客さま|NTT東日本
パテントマップへのAI活用例
AIは具体的にどのようにパテントマップ作成プロセスに組み込まれ、その能力を発揮するのでしょうか。
ここでは、AIの具体的な活用例を4つの機能に分けて紹介します。これらの機能を組み合わせることで、分析はより速く、深く、そして正確になります。
AI自動分類:独自の視点で特許を整理・分析
特許戦略を構築・運用するうえで、膨大な特許文献の分類・分析は不可欠です。企業は競合動向の把握や技術開発の方向性検討、侵害リスクの回避など、あらゆる場面で特許情報を活用しますが、年々増加する出願件数により、人手による分類作業は限界を迎えつつあります。
こうした課題に対し、AI技術を活用した特許文献の自動分類が注目を集めています。従来、人間の専門家が担っていた煩雑な分類作業を、AIが高速かつ高精度に代替することで、知財業務の効率と質の向上を実現するのが狙いです。
たとえば、ある企業では重点テーマである「環境配慮技術」の下に、「軽量化」「リサイクル性」「省エネルギー」などの独自カテゴリを定義しました。それぞれのカテゴリに代表的な特許文献を“お手本”として提示し、AIに学習させています。
AIはBERTなどの高度な自然言語処理モデルを用い、要約文や請求項、分類コード、解決手段や効果の表現など、複数の情報源をもとに分類基準を自動的に習得。わずかな教師データで、数千件規模の特許文献をミリ秒単位で分類することが可能になります。
実際の運用例では、2,357件の試験データに対してAIによるランキングテストを実施した結果、関連文献を91%の高精度でカバーしました。さらに、分類作業の作業量も67%削減され、業務効率が大きく改善されたと報告されています。
仮に月間500件の文献を分類する場合、毎月約5時間半の人的工数を削減できるとされており、日常的な業務への適用も十分現実的です。
加えて、特許専用に設計・学習されたAIモデルは、未知語の発生率を0.04%以下に抑制。小規模なモデルでも高い分類性能を維持できる点が特長です。
また、WIPOが提供するIPCCATのように、日本語を含む9言語でクロスリンガル分類に対応する技術も登場しており、グローバルな特許監視体制の構築にも寄与します。
このようなAI自動分類機能は、たとえばSDI(Selective Dissemination of Information)調査での継続的な出願モニタリングや、特定技術分野に関する侵害回避調査など、専門性の高い分析業務でも非常に有効です。
従来のキーワード検索に頼る手法では見落とされがちだった関連文献も、AIによる分類モデルが正確に抽出してくれるため、専門家はレビューや戦略立案といった中核業務に専念できます。その結果、企業の知財戦略における俊敏性と網羅性は大きく向上するでしょう。
参考文献:
- AI-based Classification for IP Data
- 最適学習モデル構築技術を搭載したAI特許 自動分類ツール(PatentNoiseFilter)
- 特許文献によるBERT事前学習モデルと特許調査業務への応用
- Patent Landscape Report – Generative Artificial Intelligence (GenAI) – Appendices
生成AIによる要約・分析:膨大な情報のインプットを効率化
特許公報は1件あたり何十ページにも及び、その内容を正確に把握するには多大な時間と集中力が求められます。こうした負担を軽減する手段として注目されているのが、生成AIを活用した特許要約の技術です。
最新の特許分析ツールでは、AIが長文の特許公報をわずか数行に要約し、要点だけをすばやく把握できるようになっています。
たとえば、AcclaimIPのツールでは、GPT-4やClaude-2といった大規模言語モデルを活用し、「発明の概要」「用途」「技術的な特徴」といった複数の視点から、特許文献を多角的に要約することが可能です。
人が見落としがちな細かな情報にも目を向け、重要なポイントを的確に抽出することができます。
また、IamIPのAIツールでは、特許文書を自動的に解析し、短時間で簡潔な要約を作成。従来よりも圧倒的に少ない労力で、多数の特許をスクリーニングできるようになっています。実際に、数百件規模の特許調査を行う現場では、作業時間を大幅に削減できたとの報告もあります。
さらに、生成AIは単なる要約にとどまらず、より高度な分析にも対応可能です。
たとえば、ある企業が過去3年間に出願した特許群をAIに読み込ませ、「どのような技術が注目されているか」「どのような課題の解決を目指しているか」といった技術的トレンドを抽出することもできます。
このような応用は、カーネギーメロン大学をはじめとする研究機関でも進められており、企業の研究開発や知財戦略においてAIが強力な分析パートナーとなる未来が、現実味を帯びてきました。
生成AIは、膨大な情報のインプットを高速かつ高精度でこなす点において、特許分析の作業を根本から変革すると考えられます。調査担当者は、膨大な文献の読み込みから解放され、より価値の高い判断や戦略立案に注力できるようになるでしょう。
▼ 生成AIで変革する製造業の未来|メリットや事例・導入ポイントはこちら
生成AIで変革する製造業の未来|メリットや事例・導入ポイント
参考記事:
- High-Quality AI Generated Summaries for Patents | AcclaimIP
- AI Patent Summarizer – IamIP
- About – Center for AI and Patent Analysis – Carnegie Mellon University
パテントマップの自動生成と可視化:複雑な関係性を一目で把握
特許データを収集し、AIで分類・分析したあとは、その結果を可視化して全体像を直感的に理解するフェーズが重要です。
こうした工程も現在ではAIツールが担い、ワンクリックでパテントマップを自動生成できるようになっています。
たとえば、出願人別の出願件数分布、技術分野ごとの出願件数推移、企業間の引用関係を示すネットワークマップなどが、瞬時に生成される仕組みです。これにより、情報が視覚的にわかりやすく提示され、誰でも直感的に全体像を把握できるようになります。
このような可視化を実現しているのは、AIが文書の内容、出願日、IPC分類、引用関係といった多層的なデータを統合的に解析し、ヒートマップやクラスター分析、フォースレイアウト型ネットワーク図などへと動的に変換する技術にあります。
たとえば、Questel、IPRally、LexisNexisといった先進的なツールでは、引用・被引用構造や技術の関連性を視覚化する高度なインターフェースが整っており、特許群全体の技術的ポジションや未開拓領域を簡潔に把握することが可能です。
また、時間軸に沿った出願件数の推移を表示することで、特定技術の成熟状況や競争の激化、新興分野の台頭といった動向も読み取りやすくなります。
さらに、AIがナレッジグラフを生成する仕組みによって、企業間における技術的なつながりや知識の流れも可視化されるようになっています。
たとえば、どの企業がどの技術を引用しているかといった情報は、かつては専門家が一件ずつ読み解いていたものでした。しかし現在では、AIがその構造を自動で抽出し、視覚的に整理されたマップとして提示することが可能となりました。
この結果、企業の技術的優位性、協業可能性、新たな競争相手の出現といった、これまで気づきにくかった戦略的なインサイトが自然と浮かび上がってきます。
このように、AIによるパテントマップの自動生成と可視化は、複雑な特許データの背後にある意味のネットワークを「見える化」する役割を果たします。知財戦略や技術開発の方向性を迅速かつ的確に導くための強力な支援ツールになるといえるでしょう。
参考記事:
- AI による特許マッピングとクレーム分析 – Questel
- Top 5 Patent Analysis Tools for 2024 | Solve Intelligence
- IP Citation Network Mapping
- A Comprehensive Survey on AI-based Methods for Patents
AIによるパテントマップ作成を経営戦略に活かす方法
AIによって効率的かつ高度に作成されたパテントマップは、単なる技術資料にとどまりません。それは、企業の未来を左右する経営戦略の意思決定において、客観的な根拠となる強力な武器となります。
▼ 製造業のDXとは?メリット・ロードマップ・事例を徹底解説はこちら
製造業のDXとは?メリット・ロードマップ・事例を徹底解説 – オウンドメディア
競合分析で一歩先を行く
AIを活用したパテントマップは、競合他社の技術戦略や提携動向を可視化し、次の一手を予測するための強力なツールです。
ある企業が特定の技術分野で特許出願を急増させていれば、その分野での製品投入や事業化が近い可能性が高く、事前にその兆候を掴むことで、他社より早く戦略を展開することができます。
実際に、中国のXiaomiは電気自動車(EV)分野への進出を正式に発表する以前から、バッテリーや自動運転関連の特許を集中的に出願していました。これを早期に捉えていた企業は、競合の参入を先読みし、自社の対策を検討する時間を確保できたはずです。
また、パテントマップでは、企業間の共同出願データから提携やアライアンスの傾向を読み取ることもできます。
たとえば、MicrosoftとOpenAIがAIモデルに関して複数の共同出願を行っていたことは、両社の戦略的連携の強さを示すものであり、そうした動きは製品やサービスの発表よりも早く、特許データから察知することが可能です。
こうした情報をもとに、AIパテントマップは競合の技術的な注力領域やパートナーシップの傾向を視覚的に明らかにし、自社のR&D戦略や市場展開を先回りで設計する支援となります。
企業はもはや、競合の動きを“見る”だけではなく、“読む”ことができる時代に突入しています。特許データを正しく読み解く力こそが、次の競争を制する鍵となるのです。
参考文献:
- Analyze Competition with a Competitor Patent Analysis
- The Role of Patent Analytics in Competitive Intelligence | PatentPC
- Identify Emerging Competitors with Patent Analysis
- How to Conduct a Competitive Analysis of Patent Portfolios | PatentPC
根拠のあるR&D戦略を立てる
自社の技術ポートフォリオと市場全体の技術動向を、パテントマップ上で重ね合わせることにより、現在の技術的な立ち位置を客観的に把握することができます。
どの技術領域に強みがあり、どこに弱点があるのかを視覚的に確認できるため、競合他社とのギャップや重複も明確になるでしょう。
混雑したレッドオーシャンに飛び込むのではなく、自社が優位に立てるブルーオーシャンを見出し、未開拓の成長機会にリソースを集中させるという選択も現実的になってきました。
AIを活用した特許分析では、膨大な特許データをもとに技術のトレンドや空白領域(ホワイトスペース)を自動的に抽出することが可能です。
たとえば、ある分野における出願件数の密度が低く、競合の存在が希薄であることが判明すれば、それは将来の差別化につながる開発テーマとなり得ます。
一方で、既に多くのプレイヤーが特許を取得している領域においては、無理に参入を試みるよりも、隣接する分野での独自技術の開発を検討したほうが、長期的には有利といえるかもしれません。
このように、勘や経験ではなく、実証的なデータに基づいて研究開発の優先順位を導き出すことで、R&D投資の方向性に明確な根拠を持たせることができます。
定量的な分析に支えられた技術戦略は、説得力と再現性を備え、社内外への説明力を格段に高める効果が期待されます。
今や、感覚ではなくデータが、勝てる研究開発を導く羅針盤となっている時代です。
参考記事:
- Analyze Competition with a Competitor Patent Analysis
- The Role of Patent Analytics in Competitive Intelligence | PatentPC
- Identify Emerging Competitors with Patent Analysis
- How to Conduct a Competitive Analysis of Patent Portfolios | PatentPC
新規事業の成功確率を高める
パテントマップは、まだ誰も踏み入れていない市場機会を見つけ出すための強力なレーダーです。
市場全体で特許出願が集中している技術領域を分析すれば、今まさに成長している分野を見極めることができます。
逆に、特許出願がほとんど見られない領域、いわゆる「ホワイトスペース」を発見することで、競合がまだ存在しないニッチ市場への参入チャンスも見えてきます。
こうした分析によって、技術面から市場の魅力度や参入障壁を客観的に評価できるため、勘や直感に頼るのではなく、データに裏打ちされた判断が可能です。
実際、特許ランドスケープを用いた分析では、AIや電池技術、半導体などの分野において、企業がどの領域に注力しているかが可視化されており、先行企業の戦略や未開拓領域の発見に活用されています。
こうして導き出された情報は、投資判断や新規事業開発の方向づけにおいて、高い確度を持った根拠となります。
新しいビジネスを成功させるには、技術トレンドと競争環境を正確に把握し、自社にとって最も可能性の高いフィールドを選び抜くことが不可欠です。
その意味で、パテントマップは単なる分析ツールではなく、成功確率を引き上げるための戦略的な羅針盤だと言えるでしょう。
参考文献:
- How Patent Landscape helps Identify Business Opportunities – GreyB
- White Space Analysis | Patent Landscape & Patent Analytics
- White Space Analysis And Patent Landscape Analysis
M&A・アライアンス戦略を加速させる
M&Aや技術提携を成功させるうえで、相手企業の技術力を的確に見極めることは、財務評価と同等以上に重要な要素です。
特許分析ツールを活用すれば、提携候補の企業がどの分野で強みを持ち、どのような技術資産を保有しているかを、定量的かつ短時間で可視化できます。
たとえば「PatentSight」などの分析プラットフォームでは、特許の質と量を評価する指標を用いて、各企業のポートフォリオの優位性や成熟度を明らかにし、M&Aの意思決定に必要な技術情報を一目で把握できます。
こうした技術評価は、単なるスクリーニングにとどまりません。自社が持たない領域を補完してくれる企業や、新市場進出に向けた戦略的パートナー候補を、特許ポートフォリオの類似性や補完性の観点から発見することも可能です。
最新の研究では、特許の分布や技術コードをもとに、企業間の技術的近接性を定量化し、買収先候補の予測モデルまで構築されつつあります。
たとえば、共有する稀少技術の多寡や技術構造の相性などが、将来的なM&Aの可能性を示す指標になるという知見も得られています。
また、表面的に技術が共通していない企業間でも、特許ネットワーク全体を可視化・分析することで、隠れた補完関係やシナジーの可能性が明らかになっていくでしょう。
こうした洞察は、従来のデューデリジェンスでは捉えきれなかった価値を掘り起こし、より精度の高い戦略的アライアンスを促進します。
M&Aや技術提携を単なる規模の拡大にとどめず、イノベーションの起点とするためには、特許データに基づく客観的な技術評価とパートナー探索が、今や不可欠なアプローチとなっているのです。
参考記事:
- Using LexisNexis® PatentSight® to Evaluate an M&A Target
- Machine learning-based similarity measure to forecast M&A from patent data
まとめ
AI技術の進化により、パテントマップ作成は、かつての「時間と手間のかかる専門業務」から、誰もが活用できる「迅速な意思決定ツール」へと大きく変わりつつあります。
膨大な情報を瞬時に処理し、人間では見落としがちな関連性まで見つけ出すAIは、知財戦略における強力なパートナーです。
ただし、忘れてはならないのは、AIはあくまでアシスタントであるという点です。AIが提示した分析結果を鵜呑みにするのではなく、そのデータが何を意味するのかを解釈し、最終的なビジネス判断を下すのは人間の役割です。
多くのAI特許分析ツールでは、無料トライアルが提供されています。まずは一度、その驚くべきパワーを体感してみてはいかがでしょうか。
貴社の知財戦略を加速させるために、AIパテントマップの活用を始めてみませんか?ご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。
エムニへの無料相談のご案内
エムニでは、製造業をはじめとする多様な業種に向けてAI導入の支援を行っており、企業様のニーズに合わせて無料相談を実施しています。
これまでに、住友電気工業株式会社、DENSO、東京ガス、太陽誘電、RESONAC、dynabook、エステー株式会社、大東建託株式会社など、さまざまな企業との取引実績があります。
AI導入の概要から具体的な導入事例、取引先の事例まで、疑問や不安をお持ちの方はぜひお気軽にご相談ください。
引用元:株式会社エムニ