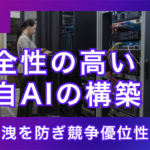
オンプレミスLLMとは|情報漏洩を防ぎつつ競争優位性あるAIを構築
2025-04-29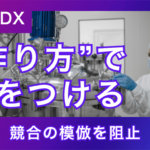
製法特許とは|定義や権利化までのプロセスを徹底解説
2025-05-18製造業の若者離れ|原因や効果的な対策を解説
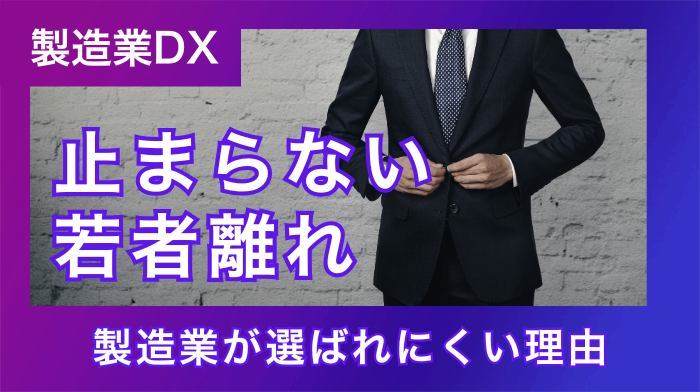
製造業では今、「若者離れ」が深刻化しています。とくに中小企業では人材確保が難しく、高齢化が進む現場では技術継承も危うくなっています。
こうした危機的な状況を受けて、本記事では若者が製造業を離れていく理由や背景を明らかにしながら、イメージの問題や働き方の変化などを具体的に掘り下げていきます。
製造業における若者離れの現状
製造業では、若年層の就業者数が長期的に減少しており、現場の活力低下や技術継承の停滞が深刻な課題となっています。
製造業の若者離れの数値と動向
以下の表は、経済産業省『ものづくり白書2024年』に基づく、製造業における若年就業者に関する主な統計データです。
引用元:ものづくり基盤技術の振興施策
34歳以下の就業者数は2002年に384万人だったのに対し、2023年には259万人まで減少しました。つまり、この20年間で約125万人もの若者が製造業から姿を消したことになります。
全就業者に占める若年層の割合も、同期間で31.4%から25.2%へと大きく低下しており、製造業が若者から選ばれにくくなっている構造が浮き彫りになっています。
| 項目 | 2002年 | 2023年 | 差分 |
| 34歳以下の就業者数 | 384万人 | 259万人 | -125万人 |
| 34歳以下の割合(製造業) | 31.4% | 24.5% | -6.9ポイント |
引用元:ものづくり基盤技術の振興施策
若年層の割合は非製造業でもおおむね25.0%程度にまで低下しており、日本全体で若者の労働力人口が減少しているのが実情です。
とはいえ、製造業では2012年以降、若年就業者数がほぼ横ばいで推移しており、他産業と比較して若者の流入が特に鈍化しているという特徴が見られます。
つまり、製造業は一度離れた若者を呼び戻せておらず、人材の新陳代謝が滞っている状態が常態化しつつあるのです。
このような傾向は、製造業における若者離れが単なる景気の波ではなく、業界特有の課題として根付きつつあることを示唆しています。
就業環境の改善や業界イメージの再構築が遅れるなかで、若者から「選ばれにくい業種」としての位置づけが固定化されてきた可能性も否定できません。
今後は、こうした状況を定量的に把握し、産業全体として若年層の関心をどう取り戻していくのかが問われています。
技能継承や生産現場の持続可能性といった視点からも、製造業には独自の中長期戦略が必要とされているのです。
参考資料:ものづくり基盤技術の振興施策
若者離れの背景にある要因
若者離れの原因は一つに絞ることができず、複数の社会的・経済的要因が複雑に絡み合っています。
ここでは、主な要因として少子高齢化、3Kイメージの定着、そして働き方の変革という3つの視点から背景を解説します。
それぞれの要因は独自の影響力を持ち、全体として製造業に大きな変革を迫っているのです。
少子高齢化の影響
日本社会における少子高齢化の進行は、製造業に限らず、あらゆる産業において労働力の供給に深刻な影響を与えています。
2023年10月1日現在の総人口は1億2435万2千人で、前年から59万5千人減少しており、13年連続の減少となっています。
なかでも、日本人の人口は1億2119万3千人で前年比83万7千人減と、減少幅が年々拡大しており、労働力の中心を担う国内人材の減少が顕著です。
| 年 | 生産年齢人口 (15~64歳) |
| 1995年 | 87,160,000人 |
| 2020年 | 75,090,000人 |
| 2050年(予測) | 52,750,000人 |
引用元:人口推計(2023年(令和 5年)10月 1日現在)‐全国:年齢(各歳)、男女別人口 ・ 都道府県:年齢(5歳階級)
特に、生産年齢人口(15〜64歳)の推移は製造業に大きな影響を与えています。1995年をピークに減少が続いており、2023年時点では7395万2千人と、総人口に占める割合は59.5%まで低下しています。
かつて70%を超えていた水準が急激に縮小したことで、企業は安定的な労働力の確保が難しくなっており、今後もこの傾向が続くと予測される状況です。
さらに、15歳未満人口は総人口の11.4%と過去最低を記録しており、将来的な労働供給力の先細りを如実に示しています。
一方、65歳以上人口は3622万7千人(29.1%)と過去最高を更新し、労働市場の高齢化が進行していることも明らかです。
このような人口構造の変化は、製造業にとって若年労働力の確保を困難にし、持続可能な人材戦略の再構築を迫る決定的な要因となっています。
新卒採用や技能継承の前提が大きく崩れつつある今、企業は採用戦略を抜本的に見直す必要に迫られているのです。
参考資料:人口推計(2023年(令和 5年)10月 1日現在)‐全国:年齢(各歳)、男女別人口 ・ 都道府県:年齢(5歳階級)
3Kイメージの定着とその影響
製造業には「きつい・汚い・危険」という 3Kのイメージがなお根強く、とりわけ「きつい」という先入観が現場を知らない若者の志望意欲を大きく左右しています。
実際、製造業未経験者を対象にした調査では76.2%が「重いものを扱わない軽作業だとは思わない」と回答し、「製造業=体力勝負」という固定観念の強さが浮き彫りになりました。
| 要素 | 内容 |
| きつい | 長時間労働や体力を要する作業 |
| 汚い | 作業環境の衛生面や原材料の汚染 |
| 危険 | 安全対策の不足や事故リスク |
こうしたイメージは就業意欲に直結します。仕事内容を知る前に「きつそうだからやめておこう」と敬遠され、企業は若手と出会う機会を逃しがちです。
その結果、人手不足が慢性化し、負担が現場に集中することで環境がさらに「きつく」なるといった悪循環に陥る危険性があります。
同じ調査では、製造業で「働きたい」または「どちらかというと働きたい」と答えた未経験者はわずか5.0%にとどまり、44.9%は「どちらとも言えない」と回答しました。
積極的な関心を示す層が極めて少ない背景には、ネガティブな先入観と情報不足があると考えられます。
したがって、3Kイメージの払拭は喫緊の課題です。採用企業は実際の職場環境や業務内容、安全対策、労働条件の改善状況を正確かつ積極的に発信し、誤解を解く努力を重ねる必要があります。
また、転居が必要な就業では家賃手当や帰省手当などを明示することで若者の就業意向を高められると示唆されています。
こうした具体的なサポート策を提示することが、若年層の関心を引き上げる有効な手段となるでしょう。
ワークライフバランスの変化と働き方の多様化
近年、若年層は終身雇用や画一的な勤務体系よりも、柔軟で“自分らしい”働き方をいっそう重視するようになりました。
就業時間や働く場所、休暇の取り方をライフスタイルに合わせて選びたいというニーズが高まっているのです。
一方、製造業では今もシフト勤務や交代制などの固定的な勤務体系が主流であり、若者の価値観と噛み合いにくい状況が続いています。その結果、業界への志望度が伸び悩み、生産現場の若返りも進みにくいのが実情です。
以下に、若者が求める働き方の主な要素をまとめます。
| 要素 | 内容 |
| フレックスタイム制 | 自分の生活リズムに合わせた柔軟な勤務時間の設定 |
| 在宅勤務 | 場所を選ばずに業務を遂行できる仕組み |
| 有給休暇の促進 | 計画的な休暇取得を可能にする制度の充実 |
柔軟な働き方を望む傾向は、単なる印象にとどまらず、具体的な行動としても表れています。国土交通省の「令和5年度 テレワーク人口実態調査」表2-6によれば、勤務先から出勤を指示または推奨された場合の対応に興味深い差が見られました。
まず、15~29歳のテレワーカーでは約20.1%がテレワーク継続のために勤務先と交渉すると回答しています。さらに約11.3%は転職や独立を検討するとしており、働き方に対する主体性の高さが際立ちます。
非テレワーカーでも、交渉は13.1%、転職や起業の検討は20.1%に達しました。若年層ほど柔軟な働き方を強く求め、必要であれば転職や独立も辞さない姿勢が浮き彫りになります。
引用元:令和5年度 テレワーク人口実態調査 -調査結果(概要) -
若年層ほど「勤務先の方針に従い出勤する」と答える割合が低く、年齢が上がるにつれて高くなるという調査結果が出ています。この傾向は、従来型の働き方に対する若者の順応度が低いことを示す一方で、柔軟性を求める価値観が世代間で大きく異なることを裏づけています。
こうした状況を踏まえると、シフト勤務や交代制といった製造業特有の勤務体系は、生活設計の自由度を重視する若年層にとって大きなハードルです。
柔軟性を欠く働き方は、採用時のミスマッチだけでなく、定着率やエンゲージメントの低下、さらには離職リスクの増大にも直結しかねません。
製造業であっても企画・管理・技術開発などの部門にはテレワーク導入の余地があります。勤務制度の選択肢を増やし、柔軟な働き方を示せば、若者にとって魅力的な職場環境の整備につながり、採用競争力の向上にも寄与するでしょう。
今後は、業界全体で働き方の多様化を前提とした制度設計と組織文化の見直しを進めることが不可欠です。
参考資料:令和5年度 テレワーク人口実態調査 -調査結果(概要) -
若者離れがもたらす問題点
若者離れは、単に労働力の不足に留まらず、業界全体の技術継承や革新の停滞という深刻な問題を引き起こしています。
ここでは、若者の減少がもたらす具体的な問題点と、それが企業経営や産業の将来に与える影響について検証します。
問題点の正確な把握が、効果的な対策の立案にとって極めて重要であるのです。
労働力不足の進行
近年、製造業や建設業を敬遠する若者が増え、新卒社員や若手技術者の定着率は伸び悩んでいます。さらに少子高齢化も重なり、企業は必要な人材を確保しにくい状況に直面しています。
その結果、労働力不足が生産性の低下や技術継承の停滞を招き、競争力までも失われかねません。
| 影響項目 | 内容 |
| 生産性の低下 | 労働力不足による作業効率の低下 |
| 競争力の喪失 | 新規採用の難航が市場での立ち位置に影響 |
| 事業継続の危機 | 人材不足による事業規模の縮小リスク |
たとえば、株式会社オーザックでは労働環境の整備が追いつかず、新卒社員の早期離職が相次いでいます。
一方、田部井建設株式会社ではベテラン社員に業務負担が集中し、長時間労働が常態化するという悪循環が発生しました。
さらに、有限会社田中製作所の場合、高齢の熟練技術者に依存する体制が長く続き、若手への技術伝承が十分に行われないまま人材が流出している状況です。
若者の離職率の高さは企業の成長戦略を阻むだけでなく、事業継続そのものを危うくする恐れがあります。
若手が働きやすい環境を整えるには、教育体制を充実させると同時に、ベテランとの協力体制を中長期的に見直すことが欠かせないでしょう。
職場の高齢化と技術継承の停滞
製造業で若者離れが進むと、高齢の熟練者に依存する構造が強まり、長年培ってきた技術やノウハウを次世代へ十分に引き継げなくなるリスクが高まります。
高木綱業株式会社では、高度な技術を持ち、将来の幹部候補となり得る中核人材の不足を課題に挙げています。
このような状況が長期化すれば、品質や生産効率の維持が困難になるおそれがあります。現場の改善力にも影響が及び、新たな技術の導入や革新が進みにくくなる可能性も否定できません。
| 問題点 | 内容 |
| 技術継承の停滞 | 若手への技能や知識の伝達が困難な状況 |
| 経験の蓄積不足 | 長期的な視点での技術進化が阻害される |
| 人材育成の断絶 | ベテラン退職後のノウハウの欠如が顕在化 |
引用元:全国「後継者不在率」動向調査(2024年)|株式会社 帝国データバンク[TDB]
日本政策金融公庫の2023年調査によると、60歳以上の代表者のうち60%超が将来的な廃業を予定しています。
事業承継に備えた後継者の育成が十分でないまま、経営者が引退に踏み切るケースが増えています。その結果、たとえ黒字であっても廃業を余儀なくされる企業が目立つようになってきました。
実際、2024年1月から10月にかけて発生した「後継者難倒産」は455件に上り、同年10月には月次として過去最多の63件を記録しました。代表者の病気や死亡をきっかけに、突然事業継続が困難になる事例も多く、こうした理由による倒産は全体の4割を超えています。
また、近年では事業承継の「脱ファミリー化」が進んでおり、社内から後任を選ぶ「内部昇格」が増加しています。
しかし、後継者に業界経験10年以上のベテランを求める企業は依然として多く、若手人材を計画的に育成する取り組みは後回しにされがちです。
このように、後継者不足と若者離れが同時に進行すれば、企業の競争力は著しく低下します。
将来的な技術開発や組織改革も停滞し、黒字経営を続けていても廃業のリスクが高まることが懸念されます。
外部の専門家を招いて事業承継を図る動きも見られますが、製造業では職人的な技能や企業固有の文化・ノウハウが不可欠です。そのため、外部人材だけで短期間に継承を完了させるのは難しいとされています。
経営陣においては、ベテランの知見を早期に可視化し、次世代を担う人材を社内で育てる仕組みを整えることが急務です。
そうした備えがなければ、将来的には事業そのものが存続できなくなるリスクがあることを、真剣に受け止める必要があります。
参考資料:
若者離れに対する具体的な対応策
若者離れの問題を解消するためには、環境改善、働き方の柔軟化、キャリア支援、採用戦略の刷新など、多角的なアプローチが必要です。
ここでは、各対策の具体的な内容とその効果について詳しく解説します。多面的な対策の組み合わせが、持続可能な解決策を実現する鍵となるのです。
職場環境の改善と3Kイメージの払拭
製造業の現場における物理的・技術的な環境改善は、若者が抱く「きつい」「汚い」「危険」といったネガティブなイメージを払拭するために欠かせない取り組みです。
最新の自動化技術の導入やロボットの活用、そして3S(整理・整頓・清掃)の徹底によって、実際の作業環境を大幅に改善することが可能になります。
さらに、新社屋の建設など物理的な刷新が加わることで、企業全体のイメージが向上し、若者が働きたくなる魅力的な職場づくりが実現しつつあります。
たとえば、株式会社オーザックが新社屋を建設し「汚い」というイメージを払拭したように、職場環境の更新は効果的な手段の一つです。
こうした具体的な取り組みは、製造業・建設業を問わず、現場が抱える3Kイメージの解消に共通して有効といえます。以下の表は、職場環境の改善に向けた代表的な取り組みをまとめたものです。
| 改善策 | 内容 |
| 自動化の推進 | 作業工程のデジタル化と機械化による効率化 |
| 3Sの徹底 | 整理整頓と清掃の徹底による清潔な職場環境の実現 |
| 労働環境の刷新 | 安全対策の強化や休憩スペースの充実による働きやすさ |
こうした物理的・技術的な施策を組み合わせることで、「きつい」「汚い」「危険」といったイメージを含めた3Kの払拭に大きく寄与できます。
また、作業効率や生産性の向上にもつながるため、企業全体の競争力を高めるうえでも重要な戦略となります。
環境改善は、若者離れを食い止めるうえで最も効果的な手段の一つであり、今後も継続的な取り組みが求められるでしょう。
ワークライフバランスの向上策
固定的な勤務体系だけでは、いまの若者にとって十分に魅力的な職場とは言えません。
そこで近年は、フレックスタイム制の導入やシフトの柔軟化、有給休暇取得の促進といった働き方改革が欠かせない要素になっています。
たとえば株式会社ズコーシャは、非正規社員も利用できるフレックスタイム勤務を導入しました。その結果、導入前と比べて時間外労働をおよそ14%も削減できたと報告しています。柔軟な勤務時間の整備が、労働負担の軽減へ直結した好例と言えるでしょう。
株式会社ときわでは、コアタイムを設けない完全フレックスを採用しています。ブライダルやイベントの繁忙期などに合わせて各自が勤務時間を自在に調整できるため、プライベートとの両立がしやすいと高い評価を得ています。
さらに、株式会社英田エンジニアリングは「月に1日以上の有給休暇を必ず取得する」という独自の規程を設けました。同社の取り組みにより、従業員は計画的に休暇を取りやすくなり、心身のリフレッシュが進んでいるそうです。
有限会社田中製作所では、有給休暇を1時間単位で取得できる制度へ改定しました。高齢者や子育て中の社員でもこまめに休みを取りやすく、働きやすさが大きく向上しています。
以上のような施策をまとめた一覧は、下表に整理してあります。取り組みのポイントを比較することで、自社にとって最適な改善策を検討しやすくなるでしょう。
| 対策 | 内容 |
| フレックスタイム制 | 柔軟な勤務時間の設定により生活リズムに合わせた働き方 |
| 有給休暇の促進 | 休暇取得のしやすい環境整備と計画的な休暇取得の支援 |
| シフト希望の反映 | 従業員個々のニーズに応じたシフト編成の実現 |
これらの取り組みによって、従業員の満足度と生産性がともに向上し、若者の採用や定着にも大きな効果が期待できます。
キャリア支援と教育プログラムの充実
若者が製造業で腰を据えて働くには、社内に明確なキャリアパスがあること、そして手厚い教育・研修プログラムを提供することが欠かせません。さらに、ハローワークや地域若者サポートステーション(サポステ)といった外部機関と連携し、就業前後のフォローを強化することも重要です。
たとえばハローワークは、求人情報の提供だけでなく職業相談やマッチングを細やかに行い、製造業未経験の若者が自分に合った企業を見つけやすくしています。
サポステでは、フリーターや既卒者など実務経験が限られる層に対し、職業的自立に向けた継続的な支援が行われています。これらのサポートを活用すれば、初めて製造業に飛び込む若者でも安心してキャリアを描けるでしょう。
企業側にとっては、人材確保等支援助成金や中途採用等支援助成金などの公的助成制度が心強い味方になります。
設備投資や職場環境の整備にかかるコストを一部補助できるため、魅力ある職場づくりを進めやすくなり、結果として若い人材の採用・定着率向上につながるはずです。
社内施策としては、多能工の育成とOJTの強化が有効です。まず多能工育成では、複数の工程を体系的に習得できるカリキュラムを整備し、本人のやりがいと柔軟な人員配置の両方を実現します。
OJTに関しては、担当者制のフォローアップやメンタリング制度を取り入れることで、若手社員が安心してスキルを身につけられる環境が整います。
定期的なスキルアップ研修やキャリア開発支援を組み合わせれば、従業員のモチベーションが向上し、業界全体の技術力底上げにも寄与します。
こうした取り組みを総合的に推進することが、若年層の定着と企業の競争力向上を同時に実現する近道と言えるでしょう。
下表は、キャリア支援に関する主な施策をまとめたものです。
| 施策 | 内容 |
| 多能工育成 | 複数の技能を体系的に習得させる教育プログラム |
| OJTの強化 | 現場での実践的な指導と継続的なフォローアップ |
| 研修プログラム | 定期的なスキルアップ研修やキャリア開発支援の充実 |
これらの取り組みに外部の就業支援施策を組み合わせることで、若者が製造業に対して抱きやすい不安を解消し、安心して働ける環境づくりが可能になります。
実際に、サポステやわかものハローワークなどの支援を受けて就職した例では、「初めての現場で不安だったが、相談員や先輩社員のサポートを得てキャリアを積めた」という声が多く聞かれます。
従業員が自己成長を実感しながら業務に取り組めるよう整備された職場は、将来的な技術継承や生産性の向上にも直結し、企業の持続的な成長を支える原動力となるのです。
参考資料:ものづくり基盤技術の振興施策
採用手法の工夫と求人方法の改善
デジタル技術を取り入れた採用活動は、従来型の求人媒体よりも若年層へのアプローチで高い効果を発揮しています。
とりわけ Z 世代の就活生は、就職活動の「情報収集期」よりも「意思決定期」に入ってから SNS を積極的に利用する傾向が顕著です。
この段階で得た情報は、仕事内容や働き方、社風への理解を深め、最終的な入社意向を大きく左右します。そこで企業が SNS・動画・ Web 広告を駆使すれば、自社の魅力や職場のリアルな姿を視覚的・感覚的に伝えやすくなります。
たとえば Instagram や YouTube では社員インタビューや職場の一日を動画で紹介し、現場の空気感を共有できます。さらに LINE や X(旧 Twitter)では日々の活動報告や社内イベントを即時に発信し、求職者との距離を近づけることが可能です。
実際、 SNS を積極活用する企業に対して学生の約 8 割が好意的な印象を抱くという調査結果も報告されています。こうしたデジタル施策は、若者に「この会社で働いてみたい」と思わせる強力な後押しとなるでしょう。
| 採用手法 | 内容 |
| SNS活用 | 企業の魅力や現場の雰囲気をリアルタイムに発信 |
| 動画・画像掲載 | 実際の作業風景や社員インタビューを通して職場環境を視覚的に伝達 |
| Web広告 | ターゲット層に合わせたデジタル広告で情報発信 |
動画や画像を使った情報発信は、就活生の行動フェーズに応じて内容と形式を変えることがポイントです。情報収集段階なら、短尺のカジュアルな動画や視覚的に理解しやすい画像が目を引きます。いっぽう意思決定段階では、長尺インタビューや詳しい解説を盛り込んだ動画のほうが安心材料になります。
Web 広告にも SNS のターゲティング機能を組み合わせれば、求める人材像に合わせて広告を表示できるため、限られた予算でも高い到達率を期待できます。こうしたデジタル施策は若者の興味をつかむだけでなく、企業ブランディングの一環として長期的な資産になるのが強みです。
発信したコンテンツはストック情報として蓄積され、企業の「顔」として継続的に効果を発揮します。従来型の求人広告に比べて費用対効果が高い点も、デジタル採用が注目される理由と言えるでしょう。
もっとも、SNS で求人情報を出す際には職業安定法に基づき、企業名・所在地・連絡先・業務内容・就業場所・賃金などを明示しなければなりません。情報開示が不十分だと、せっかく育てた信頼を損なう恐れがあります。
今後は就活生の情報ニーズをフェーズごとに見極め、「何を、いつ、どの媒体で伝えるか」を戦略的に設計することが不可欠です。こうした取り組みを徹底すれば、デジタルツールを活用した採用力を継続的に高められるでしょう。
参考資料:
- SNS等で求人募集を行う際の注意事項を喚起したリーフレット公開
- 【完全版】SNS採用で企業の課題解決!SNS採用の成功事例も紹介
- No Company、25卒就活生の「情報収集期」と「意思決定期」におけるSNS活用実態を調査。Z世代はSNSの情報で入社意向度が変化
外国人材の活用と多様な雇用形態の導入
日本の製造業は、若年層の就業離れと人口減少が重なり、人手不足という構造的課題に直面しています。こうした状況を受けて、政府は外国人材の受け入れ拡大と育成の強化、さらに柔軟な働き方の普及を通じ、企業の人材確保と現場力の維持を後押ししているところです。
具体策としては、インドネシアやベトナムなどの開発途上国に対し、日本の技能検定や評価制度のノウハウを移転し、現地での研修や制度構築を支援しています。
さらに、JICA と連携して職業訓練施設を整備し、専門家を派遣するほか、研修員を日本へ受け入れる取り組みも進めています。こうした施策により、製造現場で即戦力となる人材の育成基盤が着実に整いつつあると言えるでしょう。
| 採用施策 | 内容 |
| 技能実習制度 | 外国人労働者に対する技能習得の支援と実践的な指導 |
| 特定技能制度 | 特定分野における高度な技能を有する人材の採用 |
| 多様な雇用形態 | 派遣、契約社員、パートタイムなど柔軟な雇用の導入 |
加えて、従来の技能実習制度の課題を踏まえ、2024年には「育成就労制度」への移行が進められました。
この新制度は、単なる技能移転にとどまらず、人手不足分野における実践力を備えた人材の安定的な確保を目的としており、企業にとっては長期的な戦力としての外国人材の活用が可能になります。
また、同年3月の閣議決定により、「工業製品製造業分野」が特定技能制度の対象に新たに追加され、制度上も製造業における外国人材の受け入れが一層進めやすくなりました。
特定技能制度では、一定の技能と日本語能力を有する人材が対象となるため、採用後すぐに現場で活躍できる点も企業にとって大きな利点です。
さらに、若年層の外国人が加わることで、現場に新たな視点や技術がもたらされ、生産性の向上やイノベーションのきっかけにもなり得ます。
一方で、国内人材の確保に向けては、働き方の多様化が重要な鍵です。正社員に加えて、派遣、契約社員、パートタイムなどの柔軟な雇用形態を整えることで、多様な働き方を望む若者や未経験者にも門戸を広げることができます。
さらに、近年は正社員においても、在宅勤務やフレックスタイム、副業・兼業といった柔軟な働き方が広まりつつあり、ワークライフバランスを重視する世代にとっては、これが職場選びの大きな判断基準となっています。
製造業が今後も競争力を維持し、持続的に成長していくためには、外国人材の活用と、柔軟な働き方を受け入れる職場環境づくりの両立が重要です。
制度の変化を的確に捉え、自社の人材戦略に落とし込んでいくことが、経営層にとって今後ますます重要な課題となるでしょう。
参考資料:ものづくり基盤技術の振興施策
事例紹介:成功事例と統計データの分析
若者離れに直面する企業の中には、具体策を打ち出して成果を上げるところが少なくありません。
そうした成功事例や最新統計は、課題への取り組み方と実際の効果を示す貴重な手がかりです。実例とデータを突き合わせて見ることで、自社の戦略を練る際のヒントが得られるでしょう。
製造業における成功事例の紹介
人手不足や若者離れといった課題に対応するため、製造各社では自動化技術の導入、人材育成、職場環境の整備など、現場に根ざした多彩な取り組みが進められています。
たとえば株式会社今野製作所は、デジタル技術で業務プロセスを改善し、業務量の増加に対応しつつ従業員教育に充てる時間を確保する体制を整えました。
製造部門と設計部門が密に連携し、二〜三名のチーム制で多能工を育成している点も特筆すべきです。社員が複数工程を経験することで、柔軟な対応力を備えながら生産性も高めています。
石川樹脂工業株式会社では、仕上げ工程にロボットを導入した結果、省力化と効率化が一気に進み、現在は二十台のロボットが工場内で稼働しています。これにより作業者の負荷が軽減されただけでなく、製品品質も安定しました。
人材育成に力を入れる株式会社一ノ坪製作所は、中途採用者向けに少人数制の社内研修を実施しています。技能習得に加え、経営戦略や企業ビジョンを共有することで、社員一人ひとりの主体性を高める仕組みを構築しました。取得スキルに応じて関連部門へ異動できるキャリア支援制度も整備されています。
株式会社江北ゴム製作所が展開しているのは「成長の PDCA サイクル」と名付けた独自の能力開発プログラムです。必要能力一覧で現状を可視化し、個人目標シートとスキルマップによって進捗を管理。さらに、成長と連動した評価・処遇制度を導入し、従業員の向上心を組織の競争力に結び付けています。
高齢従業員の活躍を推進する株式会社加藤製作所では、現場のバリアフリー化を進めています。冷暖房設備の整備や身体に合わせた作業台の調整といった工夫で、年齢や体格を問わず働きやすい職場を実現しました。
こうした取り組みは高齢者だけでなく若手の定着にも好影響をもたらし、企業イメージの向上にもつながっています。
なお、下表には各社の施策とその目的・効果を簡潔にまとめています。
これらの事例は具体的な対策が実際に成果を上げることを示しており、同様の取り組みを検討する企業にとって大いに参考になるでしょう。成功事例は現場で実践可能な解決策の宝庫なのです。
| 事例企業 | 実施施策 | 成果 |
| 今野製作所 | デジタル業務改善、多能工育成、チーム制導入 | 生産性向上、人的負担軽減、品質安定化 |
| 石川樹脂工業 | ロボット導入による仕上げ工程の省力化 | 生産性向上、人的負担軽減、品質安定化 |
| 一ノ坪製作所 | 少人数制研修と経営ビジョンの共有、柔軟な部門異動 | 主体性育成、キャリア支援、定着促進 |
| 江北ゴム製作所 | 能力一覧・スキルマップ・個人目標シートによる成長支援制度 | 能力の可視化と継続的成長、評価制度との連動 |
| 加藤製作所 | 作業環境の整備(冷暖房、作業台調整等) | バリアフリー化による定着促進、企業イメージ改善 |
まとめ
製造業の若者離れは、少子高齢化、3Kイメージ、働き方の変化など複数の要因が複雑に絡み合った結果であり、業界全体の持続可能な発展を脅かす重大な課題です。
環境改善、柔軟な勤務制度、キャリア支援、採用戦略の刷新、さらにはDX推進など、多角的な対策を講じることで、現状の課題を克服し、若い世代の参入と定着を促進する必要があります。
各企業が取り組むべき課題は多岐にわたりますが、これらの施策を総合的に実施することが、業界の未来を明るく照らす鍵となるでしょう。
エムニへの無料相談のご案内
エムニでは、製造業をはじめとする多様な業種に向けてAI導入の支援を行っており、企業様のニーズに合わせて無料相談を実施しています。
これまでに、住友電気工業株式会社、DENSO、東京ガス、太陽誘電、RESONAC、dynabook、エステー株式会社、大東建託株式会社など、さまざまな企業との取引実績があります。
AI導入の概要から具体的な導入事例、取引先の事例まで、疑問や不安をお持ちの方はぜひお気軽にご相談ください。
引用元:株式会社エムニ
