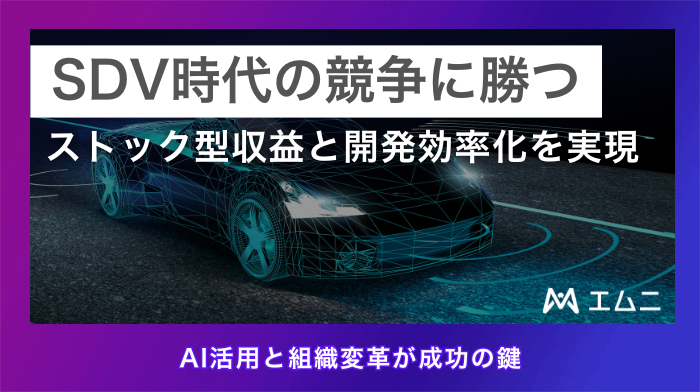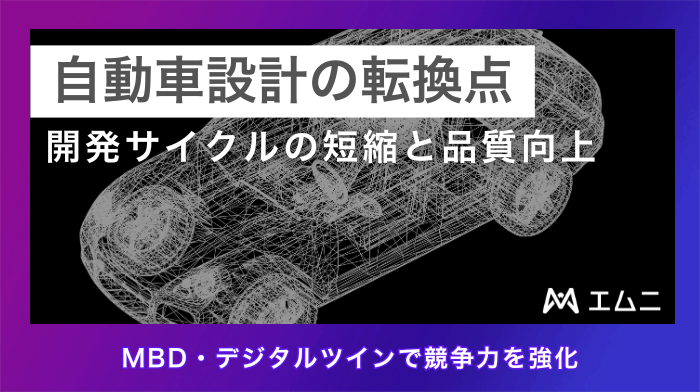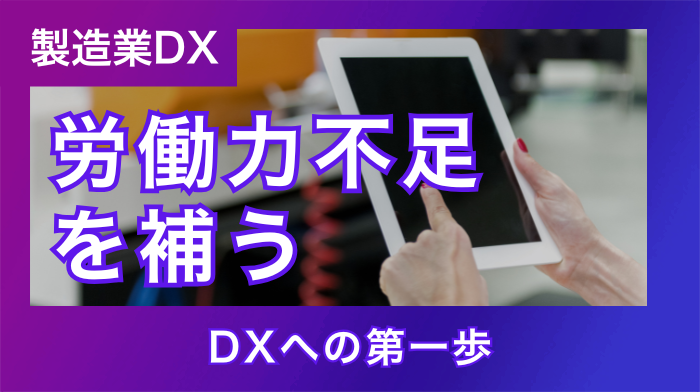後継者育成ガイド|基礎から生成AIの活用方法まで徹底解説
2025-09-29
特許ノイズとは?原因やAI活用による除去方法を解説
2025-09-30商標登録で失敗しない|45区分一覧と注意点を徹底解説

商標登録における区分とは、ニース国際分類に基づき特許庁が採用・運用している、商品やサービスの種類ごとの分類のことです。
正しく商標登録を行えば、他社の模倣を防ぎブランド価値を守ることができます。一方で、出願区分を誤ると、必要な権利を取り損ねたり、後に余分な費用が発生したりします。
本記事では、商標登録の区分とは何か、全45類の概要、ならびに区分選択の具体的な注意点を解説します。
商標登録とその区分とは?
商標権は、特許・実用新案・意匠と並んで「産業財産権」に分類される重要な権利の一つです。
商標登録とは、事業で使用する商品・サービスの名称やロゴマークなどを特許庁に登録し、その名称やマークを独占的に使用する権利(商標権)を得るための制度です。
文字や図形に加え、音や色彩、動きといった新しいタイプの商標も保護の対象です。
出願時には、保護したい商品やサービスをジャンルごとに区分(クラス)で指定して記載する必要があります。
この区分は、国際的に採用されている「ニース国際分類」に基づき、商品(1〜34類)とサービス(35〜45類)に分かれています。どの区分で登録するかは商標の権利範囲に直結するため、とても重要です。
商標登録の費用は、主に「出願料」と「登録料(10年分)」から成り立ち、どちらも選択する区分の数に対応して増加します。(※注)
- 出願料:3,400円+(区分数×8,600円)
- 登録料:区分数×32,900円
※5年ごとの分割納付も可能で、その場合は 1区分あたり 17,200円(5年分)
例えば、新開発のIoT機器について、「機器そのもの(9類)」と「機器の修理サービス(37類)」の2区分で出願・登録する場合、
- 出願料:3,400円+(2区分×8,600円)= 20,600円
- 登録料:2区分×32,900円 = 65,800円
「念のため、あれもこれも」と闇雲に区分を増やせば、コストは数十万円単位で膨れ上がります。一方で、コストを恐れて区分を絞りすぎると、肝心な事業領域を守れないという本末転倒な事態に陥ってしまいます。
だからこそ、事業の現状と未来を正確に映し出す、メリハリの効いた区分選択が極めて重要なのです。
商標登録によって得られる主なメリットは次のとおりです。
- 独占排他権の確保:登録した区分に属する商品や役務について、第三者の同一または類似商標の使用を差し止めたり、損害賠償を請求したりできます。
- ブランド価値の保護と資産化:商標権は重要な無形資産であり、ライセンス収入や譲渡によって収益化でき、M&A時の企業評価にも寄与します。
- 社会的信頼の向上:登録商標を示す®マークを使用することで、消費者や取引先に対して、正規のブランドであるという信頼と安心感を与えられます。
▼産業財産権について知りたい方はこちら
産業財産権とは何か?:特許・実用新案・意匠・商標の違いを徹底解説
注:上記は記事作成時点の公表料金(2025/09/10)を参考にした表記です。料金改定があり得るため、最終確認は特許庁の公開情報で行ってください。
商標の区分一覧【商品編】1類-34類
商品の区分は、工業用化学品から日用品、医療用品、食品、建築材料、玩具まで、私たちの身の回りにある「モノ」を対象としています。
第1類から第34類までの各区分には商品群が定義されており、出願者はその中から自社の商標を使用する商品を選択します。
商品に関する区分は1類から34類まで用意されています。たとえば、化学製品は1類、化粧品や洗剤は3類、食品や飲料は29〜33類といった具合に、多様な分野がカバーされています。
この区分を理解しておくことで、
- 自社製品がどの区分に該当するのかを正確に把握できる。
- 出願時に不要な区分を選択して、余分な費用が発生するリスクを防げる。(費用は区分数に応じて加算されるため)
といった実務的なメリットが得られます。
▼表1 商品に関する区分と区分の名称(一部は略記)
| 区分(類) | 商品の代表例 | 区分(類) | 商品の代表例 |
| 1 | 化学品 | 18 | 革及びその模造品、旅行用品、馬具 |
| 2 | 塗料、着色料など | 19 | 金属製でない建築材料 |
| 3 | 洗浄剤及び化粧品 | 20 | 家具、プラスチック製品(他類に属しない物) |
| 4 | 工業用油・油脂、燃料、光剤 | 21 | 台所用品、化粧器具、ガラス・磁器製品 |
| 5 | 薬剤 | 22 | ロープ・帆布製品、織物用の原料繊維 |
| 6 | 卑金属及びその製品 | 23 | 織物用の系 |
| 7 | 加工機械、原動機など | 24 | 織物、家庭用の織物製カバー |
| 8 | 手動工具 | 25 | 被服、履物 |
| 9 | 科学用の機械器具など | 26 | 裁縫用品 |
| 10 | 医療用機械器具、医療用品 | 27 | 床敷物、織物製でない壁掛け |
| 11 | 照明・加熱・冷却用などの装置 | 28 | がん具、遊戯用具、運動用具 |
| 12 | 乗物、移動用の装置 | 29 | 動物性の食品・加工した野菜、食用園芸作物 |
| 13 | 火器、火工品 | 30 | 加工した植物性の食品、調味料 |
| 14 | 貴金属、宝飾品、時計 | 31 | 生きている動植物、飼料 |
| 15 | 楽器 | 32 | アルコールを含有しない飲料、ビール |
| 16 | 紙・紙製品、事務用品 | 33 | ビールを除くアルコール飲料 |
| 17 | 電気絶縁用・断熱用などの材料 | 34 | たばこ、喫煙用具、マッチ |
参考:類似商品・役務審査基準〔国際分類第9版対応〕 | 経済産業省 特許庁
参考:類似商品・役務審査基準〔国際分類第12-2024版対応〕 | 経済産業省 特許庁
商標の区分一覧【サービス編】35類-45類
サービス(役務)に関する区分は第35類から第45類に分かれています。
例えば、広告・経営支援(第35類)、建設工事・修理(第37類)、設計・技術開発・ソフトウェア開発(第42類)など、製造業に関連して提供されるサービスも幅広く含まれます。
商品編と同様に、この区分を把握することで、
- 提供するサービスの実態に即した、適切な権利範囲を確保できる。
- 将来の事業拡大を見据え、戦略的に保護すべき区分を検討しやすくなる。
といった効果が期待できます。
▼表2 サービスに関連する区分と区分の名称 (一部は略記)
| 区分(類) | サービスの代表例 | 区分(類) | サービスの代表例 |
| 35 | 広告、事業の管理、小売卸売 | 41 | 教育、娯楽、スポーツ、文化活動 |
| 36 | 金融、保険、不動産の取引 | 42 | 科学技術・ソフトウェアの設計/開発 |
| 37 | 建築、設置工事、修理 | 43 | 飲食物の提供、宿泊施設の提供 |
| 38 | 電気通信 | 44 | 医療、衛生、美容、農業に係る役務 |
| 39 | 輸送、梱包、保管、旅行の手配 | 45 | 冠婚葬祭、警備、法律事務 |
| 40 | 物品の加工、その他の処理 |
区分選択のポイント・注意点
商標登録の成功は、区分選択の正確性に大きく依存します。
区分を誤ると、守りたい事業範囲を十分にカバーできなくなったり、逆に不要な区分まで指定して費用と手間を無駄にしたりしてしまいます。
これから解説する3つのポイントを事前に把握すれば、こうした失敗を避け、コストを抑えながら自社のブランドを効果的に守ることが可能になります。
事業内容と将来の展開を見据えた「適切な」区分選択
区分選択は、単に「今扱っている製品やサービス」をリストアップする作業ではありません。
商標権は「商標 × 指定商品・指定役務」の組合せで成立するため、現在の事業の核を確実にカバーする指定を行いつつ、将来予定している事業展開(製品の派生、流通チャネルの変化、SaaS化やライセンス供与など)を10年程度の視点で検討することが肝要です。
とはいえ、闇雲に区分数を増やせば、その分だけ特許庁への出願料・登録料が加算されます。
したがって、コア事業を優先的に確保したうえで、拡張の可能性が高い分野を選択的に追加する、という優先づけが合理的です。
こうした検討は、社内の事業計画と知財戦略を連動させることで、不要なコストを抑えつつ将来のリスクを下げることにつながります。
出願前の徹底した事前調査
出願前の先行調査は、区分選択の失敗を防ぐ最も確実な手段です。
J-PlatPat(特許情報プラットフォーム)をはじめとする公的データベースでは、称呼(読み)検索や図形検索、出願・登録情報の閲覧ができ、想定する指定商品・役務に類する先登録がないかを幅広く確認できます。
出願後に指定を拡張することは原則認められないため、出願前の調査と指定文言の作り込みに十分な時間と労力を割くべきです。
必要に応じて、有償データベースや弁理士による精査を併用するとより安全です。
区分が違っても類似と判断される場合
特許庁による類否判断は、単に区分が同一かどうかで決まるわけではありません。
審査では、比較対象となる商標の「外観(見た目)」「称呼(呼び方)」「観念(意味)」の三要素を総合的に検討すると同時に、当該商品・役務の需要者層や取引の実情を踏まえて混同のおそれがあるかを判断します。
たとえば、印刷された書籍(第16類)と電子書籍(第9類)のように、区分は異なっていても需要者や使用形態が近ければ類似と判断される可能性があります。
この横断的な類否判断を前提に、指定文言は「実際に使用する形態・提供方法」を明確に記載することが、拒絶リスクの低減に直結します。
審査実務や類似審査基準の改訂状況(国際分類の更新など)にも注意しておく必要があります。
ツールを活用した事前調査・登録手続きの効率化
ご覧いただいたように、適切な区分選択には、事業理解に加え、専門的な知識と丁寧な事前調査が不可欠です。しかし、本来の業務で多忙な管理職やご担当者様が、これらの作業に多くの時間を割くのは容易ではないかもしれません。
近年、このような課題に対し、AI技術を活用して先行商標の調査や区分選択をサポートするツールが登場しています。
従来は、特許庁のデータベースなどを用いて類似する商標を一件ずつ検索し、膨大な結果から該当性を確認していく必要がありました。また、複数の候補区分にわたって商品・サービスを照合する作業は、担当者にとって大きな負担でした。
さらに、こうした調査を外部の専門事務所に委託すれば、費用が高額になるうえ、結果が出るまでに一定の時間を要するのが一般的です。
AIを活用すれば、入力した事業内容や製品情報に基づき、関連性の高い区分を自動で抽出し、類似する先行商標を短時間でリスト化できます。
これにより、手作業では数時間かかる調査や、外部委託でコストと時間をかけていた作業を、大幅に短縮することが可能です。
担当者は判断や戦略立案といった付加価値の高い業務に集中でき、効率性とコストパフォーマンスの両面で大きな効果を得られるのです。
私たち株式会社エムニは、製造業に特化した生成AIの開発を行っております。もし、商標調査の効率化や、より戦略的な知財管理の方法についてご関心をお持ちでしたら、どうぞお気軽にお声がけください。貴社の状況に合わせた情報提供やご提案をさせていただきます。
商標登録の区分選択は事業を守る「知財戦略」の要
商標は単なる名前ではなく、製品・技術・信頼を守る重要な資産です。
その効果は「どの区分を指定するか」に大きく左右され、誤ると事業の保護範囲が不十分になり、不要な費用も発生します。
現在の事業を確実にカバーしつつ、将来の展開まで見据えた区分選択が不可欠です。
その際、J-PlatPatなどで類似商標を確認し、外観・称呼・観念や商品・役務の実態も含めて慎重に検討することで、登録リスクを大幅に減らせます。
商標の区分選択は単なる手続きではなく、事業戦略の延長線上にある重要な意思決定です。
適切に行うことでコストを抑えながら、自社ブランドを長期的に守る強固な権利を築くことができます。
エムニへの無料相談のご案内
エムニでは、製造業をはじめとする多様な業種に向けてAI導入の支援を行っており、企業様のニーズに合わせて無料相談を実施しています。
これまでに、住友電気工業、DENSO、東京ガス、太陽誘電、RESONAC、dynabook、エステー、大東建託など、さまざまな企業との取引実績があります。
AI導入の概要から具体的な導入事例、取引先の事例まで、疑問や不安をお持ちの方はぜひお気軽にご相談ください。

引用元:株式会社エムニ