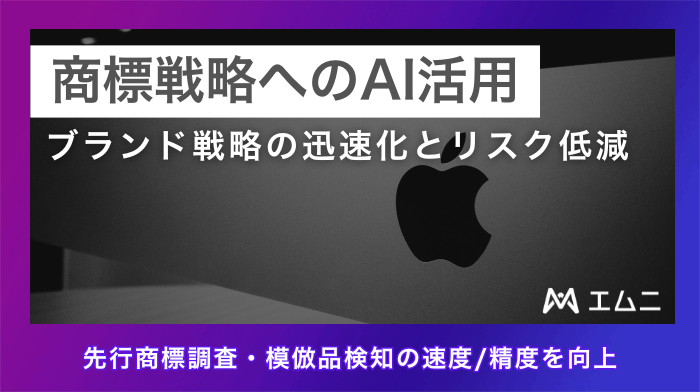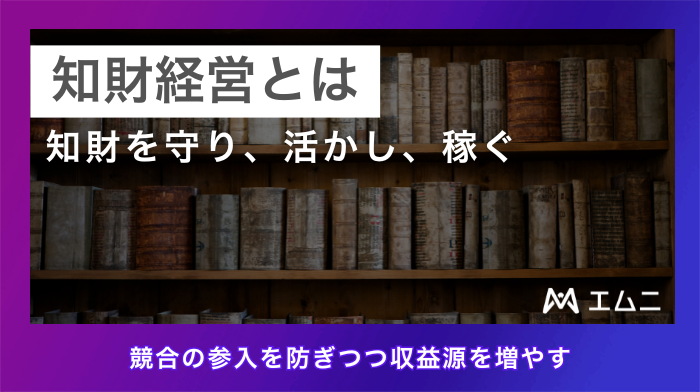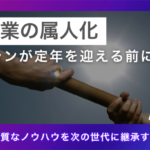
製造業の属人化とは?そのリスクと原因やDXによる解決策を徹底解説
2025-08-28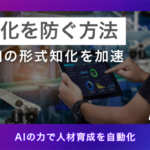
属人化を防ぐには?原因から対策、AI活用まで徹底解説
2025-08-29特許の種類|発明を守るための分類と使い分け
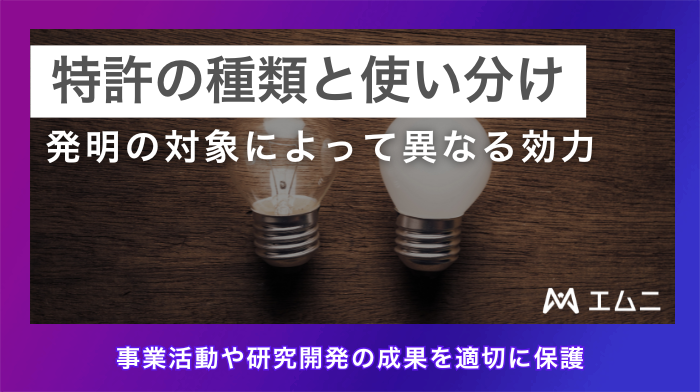
企業が持続的に成長していくためには、独自の技術やアイデアといった知的財産を守り、活用することが重要です。
その代表格である特許は、自社技術を独占的に活用できるようにするだけでなく、市場での優位性を確立し、研究開発投資を回収するための重要な手段となります。
もっとも、特許には対象や出願方法によっていくつかの種類があり、それぞれの特徴や活用法を理解しておくことが求められます。
特許とは
特許とは、新しい技術的アイデアである「発明」を法律によって独占的に保護する制度です。
特許権を取得すると、その発明を一定期間、独占的に実施できる権利が与えられます。
これにより、他社による無断利用を防ぎ、自社の競争力を強化することが可能になります。
日本における特許権の存続期間は、原則として出願から20年間ですが、医薬品や農薬などについては例外的に最長5年間の延長が認められる場合があります。
その間、特許権者は製品化やライセンス供与を通じて研究開発投資を回収できるため、特許は「イノベーションの成果を守る経済的基盤」といえます。
そのため、特許を適切に取得・管理することは、研究開発型企業をはじめ多くの企業にとって極めて重要です。
特許法で保護される「発明」とは
では、特許法が保護する「発明」とはどのようなものなのでしょうか。
日本の特許法第2条では、発明を「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と定義しています。この定義には3つの重要なポイントがあります。
一つ目は、発明は自然界に存在する法則を利用したものである必要があることです。
電気の性質を応用した回路技術や、化学反応を利用した新素材の製造方法といったものがその典型です。逆に、単なる発見やゲームのルールといった人為的な取り決めだけならば、特許の対象にはなりません。
次に、発明は「技術的思想の創作」でなければなりません。これは具体的な技術的解決手段を指しており、課題に対してどのように技術的に解決するかが明確であることが求められます。
さらに3つ目として、発明は「高度のもの」である必要があります。これは、発明として成立するための一定の水準を求めるもので、単なる思いつきとは一線を画すことを意味します。
そして、この発明が実際に特許として認められるためには、特許庁の審査において、さらに「新規性」や「進歩性」といった要件を満たす必要があると判断されなければなりません。
このように、特許法における「発明」は、単なるアイデアや発見とは異なり、自然法則に基づいて社会に役立つ技術的解決手段であることが不可欠です。
発明の対象による特許の種類
特許法で保護される「発明」といっても、その内容は多岐にわたります。
特許法では、発明を大きく「物の発明」と「方法の発明」に分け、さらに方法の発明の一種として「物を生産する方法の発明」を区別しています。
したがって、特許実務では発明の対象を3つの類型に分類して整理します。
物の発明
「物の発明」とは、具体的な形を持った物や物質に関する発明で、新しい機械装置、化学物質、新素材などが該当します。
この分類は、製品や材料そのものを対象とするため、企業の事業活動と直結しやすく、産業界で最も多く出願される発明類型です。
発明の名称としては「〇〇装置」「△△化合物」「□□材料」といった形で物品名が語尾に付くことが多く、特許権の効力はその物品自体に及びます。
例えば、
- より小型で高性能な半導体チップ
- 特定の疾患に有効な新薬の有効成分
- 環境負荷を低減する新素材や高強度プラスチック
といったものが該当します。
方法の発明
「方法の発明」とは、物そのものではなく、ある目的を達成するための手順や工程に関する発明です。一般に、発明が「順序」「時間」「操作プロセス」といった要件を必要とする場合には方法の発明に分類されます。
具体例としては、
- 金属部品の強度を高めるための新しい熱処理方法
- 画像処理アルゴリズムによるAI認識精度の向上手法
- 工場ラインでの効率化を実現する組立手順
などが挙げられます。
方法の発明は「プロセスそのもの」が対象であるため、その発明方法を業として使用する行為 に対して権利を行使できます。ただし、得られる成果物そのものが直接保護されるわけではない点に注意が必要です。
▼製造業における製法特許について詳しく知りたい方はこちら
製法特許とは|定義や権利化までのプロセスを徹底解説
物の生産方法の発明
「物を生産する方法の発明」は、方法の発明の一種ですが、通常の方法の発明と異なり、方法によって生産された「成果物」にまで特許権の効力が及ぶ点が大きな特徴です。
例えば、
- 高純度シリコンを製造するための新しい化学プロセス
- 医薬品の有効成分を安定的に合成する方法
- 食品の品質を高める新しい加工プロセス
などがこれに当たります。
この場合、権利行使の対象は「方法を業として使用する行為」だけでなく、その方法によって生産された製品を生産・販売・使用する行為 にまで及びます。つまり、「作り方」だけでなく「成果物」まで包括的に保護できるため、極めて強力な特許権の形態といえます。
出願手続の種類
特許出願を一口に言っても、その形態や目的によって複数の手続きが存在し、それぞれの特徴と適切な使い方を理解することが成功への鍵となります。
通常出願(国内出願)
通常出願とは、日本国内で特許権を取得するための最も基本的な手続きです。新規に発明が完成し、国内市場を中心に事業化を予定している場合に多く使われます。
出願人は日本国特許庁(JPO)に対して、発明の詳細を記載した出願書類を提出します。出願から3年以内に審査請求を行うことで、特許の審査が開始され、審査を経て特許権が付与されます。
PCT国際出願
PCT(特許協力条約)国際出願は、一つの出願手続きでアメリカ、フ、ドイツ、中華人民共和国など158の加盟国の中から選択して申請でき、将来的に特許を取得する可能性を確保する制度です。
出願人は、WIPO(世界知的所有権機関)を通じて国際出願を行い、将来的に複数の国に出願手続きを移行することができます。
PCT出願を通じて、各国での特許出願の優先権を主張することが可能となり、各国の特許庁での審査を受けることになります。
参考記事:国際出願(特許) | 経済産業省 特許庁
スーパー早期審査
スーパー早期審査は、特許庁が提供する特別な審査制度で、平均3ヶ月以内に完了する通常の早期審査よりもさらに迅速に、平均して1ヶ月以内に審査結果を知ることができます。
出願人は、特定の要件(下記)を満たす場合に、この制度を利用することができます。
- 要件1:「実施関連出願」かつ「外国関連出願」であること、又はスタートアップによる出願であって「実施関連出願」であること(早期調査と同じ)
- 要件:スーパー早期審査の申請前4週間以降になされたすべての手続をオンライン手続とする出願であること
優先権主張出願
優先権主張出願は、ひと言で言えば、「後から出願した発明に、最初に出願した日を適用できる制度」です。この制度は、特に開発サイクルの速い業界では、非常に重要な戦略材料となるでしょう。
たとえば、新製品のアイデアの核となる部分が固まった時点で、まず日本で特許を出願するとします。その後、市場の反応を見たり、さらなる性能向上を目指したりする中で、より優れた改良点が閃くこともあります。
この時、最初に出願してから1年以内であれば、改良後の発明全体に「最初に特許庁へ書類を提出した日」を権利の基準日として主張できるのです。
この制度を活用することで、開発現場に大きなメリットが生まれます。まず、最初にアイデアの骨子だけを押さえておくことで、その後の1年間はじっくりと改良や周辺技術の開発に専念できるでしょう。
そして、この期間中に競合が似たような技術を偶然にも開発し、先に出願したとしても、あなたの「優先日」の方が先であるため、審査では圧倒的に有利な立場を確保できるのです。
つまり、優先権主張出願を上手く活用すると、開発スピードを維持しながら、後から生まれる改良や追加アイデアも権利に含めることが可能になります。
競合の動向を常に気にかけながら、より強力な特許ポートフォリオを構築したい場合に有効な戦略となるでしょう。
参考記事:優先権主張出願について | アース国際特許商標事務所
AIを活用した特許戦略 (弊社の事例解説)
近年、AI技術の進展により、知財分野においても効率的かつ高精度な戦略立案が可能になっています。
従来は膨大な時間とコストを要していた特許調査や翻訳の作業が、AIの導入によって飛躍的に効率化され、企業の知財活動における大きな武器になりつつあります。
以下では、AIを活用した弊社の代表的な取り組みについて紹介します。
1. 高速かつ高精度なパテントマップ作成:AI特許ロケット
特許戦略を立案する上で、関連分野の出願状況や技術動向を俯瞰できる「パテントマップ」の作成は欠かせません。しかし従来の手法では、数千件におよぶ膨大な特許文献を整理・分析するため、莫大な時間とコストが発生していました。
▼パテントマップについて詳しく知りたい方はこちら
パテントマップとは?具体的な用途から導入方法まで
AIを活用した「AI特許ロケット」では、特許文献の自動分類や関連性解析を短時間で安価で実行することが可能です。
これにより、従来数週間を要していた分析作業が、わずか数分〜数時間で完了するケースもあり、迅速な意思決定を支える強力なツールとなります。
2. 特許翻訳に特化した高精度・低コストのAIモデル開発支援
国際的な知財活動を進める上で、特許明細書や関連文献の翻訳は避けられないプロセスです。
しかし、技術的に高度かつ専門性の高い文章であるため、一般的な翻訳システムでは精度に限界があり、従来は高コストの専門翻訳サービスに依存せざるを得ませんでした。
AIを活用した翻訳モデルは、特許分野に特化した学習データをもとに構築されており、専門用語や文脈の正確な翻訳を低コストで実現します。
さらに、各企業のニーズに応じてオーダーメイド型のAIモデル開発も可能であり、特定技術領域に最適化した翻訳環境を構築できます。
プレスリリース:【エムニ】ファインチューニングを用いた特許翻訳特化型LLMの開発において、GPT-4oや翻訳モデルを凌駕する性能を達成
エムニでは、様々な目的に応じたオーダーメイドAIの開発や、各条件に応じた簡単な無料デモ実装を提供しています。また、AIを活用した知財戦略立案の支援も積極的に行っており、企業の競争力強化に直結するソリューションを展開しています。
まとめ:AI×知財戦略による企業競争力の増強
特許出願手続の種類や活用法を理解することは、企業の技術を守る上で不可欠です。さらに近年では、AIを活用した特許戦略が、従来型の知財管理を大きく進化させています。
特許制度の理解とAIの積極的活用を組み合わせ、グローバルに展開する企業にとって大きな武器として活用することで、持続的な競争優位性を確立することができるのです。
エムニへの無料相談のご案内
エムニでは、製造業をはじめとする多様な業種に向けてAI導入の支援を行っており、企業様のニーズに合わせて無料相談を実施しています。
これまでに、住友電気工業株式会社、DENSO、東京ガス、太陽誘電、RESONAC、dynabook、エステー株式会社、大東建託株式会社など、さまざまな企業との取引実績があります。
AI導入の概要から具体的な導入事例、取引先の事例まで、疑問や不安をお持ちの方はぜひお気軽にご相談ください。

引用元:株式会社エムニ