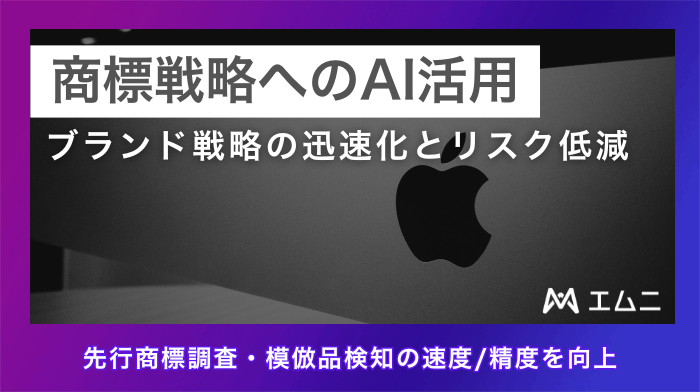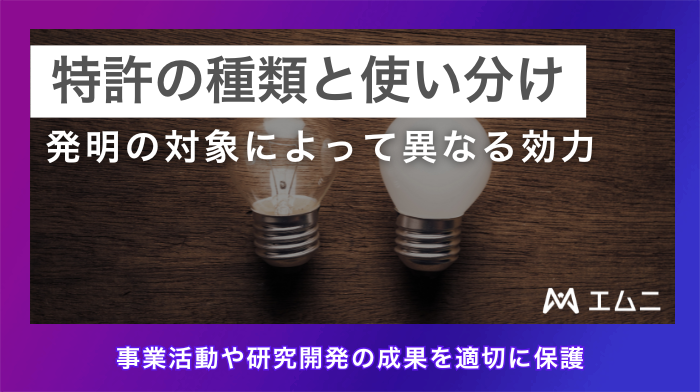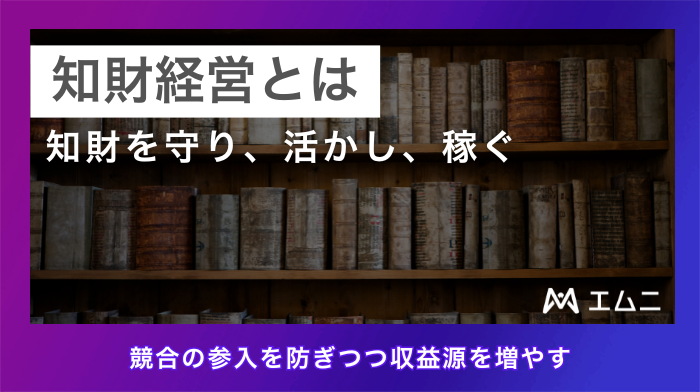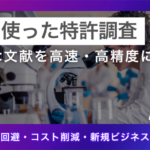
特許調査のAI活用|品質・速度を飛躍的に改善
2025-07-27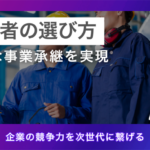
未来を託す後継者の選び方|細かなステップからAI活用まで徹底解説
2025-07-30特許訴訟の闇|パテントトロールの実態と企業が備えるべき法的対抗策
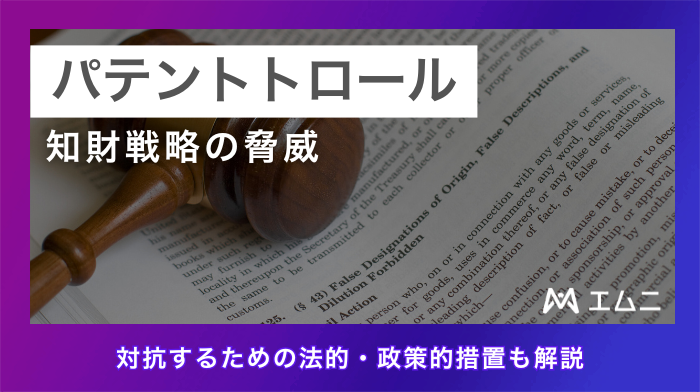
特許訴訟の増加とともに、「パテントトロール」の脅威が改めて注目を集めています。
技術開発を行わず、特許権をもとに訴訟やライセンス料の請求を行うこれらの事業者は、企業のイノベーションに深刻なダメージを与えかねません。
パテントトロールとは?
パテントトロール(Patent Troll)は、製品の開発・販売を行わず、取得した特許権を武器に訴訟やライセンス請求により収益を得る事業者を指す表現です。
「パテント (特許)」と、橋の下に潜んで通行料を強要する北欧神話の怪物「トロール」を組み合わせた造語です。
この概念は、20世紀後半にアメリカのIntel社の顧問弁護士であったPeter Detkin氏によって広められました。
パテントトロールには明確な定義はありませんが、特許権の濫用とされる活動に関連した言葉として使用されています。
「NPE」「PAE」との違い
パテントトロールに関連した言葉として、「NPE」「PAE」が挙げられます。
以下の表では、「NPE」や「PAE」の定義とパテントトロールとの関連を整理しています。
| 定義 | パテントトロールとの関連 | |
| NPE(Non‑Practicing Entity) | 特許権を持つが、自社で特許関連の製品やサービスを実施せず、他社に対する権利行使する事業者などのこと。 | この一部が該当する。大学や研究機関、個人発明家なども含むため、完全に全てがパテントトロールとは言えない。 |
| PAE(Patent Assertion Entity) | 特許主張(Assertion)を主要収益源とし、収益の過半数以上が特許権行使による事業者などのこと。 | NPEのうち、特に訴訟・ライセンス収入を主軸にする主体のことである。パテントトロールに該当する割合が高い。 |
パテントトロールの歴史的背景
パテントトロールは一過性の現象ではなく、米国の特許制度と深く結びついた歴史的背景を持っています。
この歴史的背景を理解することは、問題の根深さを知る上で欠かせません。
米国のプロパテント政策への転換
1970年代後半、米国は産業競争力回復を目的に、特許を強力に保護する「プロパテント(親特許)政策」へ舵を切りました。
この政策の一環として設置されたCAFC(アメリカ合衆国連邦巡回控訴裁判所)などにより、特許権者に有利な環境が整えられた結果、特許の資産価値は飛躍的に高まりました。
トロールの温床となった米国法制度
プロパテント政策で強化された特許権は、米国独自の法制度下で、パテントトロールにとって強力な手段となりました。
被告側に莫大な費用負担を強いる証拠開示制度は、トロール側にとって極めて有利に働きます。
特に、被告側が負担する高額な訴訟費用をテコに、それを下回る金額で和解を迫る戦術が発生する原因となりました。
象徴的事件の一例:BlackBerry事件
パテントトロール問題を象徴する事例として、カナダの通信機器メーカーRIM(Research In Motion)社が、NTP社から特許侵害で訴えられた「BlackBerry事件」があります。
NTP社は自ら製品を開発・販売せず、取得した特許をもとに訴訟などで収益を得る企業、いわゆるパテントトロールとされる存在でした。
問題となったのは、BlackBerryの中核機能である無線メール通信技術がNTP社の保有特許に抵触するとされた点です。
この訴訟は2001年に始まり、約5年にわたって争われた末、2006年にRIMが約6億1,000万ドルを支払って和解しました。
この事件は、単なる金銭的損失にとどまらず、BlackBerryのサービス停止による社会的混乱の可能性まで取り沙汰されました。
その結果、パテントトロールによる訴訟が企業活動や社会インフラにまで影響を及ぼすことを明確に示した象徴的な例として広く知られています。
参考記事:米国特許訴訟 最新事情パテント・トロール,テキサス州東地区裁判所,そして陪審審理 ヘンリー幸田
パテントトロールの手口とビジネスモデル
パテントトロールは、緻密に設計された収益モデルに基づき、法と制度の「隙間」を狙って利益を得ています。
訴訟や交渉の実務、相手企業の法務状況に精通し、「訴える側」に立つことで安定的な収益を得ようとする戦略的な構造が特徴です。
①「兵器庫」としての特許の取得戦略
パテントトロールは自ら技術開発を行わず、他者が保有する特許を買い集めることから活動を始めます。
特に、資金力に乏しい個人発明家や経営難にある企業から、特許を安価に取得する手法が典型的です。
特許は、複数のペーパーカンパニーに分散して保有されることが多く、その実態を掴みにくくするよう巧妙に設計されています。
②「収益装置」としての訴訟戦略
パテントトロールを行う企業は、取得した特許をもとにライセンス交渉や訴訟を仕掛けることで収益を得ています。
資金力のある大企業か、法務面での対応が難しい中小企業を狙い、高額な訴訟費用を交渉材料にして、それを下回る金額での和解を迫るのが彼らの中核的な戦略です。
また、彼らは製品を製造していないため、企業間で一般的に用いられるクロスライセンス戦略が機能せず、これも大きなアドバンテージとなっています。
パテントトロールがもたらす経済的損失と影響
パテントトロールによる特許訴訟は、企業単体の負担にとどまらず、産業全体の競争力やイノベーションに深刻な影響を及ぼします。
訴訟コストの増大、研究開発投資の減少、新規事業の撤退など、無形の損失も含めると、その経済的影響は計り知れません。
直接的コスト:訴訟費用と和解金
パテントトロールとの特許訴訟は、企業にとって極めて高額なコスト負担を強いる構造になっています。
パテントトロールとの訴訟では、1件あたりの訴訟費用は平均2〜3億円、和解金はそれ以上にのぼることも珍しくありません。
特許トロール(NPE・PAE)との訴訟に掛かる訴訟費用は、米国では中規模訴訟で平均200万~300万ドル(約3〜4億円)、大規模訴訟では300万~800万ドルにのぼるケースもあるとされています。(*1)
御費用が企業の年間研究開発費を上回るケースもあり、特に中小企業やスタートアップでは、1件で資金繰りが破綻するリスクすらあります。
さらに、訴訟が事業の中核技術に及べば、製品出荷の停止や取引先の離脱といった直接的な損失も発生するため、財務と事業継続の両面で甚大な影響が生じます。
間接的コスト:イノベーションの萎縮
直接的な金銭的負担とは別に深刻な問題としてあげられるのは、訴訟の脅威がもたらすイノベーションへの萎縮効果です。
訴訟に対応するために、研究開発部門の人員が法務支援に割かれたり、訴訟費用捻出のためにR&D予算が削減される事例まであるほど。
また、知的財産研究教育財団によれば、訴訟費用の高騰を受けて新製品開発予算を一時凍結または削減した国内企業も報告されており、法務対応や和解金の支払いに資源が吸い取られています。
そうして訴えられた企業は、訴訟後に研究開発費を減らしたり、新製品開発を躊躇したり断念したりするケースが存在しており、訴訟リスクを恐れた開発回避が技術革新の停滞を招く要因となっています。
スタートアップ企業への深刻な影響
パテントトロールは高額な和解金が見込める大企業だけでなく、リソースの乏しい中小企業やスタートアップを戦略的に狙うこともあります。
中小企業は長期の法廷闘争を戦い抜く資金力や専門知識を持たず、たった1件の訴訟が事業の存続を脅かす致命的な打撃となり得ます。
訴訟費用よりも少額の和解金を提示されると、たとえ理不尽な要求であっても、和解金の支払いを選ぶ状況に追い込まれやすいです。
その結果、将来的な企業の成長の芽を摘まれることになります。
参考(*1):パテント・トロールの現状と問題点
参考:Patent Trolls: Evidence from Targeted Firms
参考:未利用特許等の 知的財産取引ビジネスの実態に関する 調査研究報告書
パテントトロールに対抗する法的・政策的措置
パテントトロールへの対抗には、企業による自主的対策のみならず、法的および公的な制度・政策のサポートが重要です。
特に米国では重要な判例や法改正を契機に、パテントトロールの影響力を抑えるための法的枠組みが整備されてきました。以下に代表的な3つの事例を詳述します。
eBay事件(2006年):差止請求権の制限
2006年の米国連邦最高裁判決「eBay Inc.対MereExchange, L.L.C.事件」は、特許侵害があった場合に自動的に差止命令(injunction)が認められるという従来の慣行を大きく見直す転換点となりました。
これは、パテントトロールにとって極めて重要な意味を持つ判決だったと言えるでしょう。
この事件では、MereExchange社がオンラインマーケットプレイス大手のeBay社に対し、特許侵害で訴訟を提起したのです。
当時の判例からすれば、特許侵害が認められれば、ほぼ自動的に差止命令が下されるのが通例でした。
しかし、最高裁は本判決において、差止命令の発令は「衡平法上の4要素の基準」に基づいた裁量判断を徹底すべきであると明確に指摘しました。
具体的には、以下の4つの要素が考慮されることになります。
- 実害の証明: 特許権者が実際に回復不能な損害を被っているか。
- 金銭賠償の不十分さ: 金銭的な賠償だけでは損害を十分に補償できないか。
- 差止命令による公益への影響: 差止命令が社会全体に悪影響を及ぼさないか。
- 原告の利益: 差止命令によって原告が得る利益が、被告が被る損失に見合うか。
この判決により、「単に特許侵害が認められたからといって、無条件に差止命令が発せられるわけではない」という原則が確立されました。
パテントトロールは、しばしば自ら製品やサービスを事業展開せず、訴訟を武器に高額なライセンス料を徴収することをビジネスモデルとしています。
彼らにとって、相手企業の事業活動を停止させ得る差止命令は、交渉を有利に進めるための最大の切り札であったと言っても過言ではありません。
しかし、この差止命令の裁量制導入によって、事業実態のないパテントトロールが差止命令を得ることは格段に難しくなりました。
その結果、彼らの交渉力は大幅に制限され、特許権の濫用に対する大きな歯止めとなったのです。
参考記事:イーベイ対メルクエクスチェンジ事件が もたらす米国特許訴訟のパラダイムシフト
米国発明法(AIA)(2011年):特許無効化手続きの導入
2011年に成立した米国発明法(America Invents Act、以下AIA)は、米国特許制度に画期的な大規模改革をもたらしました。この法律は、特に特許の質の向上とパテントトロール対策を主要な目的としています。
AIAの最も大きな変更点の一つは、従来の「先発明主義(first to invent)」から「先出願主義(first to file)」への移行でしょう。
これは、特許権が発明の先後ではなく、出願の先後によって決定されることを意味し、特許出願のプロセスはより透明で公平なものとなりました。
AIAはまた、様々な特許の異議申し立て手続きを新設しました。これには、たとえば特許付与後のレビュー(Post-Grant Review; PGR)や当事者系レビュー(Inter Partes Review; IPR)などが含まれます。
これらの手続きにより、特許権の有効性を裁判外で迅速かつ効率的に争うことが可能になったのです。従来の煩雑な訴訟手続きに頼ることなく、専門的な知見を持つ特許審判部が特許の有効性を判断する仕組みが導入されたことは、特許紛争の解決において非常に重要な進展と言えるでしょう。
AIAがパテントトロールに与えた影響は非常に大きいと言えます。
パテントトロールは、しばしば弱い特許や漠然とした特許を根拠に企業を訴訟することで知られています。
しかし、AIAが導入したPGRやIPRといった審査後の無効化手続きによって、不当に付与された特許や広範すぎる特許を効率的に取り消すことが可能になりました。
これにより、パテントトロールが保有する特許の価値が大幅に低減され、結果として不当な乱訴の抑制につながっています。
これは、健全なイノベーション環境を促進する上で欠かせない要素だったと言っても過言ではありません。
これらの改革は、米国における特許権の取得、維持、行使のあり方を大きく変え、より公正で効率的な特許システムへと進化させたのです。
参考記事:米国における知的財産政策の動向 〜前編〜
企業が取るべき防衛戦略
パテントトロールによる特許訴訟は、もはや特定の業界や規模の企業だけの問題ではありません。
本章では、企業が取るべき防衛戦略を「事前対策」「集団的防衛」「事後対応」の3つに分けて紹介します。
①事前対策:プロアクティブな防御策
最も効果的な対策は、特許侵害のリスクを事前に把握し、備えておくことです。新製品を市場に出す前に行うFTO(Freedom to Operate)調査は、その基本となります。
これは単なる法的確認にとどまらず、ビジネスの健全性を保つための重要なリスクマネジメントでもあります。
近年はAIを活用し、技術情報から関連特許を効率的に抽出するツールも登場しており、調査業務のスピードと精度を大きく向上させています。
例えば、弊社の「AI特許ロケット」では、特許の技術分野を可視化するパテントマップを最短10分で作成できます。作成したマップをもとに、自社の強みや弱みの把握などに活用できます。
また、防衛策としては、自社技術を公開することで他者の特許取得を防ぐ『防衛公開』や、訴訟時の交渉材料となる『防衛特許』の取得も有効です。
こうした対策を整えておくことで、事業のスピードを落とさずに、リスクを抑える体制を築くことができます。
▼パテントマップについて詳しく知りたい方はこちら
パテントマップの作り方やAIを活用した効率化を徹底解説
▼特許戦略について詳しく知りたい方はこちら
特許戦略とは?企業価値を高める戦略・事例・AIの活用方法を徹底解説
集団的防衛:LOT Networkなどの協調的仕組み
トロールの脅威は、個々の企業では対処しきれない場合があり、業界が連携して脅威に対抗する「集団的防衛」が効果的な戦略として注目されています。
その代表格が「LOT Network」です。これは非営利の相互ライセンス契約ネットワークで、加盟企業の特許がPAEに売却された瞬間に、他の全加盟企業に無償ライセンスが付与される画期的な仕組みです。
これにより、PAEは加盟企業をその特許で攻撃することができなくなり、脅威を無力化できます。
参考記事:自社の特許を「パテントトロール」から守るための非営利組織「LOTネットワーク」が米国で急成長 | Nikola
③事後対応:無効資料調査、海外知財訴訟費用保険
万が一、警告状や訴訟が届いてしまった場合でも、迅速かつ冷静な対応が必要です。第一に行うべきは、相手特許の無効化に向けた「無効資料調査」です。
この場面でもAIの力が発揮されます。
従来は特許調査員が過去の論文や公報を手作業で調査していましたが、現在ではAIが数百万件のデータベースを解析し、出願前に類似技術が存在した証拠を自動的に抽出します。
また、特許訴訟に伴うコスト(弁護士費用、損害賠償など)は数千万円~億円単位にのぼるケースもあります。こうしたリスクに備える手段として、特許訴訟費用保険の活用も広がっています。
参考記事:海外知財訴訟費用保険制度 特許庁
参考記事:パテント・トロール5つの対策
まとめ:知財戦略というイノベーションの守りの要
パテントトロールによる影響は、単なる法的リスクを超えて、企業の技術力や市場競争力を脅かす深刻な経営課題です。
特に米国や欧州を含むグローバル市場で事業展開を行う企業にとっては、日常的な経営リスクとして無視できなくなっています。
効果的に備えるためには、訴訟前の準備から、業界横断的な企業連携、さらには訴訟発生時の戦略的対応に至るまで、総合的な知財戦略が求められます。
技術革新が激しさを増すなか、知的財産の保護こそが、企業の持続的成長を支える基盤となります。
エムニへの無料相談のご案内
エムニでは、製造業をはじめとする多様な業種に向けてAI導入の支援を行っており、企業様のニーズに合わせて無料相談を実施しています。
これまでに、住友電気工業株式会社、DENSO、東京ガス、太陽誘電、RESONAC、dynabook、エステー株式会社、大東建託株式会社など、さまざまな企業との取引実績があります。
AI導入の概要から具体的な導入事例、取引先の事例まで、疑問や不安をお持ちの方はぜひお気軽にご相談ください。

引用元:株式会社エムニ