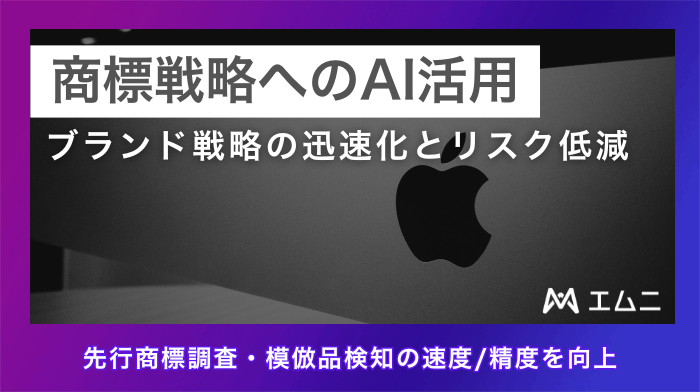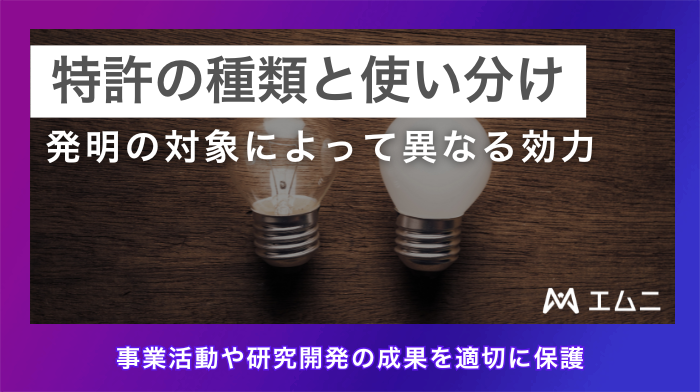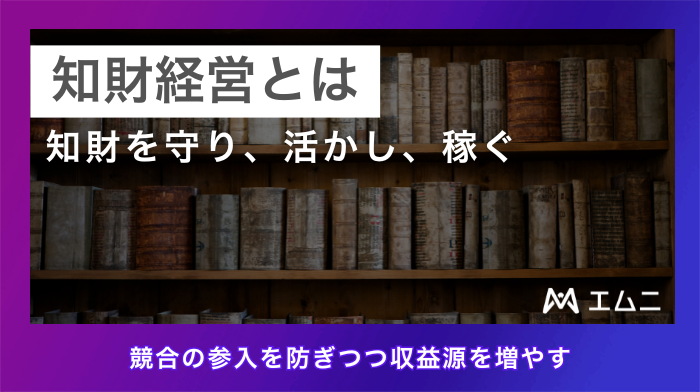AIでパテントマップ作成の質・速度を劇的にUP
2025-07-23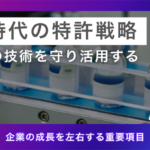
特許戦略とは?企業価値を高める戦略・事例・AIの活用方法を徹底解説
2025-07-23パテントマップの作り方やAIを活用した効率化を徹底解説
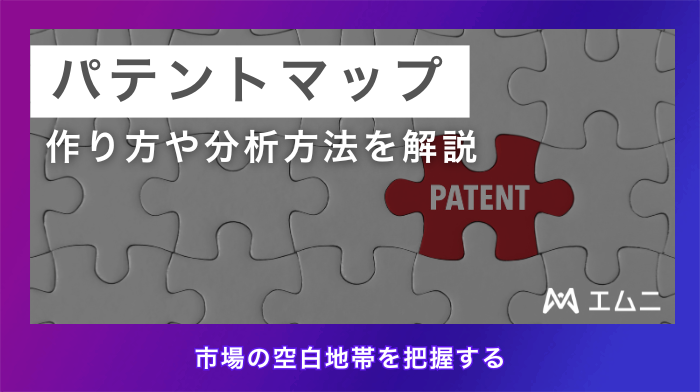
特許の分析は企業の競争力を高めるために不可欠です。
競合他社の技術動向や市場の空白地帯を把握し、自社の研究開発戦略や知財戦略を立てるなど重要な役割を果たします。
しかし、「特許の分析の仕方がわからない」「何から始めればいいのか」「従来のやり方ではコストがかかりすぎてしまう」と悩む方も多いのではないでしょうか。
本記事では、特許分析の効率化に役立つパテントマップの基本的な知識から分析方法や注意点、AIを活用したサービスまで網羅的に解説します。
▼パテントマップの概要についてはこちら
パテントマップとは?具体的な用途から導入方法まで
パテントマップ作成の5ステップ
一般的に、パテントマップの作成は「目的設定」「情報収集」「データ加工」「可視化」「分析」という5つのステップで進められます。
各ステップを着実に実行することが、質の高いパテントマップ作成の鍵です。
ステップ1:調査目的の明確化
まず「何のためにパテントマップを作成するのか」という目的を明確にすることが重要です。
「競合他社の動向を知りたい」「新規事業の可能性を探りたい」「自社の研究開発テーマを決定したい」など、目的によって収集すべきデータや分析の切り口が大きく異なります。
目的が曖昧なまま進めてしまうと、膨大な時間をかけたにもかかわらず、役に立たないマップが出来上がってしまうことにもなりかねません。
ステップ2:母集団の形成(特許情報の収集)
目的が定まったら、次はその目的に合致する特許情報を収集します。
この収集された特許データの集まりを「母集団」と呼びます。
特許庁が提供する無料のデータベース「J-PlatPat(特許情報プラットフォーム)」などを利用して、キーワードや特許分類(IPC/FI/Fターム)を指定して検索し、関連する特許公報をリストアップします。
母集団の質と量が、パテントマップの精度を左右する重要な要素です。
ステップ3:データの加工と整理
J-PlatPatなどから収集したデータは、そのままでは分析に適さない場合がほとんどです。
そのため、Excelなどの表計算ソフトを用いて、分析しやすいようにデータを加工・整理する必要があります。
例えば、出願人名の表記ゆれ(例:「株式会社〇〇」と「(株)〇〇」)を統一したり、分析に必要な項目(出願年、特許分類など)を抽出したりする作業が含まれます。
地道な作業ですが、この工程を丁寧に行うことで、後の分析が格段にスムーズになります。
ステップ4:マップの作成(可視化)
整理したデータをもとに、いよいよマップを作成します。
Excelのピボットテーブルやグラフ機能を活用することで、様々な切り口のパテントマップを効率的に作成できるでしょう。
例えば、出願年ごとに出願件数を集計して折れ線グラフにすれば「技術の盛衰」が、出願人別・技術分野別に件数を集計してバブルチャートにすれば「各社の注力分野」が一目瞭然になります。
目的に応じて最適な可視化手法を選択することが求められます。
ステップ5:マップの分析と考察
マップが完成したら、それを見て終わりではありません。
作成したマップを多角的に分析し、「マップが何を示すのか」を深く読み解き、自社の戦略に繋がる示唆を得ることが最終ゴールです。
例えば、競合の出願が少ない領域は、新規参入のチャンスがある「空白地帯」かもしれません。
また、特定の企業が近年出願を急増させている分野は、将来の市場拡大が見込まれる注目分野である可能性を示唆しています。
パテントマップの主要な分析軸
パテントマップは、様々な分析軸で切り込むことで、多様なインサイトを引き出すことができます。
ここでは、代表的な3つの分析軸をとったマップを紹介します。
これらを組み合わせることで、より深く、多角的な分析が可能となるでしょう。
時系列マップ(時系列分析)
特定の技術テーマに関する特許出願件数の年次推移を各企業ごとに分けてグラフ化することで、その技術のライフサイクルを把握するマップです。
出願件数が急増している時期は技術開発が活発な「成長期」、件数がピークに達し安定している時期は「成熟期」、そして減少傾向にあれば「衰退期」にあると推測できます。
自社が参入すべきタイミングや、撤退を検討すべきタイミングを見極めるのに役立ちます。
特許情報分析による中小企業などの支援事例(独立行政法人工業所有権情報・研修館)より引用
レーダーマップ(競合分析)
レーダーマップは各企業の出願動向をグラフ化し、技術分野の傾向を示したものです。
どの企業(出願人)が、どの技術分野に、どれくらいの数の特許を出願しているのかを分析します。
これにより、主要な競合他社はどこか、各社がどの技術に注力しているか、新規参入してきた企業はいるか、といった競合環境を詳細に把握することが可能です。
自社のポジションを客観的に評価し、競争戦略を練る上で不可欠な分析と言えるでしょう。
特許情報分析による中小企業などの支援事例(独立行政法人工業所有権情報・研修館)より引用
課題・解決マップ(技術領域分析)
特許公報に含まれる「発明が解決しようとする課題」と「課題を解決するための手段」を整理・分析する手法です。
どのような技術的な課題が存在し、それに対してどのようなアプローチで解決が試みられているのかをマトリクス状にまとめることで、技術開発のトレンドや未解決の課題を明らかにします。
他社とは異なる独自のアプローチを見つけ出し、差別化を図るためのヒントが得られます。
特許情報分析による中小企業などの支援事例(独立行政法人工業所有権情報・研修館)より引用
上記で紹介した以外にも有用な分析軸の取り方はたくさんあります。
▼詳しく知りたい方はこちら
パテントマップとは?具体的な用途から導入方法まで
パテントマップ作成時の注意点
精度の高いパテントマップを作成し、正しく活用するためには、いくつかの注意点があります。
これらの点を軽視すると、誤った結論を導き出してしまうリスクがあるため、常に意識しておくことが重要です。
データ収集におけるバイアスの排除
調査範囲の設定は慎重に行う必要があります。
調査範囲が広すぎるとノイズが多くなり重要な情報が埋もれてしまい、逆に狭すぎると、調査者の主観によって重要な特許を見落としてしまう危険性があります。
まずは広めに検索し、結果が多すぎる場合に少しずつ条件を絞り込んでいくアプローチが有効です。
意図しないバイアスがかからないよう、客観的な視点を常に保つことが欠かせません。
キーワード選定の重要性
特許情報の検索精度は、キーワードの選び方で大きく左右されます。
似た技術でも多様な表現が使われるため、類義語や関連語を網羅的にリストアップして検索式を作成する必要があります。
また、検索式に誤りがあると、収集されるデータ全体の質が低下してしまいます。
可能であれば、複数人で検索式をダブルチェックする体制を整えることが望ましいでしょう。
誰が見ても分かりやすい表現
パテントマップは、必ずしも知財の専門家だけが見るものではありません。
経営層や研究開発部門の担当者など、専門知識が少ない人でも直感的に理解できるような、分かりやすいデザインを心掛けることが極めて重要です。
グラフの種類の選択、色分けのルール、凡例や注釈の付け方などを工夫し、誤解を招かないように配慮しましょう。
AIを使ったパテントマップ作成自動化ツール
これまでパテントマップを一から自力で作成する方法について解説してきましたが、その時間的コストや専門知識の必要性は大きな負担となり得ます。
そこで、近年開発が進むAIを活用したマップ作成ツールや外注サービスの検討が非常に重要です。
そうした中で特におすすめしたいのが、パテントマップ作成をロケットのように高速で実現するサービス「AI特許ロケット」です。
「AI特許ロケット」は安価で高速に高精度な調査を実現します。人力では数週間かかる調査を最短10分で行ったり、調査コストを99.9% カットするなどその効果は絶大です。
以下は『AI特許ロケット』で作成した課題・解決マップの一例です。
このマップでは、横軸と縦軸にそれぞれ課題と解決手段の各項目を表示し、その交点に該当する特許文書の件数を可視化しています。
もちろん、これらの分析軸は自由にカスタマイズ可能です。
このように、AIの力を活用することで、分析軸を変えながら低コストで何度でもパテントマップを作り直し、深く分析することが可能になります。
AI特許ロケットに関しては、資料も配布しておりますので、ご興味のある方はぜひ以下のフォームからお気軽にお問い合わせください。
まとめ
パテントマップは、膨大な特許データを整理し、技術動向や市場状況を可視化する強力なツールです。
マップの分析軸を変更することで、競合他社の戦略を分析したり、自社の研究開発の方向性を見極めたりするなど多様な分析が可能となります。
また、新たなビジネスチャンスの発見やリスクの回避といった、戦略的な意思決定を支える役割も果たします。
現代の激しい競争環境において、パテントマップを効果的に活用することは、企業の競争力を高める鍵です。
本記事で紹介したマップの作り方やAIを活用したツールを積極的に導入して、データドリブンな経営を実現しましょう。
エムニへの無料相談のご案内
エムニでは、製造業を主として、多様な業種に向けてAI導入の支援を行っており、企業様のニーズに合わせて無料相談を実施しています。
本記事では知財業務のAI活用を扱いましたが、その他会議や書類作成業務の効率化、工場DXなど様々なAI活用をご支援してきました。
これまでに、住友電気工業株式会社、DENSO、東京ガス、太陽誘電、RESONAC、dynabook、エステー株式会社、大東建託株式会社など、さまざまな企業との取引実績があります。
「AI特許ロケット」を含むAI導入の概要から具体的な導入事例、取引先の事例まで、疑問や不安をお持ちの方はぜひお気軽にご相談ください。
引用元:株式会社エムニ