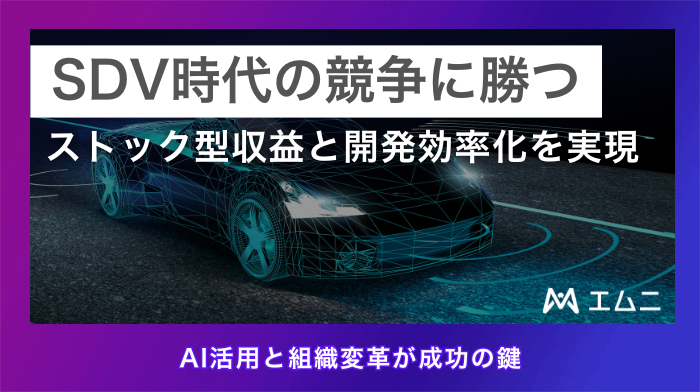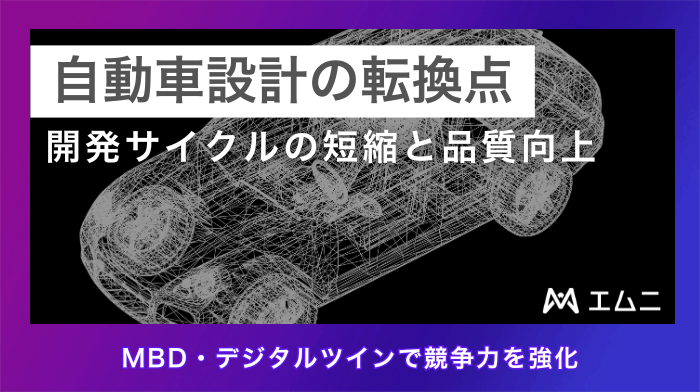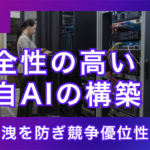
オンプレミスLLMとは|情報漏洩を防ぎつつ競争優位性あるAIを構築
2025-04-29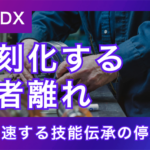
製造業の若者離れ|原因や効果的な対策を解説
2025-05-21製法特許とは|定義や権利化までのプロセスを徹底解説
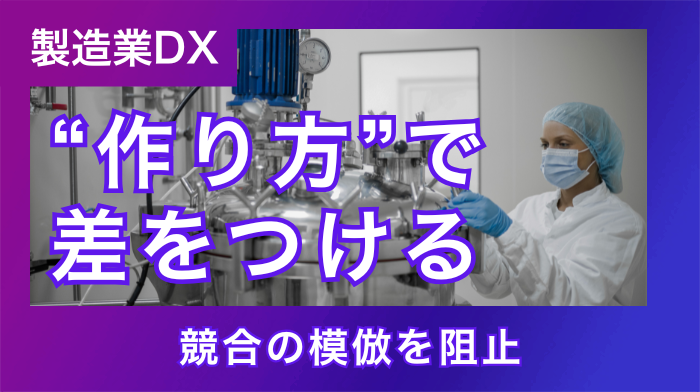
技術がすぐに真似され、製品が差別化しづらくなっている今、「作ったもの」ではなく「どう作るか」を守る視点が企業競争力のカギを握っています。
その中で、競合の模倣を防ぎながら、新技術への投資を確実に回収するための有効な手段となるのが、「製造プロセスそのもの」を保護する製法特許です。
本記事では、この製法特許にスポットを当て、制度の基本的な仕組みから実務での活かし方、注意すべきリスクまでを整理します。
製法特許とは何か
製法特許とは、「製品そのもの」ではなく、「その製品をどのように作るか(作り方)」を保護する特許のことです。
たとえば、「大豆を37℃で2日間発酵させてから粉末にし、健康成分エクオールを効率よく取り出す方法」「液体の化学物質を冷却して結晶化する方法」などが挙げられます。
このように、原料に一定の加工や処理を加えることで、新たな製品を生み出す技術が製法特許の対象となります。
製法そのものに特許をかけることで、他社による模倣を防ぎ、自社だけがその方法を用いて製品を生産できるという独占的な立場を確保できます。
参考文献:
製品にも効力が及ぶ、製法特許のカバー範囲
製法特許(物を生産する方法の特許)は、単に「作り方」だけを保護するものではありません。特徴的なのは、その製法によって作られた製品そのものにも特許の効力が及ぶ点です。
たとえば、ある企業が「海砂を特殊な方法で除塩処理し、特定の粒度の石灰石粉末を配合して施工性を高めたコンクリートを製造する方法」で製法特許を取得していたとします。
この場合、別の会社が同じ製法を使って海外でコンクリート製品を製造し、それを日本に輸入・販売したとすると、たとえ製造が海外であっても、日本国内で販売した時点で日本の製法特許を侵害していると判断される可能性があります。
つまり、製法特許は「日本国内での製造」を防ぐだけでなく、海外製造から日本への流通(輸入)に対しても効力が及ぶのです。
このように、模倣品が日本市場に流入するのを防ぐ水際対策として、製法特許は非常に重要な役割を果たします。
参考文献:JPH059052A – コンクリート又はモルタルの製造方法 – Google Patents
製法特許と物質特許の違い
製法特許と物質特許は、同じ技術領域を扱っていたとしても、保護の対象が根本的に異なります。
物質特許は、ある特定の分子構造や化学成分など、「物そのもの」に対して与えられる特許です。
そのため、仮に製法が異なっていたとしても、同一の成分を含んでいれば特許侵害に該当する可能性が高いと判断されます。
一方で、製法特許は「どのように作るか」というプロセスに焦点が当たっており、完成品が同じであっても、作り方が異なれば侵害にあたらない場合があります。
たとえば、ある化合物をAという方法で製造する特許を持っていたとしても、他社がBという別の方法でまったく同じ化合物を製造した場合、それがAの製法と異なっていれば侵害にはならない可能性があるのです。
このように、製法特許は作り方そのものの保護を目的とするため、その範囲をどう設計するかが極めて重要です。
特許の請求項にどこまで具体的に工程や条件を記載するかによって、実際に保護できる範囲が大きく変わるため、出願時の文言設計が特許の強さを左右します。
特に競合が異なる製法で類似の製品を出すことを想定すると、初期のドラフト段階からどのように権利を広く、かつ確実に取るかが鍵になります。
参考文献:
製法特許が注目される理由
製品の機能やデザインだけでは他社と差別化することが難しくなっている中で注目されているのが、模倣されにくく、技術的な強みを活かせる「製法」による差別化です。
特に、生産効率や品質に直結する製法は、単なる技術を超えて企業の競争力そのものを支える存在となります。
さらに、製法特許は、出願による情報公開や、海外製造品への対応といった観点でも、戦略的な判断が求められる制度です。
こうした背景から、製法特許は企業の知財戦略の中で重要な役割を担うようになっています。
技術公開とノウハウ保持のトレードオフ
新しい技術を開発した際、企業はそれを特許として出願するか、それとも社内の秘密(ノウハウ)として保持するかという重要な判断を迫られます。
特許を取得すれば、一定期間(通常20年)の独占的な使用権を得ることができ、他社による無断使用を法的に防ぐ強力な手段となります。
しかしその一方で、特許出願を行うと原則として出願から1年半後には技術の詳細が公開されてしまうため、競合に技術動向を知られたり、類似技術の開発を促すリスクが避けられません。
たとえば、製造工程の条件や調合の比率などが明記された特許文書を見た他社が、わずかに仕様を変更することで模倣品を開発する可能性も十分に考えられます。
このようなリスクを踏まえ、あえて特許出願を行わず、発明を企業秘密として保持する選択をとる企業も存在します。
たとえば、コカ・コーラ社は創業以来、主力商品のレシピを一度も特許化せず、社内の限られた人物しか知らない企業秘密として管理してきました。
もし特許出願をしていれば一定期間の独占権は得られたものの、公開義務によって競合に模倣されるリスクが生じていたはずです。
このように、情報を公開せず長期にわたり競争優位を保つ戦略として、ノウハウ保持は有効な選択肢といえます。
こうした背景を受けて、多くの企業が実践しているのが、「特許」と「ノウハウ」を組み合わせるハイブリッド戦略です。
たとえば、製品の構造や外部から確認されやすい部分は特許として明示し、製造条件や温度、反応時間、配合比率などの細かな技術的要素は特許に書かずに社内秘とするという分け方が典型例です。
このように、公開する部分と秘匿する部分を意図的に区別することで、法的保護と競争優位の維持を両立させることが可能となります。
実際、サントリーの緑茶「伊右衛門」の事例では、製造技術の一部には特許出願がなされる一方で、味の決め手となる茶葉のブレンド比率や加工手法などは非公開のノウハウとして管理されています。
このような運用を行うには、自社の技術の性質や業界の競争状況を的確に把握し、公開に耐える技術のみを特許化するというバランス感覚が求められるでしょう。
参考文献:
- 特許にするか企業秘密(ノウハウ)にするか?メリット・デメリットや判断ポイントを解説 | Toreru Media
- 特許権の存続期間の延長
- 特許法第64条~第65条の条文解読(出願公開・補償金請求権)
- Why Didn’t Coca-Cola Patent Their Secret Recipe? | Get A FREE Consultation
ビジネス独占力と輸入規制
日本の特許法では、たとえ海外で製造された製品であっても、それが日本国内で輸入・販売された場合には、特許権の侵害とみなされる可能性があると規定されています(第2条第3項および第68条)。
この条文の存在により、特許権者は日本国内での製造行為だけでなく、国外からの製品流通に対しても排他的な権利を行使できる体制が整っているといえるでしょう。
製法特許を保有する企業にとって、これは大きな意味を持ちます。仮に模倣品が海外で製造されたとしても、日本に輸入された時点で特許侵害に該当する可能性があるため、海外での模倣を含めた広範な保護が実現できるからです。
実際の判例としては、味の素株式会社が起こした「グルタミン酸ナトリウム事件」が広く知られています。
この事件では、シージェイジャパン株式会社がインドネシアで製造したグルタミン酸ナトリウム(うま味成分)を日本で販売しようとした行為が問題となりました。
味の素側は、自社の製法特許を根拠に、被告の行為が日本国内における特許法上の侵害に該当すると主張しました。
これに対して裁判所も、販売の申出という行為自体が国内での実施にあたると認定し、約9億9000万円の損害賠償の支払いを命じる判決を下しています。
この判決は、製法特許が国境を越えて効力を持ち得ることを示した重要な事例です。
また、企業が自社の製造プロセスを知的財産として位置づけ、それを積極的に守る姿勢が司法の場で認められたという点でも、示唆に富んだ内容となっています。
参考文献:
出願から権利化までのプロセス
製法特許の取得は思いついた順に書類を提出するだけでは終わりません。
先行技術調査で新規性を確認し、請求項を精緻化する作業が必要です。特に医薬品では化合物データベースや InChI キー検索を駆使して網羅的に調べ、抵触リスクを減らします。
以下では出願から権利化までのプロセスについて見ていきます。
事前準備と先行技術調査
特許出願に際して、まず最初に取り組むべきなのは、既存技術(先行技術)の網羅的な調査です。
発明が「新しい技術(新規性)」であることは、特許を取得するための大前提となります。すでに公開されている技術と重なっている場合、出願は拒絶されるおそれがあります。
そのため、特許庁が提供するJ-PlatPatに加え、化学や医薬品分野では専門のデータベースも活用し、類似技術が公知となっていないかを広く検討する必要があります。調査が不十分だと、後の無効審判や特許訴訟において、特許が取り消されたり敗訴したりするリスクが高まります。
この調査と並行して重要なのが、発明の技術的本質を正確な言葉で表現し、工程条件・触媒・温度・時間などの重要な変数を整理することです。これにより、請求項(特許の権利範囲)を論理的かつ精密に設計する土台が整います。結果として、取得する特許の実効性と明確さが向上します。
また、発明が特許として認められるには、単なるアイデアにとどまらず、誰もがその技術を再現できるレベルで具体化された明細書を提出しなければなりません。この点は「再現可能性」として、日本の特許審査でも特に重視されているポイントです。
そのため、温度・圧力・時間などの条件については、幅広く記載するとともに、実際に確認された最適な値を含む複数の実施例を提示することが望ましいとされています。こうした記述は、新規性や進歩性の主張を補強するだけでなく、技術の信頼性を高める役割も果たします。
もっとも、発明のすべてを開示すると、第三者が技術を模倣しやすくなるという側面も無視できません。とくに、製造プロセスの詳細や微調整のノウハウなど、解析が難しい部分については、あえて公開せずに企業秘密として管理するという選択肢も有効です。
たとえば、反応の中心となる仕組みや製品の構造部分は特許で保護し、それ以外の補助的な工程や条件設定は非公開とすることで、法的な独占と実務上の参入障壁を同時に確保することが可能になります。
このように、特許による公開と、ノウハウとしての非公開を組み合わせた「ハイブリッド戦略」は、実際の企業活動において広く採用されている実務的な手法です。
ただし、非公開とした技術であっても、他社が同様の発明を先に出願し特許を取得した場合には、自社がその技術を自由に使えなくなるリスクがあります。
こうしたリスクへの備えとして、「先使用権」の主張が一つの対策となります。これは、自社が出願前からその技術を日本国内で実際に使っていた、あるいは使う準備をしていたことを証明できれば、一定の範囲で使用を継続できるという制度です。
そのためには、研究ノート、設計図、試作記録、メールの送受信履歴、発注書などの客観的資料を日頃から保管しておく必要があります。さらに、公証制度やタイムスタンプを利用することで、信頼性の高い証拠とすることが可能です。
このような準備は、企業秘密を守りつつ知財戦略としての柔軟性を高めるためにも欠かせないといえるでしょう。
このような先行技術調査の負担を軽減する取り組みとして「エムニ」による特許翻訳に特化した大規模言語モデル(LLM)の開発事例があります。エムニは、日本特許翻訳株式会社の約120万文の特許データを学習させた専用モデルを構築し、外国特許文献の翻訳精度を大幅に高めました。
この技術は、従来コストと時間のかかっていた外国語特許の調査を自動化し、1件あたり数十円という低コストで実施可能にしています。
さらに、ユーザーの意図に即した関連文献を高精度で抽出できるため、技術者や知財担当者の調査業務を効率化し、質の高い特許出願を後押しするツールとして企業の現場で活用が進んでいます。
▼特許調査に関するAI活用について更に詳しく知りたい方はこちら
AIで特許調査のコストを1000分の1に|活用戦略を詳しく解説
出願書類の作成と提出
特許を出願する際には、願書、明細書、特許請求の範囲(請求項)、必要な図面、そして要約書の五つの書類を準備しなければなりません。これらの書類は、特許庁の窓口へ直接持参する方法のほか、郵送または電子出願システムを通じて提出することもできます。
この中で特に重要なのが「特許請求の範囲(請求項)」です。ここには、発明の保護対象をどのように定義するかが明記されており、その記載がそのまま特許権の効力範囲を決めることになります。いわば、請求項は特許の中核をなす部分であり、実質的に「権利書」とも呼べる性格を持っています。
請求項を記載する際には、明細書によって技術内容がきちんと裏付けられていること(サポート要件)、読んだ人が権利の内容を明確に理解できること(明確性要件)、そして簡潔であること(簡潔性要件)が必要です。
これらが欠けている場合、審査で拒絶されるおそれがありますし、特許が成立しても無効審判で取り消されるリスクを伴うでしょう。
また、発明を特許として認めてもらうには、明細書の中でその技術と実施方法を十分に具体化する必要があります。中でも「実施例」は重要な役割を果たします。実施例とは、発明の考え方を実用の形で示し、専門家がその発明を再現できるような水準で記載されるべきものです。
特に「物を生産する方法」に関する、いわゆる製法特許では、工程の順序や完成品の性質を明確に書き表すことが不可欠となります。加えて、実施例は、後に請求項の技術的解釈を行う際の参考資料としても用いられ、発明の保護範囲を裏付ける要素として機能します。
請求項の作成は、技術と法の両面の知識が必要とされる高度な作業です。出願人が独力で適切に対応するのは難しいのが現実でしょう。そのため、弁理士などの専門家に依頼し、記載内容の正確性と戦略的意義を担保することが強く推奨されます。
図面や明細書は、請求項で記された技術的内容を補足する資料としての役割を担っています。一方、要約書は発明の要旨を簡潔にまとめたものであり、特許文献の検索性を高める目的で使用されるものです。
出願手続きの方法には、書面提出と電子出願の二通りがあります。書面による場合、特許庁での電子化処理が必要となるため、その分の電子化手数料が別途発生します。
一方で、電子出願であれば24時間いつでも手続きが可能です。特許庁の開庁時間に左右されず出願日を確定できるほか、提出後すぐに出願番号が発行されるため、処理の迅速性にも優れています。また、電子化手数料が不要となる点もメリットの一つです。
さらに、電子出願ではクレジットカードやインターネットバンキングによる手数料のオンライン決済が可能となっており、手続き全体の効率化につながります。ただし、電子出願には専用ソフトウェアの導入や電子証明書の取得といった準備が必要であり、初めて行う場合には多少の手間がかかるでしょう。
なお、委任状や一部の証明書類については、現在も紙での提出が求められるケースがあります。したがって、すべての出願手続きが完全に電子化されているわけではない点に注意が必要です。
参考文献:
- 特許請求の範囲、特許請求項とは?弁理士が詳細解説
- 特許出願書類の 書き方ガイド
- 特許明細書で重要な実施例とは?その役割と書き方をわかりやすく解説
- 特許をオンラインで出願する方法 ~メリット・注意点を徹底解説 | Toreru Media
方式審査と出願公開
特許出願が行われると、まず特許庁で「方式審査」が実施されます。これは、願書や明細書、特許請求の範囲、図面、要約書といった提出書類が、法律上定められた形式要件を満たしているかどうかを確認するものです。
たとえば、請求項の記載漏れや図面の不足があれば補正指令が出され、適切な対応がなされない場合には出願が却下されることもあります。
方式審査で不備がなければ出願は正式に受理され、この時点で「出願日」が確定します。特に電子出願では、書類の到達時点が出願日とされ、迅速かつ正確に処理されます。
また、電子出願は24時間対応可能であるため、出願日を確保する観点でも有利です。競合他社との同日出願などが想定される技術分野では、時間単位でのスピードが重要になることもあります。
出願日から1年6ヶ月(18ヶ月)が経過すると、出願内容は「出願公開」として一般に公開されます。この制度は、特許の審査結果に関係なく、原則すべての出願が対象です。
公開された内容は「公開特許公報」に収録され、明細書、請求項、図面、要約書がインターネット上で誰でも閲覧できるようになります。
この公開により、他社が自社の技術戦略を把握できるようになるため、競合が回避設計や周辺特許で対抗してくるリスクも生じます。
こうした影響を見越して、企業によっては一部の技術情報を特許として開示し、その他は社内ノウハウとして保持するハイブリッド戦略を採用するケースもあるのです。
出願公開は制度的に不可避である以上、そのタイミングと内容に応じて、事前に保護と開示のバランスを調整しておくことが、実務上きわめて重要です。
参考文献:
- 特許請求の範囲、特許請求項とは?弁理士が詳細解説
- 特許にするか企業秘密(ノウハウ)にするか?メリット・デメリットや判断ポイントを解説 | Toreru Media
- 特許をオンラインで出願する方法 ~メリット・注意点を徹底解説 | Toreru Media
- 初めてだったらここを読む~特許出願のいろは
実体審査請求と審査応答
日本の特許制度では、出願から三年以内に審査請求を行わなければ、その出願は取り下げられたものとみなされます。出願人がこの期間内に審査請求を行った場合には、特許庁によって実体審査が開始されることになります。
実体審査では、審査官が出願内容について新規性、進歩性、記載要件などの法的要件を満たしているかどうかを判断します。新規性は、当該技術が既に知られていないかどうかを示す指標です。
進歩性は、既存技術から容易に導き出せない独自性を持つかどうかを問われる要素でした。記載要件においては、明細書や特許請求の範囲に発明の内容が十分かつ具体的に記載されている必要があります。
審査の結果、特許として認められない理由があると判断された場合には、特許庁から拒絶理由通知が発行されるでしょう。この通知に対し、出願人は一定期間内に応答することが可能です。
応答の方法としては、手続補正書と意見書を提出するのが一般的とされています。手続補正書では、請求項の文言を修正したり範囲を限定したりすることで、拒絶の根拠を解消しようとします。
これに対し意見書では、先行技術との差異や発明の作用効果を説明し、特許性を説得的に主張しました。補正と意見を組み合わせれば、審査官の理解を深め、特許査定へ導く戦略的対応が期待できます。
一方、技術的に複雑な出願、特に化学的プロセスや製造条件の最適化が関係する案件では、書面の説明だけでは審査官と認識が一致しないケースも見受けられます。そうした場合には、審査官との対話が可能な面接審査を活用する価値が高まるでしょう。
面接審査では、出願人または代理人が審査官と直接面談し、補正の方向性や技術的背景について議論できます。
審査の進行状況に応じた柔軟な対応が可能となり、特に誤解を解消したり意見を擦り合わせたりする際に有効でした。近年は特許庁のオンライン対応が進んでおり、ウェブ会議形式で面接審査を実施することもできるようになっています。
ただし、面接審査を行うには事前の申請と日程調整が必要ですし、すべての案件で必ず利用できるわけではありません。実際に活用する際は、特許庁の公式案内を確認し、手続きの流れと留意点を事前に把握しておくことが重要だといえるでしょう。
参考文献:
- 特許出願書類の 書き方ガイド
- 特許請求の範囲、特許請求項とは?弁理士が詳細解説
- 特許をオンラインで出願する方法 ~メリット・注意点を徹底解説 | Toreru Media
- 初めてだったらここを読む~特許出願のいろは
特許査定から登録
特許庁の審査で問題が解消され、「特許として認めてもよい」と判断されると、出願人のもとへ特許査定の通知が届きます。この査定を受けたら、まず最初の3年分の登録料を納付しなければなりません。登録料の支払いが完了すると正式に特許として登録され、ここではじめて特許権が発生しました。
特許の存続期間は、原則として出願日から20年と定められています。ただし、医薬品など一部の分野では事情に応じて最長25年まで延長できる場合もあるでしょう。
特許権を取得すると、その発明を利用した製品の「製造」「使用」「販売」「輸出入」などを行えるのは、権利者だけになります。もし他人や他社が無断で利用した場合、裁判で差止請求や損害賠償を求めることが可能です。
登録後の特許内容は「登録公報」として公開されます。公報はJ‑PlatPatなどのインターネット検索サービスを通じ、誰でも閲覧できるようになりました。発行までの期間は通常数週間程度とされています。
取得した特許を広く周知する手段として、製品カタログや広告に「特許取得済」や「特許番号」を記載する企業も少なくありません。その表示は技術の信頼性をアピールできるだけでなく、他社に対して「当該技術は法的に保護されている」という警告にもつながります。
参考文献:
- 特許出願書類の 書き方ガイド
- 特許請求の範囲、特許請求項とは?弁理士が詳細解説
- 特許をオンラインで出願する方法 ~メリット・注意点を徹底解説 | Toreru Media
- 初めてだったらここを読む~特許出願のいろは
登録後の維持と権利行使
特許権を維持するには、登録後も毎年「年金」と呼ばれる特許料を納付し続ける必要があります。具体的には、第4年目以降、各年分の年金を事前に納めなければなりません。これを怠ると、特許権は有効期間内であっても自動的に消滅してしまいます。
そのため、すべての特許について無条件に維持し続けるのではなく、技術の将来性や市場での採算性を見極め、事業への貢献が乏しい特許については早期に放棄することも選択肢です。
こうした判断は、企業の知財戦略において費用対効果の観点から重要とされており、製品ライフサイクルや競争環境に応じて柔軟に見直すことが望まれます。
また、取得した特許を自社で使用するだけでなく、他社にライセンスを提供して使用させることで収益を得る「ライセンスアウト」も一つの有効な活用法です。
特許を活かしたビジネスモデルの一環として、こうした外部活用の選択肢を持つことは、攻めの知財戦略としても注目されています。
なお、製法特許に関する侵害の立証や、PCT国際出願など国際展開に関する制度の詳細については、提供された情報ソースには記載がありませんでした。
これらの事項について検討する場合には、別途信頼できる専門資料や実務ガイドラインを参照する必要があります。
参考文献:
- 特許出願書類の 書き方ガイド
- 特許請求の範囲、特許請求項とは?弁理士が詳細解説
- 特許をオンラインで出願する方法 ~メリット・注意点を徹底解説 | Toreru Media
- 初めてだったらここを読む~特許出願のいろは
生成AIが変える特許調査とエムニのソリューション
特許調査は、企業の知的財産戦略において非常に重要な役割を果たします。海外での権利取得や競合他社による特許侵害の予防、新技術トレンドの把握といった目的に加え、研究開発や製品企画の初期段階でも調査の有無がその後の事業展開に大きな影響を与えるためです。
しかし現実には、特許調査には高い語学力と専門知識が求められ、特に外国語の特許文献に対する翻訳や内容把握には多大な時間とコストがかかるという課題がありました。
調査費用が1件あたり10万円以上に及ぶケースも珍しくなく、中小企業にとっては大きな負担となっているほか、翻訳精度のばらつきや情報漏洩のリスクなども無視できません。
こうした状況に対し、エムニは生成AIを活用したソリューションの開発に注力しています。特許分野におけるAI導入の先進的な取り組みの一つとして、エムニは日本特許翻訳株式会社と共同で、Meta社の大規模言語モデル「Llama-3-70B」をベースに特許翻訳に特化したLLMを構築しました。
このモデルは、数百〜数千対の実翻訳データを学習させたうえでチューニングされており、BLEUやRIBESといった翻訳品質指標において、汎用的なAIモデルや商用翻訳エンジンを大きく上回る性能を実現しています。
また、このモデルはオンプレミスでの運用を前提としているため、製造現場や研究施設など高セキュリティが求められる環境でも安心して導入することが可能です。
この特許翻訳LLMを活用することで、従来は1件10万円程度かかっていた外国公報の調査が、1件あたり数十円まで圧縮できる事例も報告されています。
これにより、特許調査を外注せずに社内で迅速に行えるようになり、大幅なコスト削減とスピードアップが実現されています。さらに、生成AIによる特許調査では、膨大な特許データの中から関連度の高い文献を短時間で抽出し、類似性の判定や検索式の最適化を自動で行うなど、人的作業では不可能な処理の自動化が可能です。
エムニではこのほかにも、特許文献の構成要素である課題と解決手段を解析し、パテントマップを自動生成する機能の提供を進めています。
従来は数百万円の外注費と1か月以上の期間を要したパテントマップ作成が、生成AIの導入によりわずか2時間・数千円で済むようになり、多くの企業にとって実用的な選択肢へと変わりつつある状況です。
生成AIを活用した知財業務の効率化にご興味がある方は、まず一部業務から導入を検討してみてください。
参考文献:
- 特許翻訳にAIを導入するメリットを事例付きで詳しく解説
- 特許調査の費用軽減|生成AIがもたらす効率化と省コスト化 – オウンドメディア
- AIで特許調査のコストを1000分の1に|活用戦略を詳しく解説
- エムニ: ファインチューニングを用いた特許翻訳特化型LLM開発において
製法特許をめぐる判例と海外動向
日本では、知的財産高等裁判所が製品の性質などから合理的に侵害が推定される場合には、製法特許の侵害を認める判決を複数出しています。これにより、製造工程が見えない相手に対しても、一定の条件下で勝訴が可能となっています。
一方、米国では「プロダクト・バイ・プロセス(PBP)クレーム」と呼ばれる方式が採用されており、製品の属性そのものに基づいて判断が下される傾向があります。
こういった国ごとの特許への考え方の違いを理解しておくことは、国際的な特許戦略を立てるうえで重要です。
日本判例:エクオール製造法事件
製法特許における典型的な争点を示す事例として、大塚製薬が起こした「エクオール事件」があります。
エクオールは、大豆イソフラボンが腸内細菌の作用によって変化する成分で、女性の更年期症状の緩和や美容効果が期待されています。
大塚製薬は、エクオールとオルニチンを含む発酵抽出物の製造方法に関して特許を取得しており、自社の特許技術が他社製品に無断で使われていると主張しました。
問題となったのは、相手方が製造方法を一切開示せず、第三者による確認も困難だった点です。通常、製法特許の侵害を主張するには、相手の製造方法が特許の技術的範囲に含まれることを証明する必要があります。
しかし、この事件では特許法第104条に基づく「推定規定」が適用されました。これは、特定の製品が通常その特許製法でしか作れないと考えられる場合には、相手企業が同じ製法を使っているとみなすことができるという仕組みです。
裁判所は、対象製品にエクオールとオルニチンが含まれていること、大塚製薬の特許がその製造法を対象としていることを確認しました。
さらに、被告企業が自社の異なる製法を客観的に証明できなかったため、推定が成立すると判断されました。その結果、大塚製薬の主張が認められ、特許侵害が認定されました。
この判決は、製造過程が見えない場合でも、特定の条件が整えば製法特許の侵害を証明できるという点で、実務上極めて重要な意味を持ちます。
とくに、食品・医薬・化粧品・化学といった分野では、製法が製品の競争力の源泉となるため、出願の段階から製品との関係を明確にしておくことが望まれます。これにより、将来的な訴訟での立証を有利に運べる可能性が高まるでしょう。
一方で、被告側にとっても教訓となる判例です。仮に実際には別の方法で製造していたとしても、それを示す証拠がなければ、特許侵害と判断されてしまうリスクがあります。防御の観点からも、自社の製法を説明可能な形で管理・記録しておくことが不可欠です。
製法特許は、その性質上、他者から把握されにくいため、攻守のいずれにおいても高度な知財戦略が求められます。エクオール事件は、大塚製薬の対応を通して、製法特許の活用方法や防御策を考えるうえで、極めて示唆に富む判例だと言えるでしょう。
参考文献:
- 大塚製薬 エクオール含有食品に関する特許訴訟に対する最高裁判所の決定について|ニュースリリース
- 令和2年(ネ)10059【エクオール含有抽出物及びその製造方法】<本多> – NAKAMURA & PARTNERS
米国 PBP クレームの実務
製法による製品の請求項(PBPクレーム)とは、「ある特定の作り方(製造方法)によって得られる製品」を特許の対象として表す方法です。たとえば、製品の形や性質だけでは特許の内容を正確に説明できないときに、その製品をどう作るかという製法を使って請求項を構成します。
こうした請求項は、日米問わず使われていますが、アメリカでは運用が非常に厳格です。
アメリカでは、「請求項に記載された通りの製法で製品が作られていなければ、その特許は効力を持たない」という立場が取られています。つまり、製品の見た目や性能が同じでも、違う方法で作られていれば特許侵害には当たらないのです。
この考え方が明確に示されたのが、2009年の「アボット対サンド社」事件(Abbott v. Sandoz)です。この裁判では、アボット社がある製法で製造される医薬品について特許を持っていました。
しかし、ジェネリック医薬品メーカーのサンド社は別の方法で似た薬を作っていたため、裁判所は「特許侵害ではない」と判断しました。
この判例以降、米国では製法による製品の請求項の扱いがより厳しくなり、保護される範囲も狭く解釈される傾向が強まっています。
したがって、アメリカでこの形式の請求項を使う場合には注意が必要です。製法に頼りすぎず、製品そのものの構造や性質を明確に記載することが重要とされています。そうしなければ、他社が製法を少し変更するだけで特許を簡単に回避されてしまう恐れがあるからです。
一方、日本では扱いがやや異なります。たとえ製法が異なっていても、製品の構造や性質が同じであれば、特許侵害と判断される可能性があります。これは、日本の実務では「製法は製品を説明するための補足手段」として見られることが多いためです。
このように、同じ技術を特許で守ろうとしても、アメリカと日本では請求項の書き方や、特許の効力の範囲に大きな違いが出てきます。
そのため、国際的に特許を取得しようとする企業にとっては、各国の特許制度に合わせて請求項を調整することが不可欠です。
参考文献:
侵害リスクとエビデンス確保
製法特許は、その構造上、外部から侵害の実態を把握しにくいという課題を抱えています。これに対応するため、特許法は推定規定や証拠収集制度を整備し、権利行使を支える枠組みを設けてきました。
ただし、こうした制度の活用には営業秘密の開示リスクがつきまとう場面もあり、企業にとって一筋縄ではいきません。以下では、この制度的背景と実務上の留意点について掘り下げていきます。
特許法104条推定規定の適用
特許法第104条は、「同じような製品が工業的に生産されている場合には、その製品は特許された製法で作られていると推定する」というルールを設けています。
これは、製造工程が外部から見えにくい製法特許において、特許権者が訴訟を起こしやすくなるよう設けられた制度です。
工程の詳細を証拠としてつかめなくても、状況的な一致から侵害を推定できるため、権利の実効性を高める効果が期待されました。
しかしその一方で、この推定規定は「自分たちが製法特許を使っていないこと」を被疑者が証明しなければならないという証明責任の転換をもたらします。
この証明には、しばしば自社の詳細な製造方法=営業秘密の開示が必要となり、企業にとっては大きなリスクを伴うものでした。秘密保持命令などの制度は存在するものの、裁判の過程で競合に自社の重要情報を知られる可能性を完全に排除することはできません。
このように、特許法104条の推定規定は、適切に使われれば権利保護の有効な手段となりますが、濫用されれば相手企業の情報を引き出すための戦術ツールともなりかねない、まさに「諸刃の剣」といえるでしょう。
さらに、現代では証拠収集制度の整備が進み、104条が制定された当時とは状況が大きく異なっています。今や特許法105条などを活用すれば、よりバランスの取れた証拠開示も可能となってきました。
こうした変化をふまえると、企業にとって重要なのは、法的リスクと情報流出リスクの両面を踏まえた対応戦略を持つことです。
特許紛争に備えるだけでなく、製法に関する機密保持体制を整え、どのような場合に情報を開示し、どのような場面では徹底して守るべきかという社内方針を明確にしておく必要があります。
場合によっては、そもそも訴訟の土俵に上がらない選択肢(代替製法の確保や契約的対応)を検討することも有効でしょう。
つまり、特許法104条は単なる法技術ではなく、企業の経営判断と知財戦略を直撃する現代的な課題です。その効力と危険性を正しく理解し、法務部門と事業部門が一体となって備えることが、いま求められています。
参考文献:特許法 104 条の生産方法の推定に 関する現代的解釈
秘匿性の高い製造ラインの調査手法
製造方法に関する特許では、他社に真似された場合でも、その証拠をつかむのが難しいという問題があります。製品と違って、作り方そのものは工場の中で行われ、外部からは見えないためです。そのため、特許を持っている側が「本当に真似されたのか?」を証明するのは、従来は非常に困難でした。
そこで令和元年の特許法改正によって導入されたのが、「査証制度」と呼ばれる新しい仕組みです(令和2年10月施行)。この制度では、裁判所が中立の技術専門家(査証人)を選び、その人が被疑侵害者の工場などに入り、製造の実態を調べることができます。
そしてその結果を「査証報告書」として裁判所に提出します。この報告書は、特許権を持つ側にとって、裁判で使える重要な証拠になります。
この調査には、基本的に申立人(特許権者側)は立ち会えません。なぜなら、競合企業が工場に入ると、企業秘密が漏れるおそれがあるからです。第三者の専門家だけが調査に関わることで、そうしたリスクを減らす仕組みになっています。
また、査証制度が乱用されないように、裁判所が慎重に査証命令を出すかどうかを判断することになっています。簡単に許可が下りるわけではありません。
加えて、調査の結果が記された報告書の中に企業秘密が含まれる場合、被調査側(被査証者)は「その部分は開示しないでほしい」と裁判所に申し立てることができます。
これを「不開示申立て」と呼びます。裁判所は必要と判断すれば、報告書の一部を相手側の代理人のみに見せるなど、限定的に開示することもできます。
さらに、もし被査証者が正当な理由もなく査証を拒否した場合には、裁判所が「特許権者の言っていることは事実とみなす」と判断する可能性もあります(特許法105条の2第5項)。このように、調査を拒んだ側にとって不利な推定が働くことで、制度には一定の強制力も備わっています。
ただし、この査証制度は、あくまで「証拠集めの手段の一つ」にすぎません。製造方法の侵害を立証する責任がどちらにあるか、という根本的な問題までは解決していないのです。
たとえば、特許法第104条には「ある条件を満たせば、相手が自分の製造方法を証明しなければならない」という仕組みがあります。
この場合、相手側は自社の機密を明かさなければならなくなるため、大きな負担を強いられます。この開示の義務は、査証とは異なる別の文脈で問題になります。
実務でも、104条による「推定の仕組み」が被疑侵害者に重い情報開示の負担をかけるとの指摘は根強くあります。査証制度が導入されたからといって、そうした問題がすべて解決したわけではありません。
以上のように、査証制度は特許権の行使を補助する有力な手段である一方で、営業秘密の保護や立証責任とのバランスといった、より大きな制度的課題を完全に解決するものではない点に注意が必要です。
参考文献:
ビジネス活用戦略
製法特許は強力な保護手段ですが、その公開性ゆえに模倣の余地が残るという側面もあります。
そこで重要になるのが、特許と営業秘密を使い分ける防衛戦略、そして技術をいかにビジネスとして収益化するかという視点です。次に、それぞれの戦略を見ていきます。
特許+ノウハウハイブリッド防衛
製法特許は、製品の製造方法に独占的な権利を与えるため、模倣を防ぐうえで強力な手段です。とくに製造プロセス自体が企業の競争力の源となる分野では、その重要性が高いといえるでしょう。
しかし、特許を取得するには、出願時に技術内容を公開しなければなりません。この公開情報をもとに、競合他社が類似の製造方法を構築するリスクがある点は見逃せません。
たとえ請求項の直接的な範囲を回避していたとしても、実質的に同じ効果を得る方法が取られる可能性は十分に考えられます。
この課題に対処するために、有効とされるのが「特許と営業秘密を組み合わせるハイブリッド戦略」です。
技術の中で、出願しても問題がない構造部分だけを特許として保護し、再現性や性能に直結する細かな製造条件、たとえば反応温度や触媒濃度、処理時間などは社内秘として管理します。
このように「見せて守る部分」と「隠して守る部分」を意図的に分けておくことで、仮に特許文献をもとに模倣が試みられたとしても、再現に必要な情報が欠けており、完全なコピーは困難となるのです。
また、営業秘密として保持された情報には公開義務がないため、特許権が満了した後でも、一定の技術的優位を維持できるという利点もあります。実際、食品や化学品、素材産業などではこの手法を取り入れている企業が多く、競争力の長期的な確保に貢献してきました。
このハイブリッド型の知財防衛は、単なる模倣防止策にとどまらず、事業の収益性や市場支配力を高めるための戦略的アプローチとしても有効です。企業が持つ技術資産を「どう見せるか、何を隠すか」という視点で再構築することで、知財の真の力が引き出されることになるでしょう。
参考文献:中小企業の知的財産戦略に関する 調査研究
ライセンス交渉と収益化モデル
技術の保護と並行して、その活用をいかに収益につなげるかという視点は、企業の知財戦略において欠かせません。
特に製法特許やノウハウを組み合わせて構築された技術は、自社で独占的に利用するにとどまらず、他社にライセンスを供与することで事業領域を拡張する手段にもなり得ます。
米国のQualcommは、このような収益化戦略を展開している代表的な企業のひとつです。
同社は通信分野の特許を数多く保有しており、スマートフォンや通信機器メーカーに対して広くライセンス供与を行っています。
製品販売に加え、特許ライセンス収入をもう一つの柱とするビジネスモデルを採用しており、それによって技術資産の価値を最大限に引き出してきました。
自社による独占的な製造にこだわらず、他社に使用を許可して収益を得るモデルは、とくに資本や生産設備に制約のある企業にとって合理的な選択肢となります。
製法特許のように再現が難しく、応用範囲の広い技術ほど、こうしたモデルによって効果的に活用される傾向があります。
とはいえ、ライセンス契約による収益化を成功させるには、契約設計の精度が極めて重要です。技術の適用範囲や使用条件、ロイヤルティの算定基準などについて、曖昧さのない形で取り決める必要があります。
報告内容に基づいて収入を得る場合には、監査権を明記することで信頼性の確保が図れるでしょう。
加えて、対象技術に営業秘密やノウハウが含まれる場合は、秘密保持義務や漏洩時の対応を契約に組み込むことが不可欠です。
こうした予防策を講じておけば、不測の情報流出に対しても一定の歯止めをかけることが可能となります。
このように、技術のライセンス供与は、企業にとって単なる収益手段ではなく、戦略的資源の外部活用を通じた事業成長の一環と位置づけることができます。
参考文献:
まとめ
製法特許は工程を保護し、市場参入障壁を築く強力な武器です。ただし公開リスクとのバランスや国際実務の違いを踏まえた出願戦略が欠かせません。
本記事で示した新規性調査、請求項作成、侵害立証のポイントを踏まえ、自社技術の守りと攻めを両立させてください。
さらなる詳細や個別事案の相談を希望される場合は、専門家へ早期にアプローチすることでスムーズな権利化と事業展開が期待できます。
エムニへの無料相談のご案内
エムニでは、製造業をはじめとする多様な業種に向けてAI導入の支援を行っており、企業様のニーズに合わせて無料相談を実施しています。
これまでに、住友電気工業株式会社、DENSO、東京ガス、太陽誘電、RESONAC、dynabook、エステー株式会社、大東建託株式会社など、さまざまな企業との取引実績があります。
AI導入の概要から具体的な導入事例、取引先の事例まで、疑問や不安をお持ちの方はぜひお気軽にご相談ください。
引用元:株式会社エムニ