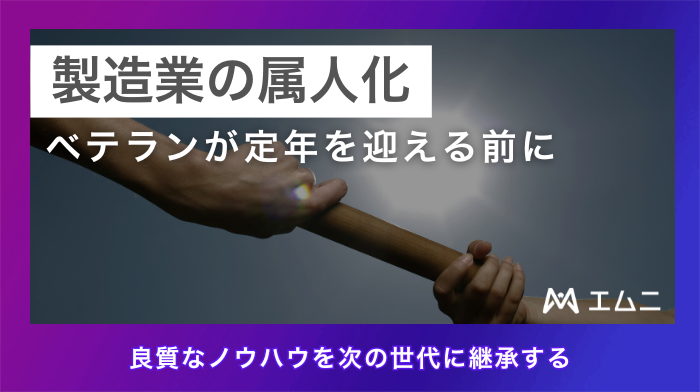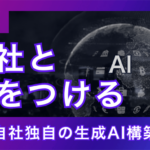
ファインチューニングとは|自社に最適化された生成AIの構築
2025-03-22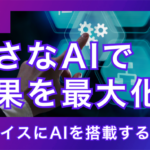
SLM(小規模言語モデル)とは| 高速・効率・安全な生成AI
2025-03-22形式知とは?暗黙知との違い、メリット、形式知化の手法を詳細に解説

製造業が直面する熟練従業員の退職や深刻な人材不足といった課題。特に懸念されるのは、長年の経験で培われた職人技や感覚的判断といった暗黙知の喪失です。暗黙知が失われると、品質や生産効率の低下は避けられません。重要なのは、個人に属人化した暗黙知を言語化・体系化し、組織全体で共有可能な「形式知」へと変換することです。
本記事では、形式知化によって得られるメリット、形式知化で重要となるSECI(セキ)モデルや場(Ba)の概念について詳細に解説し、製造現場で実践可能なナレッジマネジメント手法について具体的に紹介します。
形式知とは?
形式知とは言語化された客観的な知識のことです。文章、計算式、図表などで明確に表現され、誰もが理解可能なかたちで共有できる知識を指します。形式知の具体例としては、業務マニュアルや操作手順書などが挙げられます。
形式知と暗黙知の違い
暗黙知とは言語化が困難であり主観的な知識のことです。単純な言語や数値だけでは他者に伝達することが困難な知識を指します。暗黙知の具体例としては、熟練した職人の技能、長年の経験に基づく営業担当者の顧客対応力などが挙げられます。
暗黙知を形式知化する4つのメリット
まず、暗黙知を形式知に変換することで得られるメリットについて解説します。形式知化により具体的にどのような恩恵が得られるのか学んでいきましょう。
属人化の防止
製造業では技能や知識の属人化は重大なリスクとなります。熟練技術者の退職や異動により、個人に依存した言語化されていない技能や専門知識(=暗黙知)が失われると、品質や生産性の低下に直結するからです。
暗黙知を形式知化することで、このような属人化リスクを回避できます。特定の個人に集中していた技能や知識を組織全体の共有資産として活用できるようになるのです。また、組織全体で知識共有が促進されることで、個人で業務を行う状況を脱却し、チーム単位での業務遂行も容易になるでしょう。
人材育成の発展
暗黙知の形式知化は従来の人材育成が抱えていた問題を解決に導きます。
まず、明文化された知識にもとづく体系的な教育により、短期間での技能習得が可能になります。習得時間の短縮により、高度な技術の習得に取り組むことも期待できるでしょう。また、教育内容が標準化されることで指導者や部門によるばらつきが是正され、均質な技術水準の確保が容易になります。
教育側にとっても、形式知として体系化されたマニュアルや手順書を活用することで、指導にかかる時間と労力を削減できます。熟練技術者は自身の専門性をさらに高める活動や新たな価値創造に時間を投資できるようになり、組織全体の競争力強化が期待できるでしょう。
業務効率の向上
暗黙知を形式知に変換することで、特定の個人が獲得した効率的な手法を組織全体で活用可能になり、業務効率の向上が期待できます。
また、成功事例を分析・明文化し形式知として蓄積することで、他プロジェクトやチームでも再現可能になります。逆に、過去の失敗事例と対応策を共有することで、再発防止や組織全体での学習サイクルを確立ができるでしょう。
さらに、形式知化により整理された情報には即時アクセス可能です。過去の類似事例や解決策を瞬時に参照できるため、意思決定プロセスは大幅に高速化されます。
加えて、情報共有の障壁が取り除かれることで、部門間連携も強化されます。組織全体で知識が循環し、業務効率の改善が望めるでしょう。
知識の有効活用
形式知化により個別の知識や経験が構造化され、それらの関連性や全体像が明確になります。これにより、企業に存在するナレッジを製品開発から顧客対応まで幅広い業務に応用できるようになるでしょう。
形式知化された知識は無形資産として大きな価値があります。製造業では技術的な知見が製品の差別化や生産性の向上に直結するため、形式知化された知識は競争優位性の源泉となるでしょう。
また、形式知化により、これまで接点のなかった分野の知識が組み合わされることで、新たなイノベーションが生まれる可能性も高まります。知識領域の融合により新たな製品革新の機会が創出され、企業の持続的成長に貢献するでしょう。
ナレッジマネジメントとは?
ナレッジマネジメントとは、個人が持つ知識やノウハウといったナレッジ(knowledge)を組織全体で共有・活用することにより、新たな知識創造や組織の生産性向上に繋げる経営手法です。
ここではナレッジマネジメントを実践するにあたって重要となる「SECI(セキ)モデル」と「場(Ba)」という考え方について詳細に説明します。
SECI(セキ)モデルとは?
SECIモデルは、暗黙知と形式知の相互作用による知識創造プロセスを説明する理論であり、「共同化」「表出化」「結合化」「内面化」の4つのプロセスから構成されます。
まず、共同化では体験や観察を共に行うことにより暗黙知が共有されます。次に、表出化では暗黙知を言語や図解といった形式知に変換。さらに、結合化では複数の形式知を統合し新たな知識を生み出します。最後に、内面化では形式知を実践を通じて個人の暗黙知として定着させます。
これらのプロセスを循環することで、継続的な知識創造が実現されます。
場(Ba)とは?
場は知識創造が活発な共有空間であり、SECIモデルのそれぞれのプロセスを支える環境として機能します。
場は「創発場」「対話場」「システム場」「実践場」の4種類に分類されます。まず、創発場では対話を通じて暗黙知の共有が行われます(共同化)。次に、対話場では議論や資料作成を通じて暗黙知が形式知へと変換されます(表出化)。さらに、システム場ではデータベースやデジタルツールを活用して形式知を蓄積・統合(結合化)。最後に、実践場では、業務や実務を通じて新たな暗黙知が生み出されます(内面化)。
このような場を適切に設計することにより、知識創造の質を向上させることができます。
形式知化の具体的な手法
形式知化にはさまざまなノウハウが存在します。生成AIを活用することで、現代ならではの形式知化を実現できるので参考にしてみてください。
インタビューと観察
暗黙知の形式知化には、業務現場の観察、熟練従業員に対するインタビューが有効です。
実際の業務現場の観察は、無意識に行っている判断や技能を可視化するうえで重要です。熟練従業員が作業する様子を映像で記録、動作を分析することで、言語化されていない微妙な動作や判断を捉えることができます。このような観察結果をフローチャート、マニュアル、チェックリストなどの形式で言語化し、形式知として共有可能な情報に変換しましょう。
また、インタビューにより熟練技術者が長年の経験から獲得した専門知識や思考過程、判断基準を言語化することができます。「なぜその判断をしたのか」「どのような状況変化に注目しているか」といった観点から深掘りすることで、表面化しにくい暗黙知を引き出すことが可能です。
しかし、「何を質問すればいいのかわからない」「インタビューに手間と時間がかかる」「得られた情報の整理に時間を要する」といった問題も存在します。エムニでは、これらの問題を解決に導く「AIインタビュアー」を開発しています。詳細は後述しますので、ぜひご覧ください。
▼生成AIを活用した暗黙知の形式知化について更に詳しく知りたい方はこちら
生成AIで暗黙知を形式知化するメリットやプロセスを解説
紙資料のデジタル化・情報検索システムの導入
紙資料のデジタル化は、暗黙知を形式知化する重要な手法の一つです。OCR技術で過去の技術資料・報告書・マニュアルなどをデジタル化することで、貴重な情報を検索可能な知識として保存できます。
デジタル化された情報は、全文検索機能を備えたデータベースに統合することで価値が最大化します。従業員は必要な情報を瞬時に検索でき、過去の類似案件や解決策を即座に参照できるようになるためです。また、ヘルプデスク型ツールの導入により、頻出する質問とその回答を蓄積し、業務効率化を目指しましょう。
さらに、情報にタグ付けしたり階層構造を設けたりすることで、関連性や重要度にもとづいた情報検索が可能になります。あらかじめ体系的な分類を施し、情報のアクセシビリティ向上を目指しましょう。
コミュニケーションの充実
暗黙知の形式知化には活発なコミュニケーションが不可欠です。日常的な対話や議論を通じて、個人の頭のなかにある知識が言語化され、組織の共有資産となるためです。問題解決の過程で思考過程や判断理由を明確に表現しあうことで、暗黙知が自ずと形式知へと変換されます。
社内SNSやチャットツールの導入は、このようなコミュニケーションを促進する手段となります。これらのプラットフォームにより、時間や場所に縛られない情報交換が可能となり、部門や部署を横断した知識共有も実現できるでしょう。会話内容がそのままデジタル化された知識として蓄積される利点もあります。
マルチメディアによる知識共有
言葉だけでなく多様なメディアを活用することにより、効果的な形式知化が可能です。製造業の現場では微妙な感覚や視覚的な基準など言葉だけでは表現しきれない暗黙知が多く存在するため、動画や音声を併用することで、このようなニュアンスを含めた知識共有が実現します。
例えば、スクリーンキャプチャー技術を用いた操作手順の解説は、複雑なプロセスを視覚的に伝達する効果的な方法です。操作画面の動きと解説を同時に示すことにより、文書だけでは理解しにくい操作手順を明確に伝えることができるでしょう。
また、熟練技術者による実演を動画記録し、ナレーションを付加することも有効です。例えば、製品不具合の微妙な判別方法や調整時の音の違いなど、感覚的な判断基準を効果的に伝達できます。
形式知化における注意点
ここからは形式知化を進めるにあたって留意すべき注意点について解説します。
最も注意しなければならないのは、暗黙知の形式知化には経営層のリーダーシップが必要不可欠であるということです。形式知化は全社的な取り組みであることに加え、製造業では現場の経験や技能を重視する文化があるため、経営層による従業員の意識改革や組織風土の転換が求められるでしょう。
これを前提に、具体的な注意点について見ていきます。
段階的な導入とシンプルな制度設計
形式知化は、複雑なシステムではなく目的や対象を限定したシンプルなシステムからスタートしましょう。
多機能で複雑なナレッジマネジメントシステムは却って現場従業員の利用障壁となり、定着を阻害する原因となるからです。特に製造業では、ICT機器やデジタルツールに不慣れな熟練従業員も多いため、紙ベースの記録とデジタルツールを組み合わせるなど、現場の実情に合わせた柔軟な設計が重要です。
また、特定の部門や業務工程に範囲を限定し、小規模な成功事例を積み重ね、徐々に範囲を拡大していく段階的アプローチが効果的です。導入初期に成功体験ができると現場従業員の理解と参加意欲も向上し、取り組みの拡大にも貢献するでしょう。例えば、設備・工具の基本的な取り扱いなど、導入初期は「品質や生産に直接影響しないが、業務効率化に役立つ工程」に注力するのがよいでしょう。
定量的な効果測定
形式知化を成功させるためには、製造業の特性に合わせた効果を定量的に測定することが不可欠です。
まず、取り組みに着手する前に、生産効率、設備稼働率、不良率、新人育成期間などの現状値を詳細に記録しておく必要があります。これが効果測定の基準点となるからです。導入後は継続的に効果測定を行い、変化を数値で評価します。生産性向上率、品質不良の減少率、新人の習熟速度向上などを客観的に示すことで、取り組みの価値を可視化しましょう。
また、材料ロスの削減やエネルギー消費の最適化といったコスト削減効果、労働災害の減少など、業務効率化以外の観点からの効果測定も重要です。
さらに、投じた人的・金銭的コストと得られた効果を比較し、ROIを明確に示すことが求められます。費用対効果を明示することで、経営層の理解の獲得やさらなる取り組みの推進に繋げましょう。
形式知化に対するインセンティブ
製造業では、長年培った技術や知見を従業員個人の価値として重視する傾向があるため、形式知化に対する協力が得られにくい場合があります。多くはノウハウを共有することで得られる組織的・個人的メリットが理解されていないことが原因でしょう。だからこそ、形式知化がもたらす具体的な効果を丁寧に周知することが、参加意欲を高める第一歩となります。
また、知識共有に対して適切に評価する仕組みを構築することが重要です。人事評価制度に「技術伝承への貢献度」の項目を設定するなど、貢献度を明確に評価することで形式知化を促進できます。
さらに、知識提供者には、金銭的報酬だけでなく、新たな技術の習得やより専門的な研修など成長機会の提供でリターンを与えることも効果的です。加えて、形式知化により業務改善を実現した事例を表彰するなど、製造業の現場の雰囲気に則したかたちで形式知化を促進する仕組みを構築することが重要です。部門対抗の業務効率化コンペや技術伝承発表会なども有効でしょう。
エムニの事例
株式会社エムニでは、「AIインタビュアー」と呼ばれる、熟練従業員から暗黙知を抽出し、LLM(大規模言語モデル)を通じて技能伝承を実現するソリューションを提供しています。
熟練作業員がAIインタビュアーに対してスキルを語り、情報整理用生成AIによって得られた暗黙知をテキストベースの形式知に変換、データベースに蓄積されます。トラブル発生時には、過去の類似事例をチャットボットを通じて検索でき、チャットボットが解決案を提供することが可能になります。
AIインタビュアーを活用することで、熟練従業員の暗黙知を簡単に共有できるため、人材育成と技能伝承の効率化が期待されます。また、チャットボットで過去事例から解決策を瞬時に検索できるため、トラブル解決を迅速化できます。さらに、従来は言語化できていなかった暗黙知が蓄積され、組織全体のナレッジマネジメントにも貢献するでしょう。
まとめ|暗黙知の形式知化で、技能伝承と持続的な成長を!
暗黙知の形式知化により、知識の属人化を解消し、技能・知識伝承や人材育成の加速、業務効率の向上が実現できます。また、取り組みの成否を握るのは、SECIモデルに基づく「共同化」「表出化」「結合化」「内面化」のプロセスと、それを実施する「場」をいかに構築するかです。
一方で、形式知化の実現には乗り越えるべき障壁が多く存在します。そのため、社外の専門家の力を借りることで形式知化を着実に進めることができるでしょう。
エムニへの無料相談のご案内
エムニでは、製造業に特化したAI導入の支援を行っており、企業様のニーズに合わせて無料相談を実施しています。AI導入の概要から具体的な導入事例、取引先の事例など、疑問や不安をお持ちの方はぜひお気軽にご相談ください。