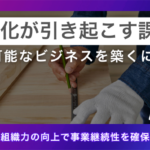
属人化とは?組織課題を解消し、持続可能なビジネスを築く方法を解説
2025-08-22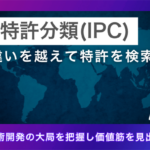
国際特許分類(IPC)を徹底解説|グローバル競争を勝ち抜く武器
2025-08-25仕事の属人化ストレスを解消|原因や取るべきアクションを徹底解説
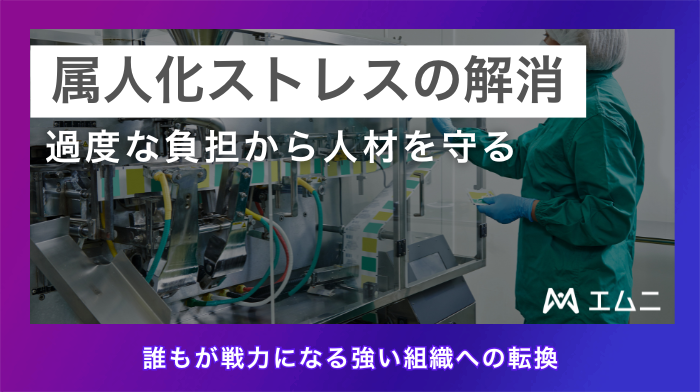
製造業の現場で慢性的な課題となっている業務の属人化。2025年に行われた調査では、製造業の9割以上が、生産工程や工程管理における現場ごとのノウハウなど属人化した仕事があると回答しています。
出典:[500人に調査]約8割が業務の非効率を実感:属人化と人手不足の実態を公表(PR TIMES)
属人化は、一見すると単なる業務分担の偏りに思えますが、実際には担当者の心理的負担、チームの機能不全、さらには組織全体の生産性低下にまで波及する深刻な問題です。
属人化が引き起こす3つのストレスとは
属人化という言葉を聞くと、多くの方が「特定の業務を特定の人間しか担当できない状況」を思い浮かべるでしょう。しかし、属人化は単なる業務分担の問題に留まりません。
ここでは、属人化が引き起こす多面的なストレスについて、個人、チーム、そして組織全体への影響という3つの観点から詳しく解説します。
個人のストレス
属人化の渦中にいるキーパーソンは大きな心理的ストレスを抱えています。
まず、「自分にしかできない」という状況から強烈な重圧が生じます。
特定の工程、顧客対応、システム運用などが特定の個人に依存している場合、ミスが発生した際には全て自分の責任になるという大きなストレスが発生するのです。
また、業務が分担できないため、慢性的な長時間労働や休暇取得の難しい状況が常態化します。
こうした状況は燃え尽き症候群(バーンアウト)や体調不良を引き起こす温床となるのです。
さらに、属人化した役割に長期間固定されることで、新しい業務やスキルに触れる機会が失われ、キャリアの停滞感が強まります。
自身の成長が望めない閉塞感は、モチベーション低下、ひいては離職のきっかけにもなるでしょう。
チームのストレス
属人化によるストレスは担当者だけにとどまりません。周囲の同僚にも確実に波及し、チーム全体の機能不全に繋がるのです。
まず、過大な負荷を抱えているキーパーソンを助けたくても、業務内容が不透明で手が出せない、あるいはその担当者が不在になると業務を代行できない、といった状況に直面します。
この「助けたくても助けられない」状況は、無力感という形でチーム全体のストレスとなるのです。
また、知識やノウハウが特定の個人に集中することは、他のメンバーから学びと経験の機会を奪います。
特に若手社員にとっては、スキル習得の場が制限され、モチベーションやエンゲージメントの低下、ひいては離職意向の高まりにもつながるでしょう。
さらに、業務が属人化すると、その領域についての対話やフィードバックが減少し、心理的安全性が揺らぎます。
「こんなことを聞いたら迷惑かもしれない」という空気が広がることで、率直なコミュニケーションが阻害され、チームの信頼関係は徐々に揺らいでいくのです。
組織全体のストレス
属人化は、個人やチームにとどまらず、組織全体にも悪影響を及ぼします。
最も深刻なのは、特定の担当者が病気や退職などで突然不在になった場合、業務が完全にストップするリスクです。
また、本来は組織の共有資産であるべき知識やノウハウが属人化していると、その個人の退職や異動に伴い知的資本が失われます。
後任者はゼロから手探りで学び直す必要があり、業務の品質や効率は大きく低下するでしょう。
さらに、知識が共有されない環境では、協働的な問題解決や業務プロセスの改善は生まれにくくなります。
その結果、改善文化は衰退し、新たなイノベーションも阻害されるのです。
ストレスを引き起こす属人化の原因4選
個人・チーム・組織と多方面にストレスを及ぼす業務の属人化。その背景には、様々な要因が複雑に絡み合って存在しています。
ここでは、なぜ多くの現場で業務の属人化が生じるのか、その原因を4つの側面から分析します。
組織構造的な要因
組織構造そのものが、属人化を生み出す原因となっているケースは少なくありません。
特に製造業では人手不足が常態化しており「まず目の前の仕事をこなすこと」が優先されます。
その結果、業務プロセスの棚卸し、文書化、マニュアル整備に時間を割けず、特定の担当者に業務が属人化することに繋がるのです。
また、部署やシステムといった部門間断絶も属人化の大きな原因となります。
情報共有を支える仕組みが不足していると、たとえマニュアルが存在したとしても、社内での情報共有やナレッジの形式知化は進まず、業務はブラックボックス化するでしょう。
さらに、「見て覚える」式の教育が主流である状況も好ましくありません。
このような従業員教育を続けていると、個人の裁量に依存した運用を脱却できず、業務標準化は難しいでしょう。
▼製造業の人手不足について詳しく知りたい方はこちら
製造業の人手不足|浮き彫りになる問題とその解決策
個人の心理的要因
属人化は組織構造だけでなく、従業員の心理によっても進行します。
多くの場合、業務の属人化は非意図的に発生します。
一般的に、従業員は業務を効率的にこなそうと努め、工夫し、遂行していきます。
しかし、多くの場合、業務の棚卸しや文書化に費やす時間的余裕はないばかりか、「自分で業務を回せているから問題ない」という心理が働くことで、そもそも情報共有の必要性を感じていない場合も。
その結果、本人も意識しないまま業務が属人化していくのです。
一方で、意図的に属人化を選ぶケースも存在します。自分にしかできない仕事を抱え込むことで、職場での地位や雇用の安定を確保しようとするという心理です。
こうした従業員は、他者への情報共有を自らの価値を下げる行為と捉えるため、ナレッジ共有に強い抵抗感を示します。
業務構造上の要因
業務そのものの構造や性質が、属人化の原因となるケースも多くあります。
専門的な知識やスキルを必要とする業務は、その複雑さから他者に引き継ぐことが難しく、自然と担当者が限られてしまいます。
例えば、設備保全における機械特有の不具合対応や、熟練工が長年の経験で習得した加工ノウハウなどは、文書化が困難であり従業員教育に膨大な時間とコストが必要となります。
そのため、特定の従業員への依存が常態化しやすいのです。
マネジメント的要因
属人化の進行には、経営層や管理職の姿勢が大きく影響します。
現場の実態を把握しきれていない、あるいは属人化の存在を認識しながらも問題解決に踏み込まない管理職は少なくありません。
特定の従業員に業務を任せることで、短期的には問題が表面化しない安心感を得られますが、単なる先送りに過ぎず、長期的には個人・チーム・組織のストレスを増幅させます。
また、評価制度が個人主義に偏重している状況も好ましくありません。
個人の成果だけでなく、ナレッジ共有や業務標準化に対する貢献を評価する姿勢が存在しなければ、業務の属人化とそれに伴うストレスがかかった状態は改善されないでしょう。
脱・属人化のための具体的な4つのアクション
このような属人化を引き起こす原因に対処するには、体系的なアプローチが不可欠です。ここでは具体的な対策を4つの観点から解説します。
業務プロセスの可視化と標準化
属人化を解消する第一歩は、業務を可視化し、誰が担当しても均質な品質で実行できる状態に整えることです。
まず取り組むべきは、部署内の業務をすべて洗い出す「業務の棚卸し」です。
担当者へのヒアリングを通じて、業務内容・所要時間・必要スキル・難易度をリスト化し、全体像を明確にしましょう。
そのうえで、重要度や頻度の高いものから、フローチャートを作成して業務の流れを可視化します。
これにより、ブラックボックス化していた工程や、特定の担当者しか担えない属人化ポイントを特定することができるのです。
次に取り組むべきは、マニュアルの作成および標準化です。
マニュアルは新人でも読めば実行できるレベルを目指し、具体的な手順・チェックポイント・よくあるトラブルとその対応策までを盛り込みましょう。
なお、マニュアルは一度作って終わりではなく、業務内容やシステム変更に応じて定期的に更新する仕組みを設けることが重要です。
さらに、これらを紙の資料ではなく、社内ポータルやチャットボットなどのデジタルツールで共有・検索可能にする仕組みを導入することで、誰もが必要なときにアクセスできる環境を整えましょう。
ナレッジマネジメント
属人化を防ぐためには、個人の知識やノウハウを組織全体の知的資産へと移行させるナレッジマネジメントが重要となります。
まず、ナレッジマネジメントを効果的に進めるためには、SECI(セキ)モデルや場(Ba)の概念について深く理解することが重要です。詳細はこちらの記事をお読みください。
▼ナレッジマネジメントについて詳しく知りたい方はこちら
形式知とは?暗黙知との違い、メリット、形式知化の手法を詳細に解説
そのうえで、作業現場の観察や熟練従業員に対するインタビューを通じてナレッジの収集を行いましょう。このとき、紙媒体で存在する既存資料のデジタル化も忘れてはいけません。
次に、収集したナレッジを整理し、誰もが利用可能な形式知に変換します。デジタル化された情報を全文検索機能を備えたデータベースに統合することで、必要な情報を瞬時に検索・入手することが可能になります。
また、近年注目を集めるのがAI技術を活用したナレッジマネジメントです。
例えば、 RAG(Retrieval-Augmented Generation) のように、社内に散在するドキュメントやデータベースからAIが関連情報を自動で検索・要約し、回答を提示する仕組みを導入することができれば、属人化の原因となる情報を知っている人物探す時間を大幅に削減できるでしょう。
▼生成AIによる暗黙知の形式知化について詳しく知りたい方はこちら
生成AIで暗黙知を形式知化するメリットやプロセスを解説
ジョブローテーションと多能工化
属人化を解消するには、ジョブローテーションや多能工化を通じて、特定の個人に集中している業務・権限・責任を意図的に分散することが重要です。
まず、各業務に副担当者を設定することから始めましょう。
副担当者は主担当者の業務内容を把握し、日常的にサポートすることで、業務に関するナレッジを自然に共有できます。
また、計画的かつ定期的にジョブローテーションを行うことで、複数の従業員が同じ業務を遂行できる体制を構築し、組織内でナレッジの冗長性を確保するのです。
なお、ジョブローテーションに際しては、スキルマップの導入し業務習熟度を可視化することで、より有効なものとなるでしょう。
さらに、従業員の多能工化を進めることで、急な欠員や繁忙期にも柔軟に対応できる体制を構築。
業務が特定の個人に依存せず、誰もが一定レベルで対応できる状況を作ることは、属人化リスクを減らすだけでなく、組織全体の安定性と生産性の向上にも直結するでしょう。
人事評価制度の見直し
属人化を根本的に解消するためには、従業員の意識や行動を変える組織文化の醸成が不可欠であり、その鍵となるのが人事評価制度の見直しです。
多くの企業では特定の従業員しかできない仕事が評価されやすく、業務標準化やナレッジ共有などの属人化解消に向けた行動は評価対象とならないことが少なくありません。
しかし、このままでは特定の従業員による業務の属人化が維持されてしまいます。
そこで、評価制度を改め、属人化解消に貢献する行動を正しく評価する仕組みを導入することが重要です。
具体的には、手順書やマニュアルの整備、社内ナレッジの共有、後輩育成や多能工化の推進といった活動を評価項目に組み込みます。
また、個人の成果だけでなく、チームとしての成果も重視する指標を導入することで、協力や情報共有が自然に促進されます。
さらに、評価基準の透明性を高め、人事部門と現場で納得感のある擦り合わせを行うことで、公正な評価が可能になるでしょう。
生成AIによる脱・属人化への貢献
近年注目を集める生成AIは業務の属人化の解消、およびそれに付随する従業員のストレス軽減にも大きく寄与します。
ここでは3つの観点から、生成AIが脱・属人化に及ぼす好影響について見ていきましょう。
暗黙知の形式知化
暗黙知とは熟練従業員の経験・勘・ノウハウなど、マニュアル化が難しい知識を指し、特に製造業では、職人技やトラブル対応の勘所など随所に暗黙知が存在しています。
こうした暗黙知を組織全体が利用可能な形式知に変換することは、熟練従業員の技能を若手従業員に効率的かつ確実に伝承することに直結するのです。
しかし、従来の形式知化のプロセスには、暗黙知の言語化に時間がかかる、そもそも熟練従業員が適切に言語化できない、あるいは、文書化しても検索性が低く活用が進まないといった課題がありました。
エムニが開発した「AIインタビュアー」は、AIとの会話を通じて暗黙知を抽出し、体系化されたデータベースを自動的に構築でき、さらにチャットボットに質問を投げ掛けるだけで容易にナレッジを得ることができます。
このように、生成AIを活用することで、暗黙知の形式知化に伴う時間やコストを大幅に削減することができるのです。
業務の標準化・自動化
業務の標準化・自動化は、生成AIの威力が実感しやすい取り組みの1つです。
製造現場では、紙ベースのチェックリストによる作業確認や、データ入力、報告書の作成、社内からの定型的な問い合わせ対応など、多くの誰がやっても同じはずの業務が存在しています。
2025年に行われた調査では、非効率に感じる業務として「請求書や伝票などの処理、データ入力」「社内報告や日報などの書類作成」がそれぞれ1位と2位となっています。
出典:[500人に調査]約8割が業務の非効率を実感:属人化と人手不足の実態を公表(PR TIMES)
しかし、実際には記入漏れや入力ミスといったヒューマンエラーは避けられず、経験や習熟度の差によって品質やスピードにばらつきが生じるのです。
ここに生成AIを導入することで、業務の一貫性と精度を大幅に向上させることができます。
例えば、チェックリストのデジタル化とAIによる自動判定を導入すれば、作業確認の抜け漏れを防ぎ、リアルタイムで不備を検知することが可能です。
また、AIによる標準化と自動化は、単なる工数削減にとどまりません。
定型業務が特定の人物に依存している場合には、その業務の属人化を解消し、担当者のストレス軽減にも繋がります。
さらに、担当者は「誰でもできる定型業務」から解放され、本来注力すべき付加価値の高い業務、例えば、属人化解消に向けた標準化業務といった領域に集中できるようになるでしょう。
社内情報検索の効率化
生成AIを活用することで、社内に存在する情報検索が大幅に効率化されます。
社内に蓄積される情報は年々増加しており、必要なデータを探すのに時間がかかることが意思決定の遅延や業務停滞の要因となる場合も少なくありません。
特に、データが様々な部門に散在する場合には人手による検索では効率が大きく低下します。
しかし、生成AIを活用した社内情報検索システムを導入すれば、膨大なデータを瞬時に横断検索し、必要な情報を入手することができるのです。
その結果、担当者は余分な検索時間を削減し、業務効率を高めるとともに、データに基づいた迅速かつ正確な意思決定が可能になります。
それだけでなく、情報が一元的に管理・活用されることで、個人の裁量に依存した対応の解消にも直結するでしょう。
エムニでは、製造業のお客様に特化したオーダーメイドAIの開発を行っており、チャットボットの開発事例もございます。
無料でのデモ開発も行っておりますので、詳細はこちらからご確認くださいませ。
まとめ|属人化を解消し、業務ストレスの軽減を!
個人、チーム、そして組織全体に多面的なストレスを与える仕事の属人化。
属人化は一見すると個人の専門性や高いスキルの現れのように見えますが、実際には組織の脆弱性を高める要因となるのです。
一方で、属人化の解消は単なるストレス軽減や業務改善だけではなく、特定の個人に依存しない仕組み作りに繋がる重要な経営戦略となります。
近年注目を集める生成AIは、ナレッジ収集からデータベース構築、情報検索まで、属人化解消に幅広くかつ大きく貢献しますが、製造業には特有の要件などが多数存在するため、生成AI技術の導入には壁が多いのもまた事実です。
エムニでは、製造業に特化し現場で培った知見をもとに、企業様と伴走しながら生成AI開発を行っています。
技能伝承を実現する「AIインタビュアー」など属人化解消に貢献するプロダクトもございますので、ぜひ無料相談からお気軽にお問い合わせくださいませ。
エムニへの無料相談のご案内
エムニでは、製造業をはじめとする多様な業種に向けてAI導入の支援を行っており、企業様のニーズに合わせて無料相談を実施しています。
これまでに、住友電気工業株式会社、DENSO、東京ガス、太陽誘電、RESONAC、dynabook、エステー株式会社、大東建託株式会社など、さまざまな企業との取引実績があります。
AI導入の概要から具体的な導入事例、取引先の事例まで、疑問や不安をお持ちの方はぜひお気軽にご相談ください。
引用元:株式会社エムニ
