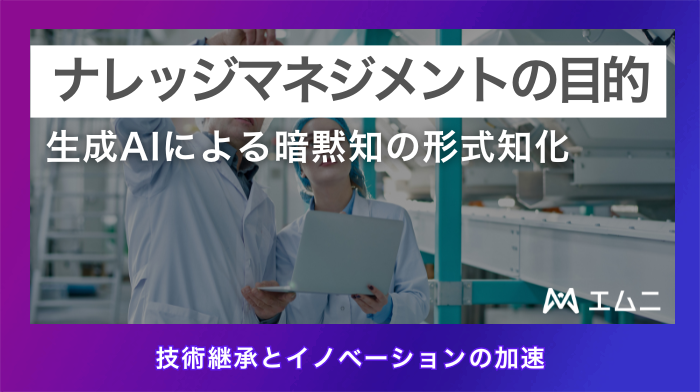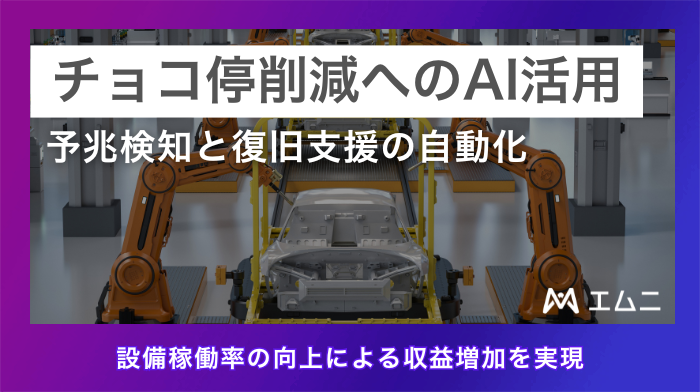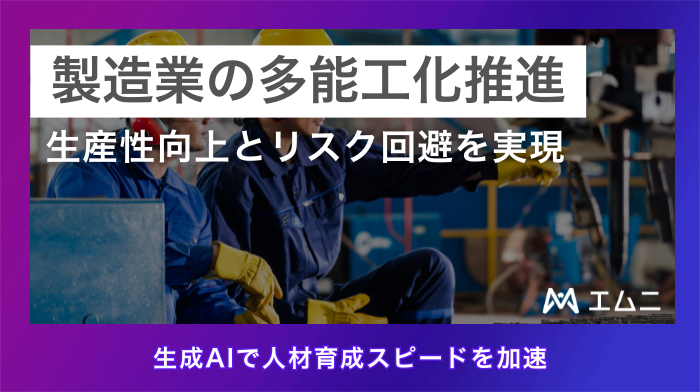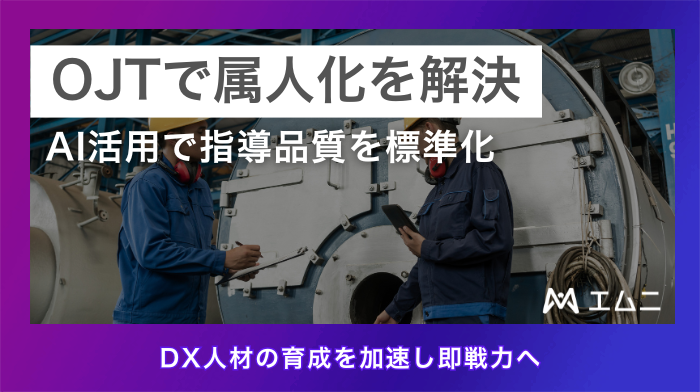社長対談|製造業界におけるAI・DX推進の展望
2025-02-12
製造業向け在庫管理システム|特徴や生成AI活用を解説
2025-02-13パテントマップとは?具体的な用途から導入方法まで

特許情報は、現代のビジネスや研究開発において競争力を高めるための重要な資源となっています。
しかし、膨大な量の特許文献や関連データに一つずつ目を通すことは骨が折れる作業であり、全体像の把握に時間がかかってしまうでしょう。
そこで、特許データを視覚的に整理し、技術動向や市場の状況を一目で把握できるツールとして役立つのがパテントマップです。
パテントマップとは
パテントマップとは、膨大な特許情報を整理し、図や表を用いて視覚的に表現したものです。
特許は一件ごとの内容が専門的で複雑になりがちですが、マップ化することで業界全体の技術動向や企業ごとの出願状況を直感的に把握することができます。
例えば、どの企業がどの分野に注力しているのか、ある技術がどの時期に活発に出願されているのかといった傾向を一目で把握できるのが特徴です。
これをもとに研究開発の方向性を決めたり、競合の動きを探ったりと、事業戦略を考える上で有用な情報基盤となります。
パテントマップは「特許を読む」作業を効率化するだけでなく、経営や研究開発に直結する意思決定を支える重要なツールとして注目されています。
パテントマップの目的
パテントマップを活用する目的は様々です。新規事業を立ち上げる上で参考にしたい、特定の技術分野に強い企業を知りたいなど、特許調査を行いたい動機はいくつも考えられます。
またパテントマップの種類も豊富です。同じデータを使用する場合でも縦軸と横軸の取り方を変えることで表現の仕方は大きく異なります。したがってパテントマップを使用する際は、目的に適したマップを選ぶことが重要です。
以下では主要なパテントマップを目的ごとに紹介します。
業界全体の傾向が知りたい
まずは広く業界全体の分析がしたい場合に役立つマップを紹介します。
特許出願件数や登録件数の推移を可視化することで、業界全体のトレンドを把握することが可能です。
■ ランキングマップ
ランキングマップは出願人・発明者・国・技術分野などの項目を縦軸にとり、出願件数に基づいてランキングで表示します。
特定の業界における主要な企業 (リーディングカンパニー)を把握したい場合などに便利です。
例えばこのランキングマップを見ると、A社とB社が一段リードした件数の特許を出願しており、この分野で強い影響力を持っていることが読み取れます。
特許情報分析による中小企業などの支援事例(独立行政法人工業所有権情報・研修館)より引用
■ 時系列マップ
時系列マップは出願件数の推移に基づいて、業界の流行や変遷を表示します。特定業界の将来の動向を予測したり、技術のコモデティ化の度合い(参入の難易度)等を把握したい時などに利用可能です。
以下の例では3つの軸にそれぞれ(時間、社名、出願件数)をとることで会社ごとの出願件数の推移が視覚的にわかりやすく表現できています。
特許情報分析による中小企業などの支援事例(独立行政法人工業所有権情報・研修館)より引用
この時系列マップから読み取れることとして、2009〜2012年にかけて主要各社が一斉に出願件数を増加させ、技術開発競争が活発化していた様子が伺えます。
またその後は全体的に出願件数が減少していることから市場が成熟段階に入っており、現在でも比較的出願件数の多いA社が業界の方向性を握っていると推定できます。
したがってこの分野へ単独で新規参入することはあまり得策ではなく、参入方針の変更やA社との提携を検討するべきだと考えられます。
■ ニューエントリ・リタイアリマップ
こちらのマップは出願情報に基づいて、新規参入時期や継続期間等の参画実態を表示します。特定の業界における主要企業の参画実態を把握したい時などに便利です。
以下のニューエントリ・リタイアリマップからは、1997〜1999年にかけて複数の企業が相次いで参入し、一時的に競争が活発化したことが分かります。しかし2000年以降は継続的な出願が見られない企業が多いです。
特許情報分析による中小企業などの支援事例(独立行政法人工業所有権情報・研修館)より引用
したがってこの分野に取り組む場合は、かつて短期で撤退した企業の領域を再評価したうえで、存続している企業が手を出していない技術テーマを重点的に掘り下げるべきと判断できます。
競合と差別化したい
次に具体的な技術分野について競合を比較したい場合に活用するマップを紹介します。
■ 材料用途マップ
材料用途マップとは縦軸に企業、横軸に競合他社毎の開発アプローチ(材料・用途)等を表示し、 交差する点にその件数を表示したものです。
各企業の件数を表示することにより、未開発技術の発見や研究開発テーマの選定に役立ち他社との差別化を図ることができます。
以下の材料用途マップからは、A社・B社・C社が「金属」「複合材」に多くの特許を集中させており、特にA社は金属(41件)と複合材(25件)の両領域で突出していることが分かります。
特許情報分析による中小企業などの支援事例(独立行政法人工業所有権情報・研修館)より引用
一方で「木質」分野は全体的に出願件数が少なく、主要各社も十分には手を付けていません。
したがって、自社の戦略としては、金属や複合材で大手と正面から競合するよりも、比較的空白の多い木質の領域に注力する方が差別化を図れると判断できます。
■ レーダーマップ
レーダーマップは各企業の出願動向をグラフ化し、技術分野の傾向を表示したものです。
朱色、青色の線がそれぞれ特定の技術分野を表します。注目する企業の技術バランスから各企業の技術的に優位性がある分野を把握することができ、競合との差別化や提携先の検討に役立ちます。
以下のレーダーマップにおいて注目すべきなのはA社で、青色分野と赤色分野の双方において他社を大きく上回る出願を行っており、突出した強みを持っていることが分かります。
特許情報分析による中小企業などの支援事例(独立行政法人工業所有権情報・研修館)より引用
したがって、この分野ではA社が技術的に優位な立場にあり、他社が差別化や提携を検討する際の重要な指標となります。
知財戦略策定の参考にしたい
次に自社の知財戦略を考える際に使いやすいマップを紹介します。
■ 課題・解決マップ
課題・解決マップは縦軸・横軸にそれぞれ課題・解決手段の各項目を表示し、交差する点に特許文書の件数を表示したものです。
交差する点の件数から、開発があまり進んでいない技術領域を発見したり、研究開発に行き詰まった際、別のアプローチを探したりといった使い方ができます。
例えば環境負荷軽減という課題で行き詰まっているときは、他社の形状改良・配置改良の特許情報から改良のヒントを得るとよいことがこのグラフからわかります。
特許情報分析による中小企業などの支援事例(独立行政法人工業所有権情報・研修館)より引用
■ サイテーションマップ
サイテーションマップは他社の出願について、その引用・ 被引用件数を表示したものです。
引用回数や出願年の情報から、重要な特許(基本特許)を発見したり、他社の基本特許の保有状況を調べたりすることができます。
以下は縦軸に特許文献が引用された回数、横軸に出願年をとったものです。各企業について何年に出願された特許のうち何回引用されたものが何個存在するかといったことを図示します。被引用回数が多く、出願年が古い特許は、重要な特許の可能性が高いです。
特許情報分析による中小企業などの支援事例(独立行政法人工業所有権情報・研修館)より引用
赤い点線で囲まれた部分の特許は被引用回数が多く出願年が古いため、重要な特許の可能性が高いです。
■ 出願人相関マップ
最後に紹介するのは出願人相関マップです。
こちらは他のマップと違い、特定の業界での共同出願の件数をマトリクス状に表示します。特定の業界における企業間の連携度合いを把握することができ、提携先の選定等に利用可能です。
例えば以下の出願人相関マップでは、D社は現在提携している企業がないため、こちらの提携先候補として適当であるとわかります。
特許情報分析による中小企業などの支援事例(独立行政法人工業所有権情報・研修館)より引用
パテントマップの作り方
ここまでいくつかのパテントマップを紹介しましたが、実際に作る際にはどのような手順を踏めば良いのでしょうか。以下では基本的な手順を説明します。
目的の明確化
まずはパテントマップを作成する目的を明確にします。例えば、自社の知財状況の確認や他社の技術動向の把握、特許取得に向けた類似特許の調査などが考えられるでしょう。
上述のようにパテントマップの種類とその活用方法は多岐に渡るため、解決したい課題、調査する範囲をあらかじめ設定することが効果的な活用に繋がります。
また、報告資料としてパテントマップを作成する場合は、報告相手がどんな立場の人であるのか(経営者やエンジニア、外部など)、どの情報が最も重要かを明確にしておくと良いでしょう。
必要なデータの収集
特許情報の基礎データは、特許庁が運営している「J-PlatPat」から無料で取得することができます。
J-PlatPatとは、特許庁が提供する無料の特許・実用新案・意匠・商標の検索サービスで、出願情報や公開公報をオンラインで閲覧できます。
またAPIを活用すると、特許データベースと自社のシステムを連携させ、自動的にデータを収集することもできます。
プログラムから直接特許情報にアクセスし、必要なデータを機械的に効率よく取得することが可能です。
API利用には利用申し込みが必要ですので、詳しくは特許庁の「特許情報取得 API 利用の手引き」をご覧ください。
マップ作成
データを取得できたらマップの作成に移ります。J-PlatPatから取得したCSV形式のデータはExcelで開くことができます。
図示する際に重要となることが分析軸の設定です。いたずらに軸を設定しグラフ化しただけでは、図で示したかったことが伝わりません。
分析軸の取り方はいくつも考えられるため、目的に適した図になるようにじっくり検討する必要があります。
例えば、出願件数を「年度×企業」で整理すれば業界全体の動向が分かり、「企業×材料」で整理すれば各社の研究テーマの違いが見えてきます。
また、2次元では情報が十分に表現できない場合は、時系列マップで紹介したように3次元の図を用いることで、変化の推移をより直感的に把握することも可能です。
パテントマップ作成時の注意点
パテントマップ作成時には、データ収集とマップ作成の段階において特に注意すべき点があります。
データ収集時の注意点
データ収集の際に最も注意すべきことは母集団の範囲とバイアスの排除です。
調査範囲が広すぎると、最も注目すべき情報が埋もれてしまいます。一方で、範囲を狭めすぎると、主観的な判断で重要な情報を見落とす可能性に気をつけなければいけません。
そのため、最初の検索では広めに検索範囲を設定し、結果が多すぎる場合にキーワードや出願日などの条件を追加して慎重に絞り込みましょう。
またキーワードは一つだけに依存せず、異なる表現を複数用意することが大切です。
表現の違いによって重要な文書を見逃すリスクがあるため、事前に複数のキーワードを用意することが求められます。
検索式にミスがあると調査全体の質が低下するため、再確認は必須です。可能であれば、別の担当者が検索式やキーワードを確認するダブルチェックを取り入れると良いでしょう。
マップ作成時の注意点
実際にマップを作成する際には、誰が見てもわかりやすい図になっているかが重要です。
図の作成者は該当する特許データについての理解が深いため、多少ラベルや説明が省かれていても図を読み解くことができますが、事前知識が少ない人でも理解しやすい図になっているとは限りません。
またパテントマップを複数人で分担して作成する際にはそれぞれのマップで色分けや字体等の規則を統一することを意識してください。
個人個人が自由に配色を決めてしまうと、あるマップではA社が黄色、あるマップではB社が黄色といった表現のばらつきが生じ、理解に時間がかかったり、誤認してしたりしてしまう可能性が高くなります。
パテントマップ活用の事例
以下では実際にパテントマップを活用して成功した企業の事例を紹介します。
株式会社Surfs Med
株式会社Surfs Medは、変形性膝関節症に対する新しいインプラント開発にあたり、特許情報分析を活用しています。
特にFTO(Freedom to Operate)に重点を置き、時系列マップを通じて他社の出願状況を把握した結果、自社の技術が他社の知財を侵害しないことを早期に確認できたとされています。
パテントマップの活用により事業化に伴うリスクを低減しつつ、開発投資を進める判断につながった事例です。
引用:特許情報分析による中小企業などの支援事例(独立行政法人工業所有権情報・研修館)
株式会社パームホルツ
株式会社パームホルツは、オイルパーム樹幹を利用した新建材技術を持ち、インドネシアやマレーシア進出の際に特許情報分析を行っています。
主要出願人の年度別出願件数をマップ化することで、競合の関心が高い分野と手薄な分野を客観的に把握し、自社技術の強みを生かせる領域を明確にできた事例です。
結果として、現地パートナーとの提携や事業戦略の具体化に結びついたといえるでしょう。
引用:特許情報分析による中小企業などの支援事例(独立行政法人工業所有権情報・研修館)
株式会社バイオメディカルサイエンス
株式会社バイオメディカルサイエンスでも、生体試料を高速かつ均質に破砕可能な装置開発の過程で、課題・解決マップを活用した事例が紹介されています。
マップを通じて、競合企業が十分に取り組んでいない課題領域を特定し、自社の差別化要素として営業活動に活用したとされています。さらに、潜在的なニーズに基づいて事業戦略を策定する判断につながった事例です。
引用:特許情報分析による中小企業などの支援事例(独立行政法人工業所有権情報・研修館)
エムニの事例
ここまで様々なパテントマップとその作成方法を簡単に紹介しましたが、特許文書は膨大なため、パテントマップの作成には多くの費用と時間がかかります。特に大規模な事業では、その傾向が顕著です。
そこでエムニでは得意とする生成AIを活用して、パテントマップを自動生成するサービスを開発しました。膨大な特許文書を一つ一つ確認して分類し、分布図を作成するのは骨が折れる作業ですが、AIを活用すれば短時間で作成することができます。
エムニが作成したのは記事前半で紹介した課題・解決マップです。パテントマップを見ることで競合の多い領域を避けたり、課題に対してソリューションが揃っていない領域を発見したりすることが容易にできます。またご要望に応じて、横軸縦軸をカスタマイズして別のパテントマップを作成することも可能です。
さらに、エムニではパテントマップ作成に留まらず、より包括的な特許業務を支援する「AI特許ロケット」も提供しています。
「AI特許ロケット」は、AIによる高精度な先行技術調査、発明の要点を基にした請求項や明細書の草案自動生成、さらには特許の有効性や侵害リスクの分析が可能です。
調査から出願書類の作成、知財戦略の分析まで、一連のプロセスをAIが強力にサポートします。
パテントマップの自動化や「AI特許ロケット」の活用など、特許調査・業務全般にAIを活用したい方はお気軽にご相談ください。ご相談いただく際は、以下のフォームからお申し込みいただけます。
▼特許業務への生成AI活用について詳しく知りたい方はこちら
AIで特許調査のコストを1000分の1に|活用戦略を詳しく解説
多種多様なパテントマップを使いこなして知財業務を効率化
パテントマップは、膨大な特許データを整理し、技術動向や市場状況を可視化する強力なツールです。マップの活用によって競合他社の戦略を分析したり、自社の研究開発の方向性を見極めたりすることが可能となります。
また、新たなビジネスチャンスの発見やリスクの回避といった、戦略的な意思決定を支える役割も果たします。
現代の激しい競争環境において、パテントマップを効果的に活用することは、企業の競争力を高める鍵です。ぜひ積極的に活用して未来の成長を見据えたデータドリブンな戦略を実現しましょう。
エムニへの無料相談のご案内
エムニでは、製造業をはじめとする多様な業種に向けてAI導入の支援を行っており、企業様のニーズに合わせて無料相談を実施しています。
これまでに、住友電気工業株式会社、DENSO、東京ガス、太陽誘電、RESONAC、dynabook、エステー株式会社、大東建託株式会社など、さまざまな企業との取引実績があります。
AI導入の概要から具体的な導入事例、取引先の事例まで、疑問や不安をお持ちの方はぜひお気軽にご相談ください。
引用元:株式会社エムニ