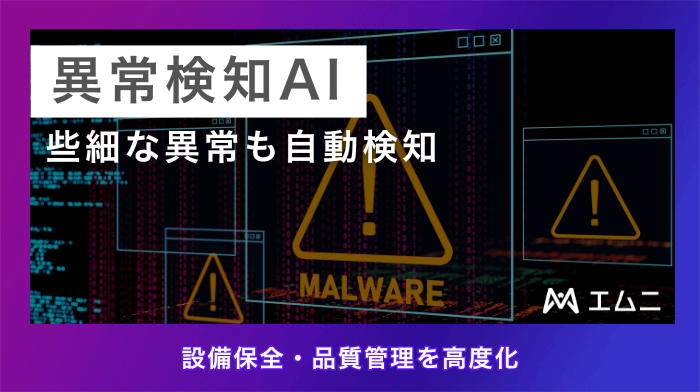生成AI×IPランドスケープで研究開発と事業戦略を接続する
2025-10-30FTA(故障の木解析)でリスク管理強化と信頼性向上を実現

IoTやクラウドの普及により、製造システムは高度に連携し、ひとつの不具合が全体へ波及するリスクが高まっています。こうした中で、原因を体系的に整理する「FTA」は、経営判断を支える重要な手法です。
また生成AIを組み合わせることで、従来のFTAに伴う専門知識への依存や更新作業の負担を軽減し、データ収集や因果関係の特定を自動化できます。AIを活用したFTAは、リスクの全体像を迅速に把握し、対策の優先順位を明確にする有効な手段です。
本記事では、AIを活用したFTAの考え方と、その導入によって生まれる新しいリスクマネジメントの形を解説します。
DX時代に「FTA」が重要な理由
デジタル技術の進化により、製造業のシステムは大きく変化し、利便性と同時に新たなリスクも生まれています。
この複雑なリスク構造を解き明かすうえで、FTAの重要性は一段と高まっているのです。
▼製造業におけるDXの課題についてはこちら
製造業におけるDXの課題|技術・組織・人材・コストの観点から解説
相互依存システムがもたらす連鎖的リスク
現代の製造業は、IoTセンサーや制御機器、クラウド基盤、外部サプライヤが密接に連動することで効率が大きく向上しています。
一方で、依存関係の複雑化が脆弱性の拡大を招いているのも事実です。
実例として、わずか一台のサーバー不具合や通信遅延が、数百の制御システムや物流の同期を崩す事例も確認されています。
実際に、トヨタでは部品発注システムのディスク容量不足を契機に国内全工場の稼働が停止しました。原因はサイバー攻撃ではなく、データ処理設計上の問題によりバックアップが機能しなかったことが原因です。
この事例は、わずかな設計上の欠陥が企業全体の稼働停止に直結し得る現実を示しています。 こうしたダウンタイムは、機会損失や修理費用といった直接的損害に加え、顧客・取引先の信頼低下やブランド価値の毀損など、長期的な経営リスクも伴います。
このような設計起因の停止は、 数時間でも受注遅延や供給網全体の混乱を招き、国際的なCSR基準に基づく企業評価にも影響が及ぶかもしれません。したがって、経営層はこれらのリスクを一時的な障害として片づけず、事業全体に関わる経営課題として捉える必要があります。
対応にあたっては、システム同士のつながりを見える化し、重要な機能を複数の経路で確保することで、万が一システムが停止しても被害を最小限に抑えられる仕組みを整えます。
また、障害が発生した際には、迅速に状況を判断し対応できるよう、体制や手順を明確にしておくことも重要でしょう。
▼製造業のDXについてはこちら
製造業のDXとは?重要性や成功までのロードマップを徹底解説
▼IoTとAIの融合がもたらすメリットについてはこちら
IoTとAI|組み合わせるメリットから活用事例まで
参考文献:
- Guide to Operational Technology (OT) Security
- Concerning the production order system malfunction | Corporate | Global Newsroom
- NIS2 Technical Implementation Guidance | ENISA
伝統的FTAを「データ駆動型リスク管理」へ再定義する
DXの進展により、AIはリスク管理の中核を担う存在となりました。
しかし、その判断過程はしばしば不透明で、「なぜその結果になったのか」が分かりにくい、いわゆるブラックボックス化が問題視されています。
この課題に対し、FTAを活用すれば、AIの出力を単なる相関ではなく因果として捉え、説明可能性と信頼性を高められます。
FTAは「結果から原因を逆にたどる」構造を持つ手法です。たとえば「機械が止まった → 故障 → 温度上昇 → 冷却水不足」といった因果連鎖を階層的に整理できます。
この枠組みをAIの異常検出と組み合わせれば、AIが示した兆候が真の原因なのか、それとも偶然の相関なのかを検証できるでしょう。
AIは膨大なデータからパターンを見つけることに優れていますが、そのパターンを引き起こした要因の説明は得意ではありません。
FTAはこの弱点を補い、AIの判断を因果構造の中に位置づけることで、結果の妥当性を点検できます。これにより、誤った判断や不要な対策を避ける助けにもなります。
また、FTAを用いれば、AIの判断を関係者に説明する作業も容易です。AIが「この部品に問題があります」と示した場合でも、「なぜ」「どの経路でリスクにつながったのか」をツリー構造で可視化できるため、経営層・現場・監査担当といった立場の異なる関係者の理解と納得を得やすくなります。
要するに、FTAのような原因追究の枠組みをデータ駆動型リスク管理に組み込むことは、AIの出力を推測で終わらせず、「なぜ起きたのか」「どう防ぐのか」まで踏み込むことにほかなりません。
▼AIによるデータ分析についてはこちら
「AI x データ分析」で経営戦略の精度を向上・経験と勘からの脱却
参考文献:
- The Role of Causality in Explainable Artificial Intelligence | ProCAncer-I
- Implications of causality in artificial intelligence
- Beyond Correlations: The Necessity and the Challenges of Causal AI
- IEC 61025:2006
- Beyond Correlations: The Necessity and the Challenges of Causal AI
経営層が把握すべきAI投資におけるFTAの戦略的位置付け
FTAは、DX時代のAI投資において、ROIの確実性とリスク削減効果を同時に担保するための有効な枠組みです。
その理由として、AIやIoTによってシステムが複雑化するなか、FTAはリスクの因果構造を明確化し、経営層がどこに投資と対策を集中すべきかを論理的に判断できる基盤を提供するからです。
近年は、FTAをAI、とくに機械学習と統合することで、リスク評価の精度と説明可能性が大きく向上しています。FTAの構造を活用したAIモデルは、基本的な故障要因を学習し、それらの組み合わせからシステム全体の障害確率を算出します。
実験では、従来の方法に比べて精度が99.1%から99.4%、再現率が98.6%から99.1%へと改善し、主要指標すべてで優位性を示しました。これにより誤検出の削減や予兆保全の精度向上が確認され、設備停止リスクを低減する実証的な根拠が得られています。
さらに、ネットワークとハードドライブの故障を対象とした25,942件のデータ分析では、FTA構造を取り入れたAIが誤警報率を下げ、高い診断精度を示しました。これは、AI導入によるリスク低減効果を経営層が定量的に把握し、確実性の高い投資判断を行う上での有効な証左となります。
FTAは、AIが予測したシステム障害に至る因果関係を理解可能な形に変換し、経営層がリスクを制御しながらROIを最大化するための実践的なツールです。
参考文献:
- SAE International | Advancing mobility knowledge and solutions
- Machine Learning Models with Fault Tree Analysis for Explainable Failure Detection in Cloud Computing
FTAがもたらす戦略的メリット
FTAは、単にシステムの安全性を高めるための手法ではありません。原因を可視化し、リスク対策の優先順位を明確にすることで、経営判断やコスト最適化にも貢献します。さらに、部門間の連携を促し、設計段階からの品質向上にもつながります。
ここでは、FTAがもたらす4つの主なメリットについてより詳しく見ていきましょう。
システム障害原因の体系的かつ網羅的な特定と可視化
FTAの最大の強みは、システムの故障原因を整理し、わかりやすく可視化できる点です。
FTAでは、問題の発端となったイベントから順に原因をたどり、どこにリスクが潜むかを論理的に明らかにします。これにより、勘や経験に依存せず、根拠に基づいた原因特定が行えます。
さらに、FTAを用いてリスクの優先順位を数値化することで、どの部分を優先的に対策すべきかを明確に判断できます。
たとえば、中国の大学研究グループが実施した電力バッテリー管理システムの設計検証事例では、通信ラインやセンサーの故障リスクが特に高いことが判明し、設計に通信経路の二重化とセンサーの冗長化が反映されました。
その結果、トップイベントの故障確率は0.11981となり、従来の分析結果より優れた評価を得ています。あわせて、バッテリー管理システムの設計が安全要件を満たしていることも確認されました。
また近年は、FTAを設計段階から活用できるよう、設計データと連携する仕組みを導入しています。これにより、後追いで問題を修正する手間を抑えつつ、効率的に信頼性を高められます。
加えて、時間経過や複数要因の連鎖といった現実的な条件も分析に取り入れられるようになり、従来より高精度な評価がFTAを通じて可能になりました。
参考文献:
- Dynamic Fault Tree Generation and Quantitative Analysis
- Dynamic and dependent tree theory (D2T2): A framework for the analysis of fault trees
- What is Fault Tree Analysis?
リスク対策の優先順位決定による投資対効果の最大化
リスク対策の成果を高めるには、勘や経験に頼らずデータと論理に基づいて判断することが不可欠であり、その要となるのがFTAです。
FTAでは、望ましくない故障から原因をさかのぼり、根本原因を一つひとつ洗い出します。故障に至る筋道を可視化でき、どの原因を断てば連鎖を止められるかを根拠をもって示せます。
その結果、対策の優先順位を合理的に定められ、限られた資源を効果が最も大きい箇所へ集中できるのです。
このFTAをさらに発展させた手法として、モジュラー動的故障の木解析やモンテカルロシミュレーションが挙げられます。これらを用いれば、時間経過による故障やメンテナンス効果といった現実的な要素も数値的に評価可能です。
優先順位づけが投資対効果を高めることを示す事例として、米国メリーランド大学の研究グループによる無人水上艇を対象とした分析が挙げられます。
具体的にこの研究では、システム設計上の「重要部品」を一律に監視するよりも、故障頻度が高く修理コストや停止損失の大きい部品に絞って対策するほうが、高い投資効果を生むと判明しました。
つまり、設計上の重要度ではなく、実際のリスクに基づいて優先順位をつけることが、ROI最大化の鍵となることが示されたのです。
結果として、約64万ドル(約9,700万円)の投資で約315万ドル(約4億7,600万円)のコスト削減を実現し、ROIは9.72倍となりました。
この結果は、リスク対策を理論上の重要度ではなく、実際の故障データと経済的影響に基づいて決定する重要性を示しています。
そしてFTAを活用すれば、どこに投資すれば最も効果的にリスクを減らせるかを論理的に示せるのです。
参考文献:
設計・製造・運用の垣根を越えた部門間コミュニケーションの促進
設計・製造・運用の連携を強化するには、立場の違いを超え、共通の根拠に基づいて判断できる仕組みが不可欠です。
FTAは、その共通基盤となる考え方として、部門間の合意形成を支援します。
具体的な合意形成の手順としては、「何を防ぐべきか」を定量的に定義し、全員で同じ目標を共有できる状態をつくることが肝要です。
たとえば、防ぎたい結果を「ポンプが壊れる」ではなく「冷却水の流量が30秒以上100L/分を下回る」といった測定可能な条件で定義します。これにより、経営層から現場までが同じ視点で課題を共有できるでしょう。
FTAは、先述した通り、原因を論理的に分解し、最小単位で整理する手法です。どの要因がどの組み合わせで問題を起こすかが明確になり、各部門は自工程の影響を客観的に把握できます。会議ではFTA図を用いることで、結論と根拠の対応が明確になり、合意形成が早まります。
さらに、保全記録や運転ログで故障確率を更新すれば、分析の精度が上がり、実態に即した設計・対策が可能です。システム連携により、結果を点検や修理計画へ自動反映すれば、現場対応の最適化も進みます。
こうしてFTAを中心に据えることで、設計・製造・運用がデータでつながり、切れ目のない改善サイクルが生まれます。
参考文献:
- Fault Tree Analysis (FTA): The Ultimate Guide for Engineers – InstruNexus
- Fault Tree Analysis: A Strategic Guide to System Failure Prevention
- What is Fault Tree Analysis (FTA)
予防保全と初期設計段階でのコスト削減効果
FTAは、システムに潜在する故障要因を体系的に洗い出し、問題が発生する前に対策を講じるための有効な手法です。
特に、製品やシステムの初期設計段階で導入することが重要です。なぜなら、この段階でリスクを把握しておくことで、後の工程における手戻りや不具合の発生を防ぎ、結果的に全体コストを大きく削減できるからです。
たとえば、開発後にリコールや修理対応が必要になる場合と比べると、設計段階で問題を修正する方が、対応の手間や費用を大幅に抑えることができます。
またFTAを活用すれば、システム構成上の脆弱性を定量的に把握でき、設計段階でのリスク除去が可能です。
こうした早期対応は不具合発生率の低減だけではなく、保証修理や製造段階での不良対応コストの削減にもつながります。
さらに、試作段階で得られるデータをもとに設計を見直す取り組みも効果的です。
確かに一時的には開発コストが増える場合があります。ですが、その後の欠陥対応やアフターサービス費用を抑制できるため、長期的にはコスト削減と品質向上の両立を実現できるでしょう。
加えて、FTAを取り入れた設計最適化は、技術的な改善にとどまらず、企業の財務的な安定性にも寄与します。
たとえば、単位生産コストを10%削減した場合、正味現在価値(NPV)が約4〜5%上昇するという分析結果があります。
つまり、初期段階で品質と効率を高めることは、短期的なコスト対策ではなく、長期的な収益性を高める投資だといえます。
このように、FTAを設計段階から活用することで、技術的な信頼性、コスト効率、そして事業の安定性を一体的に高めることが可能です。
総じて、FTAの初期導入は、「予防保全の高度化」と「コスト最適化」を同時に実現する、戦略的かつ持続的な手法といえるでしょう。
参考文献:
- Fault Tree Analysis for Robust Design
- Reducing the Total Product Cost at the Product Design Stage
- What is Fault Tree Analysis? Benefits and Use Cases
伝統的FTAの注意点
FTAが強力な手法である一方で、その実行にはいくつかの伝統的な制約が伴いました。これらの課題を認識することが、生成AIによる克服戦略を理解するための前提となります。
ここからは伝統的なFTAの2つの注意点について見ていきます。
高い専門知識と属人性の問題
FTAは、品質や速度が担当者の熟練度に大きく左右されるのが実情です。
担当者が異動や退職するとノウハウが途切れ、継続性や一貫性の確保が一気に難しくなります。そもそもFTAは長年にわたって「専門家の手作業」に依存してきた経緯があり、システム構造と故障要因の関係を正確に整理するには高度な知識が欠かせません。
そのため最終判断は個人に委ねられやすく、属人化が避けにくい状況にあります。また、専門家の数が限られていることも、分析の頻度や質を押し下げる一因となっています。
これらの課題を踏まえると、効率化と標準化を実現するための核心は明確です。
その核心とは、専門家の知見を形式知としてモデル化し、それを共有・自動化できる仕組みを整えることにあります。
組織として知見を体系的に蓄積し、誰が担当しても同じ水準の分析を再現できる体制へと移行することで、属人性の壁を越え、継続性と一貫性を安定的に確保できるようになるでしょう。
参考文献:A Hybrid Real-Time Framework for Efficient Fussell-Vesely Importance Evaluation
大規模システムにおけるモデル構築の時間的・コスト的制約
大規模なシステムでは、故障の因果関係を分析するFTAモデルの構築と維持に、膨大な時間とコストがかかります。
要素が増えるほど組み合わせが爆発的に増加し、数十万もの状態を扱うことも珍しくありません。さらに、設計変更のたびにモデルの検証や更新が必要となるため、開発から運用に至るまでの過程で負担が累積的に大きくなっていきます。
特に課題となるのは、モデル構築後の分析処理です。故障の最小原因の特定や要素の重要度の算出には高い計算負荷がかかり、大規模システムでは手作業での対応が非効率になります。
機械学習を使えば数ミリ秒で終わる処理でも、人の手では数分かかることがあり、従来手法の限界が明確に表れています。
このように人の手に頼る運用では、モデルの内容がすぐに古くなり、現実の変化に追いつくのは困難です。その結果、分析の信頼性が低下し、誤った判断や不要な投資を招くおそれがあります。
また、モデルが巨大化するほど特定の担当者に依存しやすくなり、引き継ぎや管理が難しくなることで、知識共有や意思決定の迅速化を妨げる要因にもなります。
つまり、大規模システムでは、モデルの複雑さそのものが時間的・経済的な制約を生み出し、属人化や情報の陳腐化を招く悪循環が起こっているのです。
この悪循環を断ち切るためには、モデルの構築や更新を自動化し、変化に強く柔軟な分析体制を整えていかなくてはなりません。
参考文献:
- Modular Criticality Analysis for Dynamic Fault Trees
- Dynamic Fault Tree Generation and Quantitative Analysis of System Reliability
- Reliability analysis of dynamic fault trees with Priority-AND gates
- A Hybrid Real-Time Framework for Efficient Fussell-Vesely Importance Evaluation
FTAの弱点を生成AIで克服
従来のFTAは、専門知識への依存や作業負担の大きさから、実施頻度や適用範囲に制約がありました。しかし、生成AIの導入によって、こうした時間的・人的制約を大幅に緩和し、FTAの戦略的価値を飛躍的に高めることが可能となっています。
以下では、生成AIがどのようにしてこれらの課題を克服するのかを具体的に見ていきます。
▼製造業への生成AIの影響についてはこちら
生成AIで変革する製造業の未来|メリットや事例・導入ポイント
▼生成AIの基本的なメリット・デメリットを知りたい方はこちら
生成AIのメリット・デメリットを徹底解説!
モデル構築の短縮化
生成AIは、これまで時間のかかっていた故障解析をスピーディに行えるようにし、専門家が確実な判断を下すための支援ツールとして機能します。
具体的にAIは、作業指示書や保守ログ、フィールドレポートなどのデータを解析し、テキストや時系列情報の中から故障原因と結果の関連性を迅速に抽出します。
これにより、専門家が行っていた論理構造の推定や検証を短時間でできるようになり、分析全体のスピードと精度が大幅に向上しました。
またAIは多様なデータソースを統合し、人間の記憶や経験だけでは捉えきれない相関関係を明らかにします。
その結果、現場でのトラブル要因をより早く把握、再発防止策の立案に必要なデータ駆動型の洞察を迅速に提供することで、人間の意思決定を強力に支援することが可能です。
これにより、従来数週間かかっていた分析が、数日以内で完了するケースも見られています。
さらに、生成AIを用いれば、構築された故障ツリーの整合性検証を支援し、論理の抜け漏れを補う新たなサブ原因を提案することもできるでしょう。
この支援により、専門家は分析の主導権を維持しながらも、AIの支援によって網羅性と一貫性を高め、より戦略的な判断や改善策の検討に注力できるようになります。
このように生成AIは、故障解析を自動化するのではなく、迅速で的確な判断を可能にする補完的ツールとして機能していくのです。
参考文献:
- AI in Root Cause Analysis: How Emerging Tools Are Changing Reliability
- Beyond the breakdown: How EAM software supercharges fault tree analysis for smarter maintenance
- Facilitating Fault Tree Analysis with Generative AI | SpringerLink
原因特定から再発防止までの高度化
故障や異常の原因を迅速かつ正確に特定するうえで、生成AIは有効なツールです。
生成AIは、構築済みのFTAモデルと膨大なセンサーデータ、稼働ログを照合し、論理構造の欠落や矛盾を自動的に検知します。これにより、どの要素や事象が根本原因となっているのかを高精度に突き止めることが可能になります。
従来は、専門家の経験や直感に基づく分析が中心であり、判断にばらつきが生じやすいという課題がありました。AIの導入により、原因分析はデータ駆動型へと移行し、判断の一貫性と客観性が大幅に向上しています。
その結果、組織全体でのリスク評価や対策立案が標準化され、属人的な分析に依存しない体制が実現できるようになっています。
さらに、生成AIはFTAとベイジアンネットワークを統合することで、故障確率を継続的に更新できる仕組みを構築します。新しい運転データや故障実績が追加されるたびに、AIが確率を再計算し、システム全体のリスク構造を再評価します。
これにより、原因特定の精度が時間とともに向上し、安全性評価も常に最新の状態を反映できるようになります。
実際に、700件に上る炭鉱での事故調査報告を対象に、生成AIが14の直接要因・38の複合要因・75の具体要因を抽出し、それらを基にベイジアンネットワークで確率モデルを構築・可視化した研究があります。このように、生成AIが要因抽出を担い、確率推定と「見える化」を一貫して実現しているのです。
こうした分析を踏まえ、生成AIは単なる原因特定にとどまらず、改善策や予防策の立案にも貢献します。
たとえば、高リスク要因とされた知覚システムに対しては、検出精度を高めるための訓練データ拡充や、安全モードへの自動移行を行う適応型AIの導入が有効です。
また、FTAで特定された単一故障点には、センサーや制御系の冗長化、リアルタイム診断、フェイルセーフ機構の実装などが推奨されます。
最終的に、生成AIは「故障や異常の原因特定」から「再発防止・設計改善」までを一貫して支援する技術基盤として機能します。これにより、安全性評価はより透明で再現性の高いものとなり、技術者は定型的な分析作業から解放され、創造的で高付加価値な業務に専念できるようになります。
▼異常検知AIについてはこちら
異常検知AIとは|メリット・活用事例・技術情報を徹底解説
参考文献:
- FTA generation using GenAI with an Autonomy sensor Usecase
- Coal Mine Accident Risk Analysis with Large Language
製造業DXにおけるFTAと生成AIの具体的な連携戦略
FTAと生成AIの連携は、リスク管理を知的かつ自動化された運用へと昇華させます。
ここでは、その具体例として、故障予測の高度化、仮想検証による信頼性向上、設計・プロセスの自動改善という三つの方向性について述べます。
▼製造業でのAI活用についてはこちら
製造業でのAI活用|活用事例と導入法を徹底解説
予兆保全システム構築のための故障原因予測モデルへの応用
AIモデルはデータを学習することで、単なる異常検知ではなく、故障発生のプロセスそのものを予測できるようになります。
そのために、AIが最初に行うのはFTAで明らかになった「どのような原因がどの故障につながるのか」という関係性を把握することです。
その上で、センサー群から取得した時系列データを解析し、異常値の発生順序や関連性をもとに、故障が進行する可能性の高い経路を推定します。
実証では、FTAの構造を統合したAIモデルが12種類の故障状態を高い精度で識別し、早期に異常を検出できることが示されています。これは、FTAがAIに「どこを見るべきか」という明確な判断軸を与えた結果です。
FTAを中核に据えることで、AIの判断はブラックボックスではなく、技術者が理解・検証可能な形で可視化されます。またAIが検知した予兆は、FTAで抽出された情報をもとに、リスク要因・発生経路・推奨対応策を整理したテーブル形式で提示できます。
これにより、関係者はリスクの位置づけと影響範囲を明確に把握し、迅速な対応判断が可能です。
結論として、FTAの統合により、予兆保全は因果に基づく高精度な故障予測へと進化します。
▼予知保全AIについてはこちら
予知保全AI|設備保全を進化させる第三の選択肢を紹介!
参考文献:
- Towards an extension of Fault Trees in the Predictive Maintenance Scenario
- AI-Driven Predictive Maintenance in Modern Maritime Transport
シミュレーション環境における仮想故障の網羅的検証(デジタルツイン連携)
デジタルツイン環境を用いることで、現実では再現困難な高リスク故障を仮想的に再現し、その発生確率と影響度を定量的に評価できるようになります。
これにより、従来は一時的な分析に留まっていた信頼性評価が、リアルタイムデータと連携する継続的な検証プロセスへと変化します。仮想空間上で多様なシナリオを再現し、異常な挙動を事前に把握することで、システム全体の安全性と信頼性を設計段階から確保できるのです。
この仕組みの強みは、シミュレーション結果を検証・妥当性確認のプロセスに統合する点です。デジタルツインは物理的なシステムと連動し、リアルタイムの挙動データを反映しながら、モデルの妥当性を逐次評価します。
これにより、設計段階で潜在的なリスクを早期に特定し、開発コストを抑制しながら品質を高めることが可能になります。
さらに、設計者は仮想環境内で複数の構成案や制御ロジックを比較すれば、それぞれの設計がシステム全体の堅牢性に与える影響なども可視化できるでしょう。
このような継続的な評価により、リスク排除を前提とした堅牢なシステム設計が実現されます。
加えて、新規設備導入やプロセス変更においても、仮想的に稼働シナリオをシミュレートし、効率性や保守性を事前に評価できます。そのため、DX投資の意思決定をより合理的かつ実証的に行うことができるのです。
参考文献:
- Integrated Fault Tree and Case Analysis for Equipment Conventional Fault IETM Diagnosis
- Manufacturing Digital Twin Standards
FTA結果をフィードバックした設計標準化とプロセスの自動改善
FTAを用いて結果を図で可視化することで、設計におけるリスクや運用上の問題点を具体的に把握でき、再発を防ぐための改善方針を明確にすることができます。
また可視化して問題点を把握するだけにとどまらず、分析結果を保全管理システムと連携させることで、保全作業を自動的に計画・実行できるようにもなります。
たとえば、FTAによって「特定の部品が2,000時間稼働後に故障しやすくなる」と判明した場合、保全管理システムが1,800時間時点で点検指示を自動で出すように設定することが可能です。これにより、担当者が都度判断することなく、リスクを先回りして対応できます。
さらに、運用中に蓄積されたデータ(故障履歴、修理時間、コストなど)を再びFTAに反映させることで、原因分析の精度が高まります。こうした「分析→自動化→改善」の循環が、効率的で信頼性の高い運用体制を生み出すのです。
加えて、AIやデータ解析技術を活用することで、FTAの結果や保全データをもとに故障確率を継続的に算出し、メンテナンスの優先順位を継続的に調整することができます。
こうした一連の仕組みは改善サイクルをより速く確実に回すための基盤となっていくでしょう。
▼形式知化によって得られるメリットはこちら
形式知とは?暗黙知との違い、メリット、形式知化の手法を詳細に解説
参考文献:
- Essential Guide to Fault Tree Analysis for Improved System Reliability | Learning Center | MaintainX
- A Comprehensive Guide to Fault Tree Analysis for Maintenance
- Enhancing Cybersecurity: A Guide to Fault Tree Analysis (FTA) – Blue Goat Cyber
FTA×生成AIでデータ駆動なリスク管理を実現
製造システムは、IoTやクラウドの導入によってますます高度で複雑なものになってきており、ほんのわずかな不具合でも全体の停止につながるリスクが高まっています。こうしたリスクを見つけ出し、対策を講じるために有効なのがFTAです。
ただ従来のFTAは、専門家の経験や知識に大きく依存し、多くの時間と手間を必要としていました。
しかし近年では、生成AIの活用によってこの分析方法が大きく進化しています。AIがデータから因果関係を自動的に抽出し、分析の構造を柔軟に更新していくことで、特定の人に依存せず、スピーディーかつ精度の高い分析が実現可能になりました。
このようにAIによって高度化されたFTAは、リスクの全体像を把握しやすくし、どの対策を優先すべきかを明確にする助けになります。
その結果として、経営判断の質が高まり、製造システム全体の信頼性向上にも大きく貢献しているのです。
エムニへの無料相談のご案内
エムニでは、製造業をはじめとする多様な業種に向けてAI導入の支援を行っており、企業様のニーズに合わせて無料相談を実施しています。
これまでに、住友電気工業、DENSO、東京ガス、太陽誘電、RESONAC、dynabook、エステー、大東建託など、さまざまな企業との取引実績があります。
AI導入の概要から具体的な導入事例、取引先の事例まで、疑問や不安をお持ちの方はぜひお気軽にご相談ください。

引用元:株式会社エムニ